第5回
崖の上の歌(2)
2025.06.20更新
朽葉をざくざくと踏んで、私たちは歩を進める。クワズイモの群生している窪地のそばを過ぎ、少し歩くと開けた場所に出た。
湧上さん 実はここが、昔の
村 屋 。――ここですか。
湧上さん ここが中心になってます。
中 之 殿 という。〔...〕村屋の跡なんです。ここ、前の広場です。
生い茂る樹々と下生えに囲まれ、朽葉の散り敷いた小さな空間。琉球王府の時代には、ここに集落の中心があって、毎日のように人びとが集い、道を往来していた。こんな山の奥に。にわかには信じられない。
その昔の広場に立って、湧上さんは南側の木立を指差す。
湧上さん この向こうに行けば、崖になっているんですよね。ここからいろんな通報する。昔は放送装置がないから太鼓を叩いて、声で、「税金を徴収するぞ」とか何とか、いろいろやります。「誰かが亡くなったよ」とか。ウテーバンタといって、連絡する。声を出す。
――ウテーバン、歌う番ですか?
湧上さん みんなに声をかける場所をウテーバンタと言ってるんです(1)。
――ここにあったんですか。
湧上さん 向こうの崖ですね。
村の大事な出来事を、崖の上から人びとに鼓の音と声で伝える。ここは集落の中心であり、情報や意志決定の中枢であり、村と村の間をつなぐ道の要所でもあった。
十九世紀の初め頃に船越の集落は山中の
湧上さん 自分たちも青年の頃、二十四、二十五ぐらいのとき、〔字に〕各組があって、組の連絡員として一年間はさせられるわけです。それで、人が亡くなった場合は、朝、
鉦 を叩いて。〔...〕高台に上って鉦を叩いてから、「誰かが亡くなりましたよー」と言って。放送じゃなくて、大きな声を出して。――鉦を叩きながらですか。
湧上さん 叩いてからね。そしたら、「誰が亡くなったか?」と言って、尋ねてくる人がおるわけよ。〔そうしたら〕「誰々が亡くなったよ」と言って、それで〔情報が〕拡がっていって。〔...〕あの、香の典を徴収するんです、人が亡くなった場合。
――香典を?
湧上さん 香典。あれは小さいお金ですよね。各
家 から、区民から。それで、「香典抜きますよー」という風な感じで、大声を出すわけです。誰が亡くなったとは言わないで。〔...〕
ウチナーグチで、方言でやるんです。「コーヌジン、ヌチャーシンソーレー〔香典を徴収しますよ〕」とか言うんです。そしたら、「誰が亡くなったか?」って近くの人が来て。――やって来て。
湧上さん それで拡がっていくわけです。
――それは言わないわけですね。名前は、声では言わない。
湧上さん 言わないです。
集落が平地に移って以降、皆に報せを告げる場所は
湧上さん 〔岩山の〕上の方に、わりと広々した広場があったんですよね。向こうに上って、〔鉦を〕叩いてですね。人が亡くなった場合に、「コーヌジンヌチャーシンソーレー」とか言って、やってたんです(4)。
――ここがその、ウテーバンタの......?
湧上さん いえ、ヒラカーイシンブリー。上の方が平たい広場になってますからね。石の、森というんですかね、イシンブリーというんです。
平川 石壇 、岩山ということです。
平たい頂上をもつ大岩、ヒラカーイシンブリー。お伽話に出てくる地名のような響きだ。若き日の湧上さんもあそこに上って、集落に向かって大声で叫んだのだ。山を背にして。
一本の道路を隔ててその岩山に面した上山の裾地に、石灰岩で造られた小さな祠が立っている。それは、五月と六月の
湧上さん ここが、
山 川 之 殿 ですね。祝女さんは、ここ〔祠〕に近いところにいて。そこに各門中の神人 、ウクディーというんですが、そういう方々が並んで、立っていたんですよね。そんで、ここでいろいろ拝んでたんです。〔...〕そして、ウンサクというのは、神酒ですね。神に捧げる酒。あれ〔神酒を捧げる役〕をやる人がおるんです。柄杓 取り といってね。この人が、〔神酒を〕汲んでやるんです。
祠から数歩のところに、台座のような平たい石が設えてある。その傍に立つと、疎林の向こうはすぐに道路だ。いまはアスファルトで舗装されたこの道も、昔は樹々の鬱蒼と生い茂る小暗い小径だったという。
湧上さん ここ〔石の上〕に、神酒を入れた桶を置いてあったんです。それから汲んでね、〔祭祀を〕やっていたんです。〔...〕当時は、私は子どものときですからね、まだ学校に行ってないときのことですよね。そこ〔道端〕から見てたんですね。一般区民は向こうに立って、この状況〔祭祀の様子〕を見てたんです。そんで、〔神酒の〕余った分をまたみんなに。
そのときは、瀬戸物はあまりなかったもんですからね。自分の家 から木でできたお椀をですね......着物姿で、裸足なんですよね、当時は。〔お椀を〕懐の中に入れてきて、それを出して、注 いでもらって飲んで、また持ち帰ってたんですよね。
山際の道端に鈴なりになって、祠の前の大人たちの様子を一心に見つめている子どもたちの姿が目に浮かぶ。みな素足で、着物のかくしに木のお椀を入れて。大きい子は小さい子をおぶったり、その手を引いたりして。そわそわしながら、でも
山川之殿のある場所から東へ向かう山道を上っていくと、やがてもうひとつの拝所に辿りつく。クボー御嶽。かつて
湧上さん この辺一帯が本来、クバの木があってですね......立派な祠があったんですね。
もとは三日月と太陽のシンボルが彫り込まれた素焼きの祠があったけれど、それは数十年前の台風で壊れてしまった。新しい祠ができたいまでも、古い祠の破片がその傍らに積まれている。そのそばにしゃがんで、素焼きのかけらをより分けながら、湧上さんは独り言のように呟く。
そして、これは、月と太陽の形をしているのがあるんです......もうわからんですね。
こんな風に歩いてみると、上山の全体にその地形や水源と結びついた拝所が点々と、有機的に配されていることがよくわかる。山裾から山頂へ、人びとのいる場所から神々に近づく場所へ。いくつもの拝所を経由しながら、祈りは螺旋状に昇ってゆく。反対に、人びとへの報せは高所から低地に届き、波紋のように拡がっていく。
目にみえず、いまは耳にも聞こえないその声や祈りの流れが、山々と集落の、泉や樹々や岩山や、いくつもの拝所からなる場所の構造に表れている。飛び石が道を浮かび上がらせるように。
その道を通って伝えられていくもの、伝わってくるものは何だったのか。
時のめぐりと連動した作物の成長と実り。生きものの成長と繁殖。人びとの生と死。そうした事柄がたぶん、もっとも重要なことだった。
こーぬじん ぬちゃーしんそーれー
死者の名を告げることなく、誰かの死を伝える声。
その声は崖の上から集落全体に届くけれど、その呼びかけは路傍や畑地や、家の中でその声を聞いた一人一人に向けられている。自分がどのようにその声に応え、出来事にかかわるべきかを、それは知らせている。声は報せであり、合図であり、要請でもあった。
それが誰であったとしても、集落の中で起こった死という出来事に、その一員として私は適切に応答し、関与しなくてはならない。その死を弔い、死者をこの世からあの世へ送り出すために。
*
オブリティマに葬儀つづく。
日曜日からエウェの人びとはずっとドラムを叩き、踊りつづけている。
ゆうべ、パチコが亡くなったという(6)。
ずっと昔、一九九〇年代の終わりにガーナの村で調査をしていた頃のことを思いだす。多民族からなる移民たちの村だったオブリティマで、エウェ民族の人びとが自分たちにかかわる重要な出来事を知り、告げ知らせる手段は太鼓の音だった。
朝まだき、特徴のある太鼓の音が村の一角、エウェの人たちの集住している辺りから響いてくると、私にもわかる。彼らの間で何かが起こった、あるいは今日、起ころうとしているのだと。
誰かが亡くなるたび、エウェの人たちは紺色の衣装を身につけて、油椰子の葉で葺いた日除けを設えた空き地に集まってくる。そして大小の太鼓を叩き、三角形の鉦と瓢箪製のマラカスを打ち鳴らしながら、延々と歌い、踊りつづける。自分たちの中で起こった死を弔い、消化するために。
硬質な鉦のリズムに合わせて彼らの歌っていた、もの哀しい旋律の歌が思いだされる。それは、こんな歌詞をもつ歌だった。
夜は歌い手たちへの伝言をのせてやってきた
夜のとばりが降りたとき、これはいったいどのような死だというのか?
人生にあることが起こったとき、あなたは嘆き悲しむこともできない
歌い手たちは言う、どの死もみな墓場へと通じていると
けれど、このことはもっと哀れみを誘う
そして彼らは
墓を掘る人びとにこう言い残して
「生まれてきた者は、誰もが死ななくてはならない
だから私はこの太鼓を、まだ生きている人びとに残していこう」
(1)『玉城村 船越誌』によれば、ウテーバンタは「お触れの鼓を打つ崖」を指す(船越誌編集委員会 二〇〇二:四八)。
(2)上間原と屋敷原については、船越誌編集委員会(二〇〇二:一〇三)参照。
(3)平地に移った後の船越には、字の東側と西側にそれぞれ、住民に連絡事項を告げ知らせるための場所があった。ヒラカーイシンブリーは字の東側に位置している。船越誌編集委員会(二〇〇二:三一四)参照。
(4)以降の湧上さんの語りは、二〇二五年三月十七日に船越で行ったフィールドワークの録音記録に基づいている。
(5)五月の稲穂祭と六月の稲大祭のこと。
(6)ガーナ東部州のオブリティマ村で調査をしていた頃の日記(二〇〇〇年十月二十五日)より。
参照文献
船越誌編集委員会 二〇〇二『玉城村 船越誌』玉城村船越公民館。


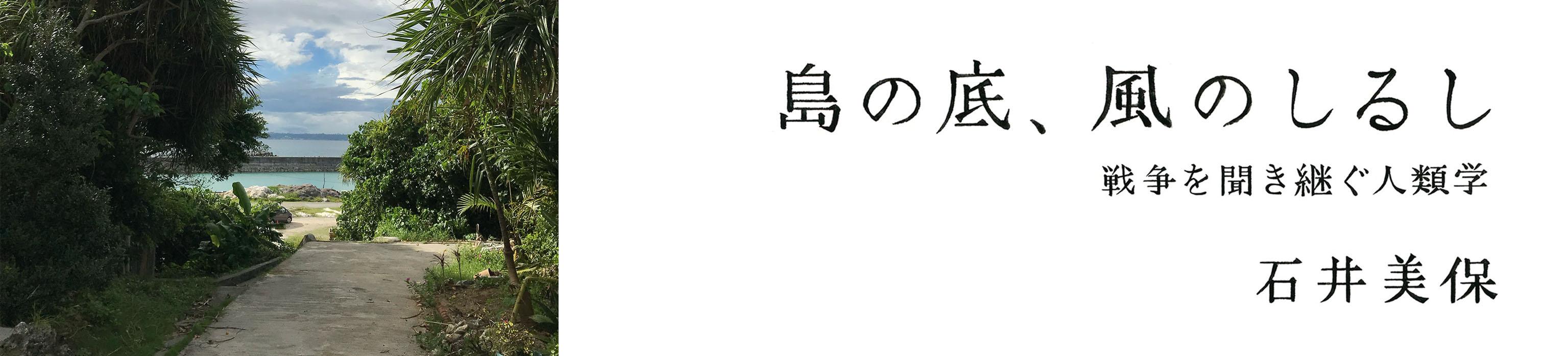



-thumb-800xauto-15803.jpg)


