第10回
市場と港(1)
2025.11.20更新
前川集落の北西から南東へと流れる
雨の降りしきる十月のある日、湧上さんに案内してもらった港川の漁港には人影もなく、数隻の漁船がドックにつながれていた。一軒だけの食堂も閉まったまま、雨にそぼ濡れている。たっぷりとした暗緑色の水をたたえ、ほとんど流れていないようにみえる雄樋川の対岸は、玉城村だ。
昭和十五年(一九四〇)頃までの長毛は、粟石採掘で一攫千金を夢見る人々や、それに関連する仕事を求めて、沖縄各地から人々が集まり、部落は町の形態を成し、糸満や与那原と並んで、沖縄本島南部における商業の中心地であった(1)。
いまも港川には、切り立った崖から粟石を切り出した採石場の跡が残っている。当時、この地域には粟石を運搬するための荷馬車が日に三百台以上も集まり、港川と目取真を結ぶ県道十七号線には、馬車が列をなしていたという。この道を通って粟石を運ぶ馬車持ちたちのために、前川の県道沿いには食事処もあった。
当時の様子について、湧上さんはこんな風に語っている(2)。
〔馬車は〕那覇とか、与那原とか、中部からですね、目取真から前川の前を通って港川に行くわけですね。それで朝、前川の前を通るときに、そこ〔食堂〕に寄ってお昼の予約をして、馬に与える餌をお願いして。それから長毛の石切場に行って、向こうで石を積んで、ちょうどお昼頃に帰るわけですね、石を運搬して。そして前川に来ると、この食堂で食事をして、馬にも餌を与えて。それからまた、〔各地に〕運んでいくわけです。
当時は前川の道も二、三百メートルぐらい、馬車馬が並んでいたみたいです。食事するときに。
港川の隣の長毛は、前川や船越あたりに住む農家の人たちにとって、那覇よりも近場の市場だった。人びとは朝早く、畑で収穫したイモなどをザルに入れて頭に載せ、あるいは背負子で担ぎ、長毛までの二キロ余りの道のりをせっせと歩いてくる。その途中、雄樋川を越えるためには、「潮洗い橋」という橋を渡らなくてはならなかった。湧上さんによれば、昔、雄樋川の水量がいまよりも多かった時分には、上流から流れてくる川の水と満潮時に海から押し寄せてくる潮がぶつかりあい、橋を越えて渦巻くこともあったという。想像するだに、なんともすさまじい光景だ。
そんな道のりを歩いて長毛に辿り着くと、マチグヮーと呼ばれる露天市場の道端で、担いできた荷物を下ろす。すると、それを目ざとく見つけた仲買人たちが寄ってくる。
大城勲さんは、幼い日に祖母について長毛の市場に出かけたときのことを、こんな風に語っている(3)。
勲さん この〔長毛の〕通りは、みんなここに座って商いをする人たちが〔いた〕、おばあたちとか、おかあたちとか。おイモは、そこに持って行って下ろせば、もうみんな、仲買人が来てから勝負で取っていく。〔...〕何回か私も〔祖母と〕一緒に行って、イモを下ろすのを見て。
――ザル一杯いくら、とかの相場はあったんですか。
勲さん あったと思うよ。〔...〕秤は持ってないからないよ、「ミージョーロー〔見候〕」と言ってね、方言ではね。だいたい、見ての相場。天秤にかけたんじゃないし。
露天の市場に加えて、当時、長毛の通り沿いには大小の商店が軒を並べていた。持参した農作物を売ったお金が手に入ると、農家の人たちはその足で商店街に立ち寄って日用品を買ったり、そば屋で軽食をとったりと、ちょっとした買い物を楽しんだ。
『具志頭村史 第二巻』には、一九三五年頃の長毛大通りにあった店々の屋号と所在地が記されている(4)。それを見ると、食料品や雑貨を扱う一般の商店に加えて、じつにさまざまな商売がなされていたことがわかる。
銭湯、旅館、そば屋、散髪屋、フルガニ屋、カマボコ屋、菓子店、酒屋、タルガー屋、サンジンソー屋、ブリキ屋、ボージ屋、ヤブー屋、材木店、鍛冶屋、自転車店、歯科医院、写真店、古着屋、蹄鉄所、鞍屋、桶屋、しっくい屋、呉服店、薪炭屋、などなど。
そば屋や銭湯、散髪屋などは、それほど長くない通り沿いに何軒もある。フルガニ屋は古鉄、つまり古い鍋釜などを扱う店、タルガー屋は樽の制作と修理を請け負う店。蹄鉄所と鞍屋があるのは、日に何百頭とやってくる馬と馬主たちのためだろう。サンジンソー(三世相)屋は易占い、ヤブー屋は鍼灸院。ボージ屋は坊主、つまり僧侶が葬式や供養に関する相談にのる場所だった。地図には明記されていないが、このあたりには遊郭もあったらしい。
石切人夫に馬車ムチャー、山原船の乗組員、漁民と農民、露天商に商店主、易者に坊主、遊郭の芸者......。この頃の長毛と港川は、多種多様な人びとが集まり、賑やかに行き交い、商売を通して交流する盛り場だったのだ。
湧上さんと勲さんは、大人たちに連れられて港川に出かけたときの、印象深いエピソードのいくつかを教えてくれた。
勲さん 親たちの話では、この地域では与那原の町よりは、港川の方が活気があって、とっても栄えていたって。私たちもまた親に連れられて、月に一回か二回ぐらい、港川の銭湯に、冬は行きよったですね。で、親に連れられて向こうで、そば食べた覚えが。「へんなのそば」といって。
――ここ〔『具志頭村史』〕に載ってますかね。これですね、平安名そば屋......。
湧上さん 「へんな」と言ってたね。
勲さん 方言で、「へんな」と言ってたね。
――どんなおそばだったんですか。
勲さん ともかく大衆的な、量も多いみたいで。〔...〕沖縄そばというのは、出汁骨ね、豚の、ソーキボネとか、いろんな骨で出汁を取るんですが、とにかくおいしかったんですよ。もう子どもながら、そこに行くのを待ちかねて行ってますからね。
――おそばの中には何が?
勲さん かまぼこと、三枚肉と。いまでもそうですよ、どこに行っても。それが上にのっからないと、沖縄そばとはいえない(笑)。〔...〕
日頃はね、昔は生活がそんなに豊かではないから。港川に行くのもそうだけど、たまには那覇に行くときもあったんですよ。そういうときもそばだったね。
古くからの漁港のある雄樋川の入江では、旧暦の五月四日にハーレーと呼ばれる爬竜船の競漕が行われていた。港川の集落は北組と南組に分けられ、それぞれの組で選り抜かれた十三名の乗組員が華やかなハーレー舟に乗り込んで、入江の入り口から奥に向かって勇壮に漕ぎ進む。入江に面した船揚場では、女性たちが腰まで海に浸かって鼓を打ち鳴らし、歌を歌い、カチャーシーを舞い踊って自分たちの組を応援する(5)。
港川の海人たちにとって、ハーレーは豊漁と航海安全を海の神に祈願する、大切な年中行事のひとつだった。農村での綱引きと同じように、それは共同体を挙げて神を歓待し、喜ばせ、豊饒性を招き寄せるための真剣な遊びだったのだろう。
ハーレーの日には、前川や船越といった近隣の集落からも大勢の人びとが見物にやって来た。港川の浜辺には那覇から来たおもちゃ屋の出店がいくつも並び、子どもたちの人気を集めていたらしい。
勲さん 爬竜船といって、ハーレーのときは必ず、あのときは子どもにはおもちゃが。観に行ったら親たちはもう、かならずおもちゃは買いよったんですね。だけど、高価なおもちゃではないですよ。あの、ハッチブラーといって、お面とかね。鬼の格好したのと、また変てこりんな顔したのと、いろいろあるわけですよ。そういうのを買った覚えがあるね。〔...〕
〔ハーレーは〕朝、午前中で終わるからね。潮の干満があって、潮が引いたら舟が浮かばないから(笑)。朝早く親に連れられて、昔は車もなんにもないから、向こう〔港川〕まで歩いて行って。で、向こうでは見物人がいっぱいいるし、またその中で出店もいっぱいあるから。もう舟の競争を観るのも、親たちは観たかもしれんが、私たちはもう、舟が競争して、漕いで、あんなのなんか観ないですよ。みんなもうおもちゃばっかり見て(笑)。――昔は奥武島よりも盛んだったとか。
勲さん 港川のハーレーはね、〔...〕とっても有名でした。というのは、ハーレーだけじゃなくて、
角力 があったんですよ。沖縄県全体の角力。だから、山原や離島からも、角力とる人たちが来よったですよ。久米島の人がよく優勝しよったが(6)。〔...〕ハーレーがだいたい十一時頃終わるから、それから角力が始まって。あちこちの村には角力の強い人が何名かいるから、そういう人が出よったんですよ。だけど、この辺の人はみんな弱かった(笑)。
勲さんによれば、その頃、前川や船越の出身者で、港川の角力大会で一等になるような人はそうそういなかったらしい。ところが、湧上さんや勲さんが生まれる前の昭和初期、ひょんなことから、この地域一帯の名力士として名を馳せることになった人がいた。湧上さんの父である。
(つづく)
(1)具志頭村史編集委員会(一九九一:二八八)参照。
(2)本章で引用した湧上洋さんの語りは、二〇二五年十月二十日、南城市玉城船越にて行った聞き取りに基づいている。
(3)本章で引用した大城勲さんの語りは、二〇二五年十月二十日、南城市玉城前川にて湧上洋さんと堀川輝之さんとともに行った聞き取りに基づいている。
(4)具志頭村史編集委員会(一九九一:二九〇-二九二)参照。
(5)港川のハーレーについて、詳しくは具志頭村史編集委員会(二〇〇五:六九三-六九八)参照。ハーリー(ハーレー)一般については源(一八五-一八六)参照。
(6)沖縄角力については、大城(一九八三:五四一-五四二)参照。
参照文献
大城清功 一九八三「沖縄角力 おきなわずもう(ウチナージマ)」沖繩大百科事典刊行事務局編『沖繩大百科事典 上』、五四一-五四二頁、沖縄タイムス社。
具志頭村史編集委員会 一九九一『具志頭村史 第二巻(通史編)』具志頭村役所。
具志頭村史編集委員会 二〇〇五『具志頭村史 第五巻(村落編二)』具志頭村役所。
源武雄 一九八三「ハーリー」沖繩大百科事典刊行事務局編『沖繩大百科事典 下』、一八五−一八六頁、沖縄タイムス社。


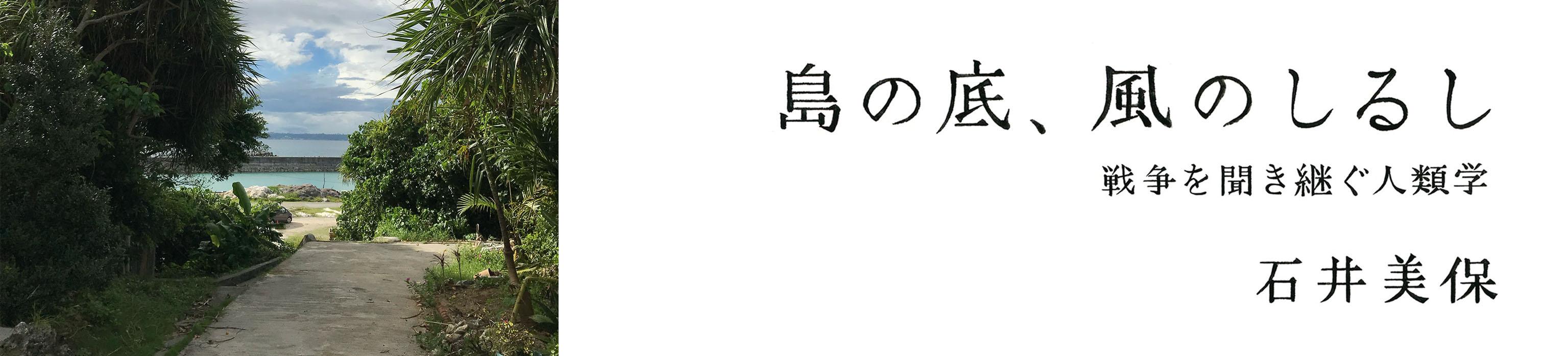



-thumb-800xauto-15803.jpg)


