第52回
おひさしぶりです しんじです ひとひです
2020.05.05更新
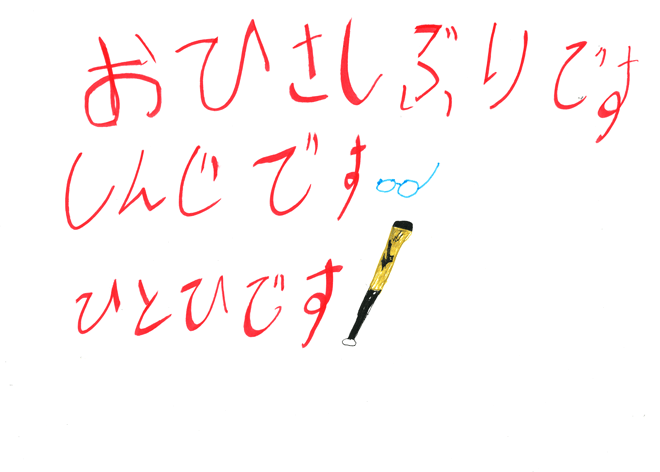 あたらしい「きんじよ」コラムを書かずにいるうち、まさかこんな日々が到来するとは思ってもみなかった。
あたらしい「きんじよ」コラムを書かずにいるうち、まさかこんな日々が到来するとは思ってもみなかった。
外食がない。映画もない。本屋さんでばったり、ひとに会えない。電車に乗れない、バスに乗れない。
馬にはこないだまで乗れたけど、緊急事態宣言が出されてしまっては、もう乗れない。
いつか詳しく書くつもりだった、ひとひの野球。3年の秋から参加した少年野球のチームも、学校が再会しないうちは、グラウンドも使用禁止なので、練習がない。
町をいく皆が皆、マスクしている。ここは京都だから、用事があって「きんじよ」に出歩くと、やはりどこいらじゅうで知り合いに出会う。姿をみとめると、遠巻きに声をかけあい、大きく手を振って別れる。マスクの下にかくれて、その表情はみえない。
小説を書く日常は、なんにも変わらない。毎朝机にむかい、昼過ぎまで鉛筆、ペン、キーボードで字を書く。イベントや対談、取材やなんかがすべてなくなったから、かえって前より仕事がはかどるくらいだ。
文芸誌「新潮」で連載中の「チェロ湖」は二年目をむかえた。現代と1950年代、さらに戦前、戦中を、チェロと蓄音器の音でつないでいく話。
机のそばにはちゃんとほんもののチェロがある。上賀茂に住むチェロ奏者ヨース毛くんから借りている、ボディにペンキで模様が書かれたチェロ。たまにケースからだして弓で弾いてみると、ふくよかな振動音がおなかから全身にひろがる。
気がつくと家じゅうが鳴っている。木造の楽器と家屋が共鳴しあい、あたらしい音の響く「場」に、ぼくは浸りこむ。チェロ湖の水面に、頭からしずみこんでゆく。
京都新聞のあたらしい企画で、毎週ひとつ「禅語」をとりあげ、思いつくことを書く、ということをはじめている。
たとえば「主人公」「無」「挨拶」「一笑千山青」「日々是好日」「野火焼不尽 春風吹又生」「休休休」。
ほんとうに禅僧の修行にかかわる語でなくて、僕が「なんとなく禅語っぽいなあ」と感じることばもとりあげてよいらしい。
三崎まるいちの美智世さんが初孫の誕生に漏らした「どんなことでも、増えるっていうのはなんか、楽しいよね」。湯浅学さんがひとひのために作ってくれた「毎日は一日だ。毎日は、ひとつの日」。その一日が3歳のときにしょっちゅう使っていた「きのう」。
きのう、「楽只在中」について書いた。「たのしみはただなかにあり」。
京都の暮らしは、戸をあけて家を出てもすぐ「そと」にはならない。「うち」と「そと」が混じり合った、豊かな中間領域がひろがっている。その共有スペースで、みな出会い、話し、笑いあう。
町の中、家の中。自分の中。
楽しみを、わざわざ外に求めなくてよい。それは「ただ、なかにある」。
新学期のスタートがえんえん引き延ばされつつあるいま、子どもたちのために、錦林小学校のホームページで、「図書館怪鳥トリボン」という「おはなし」の連載をはじめた。トリボンとは、去年から学校の図書館に登場した、本と鳥が合体したキャラクターだ。ふだんは本棚で眠っているが、子どもたちのいないときに出てきて、本のリクエスト用紙や、図鑑の小虫、果物などをついばむ。
「トリボンに、こんなひみつがあったなんて知らなかったです」
「こんな図書館だったら、毎日、いってみたい」
「もっともっとつづきを書いてください」
と、少しずつ、声が寄せてくる。文面のむこうから、ほのかに笑い声がきこえる。
「ようし」
机にむかう。ノートをひらき、鉛筆で走り書き。それをキーボードで一気にうつす。おはなしのなかでトリボンが笑う。それを読むこどもたちの笑い声がひびく。中と外が、窓をあけはなったかのように、自然に入りまじる。
三浦半島南端の港町、三崎から、厚めの封筒がとどいた。差出人は老舗旅館「三崎館本店」の若主人・渡辺達也さん。封をあけてみると、折りたたんだ布の束がはいっている。
「世間で、てぬぐいでマスク作るのがはやっているみたいで、ふと、店のてぬぐい見ていたら思ったんです。これでマスク作ったら派手だな。こんなの付けられるのはいしいさんしかいないじゃん」
と、渡辺さんは書いていた。
「じゃあ、石井さんに作ってあげればいいや。というわけで、うちの妹に作ってもらって送った次第です。総理大臣のマスクより、迅速に送ることができました」
手ぬぐいの両端とまんなかを使ったマスクが三枚。宿は創業明治四十一年。字が左から右へ流れるから、おそらく戦前に作られたものだろう。三崎港からみた海原にカモメが飛びかう、オリジナルてぬぐいの柄は、目がさめるくらい青く、明るくてしゃれている。
つけてみると、三崎の潮の香りがした。京都にいながら、いま、マスクを通して、三崎の風を吸っている。どれほど離れてみえようとも、ひととひとの、ほんとうの社会的距離は、キロ数などで計れない。僕と三崎とのちょうどよい距離は、あいかわらず、こんなにも「密」なのだ。
三崎マスクをつけて、チェロケースを背負い、ひとひといっしょに上賀茂へむかった。ひとひの自転車は、京都じゅう走りまわって選んだBMXでなく、大ぶりなマウンテンバイクに代替わりしている(もちろんBMXは玄関で待機中)。
ヨース毛くんは家で待ちかまえていてくれた。ペグの緩みを一瞬でなおし、さらに四本弦のそれぞれをていねいにチューニング。
マスクの下からわくわくの笑みをこぼすひとひは、野球のグラブをつかんで加茂川の河原へ。ヨース毛くんは中高まで野球をやっていた。ひとひや僕に投げてくる球の質、いきおい、やさしさがちがう。
ひとひからヨース毛くんへ、ヨース毛くんから僕へ、僕からひとひへ、ボールが渡っていく。音符のように。カモメのように。ちょうどよい距離を保ち、越えていく。加茂川の河原をゆるい春風が吹き抜ける。きっとこのまま太平洋岸沿いを、三崎まで、京都のこの空気を運んでいってくれるだろう。
うちに戻ると、まるいちの美智世さんから発泡スチロールの宝箱が届いていた。あけてみるとイシダイ、カマス、トコブシと、宝玉がごろごろ。京都いち魚好きな小学生ひとひは狂喜乱舞し、すぐさま三崎へお礼の電話をかけた。
外食でもない、台所だけでもない、「うち」と「そと」、京都と三崎が、絶妙に入り交じった、魚祭の晩ごはん。
初日、中トロとイシダイのお刺身。
二日目、カマス塩焼きとイシダイお刺身。
三日目は、アジフライ、トコブシ煮付け、イシダイのあら汁にカマ焼き。
ぶじに祭は終わった。
三崎でとれた魚たちがいま僕たちの「中」にいて、そうして僕たちの「外」をかたちづくる。マスクの下にかくれていても、ひとは息を吸い、息を吐き、食べ、話し、生きている。
表情がみえないからといって、いつも必ず暗く沈みこんでいるわけじゃない。マスクの下のその顔は、ときどき僕たちに向かって、ちょうどよい距離の笑みを、きっと投げかけてくれている。



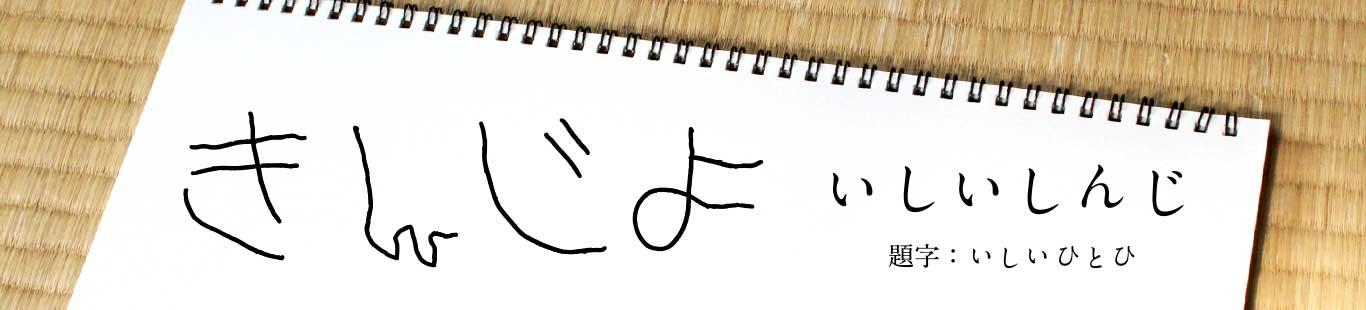

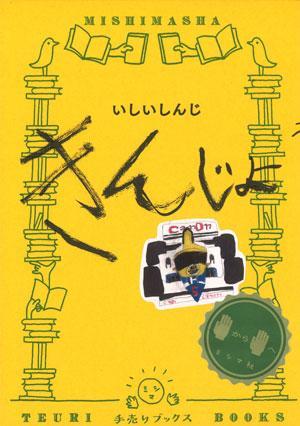




-thumb-800xauto-15803.jpg)
