第3回
『パパパネル』の刊行によせて、tupera tuperaからのメッセージ
2020.06.19更新
こんにちは。ミシマガ編集部です。いよいよ明日、6月20日(土)に『パパパネル』が発売日を迎えます。発売日を目前に、作者であるtupera tuperaのお二人よりメッセージをいただきました。
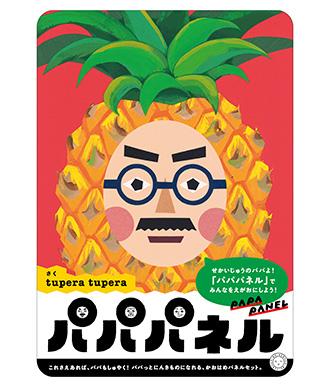
刊行によせて
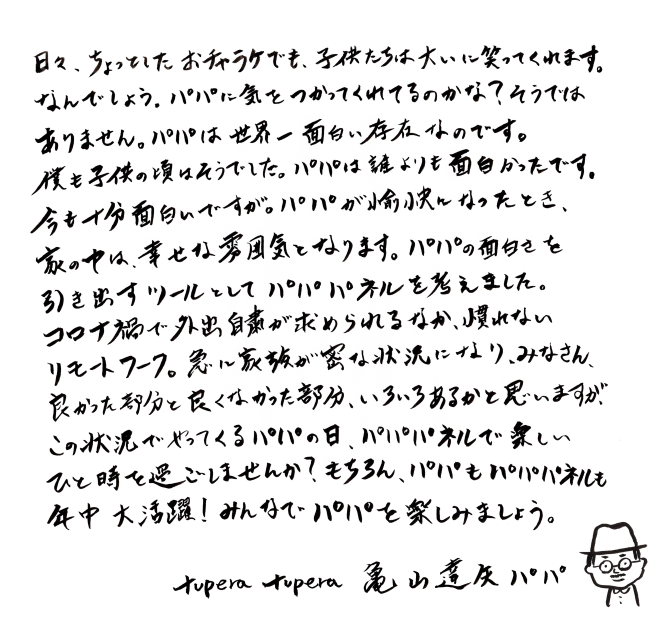
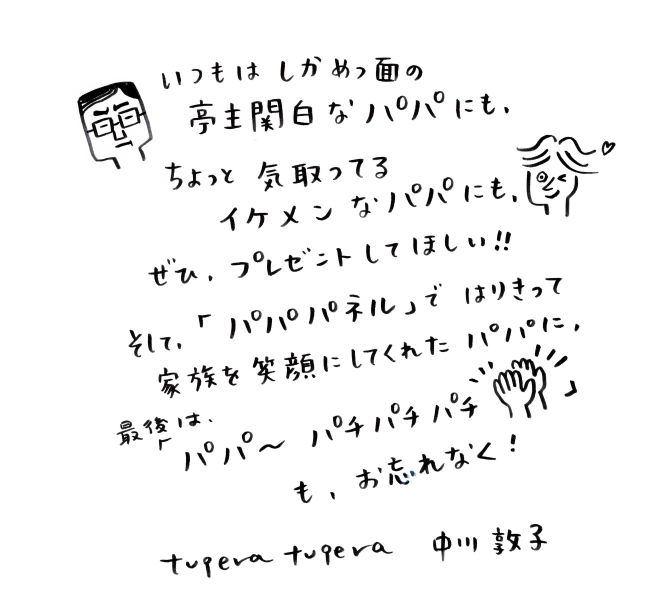
パパパネルをもっと素敵に!
今週末は父の日、ということで、お家でカンタン!パパッとラッピングのご提案です。
『パパパネル』は10枚の「顔はめパネル」とあそびかたの「せつめいしょ」が透明の袋に入っています。袋にメッセージを書いたり、お家にあるリボンやシールを貼るだけで、自分だけの『パパパネル』のパッケージが完成!アイデア次第で『パパパネル』をもっともっと楽しめます。
父の日に限らず、新米パパへのパパ応援アイテムとして、お誕生日プレゼントや還暦のお祝いとしてなどなど、まわりがパーッと明るくなる贈り物として、おすすめです。世界中に笑顔が広がりますように。
1 好きなリボンやシールでデコろう
2 リボンがないならマスキングテープを使えばいいのだ
3 お父さんの顔をこっそりはめちゃおう!
(写真:ミシマ社営業、イケハタパパ)
4 ちょっと渋めにのしスタイル
***
初回限定特典として『パパパネル』の中には「パパパーフェクトメダルカード」が同封されています。メッセージを添えてパパにありがとうを届けよう!

パパパネルをやってみた! あそんでみた! そんな様子を「#パパパネル」のハッシュタグとともに、ぜひぜひお寄せください。
編集部からのお知らせ
企画展「tupera tuperaのかおてん.」が開催中です!
2020年の6月10日に、東京の立川に新たにオープンしたPLAY! MUSEUM(プレイミュージアム)。そのオープニングを飾るのが、tupera tuperaさんの「tupera tuperaのかおてん.」です!こちらのミュージアムショップでも『パパパネル』を販売させていただきます。ぜひ足を運んでみてください!


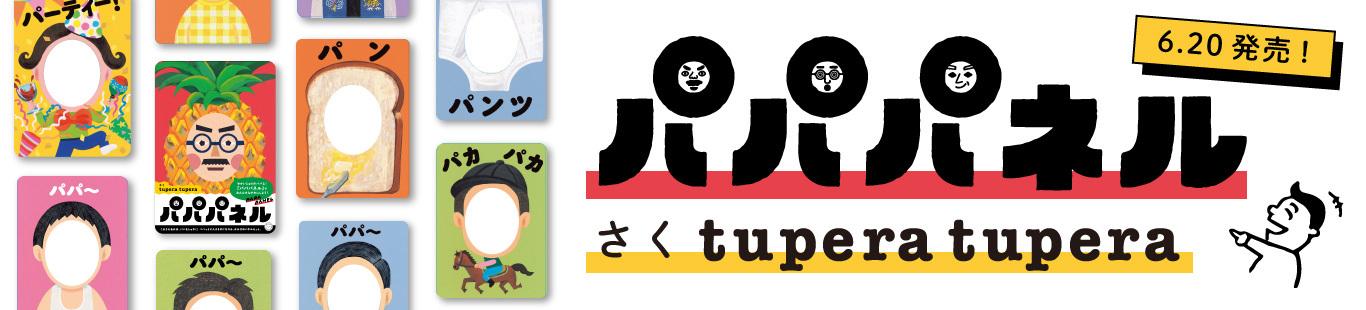


-thumb-800xauto-15803.jpg)


