第10回
ただの失敗が笑われるとき
2019.02.15更新
ものごとが順調に進んでいるときには、取り立てて滞りを感じません。だから「なぜうまくいっているんだろう?」と考えたりはしないでしょう。たとえば、いつも通りに目が覚めて起きる。電車に乗るために見慣れた街を歩くだとか、ごく普通にできるのだから恐る恐る試みたりしませんし、その行為についていちいちできるかどうか不安になりはしないでしょう。
けれども、前回述べたように生きるとは不確定の未知に向けての歩みの連続です。一寸先は闇の、まったくのわからなさを手探りで生きるのが私たちの日常の正体です。何が起きるかまったくわかりません。予測不可能です。それにもかかわらず、ものごとが破綻もせず順調に流れていくのですから、ありえないくらいの奇跡に思えてきます。
確かに驚くべきことではあります。それでも朝になればいつものように太陽は昇り、春になれば桜が咲きます。昨日と一緒の太陽、去年と同一の花ではなくとも、同じ現象が自然に生じています。世界の進展はフリーズすることも失敗もなく淡々と進んでいて、それは不可思議でありつつ当然で普通の姿であるとすれば、かえって疑問に思うのは、それでは逆調が生じるのはいったいどういうときなのだろう? ということです。
今から200年ほど前、現在の長崎県の一部にあたる、平戸藩を治めた松浦静山という大名がいました。世相や人物評などを記した『甲子夜話』の著者であり、また剣術の修練に励み免許皆伝を得たことでも有名です。静山は「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」と書き残しています。この言葉を逆調を考えるための材料にしたいと思います。
仮に勝ちを成功=順調、負けを失敗=逆調と言い換えれば、物事がうまく行くのは当たり前のことをしているからで、だから特別さを感じない。しかし、それはありえないほどの奇跡的なことでもあるわけです。
比べて失敗に「不思議がない」のは、そうなるだけの必然性があるからです。要は自然のルールから外れたから逆調が起きるのだということです。
シビアに勝敗を問われる実際の戦いでは、失敗は死を意味します。ですが、いくら生き死にを厳しく問う武術といえども、稽古においては失敗が許されています。失敗から学ぶことが学習体系に組み入れられているということは、その意義が十分に見出されているからでしょう。
幸いなことに私たちの暮らしは、実戦のようにほんの少し間違えたからといって致死に至るほど厳しい状況にさらされてはいません。原発に関わる仕事だとか紛争地の武装解除、旅客機のパイロットだとか、多くの命を預かり、ミスが許されないといった例外を除いて、さほど過酷な局面に置かれている人はそう多くはないでしょう。ですから、私たちは失敗を「絶対にあってはならないこと」ではなく、試行錯誤を通じて研鑽する機会に置き換えることができます。そういうことが可能な社会は豊かであり、度量が広いと言えると思います。
しかしながら、現状のこの社会は失敗に寛容ではありません。そのため私たちは些細なミスですら怖れるようになっています。強風が吹いて電車が数分遅れるだけで「申し訳ありません」と車掌は謝ります。主体的に行動するにもかかわらず、「させていただきます」というへりくだった言い回しをする人も多くなっています。心から思ってはいなくとも、あらかじめ怒られないための防御として言葉を用いる機会がずいぶん増えています。
それにしても世の中の雰囲気がこれほどまでに他罰的で厳しくなったのはなぜなのでしょうか。それを明らかにするには、社会全体を問題として扱うといった高所から眺めるよりも、一人ひとりの人生を振り返ることがいいのではないかと思います。そうすれば自ずと理由が見いだせる気がします。そう、いつから私たちにとって成長とは怖れを知る過程となってしまい、失敗を怖れ、他罰を好むようになったのでしょうか。
その別れ道を辿っていくとわかるのは、誰しも生まれてからしばらくは、うまく立てなくて転んだり、尻もちをついて失敗しても、「すごいね」と誉められていた体験があったことです。周囲は叱咤するどころか、にこにこと笑い、歓声をあげていました。ぎこちなく手にした椀からご飯を手づかみで口に運び、ちゃんと食べたとは言えないくらい、米粒を床にこぼしても「そんなこともできるの! すごいね」と手放しで誉められもしたでしょう。
けれども、そうした不首尾を肯定される時節は幻だったかと思うくらい、ある時期を境に「そんなこともできないの」と言われるようになり、「ちゃんと・早く・もっとできるようになりなさい」と叱責されるようになりました。そうして人と同じようにできないことは恥ずかしいし、人と違っていては世間に笑われるのだと、私たちは胸に刻むようになりました。
周囲から「できない」ことを指摘され、その否定的な評価をくだされる自分に罪悪感を覚えるようになった挙句、そのような他罰的な態度を受け取ると、人から「笑われないようにしないといけない」と考え、それを健気にも実行するようになりました。そうした学習の結果、失敗とは恥ずべきことで、もしもそんな人間がいたとしたら笑うことが当然なのだと学んでしまいました。
ところで、一口に「笑う」と言っても、幼な子の時代と他罰的態度を身につけた後とでは意味合いが違います。赤ん坊の尻もちのように、本来からすれば失敗であっても、周囲はそこに何とも言えない愛らしさを見出して微笑みました。そうした仕損じたことに対し、つい笑みがこぼれてしまうのは、きっと人間の原始的な感覚に基づく振る舞いだからなのでしょう。さらには誰かが何かしくじった際、その失敗をおどけて真似ると、いっそうさざめきが広がっていくのは、物事が順から外れてしまったズレにおかしみを覚える感性を私たちが持っているからでしょう。逸脱に出会うとなぜか身の内から笑いが込み上げてくるようなのです。失敗した時と物事が順当に行った時とを比べて差異を感じ、そこにおかしみを覚える。そういう意味では笑いとは知的な行為であり、人間の徴(しるし)とも言えるかもしれません。
逸脱をおかしく感じることから「何が笑いに値するか?」といった探求が始まり、センスが芽生え、文化が生まれます。私はスタンドアップコメディアンによる、いわゆるアメリカンジョークを聞いても大笑いすることは滅多にありません。それは吉本新喜劇をはじめ、上方の漫才を幼い頃から見て育つといった、関西に生まれ育ったがゆえに身につけた、笑いに関する習慣と感性とがアメリカ人のそれとは違うからなかなか共感できないだけのことで、別に彼らのジョークのレベルが低いからではないのだと思います。向こうにして見れば、私がおもしろいと感じる漫才の何がおもしろいのかわからないかもしれません。失敗や誤りという行為のズレを笑うことに普遍性はあっても、何におかしみを感じるかは文化、風土によって偏りがあると言えそうです。
失敗におかしみを感じて笑う。そして笑いは文化によって違う。ここまで述べたことを前提に、では今どきの笑いはどういうものか考えてみます。流行りの笑いは現代人の感性によって作られています。だとしたら、今を生きる私たちは何を笑い、何を笑ってもいい対象だと考えているのでしょう。それを笑いの文法と言ってみます。この30年くらいメディアにおける笑いの文法は関西系のお笑い芸人がリードしてきたと言っていいでしょう。人を笑わせる方便として、ボケやツッコミという定型があるのを今や誰しも知っています。
ボケとは、常識や当たり前といった通常からはみ出た言動で、ツッコミはその逸脱を明らかにしたり、大仰に解釈することでボケの異様さをデフォルメするわけです。そうした笑いの手順を踏まえ、今どきの「何を笑ってもいい対象にしているか」を考えると、「いじる」という手法が否応なく浮かび上がってきます。
「いじる」とは、いわば勝手にボケを見出す手つきです。たとえば容姿やセクシャリティ、人種といった変えようのない属性を抱える人やマイノリティ、社会的弱者をいじって笑いにしようとするのがお決まりのパターンとしてあります。「それは普通ではない」とジャッジし、いじるわけです。これがいじめや差別につながっているという批判が以前に比べて高まっているのは、皆さんもご存知でしょう。
人によっては「冗談のひとつも言えない息苦しい世の中になった」と思うでしょうが、今までが単に無神経さと傲慢さが野放しにされていたに過ぎないのかもしれません。少なくともマイノリティや社会的弱者はマジョリティの息抜きのために生きているのではないとだけここでは言っておきましょう。
「それは普通ではない」といじるとき、その発言者は「ただ存在しているだけの人」に正常からの逸脱を認め、いわばそれを失敗と位置づけているわけです。ゲイである。肌が黒い。女である。太っている。どれもこれも他人に笑われるべきことではありません。その人が現に今そうであること以外の何者でもないからです。
笑いは普通との違い、逸脱に見出されると先述したのであれば、セクシャリティも容姿も笑いの対象になるのではないか? と思う人もいるでしょう。しかし、いじる笑いは人間の原始的な振る舞いにつながっているでしょうか。おかしみを誘う、愉快な笑いでしょうか。どちらかと言えば、ことさら違いをしつこくあげつらい、愚弄し、嘲る笑いです。そこにユーモアと知性はあるかと問えば、ノーと答えざるを得ないでしょう。
さらに言えば、「普通との違い」という時の「普通」が極めて狭い範囲で成り立っているとしたら? しかも人から笑われないよう、失敗する事のないように腐心した結果、身につけた習慣的な常識でしかないとしたら?
逸脱をいじりさえすればただちに笑いになると思えるのは、いじる側が平均値としてのみんなと同調していると思えるからでしょう。そういう「みんな」がどこにいるかはわかりませんが、なぜそこに依拠することに自信が持てるかと言えば、世間に与えられた正しさを額面通り受け取り、ひたすら叱責されないような生き方をしてきたからではないでしょうか。
つまり自ら体験した中で得た了見ではなく、ただ他人が提供してくれた常識にのみ寄りかかっている。他罰の果てに得た態度は「決して常識から逸脱してはならない」という、極めて穏当でかつ偏狭な態度です。それを自らに強いて来たのだとしたら、自罰に等しいとは言えないでしょうか。



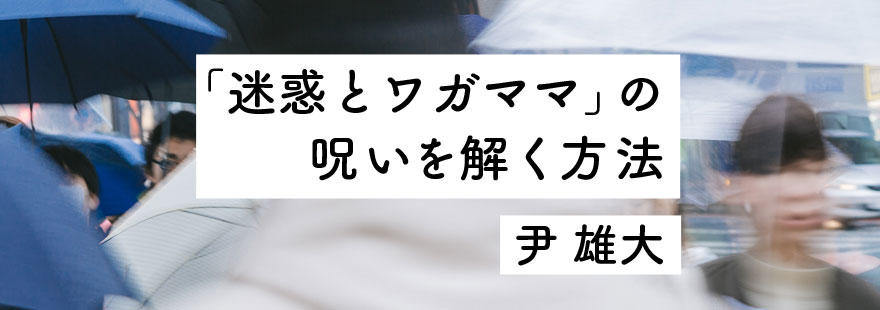





-thumb-800xauto-15803.jpg)
