第11回
恥と恐怖
2019.03.21更新
小学校6年生のとき、家庭科の授業で枕カバーを作り、そこに刺繍を施すという課題が出されました。その頃の私は城の石垣や楽焼、尾形光琳の燕子花図といった古の文物に魅せられていて、それらの絵を好んで描くのを趣味としていました。当然ながら枕カバーの刺繍に選んだ題材はと言えば、屋島の戦いにおいて汀に馬を進め、平家方の船にかざされた扇に向けて矢をつがえる那須与一というシブいものでした。それほどレベルの高い刺繍ではなかったでしょうけれども、内心満足のいく出来映えでした。
後日、授業の終わりに担任が提出した課題を一人ひとりに返し始めました。私の番になると、彼女はカバーを広げて衆目にさらした上で、「なんやこれ。わけわからん」と言い放ったのです。
その教員は今なら懲戒処分を受けるような人物で、少しでも気に入らない発言を生徒がすると職員室に引きこもり、全員が謝りに行かなくてはならないという茶番を毎日のように繰り返していました。皆の前で一番触れられたくないことを取り上げては嘲笑い、傷つける。そういうことを常にしていました。
誰しも「この先生はひどい」と思っていたでしょう。しかしながら、今よりずっと教師の社会的地位が高かった時代ですから、逆らうことはなかなか難しかったのです。
教師が「なんやこれ」と言った途端、教室中が笑い声で沸き返りました。私はそのとき、担任の一言に赤面しつつも、周囲の笑い声に驚き、ついで激しい怒りを覚えました。媚びへつらうことで生きながらえるさもしさに、二度と彼らとまともに口を利くまいと心の中で誓ったのです。
この一件は、長らく私の中で解消されない出来事として残っていました。というのは、嘲笑された後の展開は、恥辱を感じた分だけ周囲に同調せずに個として生きていく強さを目指したわけではく、むしろ笑われることに敏感になり、「また、おかしなことをしていないだろうか」とびくびくするようになったからです。
そのため12歳からは「勇気を奮う」という意味合いが変わってしまいました。周りから笑われるのをあらかじめ念頭に置いて、それを克服するところから始めなくてはいけないので、本来発揮すべきエネルギーを目的に向けて全力で注げなくなったのです。
私に限らず、大人になっても他人の顔色を伺い、空気を読むのを習い性にしてしまった人は多いでしょう。宿してしまった恐怖の姿を明らかにするのが案外難しいのは、「怖れ」の体感は生理に根ざしているからです。
たとえば、何か新しいことに挑戦しようとすると、ドキドキして足がすくんでしまいます。たった今感じている、この恐怖はありありとしていて心と身体に影響を及ぼします。生理的にリアルに感じるがゆえに、果たしてこれが「新たな挑戦」への怖れなのか。それとも世間から笑われることへの怖れなのか。体感としては両者は見分けがつきません。
つまり、未知に対して危機感を覚えるといった生物として正常な怖れなのか。仲間から見放されるという社会的な怖れなのか。体感レベルとしては同じ恐怖として感じられてしまうため、いったいどちらなのかわかりにくくなってしまいます。こうした混乱は、周囲から笑われることで失敗への怖れを逞しくした習慣がもたらした結果かもしれません。
私たちが自分自身として十全に生きようとするならば、そうした恐怖のメカニズムを解剖することが必要なのです。本当のところ、私たちはいったい何について笑われることを怖れているのでしょうか。また、真に恐るべきことを怖れているのでしょうか。
前回で述べたように、誰かの逸脱した言動を笑ったり、自分が笑われたことに恥じらいを覚えるようになった起源はいつからかはわからないものの、人間的な振る舞いのひとつだと思います。そうした人間に備わる感性は、「恥をかかすために笑う」に転換したり、場合によっては「笑われることを屈辱」として受け取る感受性が培われることにもなります。それを文化と名付けることもできるでしょう。
ちなみに、この島の文化は和を乱す言動を好まないとされています。がしかし、いつの時代もそうだったわけではどうもなさそうです。
先日、中世のトラブル解決法を取り上げた『喧嘩両成敗の誕生』という本を手に取りました。読んでいくうちに明らかになったのは、中世の住人は命のやり取りに実にためらいがないことです。
たとえば、立ち小便を笑ったことから抜刀しての斬り合いになり幾人か死ぬ。あるいは子供が有力大名の女中を載せた輿の行列について囃し立てたところ、供の侍がやおら童子を突き刺した。一方、刺された子供はと言えば「菖蒲刀(玩具の刀)でもあれば、不覚はとらなかったものを」と、血塗れの姿で行列を睨みつつ、周囲に訴えたといいます。どうも京の路上では、今からすると些細な理由で毎日のように殺し合いが起きていたようです。
現代人である私は中世人の感性の実際のところがわかりません。いとも簡単に人を打ち殺すにしても、その意図や行為の因果関係について想像の範囲でなんとか了解できます。しかしながら、すべてにわたって共感を覚えられはしません。
かと言って、まるで理解の外の他人事でもないと思うのは、与えられた恥辱を看過しない彼らの自尊心に注目すると、内心に疼くところがあるからです。身の内に感じる痛みを通じて、彼らの何に同調しているのか。そこを探っていけば、私たちの抱えている恐怖の正体を鮮明にする手がかりになる気がするのです。
与えられた屈辱に対して、暴力を辞さない姿勢は現代人にとってはあまりに過激です。言語によるコミュニケーションの価値が低すぎるのではないか。互いの言い分を聞き届ける余裕が持てないものかと思うでしょう。
しかし、もう少し分け入ってみると違った風景が見えてきます。彼らは笑うという行為の重み、人に向けて言葉を発することの取り換えの利かなさを我々以上に知っていたのかもしれません。沽券に関わることを言いながら、「誤解を招いたのだとしたら撤回したい」といった寝言は通用しない世界で生きていたのは間違いないでしょう。
中世人が誰かを笑って恥じ入らせることを存亡に関わる重大事とみなしたのは、「気に入らない」という気分の問題ではなく、その行為が他者に従属を求めることにつながると捉えたからではないでしょうか。子供であれ大人であれ日々全力で生きており、身分を問わず膝を屈することを肯んじ得ない。だからこそ年端もいかない子供が息も絶え絶えに己の不覚を口惜しんだわけです。
従うべき法や善し悪しはあるにしても、私のなすべきことがそれとは違う場合、自らの意の赴くところに従う。そんな強烈な生き方を古人はしていたようです。世間が、他人がどうあれ、己の命に代えても名誉を貫き通すという生き方が個人や自由、尊厳という概念のない時代の感性としてあったのではないでしょうか。
笑われることを恥と感じたならば、恥じらい臆病になるのではなく、すかさずそれを雪ぐべく行為に出る。そこに恐怖の入り込む隙間はありません。まして、笑われないようにと大人しくこじんまりと自己規制に勤しむという発想は皆無です。
かつてと今ではものの考えも常識もまるで異なります。「笑われて恥ずかしい」と思う感性においては多少なりとも共通しています。ただし、現代は中世のように恥辱に対して暴力で応えることは許されません。そのためでしょうか。報復されるという危機感がないがためか、笑う側は「辱めを与えるために笑う」を切迫感も覚悟もなく使っている節があります。そして、そこに共感を持たせようとしています。それがいじめであったり、「いじる」という笑いの手法であったりと、空気という名の支配のコミュニケーションのあり方として現れます。
それにしても共感という語は今どきの殺し文句のひとつで、コミュニケーション能力の重視とともに高まっています。コミュニケーションそれ自体はプロセスの連続なので、成功も失敗もないはずですが、日頃耳にする「コミュニケーション能力の高さ」という代物は、人間関係を円滑にするという結論ありきで語られがちです。しかも相手に寄り添う共感が強調される傾向にあります。
共感がゴールに設定されるというのは、かなり不可思議なことです。たとえば同じカレーを食べてもあなたは辛いと感じ、私は辛くないと感じる。感覚は人それぞれであるにもかかわらず、「このカレーは辛い」をゴールにし、そこに共感する手練手管をコミュニケーション能力だとすれば、それぞれの感性を殺すことを意味します。
私が「何をどう感じているか」を封じてまで共感しなくてはいけない他人の感性とは何でしょうか? そもそも他人の感覚はわかりはしないにもかかわらず。
共感が何をおいても大切なら、もはや私が私である必然性などありません。しかしながら私の感じることは私にとって不可欠であり切実であり、本来は他人からの共感は必要としないことです。
そうなると明らかになるのは、世間は共感を重視してはいても、本当は感覚的な共感ではなく、頭の同意を求めているのだということです。何への同意かと言えば、やはり「みんなと同じ」です。そのことでつかの間でも得られる安心感を満たそうとしているのでしょうか。
「みんなと同じ」に価値を置けば、私たちは差異を、他者性を認められません。私と異なる他者を認めないということは、つまりは私自身を認めないことにつながります。
なぜなら、それは「習慣や概念の中で作られた私」ではない、自分を否定することになるからです。私にとっての最初の他者は私の中にいます。私の思わぬ私が存在します。
私が誰かと出会い、言葉を交わし、何か通じあったと感じ、喜びを覚えるのはなぜでしょう。あなたの中にまだ見ぬ「私」を見出すからです。そして、私の中にいる「あなた」という名の他者を通じ、私はあなたと出会うのです。
私は目の前にいるあなたとは違う。同じではない。そして、「私の思う私」ではない私が自己のうちに存在します。みんなと同じことにしか価値を置けない世界では、その内なる他者の存在は生きながらえることはできません。
こんなにも自己肯定感の低い人が多いのは、常に私が私自身を殺しにかかっているからではないでしょうか。
けれども、誰があなたにその振る舞いが正しいと信じさせたのでしょう。そして、どうしてあなたはそれを受け入れてしまったのでしょうか。



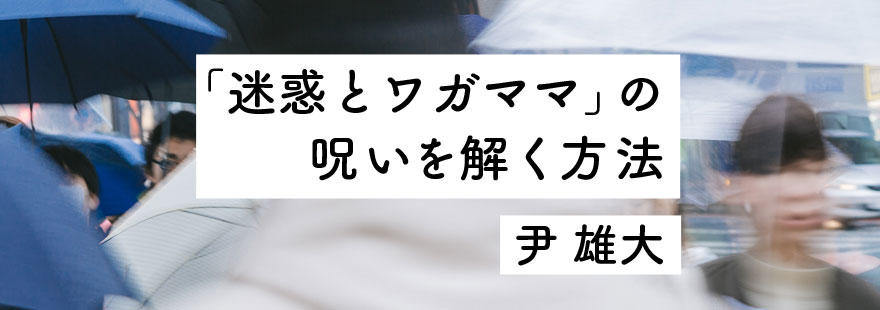



-thumb-800xauto-15803.jpg)


