第2回
「もれ」についてーー「直耕」としての食(1)
2020.03.22更新
生命の動詞、「洩る」
洩る、あるいは、漏る、という動詞のイメージは総じてネガティヴだ。
雨もりは典型的だろう。「ぽたっ」というあの音を聞けば、途端に家の中は大騒ぎだ。子どもが眉を潜めて「もれそう」と言ったとき、それが何であるかは問うまでもない。選考からもれると大会に出場できない。スポーツの世界での動詞「もれる」の縁起の悪さは、受験の世界での動詞「落ちる」に匹敵する。税金の申告もれはペナルティが課されたり、社会的制裁を受けたりする。タンカーからもれでた油は海洋汚染の元凶だ。リュックの中の水筒から水がもれているのを職場で発見した朝ほど、爽やかさからほど遠い朝はないだろう。秘密がもれるとその秘密を守っていた共同体はもはや復元不可能である。高速道路でのタイヤの空気もれは、天国への階段を登るのと同義と言ってよい。
いずれにしても、本来はしっかりと囲われていたり、包まれていたり、閉められていなければならないものが、何かの拍子に外へと出てしまうことを「もれる」と表現する。ネガティヴに聞こえるのも無理はないかもしれない。
ところが、江戸中期の思想家で医者であった安藤昌益は、1750年頃に刊行された『統道真伝』(以下、引用は、『安藤昌益全集 第十巻 統道真伝 人倫巻』農山漁村文化協会、1985年より。ページ数は全集のもので、旧仮名遣いは新仮名遣いに改めた)で、「洩るる」という言葉を生命の根源をあわらす言葉として頻繁に用いている。なんだかとってもポジティヴに響くのである。「食無き則ち人無し。故に食を思うは中真の
安永寿延『安藤昌益』(平凡社、1976年)や小林博行『食の思想ーー安藤昌益の思想』(以文社、1999年)でも詳細に論じられているとおり、安藤昌益は、医、農、食、性の四つの領域を貫く思想を編んだだけでなく、その思想を元に、耕すことなく民を支配する人間たち(
安藤昌益がどうして、この生命の根拠を、出る、生まれる、成ると言った動詞ではなく、わざわざ「洩るる」という動詞を使って説明したのか。安藤昌益について勉強を始めたばかりなので、あくまで不十分な読みに基づく推論にすぎないけれども、『統道真伝』の別の箇所で、権力者を痛烈に批判するこの動詞を用いている点を見逃すわけにはいかないだろう。「未だ交合せざる前に男の思発の神気、妻女に感通し、妻女の神、感通・応合し、暫くして誠成る交合を為し、動術暫くして精水出づ。故に精水洩れざる
人間的な感の通じ合いの果てに、どうしようもなく、地から何かが沸き起こって、それが自分の意志とは関係なく、自然の摂理に基づいて流れ出る、というイメージが「洩るる」という言葉に込められているようだ。
昌益の「土と内臓」論
しかも、昌益は、単に人間の生命の摂理を「洩るる」という動詞を元に描いただけではなかった。安永寿延は、安藤昌益が、人間の腸を活性化することと、土を活性化することをどちらも「
ただ、18世紀の『統道真伝』は、この「土と内臓」の世界をも、「もれ」の意味を深くつなげて論じてはいないように思える。他方で、21世紀の『土と内臓』はそこにこそ、土壌学や医学のまなざしを投じている。『土と内臓』によると、植物は、光合成で生じたブドウ糖を全部自分の生命維持のエネルギーに用いているのではなく、根を通じて、土壌中の微生物たちに分け与えている、という。つまり、もらしているのだ。さらに、動物の大腸も、微生物の居住環境を改善するために、腸壁から微生物が喜ぶエキスを洩らしている。安藤昌益が述べているように、農業とは人間が耕すのではなく、土壌中の微生物や空気や水などの自然が、植物がもらしたものに寄り集まって、生きものたちの死骸や抜け殻や糞を耕す。これを「直耕」という。同時に、食べものも人間の消化器官が吸収しているのではなく、消化器官を借りて微生物たちが腸壁から沁み出ているものにつられて集まり、生きものたちの死骸を「耕して」いるのである。
編集部からのお知らせ
ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台』Vol.2〜Vol.5に、藤原辰史さんによるこれまでの「縁食論」を掲載しています。ぜひ、お手にとってみてください。
*
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台「移住×仕事」号』藤原辰史が語る「食、戦争、そして」
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.2 革命前々夜号』縁食論(1)孤食と共食のあいだ
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.3「教育×地元」号』縁食論(2)弁当と給食の弁証法



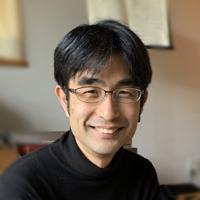


-thumb-800xauto-15803.jpg)


