第3回
パンデミックの孤独ーー「居心地のよい空間」をめぐる人文学(1)
2020.05.03更新
パンデミックが機能させないもの
いま、多くの人たちが外出の制限を続けている。「共に食べる」という行為が、家庭の中でしかできない。共食は、他の動物にはほとんど見られない行動である。しかも、人間は食べることを通じて、家族以外の人間とも関係を深めていく。つまり、人間が、動物でも植物でもなく人間である、ということを絶えず証明しつづける重要な機会のひとつを、私たちは停止している。「これが人間か」と自問しなければならないほどの悲しみや苛立たしさが、医療現場や介護現場で次々に抱かれているにもかかわらず。
話したり食べたりするのに必要な人間の諸器官は、ウイルスにとって「居心地のよい空間」にほかならない。口にせよ、鼻にせよ、舌にせよ、喉にせよ、それらの粘膜に覆われた諸器官を存分に利用して止まないレストランや居酒屋や給食や子ども食堂は、飛沫感染の恐れがあるため、やむをえず、店を閉めたり、中止したりせざるをえない。狭い部屋で口角泡を飛ばす研究会や会議は、ウイルスの増殖にとって最高のコンディションを提供する。ライブハウスにせよ、図書館にせよ、カフェにせよ、学生食堂にせよ、社員食堂にせよ、長居ができて、見知らぬ人と同じ空間にいても、大きな違和感もなく、おしゃべりや読書を楽しめる居心地のよい場所を、新型コロナウイルスの感染拡大は、もっとも危険な場所の一つに変えてしまった。結局のところ、文化は、ヴァーチャル世界よりも「三密」の空間の方が生まれやすいことを、「移動の制限」という犠牲を払って私たちは日々学んでいる。人間にとっていい場所はウイルスにとってもいい場所なのだ。
もちろん、普段はあまり一緒にご飯を食べない家族が一緒に食べるようになり、仲良くなったというニュースを見ることもある。残業で帰ってこなかった親が、家でご飯を作ったり、子どもの宿題を見たり、子どもを寝かしつけたりする機会も格段に増えているだろう。家庭の中で、家族が初めて本格的に機能している、という家も珍しくないと思う。これまでお飾りでしかなかったような台所が、ここにきてようやく家族の生命の土台という本来の機能を取り戻した事例もあるだろう。それは、これまでの働き方が異常であった証拠でもあるのだが。
ただし、喜んでばかりもいられない。家族以外の人と飲んだり食べたり笑ったりしながら、意見や情報やアイディアを交換したり、くつろいだりできる行為を、私は「個食」でも「共食」でもなく「縁食」と呼んできた。だが、「ステイホーム」の号令のもと、縁食は機能不全となった。「ホーム」に「ステイ」しにくい人、ホームに心地よさを感じない人、ホームが監獄でしかない人、ホームがそもそもない人、そんな人びとにとって、「ステイホーム」という命令形は、じつは、極めて深刻な事態をもたらしているのである。
シングルマザーの声が示す社会の脆弱性
4月20日付『西日本新聞』の御厨尚陽記者の記事は、こうした事態を考える上で、とても貴重なものである。この記事が報道しているのは、今回の災厄がひとり親世帯に直撃しているという事実だ。
御厨記者によると、北九州市の41歳のシングルマザーは、身体障害のある長男を新型コロナウイルスの蔓延の影響で施設に預けられなくなり、仕事を一時的にやめざるをえなくなった。元夫からは養育費をもらっておらず、借金もあり、「泣きながら市役所に駆け込んだ」。彼女は一日一食しか摂らないで、残りを子どもに回している。フードバンクは家族の生命線だ。
小学生の長男と保育園児の長女を持つ熊本市の34歳のシングルマザーは、「勤務先の飲食店から退職を促され、職を失った。ハローワークに通うが、次の仕事が見つからない。小学校の臨時休校で給食がなくなり食費もかさむ」。政府の1人10万円の現金給付は、「一時的には助かるが、仕事が見つからなければ生活を立て直せない」と不安を抱えている。
北九州市にあるNPO法人「フードバンク北九州ライフアゲイン」によると、食材を提供する生活困窮家庭の世帯数は3月に入って約3割増えたというし、この法人の理事長は、以前はお菓子の需要が多かったが、最近はコメを求める家庭が多い、という。お菓子ではなくコメを必要とする。これは何を意味するのかは、もはや書くまでもないだろう。
また、ウェッブ版の「現代ビジネス」には、FRaU編集部のシングルマザーへのアンケートが掲載されている。あしなが育英会の小学生保護者への質問であり、後世の歴史家が引用するに違いない、貴重な史料と言える。
子どもたちは学校で給食を食べられない。自宅の食費・光熱費がいつもよりかかると子どもに漏らすと、「子どもから『1日2食でも構わない』と返事がきました」という福井県のシングルマザーの声。「仕事ができなく収入が減って、食べるばかりの子達なのでお金がない。電気代水道ガス代がかかるからもう家族全員で路上生活するしかありません」と言う福島県のシングルマザーは、糖尿病を患っていて、感染したときの重症化のリスクを背負う。そのとき、子どもたちは取り残される。
症状が現れたときの恐怖は、尋常ではない。千葉県のシングルマザーはこう述べる。「不安で仕方ありません。この前熱が38度まで出たとき『私がコロナで隔離されて死んだら、娘はどうやっていまの生活を処理し、ひとりぼっちなのにどうやって、死んだあとのことをするのか』とそればかりで、生きた心地がしませんでした。熱があっても病院にも行かないで、トイレも這うようにして熱であえぐのに、困ったことを助けてという行き先もなく、娘に買い物をしてもらって泣いて布団にいるだけのみじめさを、国の議員さんになんかわからないと思います」。
北海道のシングルマザーは、仕事が休みになり、収入が減る中で、高校には入学のための諸経費を払わなければならないが払えないと訴える。政府には「生活費の支給を望みます。商品券ではなく現金を望みます」と要望する一方で「いくら頑張っても格差がうめられず」と漏らす。この言葉は、シングルマザーの苦境が、各々の自己責任ではほとんどなく、政府が(とりわけ小泉政権下で)労働者を保護する規制を緩めたこと、政府が再分配を失敗したせいであることが如実にあらわれている。
シングルマザーの言葉の有用性
こうした恐怖は、新型コロナウイルスが蔓延するずっと前から存在し、持続してきた。そして、それゆえに、シングルマザーの指摘は、凡百のコメンテーターの発言を凌駕する社会構築のヒントが詰まっていることである。
この点、やや迂回するけれども、上記のアンケートの記事に対する「コメント」からみていきたい。これは匿名であるだけ、日本人の「無意識」を示す貴重な歴史的史料である。
私もシングルマザーで子供を2人育てているけどこんな貧困ではない。まず東京に住むのをやめては?仕事を選ばず働けばいい。その年収なら非課税世帯のはずなので色々免除されたり、児童扶養手当も満額なはず。くれくれ、ばかりいってないでもっと自分でできることを探したら?
このコメントは、最も読まれていて、最も賛同が多い。ある程度の月収が確保されているシングルマザーからの発言であると思われる。苦労や努力を重ねてきたことも、十分に推測できる。だが、このコメントは自己責任論形式の繰り返しで、発言に根がきちんとついていないので、根源的な批判になりえてない。
その理由として第一に、そのコメントの主やその愛する人が、この災厄によって、あるいは災厄の始まるずっと前から、いつも同様の立場になりえたし、将来なりうることへの想像力を欠いている。言葉を交わし、それを残していく作業の中で重要な前提条件は、自分の未来が不安定でありうることへの想像力の確保であるというのに。
第二に、政府の給付金が個人ではなく世帯に振り込まれる政府のやり方にみられるように、家父長制的思考、つまり、家族の中の一致団結を前提として考える思考が、危機の時代にはとりわけ、まったく使いものにならないからである。今自分が歩いている道が唯一の道ではない、という冷静な自己認識もまた、公共空間で創造的な対話をしていく上で欠かせない資質である。
第三に、看護師にせよ、清掃員にせよ、スーパーの店員にせよ、「テレワーク」が不可能な仕事によって、テレワークが可能な仕事が保証されている事実を見逃すという論理の脆弱性を示しているからである。「仕事を選ばず働けばいい」という提案を、仕事を選ぶことができる人間からなされているとしたら、それは社会の仕組みを理解していない。職業選択の自由が憲法でうたわれるのは、身分制による職業の固定を打破してきた世界史の達成がある。それを制限するとすれば、職業選択の自由権の延長として存在する「営業の自由権」が貧困層を阻害してまで進めることを「公共の福祉」の名において制限することであろう(このあたりの問題については、円谷勝男「職業選択の自由権について」『東洋法学』37巻2号、1994年、から学んだ)。
だが、ここでは、まったく逆のことが考えられている。シングルマザーを身分的に固定した上で、這い上がれないのは個人の責任だと決め付けて、なおかつ「営業の自由」がシングルマザーに対する生命活動を阻害することをそのまま放っておく、という意見である。上記の「移動の自由の制限」の提案などからは、私などは身分制への回帰への衝動を感じさえする。「生活保護を受ける世帯」を差別する身分制である。「高みの見物」はしばしば自分自身の未来さえ見失うほど論理が破綻することがあり、やはりまったく役に立たない。言葉を交わす上で重要な前提条件は、自分の存在条件を自分であるとしかみない視野狭窄を廃棄することである。
第四に、誰がどの権限で、東京から別の地域に移動して、そこで職を見つけて働けと言えるのか、ということである。政府が、働く場所を確保できているならば、たとえば、労働力不足が危ぶまれる農山漁村で働く場所をきちんと確保した上であれば、まだ、少しはこのような発言から批判的に政策を考えていく可能性もあるかもしれない。しかし、これだけ、移動中の感染リスクや引越先での生活のリスクが明らかになっている上に、仕事の場所も確保されていないことを無視して、「東京に住むのをやめては」と提案するのは、「生きるな」と宣告しているのと変わらない。
新型コロナウイルスは、よく言われるように「平等なウイルス」ではけっしてない。社会や政治という現象を消し去った真空状態ならば平等かもしれない。しかし、人間はそんな、摩擦のない世界を生きていけない。人間は、住んでいる場所や働いている場所、住んでいる環境によって免疫力も、ウイルスの居心地のよさも異なる。たとえ感染しなくても、感染症とは、経済活動の停止によって、体や心が弱っている人びとや弱りやすい経済状況にある人びとから、為政者は切っていく。新型コロナウイルスは、人間を平等にするのではなく、不平等をより拡大していく災厄にほかならない。
このような「高みの見物」が提出する論点の凡庸さに対し、これらシングルマザーたちの発言は、歴史学的に重要な論点を提出しているという点で、思考に役立つ。自己責任論にあるように厳しい社会をどのように乗り越えるべきか、という論点ではなく、どういう社会が生きやすいか、という論点にほかならない。彼女たちにとって、子ども食堂やフードバンクの試みや給食という制度は、子どもたちを成長させるためだけではなく、子どもたちに「二食でいいよ」という気遣いをさせない、子どもに買いものをさせる罪悪感を母親たちに感じさせない、急病に襲われてもひとまず子どもたちが食べていける場所があると考えることができてあの罪悪感を感じなくて済む、という意味において、子どもだけでなく親たちの精神的な「居心地のよさ」を作っていたことを意味する。
それが意味するのはつまり、公的な支援をしてもらっても罪悪感が沸き起こらない社会設計のあり方の基本である。
私のまわりにもひとり親はたくさんいるが、私に漏らす不満の一つは、どこかに異議申し立てをしたとき「なめられやすい」ということである。とりわけ、女性が一人であることに対して優位性を示すことがよくあるという。差別意識と発言者の思考の浅薄さを露骨に晒されることが多い。とともに、それと並んで鬱陶しいのが、イニシエーションのような行政の制度設計だ、ということを聞いたのも一度や二度ではない。ひとり親であることによって、ちょうど障害者がそうであるように、居心地のよい市民生活を送るために、いちいちイニシエーションのような手続きを踏まされ、ありがたさを感じなさい、と言わんばかりのメッセージが陰に陽に伝えられることである。ほからならぬ、経済格差を放置してきたはずの中央政府や地方政府が、こうしたイニシエーションを準備するのである。
子どもたちに「一日二食でいいよ」とその親に言わせる社会は端的に言って失敗である。なんの手続きも踏ませずに、普通に食にアクセスできるような社会、生命維持物資の提供に対し「ありがとう」という見返しを求めない社会の設計もまた、その生命維持物資の生産や消費にも増して重要だと考える。つまり、「居心地のよさ」である。
編集部からのお知らせ
「パンデミックを生きる構え」イベント動画 期間限定配信中(4/30〜5/10)
4/25(土)に配信された「パンデミックを生きる指針」動画視聴チケットを販売しています (動画では「パンデミックを生きる構え」にタイトルを変更しました) 。今こそききたい藤原辰史さんのお話を期間限定配信します!
出演:藤原辰史(京大准教授)、鈴木潤(メリーゴーランド)、三島邦弘(ミシマ社)



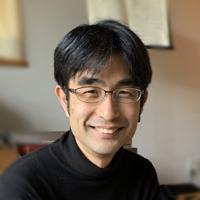


-thumb-800xauto-15803.jpg)


