第1回
飲み込まされる言葉と飲み込める食べもの ーー『ポースケ』に寄せて(後編)
2020.01.17更新
3 ヨシカの場合
ヨシカは、店を持つ前、27歳のときに食品メーカーを辞めている。同期は女子が二人だけ。その一人は「愛想がよく、かわいらしいタイプ」だったので、ヨシカは「女扱い」されなかった。それは彼女には「他人の心の襞の世話をせずにすむ分、気楽だ」った。だが、その同期が「道端の猫に気が向いたら構うみたいにオチのないことを話かけられるのがもう嫌」という理由で辞めていった。そのあとヨシカはますます孤立を深めていく。
職場や大学や自宅で男たちが女たちに向ける「品定め」や「慰安」の視線は、津村作品でよく登場するが、津村はその事実よりは、その視線がデフォルトとして職場で女性に飲み込まされている事実の方を問題にしているようにわたしには思える。
そんな職場でヨシカを食事に誘っていろいろ話を聞いてくれるのが、職場で唯一の役職つきの女性である篠宮さんだった。じつは、この篠宮さんにまつわる小さな物語が、このカフェの創世記になっている。
篠宮さんはある日、雨の日の仕事の帰りに転倒して亡くなる。ヨシカは死後一週間ほど立って、朝の通勤電車で涙が止まらなくなる。配偶者が居るかさえ知らないほど、そんなに親しい関係ではなかったのに。
ヨシカは、彼女の夫から食事会に呼ばれる。彼は、生前の妻との会話から親しかったと思われる人たちに声をかけたらしい。ヨシカは会社では唯一の人間だった。この食事会でヨシカは不思議な体験をする。
食事会では、野菜炒めと生春巻き、回鍋肉、中華粥などが振舞われた。篠宮さんの旦那さんの料理は、おいしかった。旦那さんがそれほど気落ちした様子を見せなかったせいか、食事は終始和やかな、篠宮さんの思い出話に終わった。[......]
篠宮さんは亡くなったのに、楽しいとすら思いながら食事をしていることを、ヨシカは不思議に思った。まずかったり、妙にストイックだったりする食事なら、もっと違っていたかもしれないけれども、篠宮さんの旦那さんが出したものは、味付けが濃くて、器になみなみと盛り付けられていて、単純なおいしさのあるものばかりだった。それこそ、泣いていて舌が固まっていても味がわかってしまうような。(247-248頁)
ヨシカは、このときの感情が夜に思い出すと寝られなくなるほど、心に残る。無視され続ける職場を辞めて、自分で「食事ができる店」を開きたいと考えるようになる。篠宮さんの夫の料理から、カフェ開店までの心の動きはここではあまり詳しく書かれない。だが、それは物語の初めのほうでヨシカが語るこんな感慨の中にひっそりと書かれてある。
何か口に入れるものを傍に置きながら、誰かの薄い気配を感じつつ、一人で何も考えずにじっとできる、という状況は、意識的に作り出さないと存在しにくいものなのかもしれない、とヨシカは思う。かつ、もし店にいる時に災害があったら、それなりに助け合えるような客層であること、そういうふうに呼びかけられる店の人間がいること。人は難しい。一人になりたいといつも思っているけど、完全に放っておかれるとかまわれたいと思う。(17頁)
私は、このような食のあり方を縁食と名付け論じてきた。縁があって、人々が集う場所であり、縁がない場所に縁が芽生える場所である。ものを口に含みながら、「薄い気配」を感じられる空間である。
さらに、「災害」という言葉には立ち止まらざるをえない。『ポースケ』は、東日本大震災からわずか二年弱で刊行されている。このことはあとがきでも明示されていないけれども、この作品を読み解くうえで欠かすことのできない事実だろう。災害があったら、というヨシカの想定は唐突ではない。どんな言いたいことも飲み込むような権威的人間関係は、統率は取れているだろうが、柔軟な対応を毎秒にように要求するような災害時には脆い。かといって、誰もがお互いの距離感を考えず、言いたい放題になるのも、とりわけ災害時には危うい。
それぞれの弱点はやや棚上げしつつ、メリットを最大限引き出すような防災思想のようなものを、カフェの店主のヨシカがある意味で政治家よりも的確に考えているのは、偶然ではない。カフェは、その場に居る人間が食べものや飲みものを飲み込んで明日まで生きようとすることが、言葉を飲み込んで支配を受けることよりも、原則として優先される場所だからである。
4 ポースケーー縁食の祭り
さて、本書のタイトルであるポースケとは、ノルウェーの復活祭の意味らしい、と本書には書いてある。ヨシカは、ポースケという名前のバザー兼食事会をカフェでやろうと考え、それがこの物語の最終章である。小さな、地味な、ささやかな、そんな形容詞ばかりしか思いつかないお祭りが、「食事・喫茶 ハタナカ」の物語のクライマックスになる。
面白いのは、僅差で他人より抜けていると思われるそれぞれの特質を、それぞれが持ち寄ってくる、ということだ。ナガセは、習いたての弾き語りを遠慮がちに披露する。友人のヨシカには驚きの一面だ。ナガセにピアノを教えている冬美先生は異星の生物の生殖行動を描いた『愛はさだめ、さだめは死』というSF小説の一節、たとえば「母さんはやつを裂いて、食っている」とか、かなり18禁的なところを楽しげに朗読している。海外ドラマが好きな50代の主婦とき子さんは、刑事ドラマのマニアックな情報を書いたフリーペーパーを作る。恵奈は学校で育てた苺を使って宇宙食であるドライ苺を持ってくる。恵奈の母親のりつ子は、かやくごはんのおにぎり。この親子も、『ポトスライムの舟』の主要人物でもあった。料理がまったくできなかった31歳のゆきえは、元彼のストーカーから逃げ切り、新しい彼氏と同居を始めたのだが、自家製のキッシュを焼いて持ってくる。キッシュの野菜の切り方は雑なのだが、けっこう美味しい、とヨシカは味見する。佳枝は、得意の語学力でお客の翻訳の質問に答えている。
夕食は、ステーキと目玉焼きである。「死刑囚最後のごはん」というコンセプト。しかし、死ぬためではもちろんない。「食べて、端的に、明日の活力になりそうなイメージのもの」である。「善良な小市民である自分たちは、それを食べて明日も生きるのだ」(272頁)。
共食とは、祭事に神様に捧げた料理を共同体の構成員で食べる行為のことである。だから、祭りと深い関係にある。では、縁食はどうだろう。縁食にはどんな祭りがふさわしいのだろうか。そんなことを私は考えたことがなかったが、おそらく大きな力をもった霊験あらたかな神様の祭りではない。
ヨシカは、「ポースケ」に惹かれ始めていたときに、夕食を御馳走してあげた恵奈に「お祭りってどんなイメージがあります?」と聞く。最初、「おみこし」と言ったあと、「それか、バザーですかね」と補う。学校の学芸会のバザーで、そよ乃さんが母親のりつ子の代わりにししゅうの膝掛けを作ったと、恵奈は答える。
バザーの原語であるバザールとは、ペルシャ語で「市場」を意味する。普通は屋根付きで歩廊式の建物内に店や工房が立ち並ぶような雑多な空間である。いろいろな商品が所狭しと並び、いろいろな人が行き交う。それが転じて、日本ではフリーマーケットのようなものも意味する。ポースケは、もっとその先端を行く。お金のみならず、ものと行為が交換がされる。交換の祭りだ。
SF小説の朗読、キッシュ、スコーン、フェルトの置きもの、刑事ドラマのフリーペーパー、古本、ハンガリアンウォーター、ドライイチゴなど、いろいろなものが行き交う中で、行為も行き交う。それは、お手伝い、経済学の用語でいえば「労働力」である。
フリーペーパーを折る作業、ハンガリアンウォーターの容器にリボンを巻く作業、お茶のおかわり。いろいろな労働力が自然に、何か嫌なことを飲み込むことなく、提供されていく。自然発生的に始まったのが、語学勉強が趣味で、睡眠障害を克服しつつある竹井佳枝の翻訳サービスだ。エコバック、カバン、Tシャツ、文具、洋菓子の箱、アルゼンチンのサッカー選手の移籍記事、イランでお世話になった家族からのプレゼントである絨毯に挟まっていた紙切れ、など、機械翻訳で訳しても意味のわからないものを訳していく。
この自然に湧き上がるささやかなお手伝い、あるいは小さなおせっかいの嵐こそ、私は、縁食が大地から召喚するものであり、その祝祭がポースケであると思う。
5 別れ
佳枝は、ポースケのあとしばらくしてカフェのパートをやめることになっている。小学生向けの学習塾の代用教員が特急で15分ほどかかる場所で見つかったからだ。その後の佳枝については、この小説の中では描かれないけれども、ヨシカと佳枝の別れがこのあとに待っていると想像すると、少しだけジンとくる。もちろん作者は、抱きあって涙流してわかれるシーンは描かないだろうとは思う。たぶん、ちょっと声をかけて、淡々と握手をするくらいだろう。別れとは、物理的には分岐でしかない。別れと出会いの頻発は、宿木でしかないカフェの宿命である。
永続を目的とする人間集団は、それがいきすぎると生贄なり、排除される人間が必要となるが、ヨシカのカフェは、包摂と排除を意識しなくてもよい。カフェの原理は、無理に飲み込ませないこと。自然に飲み込んでもらうこと。自分が属する人間集団に無理やり何かを飲み込まされつづけている人びとが、じっくりと、やんわりと飲みものばかりでなく食べものまでも飲み込むことができる場所なのである。そして、食べものの嚥下に慣れたその喉に、たまたま飲み込みやすい言葉が通るアヴェレージが結構高い場所こそが、「食事・喫茶 ハタナカ」であり、縁食の場所なのだ。おそらく、そんなおいしい言葉しか、品定めの視線に網羅された社会を変えることはできない。
編集部からのお知らせ
ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台』Vol.2〜Vol.5に、藤原辰史さんによるこれまでの「縁食論」を掲載しています。ぜひ、お手にとってみてください。
*
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台「移住×仕事」号』藤原辰史が語る「食、戦争、そして」
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.2 革命前々夜号』縁食論(1)孤食と共食のあいだ
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.3「教育×地元」号』縁食論(2)弁当と給食の弁証法



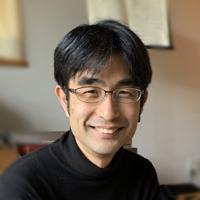




-thumb-800xauto-15803.jpg)
