第1回
飲み込まされる言葉と飲み込める食べもの ーー『ポースケ』に寄せて(前編)
2020.01.16更新
1 言葉を飲み込む
津村記久子の『ポースケ』(2013年)という小説は、人間が主役ではない、と思った。主役はきっと小説の舞台、つまり、奈良の商店街のカフェ「食事・喫茶 ハタナカ」ではないか、というのが私の読後感である。
たしかに、この喫茶店の主人である「ヨシカ」や、彼女の友人の「ナガセ」など、『ポトスライムの舟』(2009年)の作中人物たちが再登場を果たしていることは、津村ファンにはたまらない。パワハラのトラウマから睡眠障害に悩み、電車に乗ることができない「竹井さん」は津村作品でたぶん初登場だが、主人公と言ってもなんら違和感のないくらいの存在感をこのカフェに放っている。
けれども、この小説の語り手がそれぞれの個性際立つ人間を描きながらも、それと同じぐらい細やかに表現しているのが、このカフェのふところの深さである。ここでは、それぞれ絶対に傷つけあわない程度の距離感を保ちつつ、疲れない程度に気を遣いあい、衝突しない程度に言葉を交わし合う女性たちや男性たちが、なんとか「居る」ことができる。じつは、ヨシカのカフェは、『ポトスライムの舟』でも繰り返し言及されていて、後景の役割に甘んじていたのだが、今回は前景化されている。なんとか居ることができる、ということをことさら強調するのは、作中人物たちが抱えている各々の問題は、それなりに深刻だからである。娘が就活で苦しんでいる。元彼のストーカーにつけられている。子どもが欲しいのに子どもができない。職場に適応できずにやめる......。
ふところが深いカフェ、というのはちょっと変な言い方かもしれないが、この作品にはあっているような気がする。社会に適応しづらい人間たちの存在を認めて、居させるそのふところの深さ、という感じだろうか。とにかく、食べるものではなく、食べる場所、もっといえば、その場所をめぐる人間たちの浅かったり深かったりする交流や接触が描かれている。このこと自体、子ども食堂が多くの子どもや大人の居場所を提供している昨今、興味がそそられる。そうした背景から、わたしは、『ポースケ』について一度じっくり取り組んでみたい、と前から思っていたのだった。
ところで、津村記久子の作品には、言いたいことを言葉にして頭に描いたあとに飲み込む場面が少なくない。職場や家庭内での身体的ないしは肉体的な持続的暴力に傷つき続ける女性たちの姿は、津村作品に繰り返し登場する原型である。暴力の担い手である人たちの前で、受け手である作中人物たちは、言葉をゴクリと飲み込む、いや、飲み込まざるをえない空気を前提にして過ごす。力の流れが一方向に傾く空気は、『ポースケ』の作中人物たちがそれぞれ自己のオフィシャルな領域で苦しめられてきた空気でもある。言ってしまうとその場がしらけたり、罵り合いに発展したり、殴り合いになったりしそうなその寸前で止めて、飲み込む。そういえば、私たちは毎日ご飯と同じくらい言葉を飲み込んでいるかもしれない、と読者は思わされるかもしれない。
この喫茶店は、公共空間というにはクローズドで親密空間というにはオープンである。なので、客も店員も、それなりに気を遣いあってはいるが、言いたいことをグッとこらえる、ということはあまりない。しかも言葉を飲み込んだとしても、上記のような暴力の受け手として抵抗の言葉を飲み込んできた人にとって、けっして辛い「飲み込み」ではない。逆に、ぽろっと漏れでた独り言のようなささいな言葉の屑が、サラッと見ず知らずの人に拾われやすい空間にもなっている。いわば、抵抗になりきれなかった言葉屑だ。言葉屑は、オフィシャルな場所では、有効に働かず、飲み込まれたり、独り言として片付けられたりするが、このカフェのような場所では、言わずとも床に落とすことはできる。しかも、この場所で人びとが飲み込むものは、主として、言葉ではなく、ダージリンであったり、コーヒーであったり、チャイであったり、あるいは、湯気がもくもくとたつ色とりどりのランチメニューであったりする。「大きめに握った鮭とごま、塩と海苔のおにぎりと、ほうれん草のおひたし、かぶの漬け物、豚ばらの生姜炒め」(8頁)なんていうメニューの選び方は、あとがきに書かれてあるような作者の入念なカフェ調査の上で成り立つのだが、それにしても、そういうカフェにぴったりなメニューであるうえに、空腹の読者泣かせの描写力である。
2 佳枝の場合ーー睡眠障害者の居場所
竹井佳枝は、昼間から眠くなる睡眠障害に悩まされている。公共交通機関にも乗ることができない。それを心配した母親が、自宅から徒歩2分にある「喫茶・食事 ハタナカ」の主人、ヨシカに頼みこんで、7時から14時という時間帯で働かせてもらうことになった。それでも、帰宅の2分のあいだに商店街のゴミ箱に倒れ込んで寝てしまうほど重症だ。この奇病に対し「ハタナカ」がどう向き合うか。これが、この小説の見せ場の一つである。
睡眠障害のきっかけは、職場の上司のパワハラであった。職場の夢を見てしまうかもしれない、という恐怖心が夜の安眠を妨げるのである。同族企業の会社役員の秘書になった佳枝は、一日中ふんぞり返って何もしない役員から悪口を言われ続けた。日本で大きな地震があった週明けの月曜日には、「椅子に座る姿勢が悪い、だから血行が悪くなって冷え、頻繁にトイレに行きたくなるのだ」と佳枝を謗った。言い返すことをせず、趣味で学んでいたドイツ語で「彼が人を悪く扱うのは、自分に自信がないからです」と書いて、不満を飲み込む。上司はドイツ語は読めない、と佳枝は思っているからだ。その佳枝にとってヨシカの喫茶店はこんな感じであった。「このまま、あらゆる人間関係に深入りせず、永遠に「誰かの好きな店」の目立たない店員でいたいと思う」(96頁)。深入りしなくても居させてくれる、つまり飲み込みたくないものは無理に飲み込まなくてもいい場所は、いまの社会に切望されている気がすると思う。
ヨシカと佳枝との関係も、あっさりしたものである。開店の前にヨシカは佳枝にコーヒーを入れる。
二人は厨房の隅に置いてある椅子に座り、無言で飲む。最初の頃は、少しは雑談をしたかもしれないが、今は、特に開店前のこの時間は、まったく口をきかない。ヨシカさんは、生来が無口でもおしゃべりだというわけでもなく、相手によってよく喋ったりぜんぜん話さなかったりする人のようだった。佳枝も、会社員だった頃はけっこういろいろ話す人間だったような気がするのだが、家に引きこもるようになってから口数がかなり減った。いずれにしろ、無理に話題を見つけなくていいのはいいことで、かといって、勤務時間全体においてまったく会話がないわけでもないので、佳枝は楽だった。(101頁)
とっても仲の良い友人でも、かといってアカの他人でもない、この関係性の静けさと、放っておかれるぞんざいさと、交わす言葉の抑制が、じつのところ、この小説の言語交通の道路交通法になっている。ここはガッチガチの共同体ではない。一体感を求める同質化の圧力がとても少ない。ただ、店員として、あるいは客として居るにすぎない。会社に居るように、無理に口角をあげなくてもよい。家以外で口角の筋肉を休ませること。こんな場所の確保は実は難しい。
このファジーさゆえに、佳枝がこの睡眠障害を克服するきっかけも、半ば強引に転がり込んでくる。彼女にはやや苦手なお喋り好きの客で、神戸の有閑マダムのそよ乃は、佳枝の壊れたメガネを直すために、電車に乗れない佳枝を無理やり自分の車に詰め込んで、店まで向かってしまうのである。その強引さに呆気にとられ、いつの間にか修理が終わったと思いきや、そよ乃は息子の怪我を携帯で知って急いで帰ってしまう。残された佳枝は電車で帰らざるをえなくなるのだが、その突然降って湧いた試練に試される中で、不思議と佳枝は会社の重い過去を払拭し始めていくのである。そよ乃もやはり『ポトスライムの舟』でヨシカとナガセの大学時代の友人として登場していて、とりわけヨシカとはあまりウマのあう関係ではない既婚女性として描かれていた。
自分の魂を鍛え、キャリアアップをし、社会に貢献するという自立した近代市民モデルではなく、不完全であることを前提に同質化圧力の弱い場所に漂い、偶然性に身を任せ、お互いにある部分を依存しあいながら、乗り越えられそうだったらチャレンジしてみて、無理だったら投げる。場合によっては投げたものを誰かが拾う。誰か、とは、自分のやや苦手な人物である可能性もある。強い心を持ち、チャレンジ精神をいつも忘れない「近代市民」からすれば、なんとも情けない受け身の乗り越え方かもしれないが、自立的発展に疲れた人間には、この偶発的展開は、それほど負担がない合理的選択なのかもしれない。
編集部からのお知らせ
ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台』Vol.2〜Vol.5に、藤原辰史さんによるこれまでの「縁食論」を掲載しています。ぜひ、お手にとってみてください。
*
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台「移住×仕事」号』藤原辰史が語る「食、戦争、そして」
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.2 革命前々夜号』縁食論(1)孤食と共食のあいだ
◉ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.3「教育×地元」号』縁食論(2)弁当と給食の弁証法



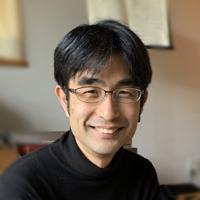




-thumb-800xauto-15803.jpg)
