第7回
縁食論後縁録
2021.02.21更新
1 本も修行する
本は、本屋に並んだ瞬間に著者の手を離れる、という摂理に最近疑いを抱くようになった。たとえば、二〇一八年一一月に上梓した『給食の歴史』と、昨年一一月に上梓した『縁食論』についてはなかなか我が手を離れてくれない。前者については、全国の給食関係者との交流が増え、たびたび現場からの厳しい問いの前に立たされる。後者の場合も刊行早々、新しい食のかたちに関心のある人々からの反応をいただき、縁食空間の夢を持っています、すでにやっています、という実践者たちからの切実なお便りもひっきりなしに届く。
『縁食論』で私は、孤食でも共食でもない、食を通じた賑やかで緩やかな集いのかたちを「縁食」と呼び、その可能性を歴史と理論とフィールドワークで得た知見をもとに書いた。読者から共感するが、ではどうすれば良いのか、こんなに外食が難しい時期に、という実践的な問いが次々に強襲したことで、私は軽い「産後ブルー」に陥った。
ここでは、『縁食論』刊行後数ヶ月で届いたコメントを具体的に検討しながら、『縁食論』という「実験書」がどのように他流試合をし、どのような批判を受け、どのように答えてきたのかの中間報告をしたい。修行は死ぬまで終わらないのは人間だけでない。本だって修行を続けるのだ。本は、それぞれの読者の心の中で、色々な経路を通って受容されるものだから、「完成」はあり得ない。本の修行は、著者が死んだあとも永遠に続くのである。
以下、縁食論の後縁、つまり刊行後にいただいた、さまざまなご縁について記録しておきたい。
2 「あげる」と「もらう」を超えて
昨年の一二月三日に、ミシマ社で企画された松村圭一郎さんとの『縁食論』をめぐるオンライン対談は、松村さんの事前の準備も万端で、その思考から松村さんが捻り出したコメントは深く、鋭く、心に刺さった。〈藤原辰史×松村圭一郎対談「縁食から世界を変える」のアーカイブ動画が現在配信販売です(2/28まで)〉
そのうちで最も返答が難しかったのは、無償贈与の難点を指摘されたときである。
『縁食論』では、ベイシックインカムを補うものとしてベイシックフード、すなわち食の無償化の可能性を論じた。ベースとなる食べものを商品化から外すことで、貧困問題も食品ロスの問題も飢餓の問題も同時に解決へと向かうことができると思ったからだ。
しかし、松村さんは、無償化された食べものを何も払わずに食べることで、果たして縁食のもたらす人間たちのふれあいは成り立つだろうか、と私に問うた。どんな人も、おそらく、無償でものを食べるだけで終わるのではなく、何らかのお返しや貢献をしたいはずだ。お金も払いたいかもしれない。一方的な贈与には限界がある。これを組み込んだ縁食はあり得ないのか。
私は、金銭が絡むことで大資本が縁食空間に入り込むことを恐れていたから、地域通貨を縁食に絡ませるのはどうだろうか、と述べた。ちょうど新聞で、飲み屋で大人たちが子ども食堂のためのチケットを買って、壁に貼り付けておくという記事を読んだばかりだったからである。開店までの飲み屋は、子ども食堂として機能しているのである。
とともに、縁食の場所でご飯を食べにきた人たちが、単に善意を受け取るだけではなく、なんらかのかたちでその空間に貢献をする設計も必要ではないか、と松村さんは指摘したし、私もそう考えた。とっさに、イタリアのボローニャで、ホームレスの演劇団があって、それを市民が見に行く、という話を思い出した。「あげる」と「もらう」。この二項対立に還元されると縁食は固定化し、「あげた人」と「もらった人」というレッテルが貼られてしまう。関係性を固着させない空間設計こそが、縁食を強靭にしていくだろう。これは建築家の課題だと私は光嶋裕介さんとのMSライブ(二月一二日)で伝えたように、食に限らず、スティグマを与えられなくてもよい空間づくりは、今後の建築の大きな課題と私は考えている。〈光嶋裕介×藤原辰史対談「『あいだ』のつくり方、ひらき方」が現在配信販売中です(3/12まで)〉
3 震災の縁食
今年の二月九日に、大阪駅の近くで『縁食論』の読書会に参加した。朝日カルチャーセンターの企画だった。当日はゲスト二名とスタッフ三名に私を入れて五名の会だったが、それだけいっそう議論は深まった。
参加者のひとりであるフリージャーナリストの粟野仁雄さんは、縁食論の感想としてこんなことを述べた。
『縁食論』で書かれた食の無償化に、違和感はない。阪神・淡路大震災のとき、取材に入ったが、当然泊まる場所もない。すると、避難所の一角を被災者たちが空けてくれ、そこに寝泊まりをすることになった。避難所で自転車を借りて、朝から晩まで神戸を右往左往した。今思うと不思議なのだが、取材中自分は一度も食べものにお金を払わなかった。どこへ取材に行っても広場で炊き出しをしていて、たとえその避難所の人間でなくても、食べものを譲ってくれた。余るほど作られているからだ。さらに、レストランのコックのようなプロも避難生活者には多かったので、料理もとてもおいしかった----。
私は、粟野さんの取材話を聞いて、災害時の縁食についてもっと書けばよかったと反省するとともに、ご飯を他人と共有しにくい平常と、ご飯を他人と共有しやすい非日常、どちらが人間的だろうか、ということを考えた。災害は、眠っていたケアの感情を再燃させる。利他的でなければお互いに生きていけないから。本来的な食を通じた縁の結び方を、そして、人間同士のケアのあり方を、避難所は教えてくれる。それと、マンションの隣人と挨拶しない在り方と、どちらが居心地よい在り方なのか。かなり根源的な問いを災害列島は私たちに突きつけていると思う。
4 「子ども」という言葉の罠
2月に刊行された『中央公論』の企画で斎藤幸平さんとオンラインで対談したとき、私は斎藤さんから事前にメールで『縁食論』の感想をいただいたことに触れた。メールで斎藤さんはこんな批判をしてくれた。子ども食堂が必要なのは子どもだけではない。大人がきちんと食べられることが重要なのに、大人だと世論の支持が得られないから「子ども」と名乗っている点もあるのではないか、という批判だった。
年末年始に「大人食堂」がメディアで話題になったように、食べることや関係を作ることが困難な人びとが、大人食堂にやってきてご飯を食べた。日本社会では結構な大人たちが食うことに困り、仕事の少ない年末年始にはおせち料理にありつけない。本当は大人食堂に子どもが来るべきである。ところが、大人食堂についての理解は子ども食堂ほど深まらない。なぜ、お母さんやお父さんが朝、仕事の前に子どもと一緒に、街角の食堂に訪れ、朝飯を済ませられないのだろうか。いわば「自己責任論」は今もなお蔓延している。
「子ども」といえば人びとに支持されやすいから、という発想は危険である。実際に全国の子ども食堂には大人もたくさん訪れているし、大人のスタッフもそこに生きがいを見出すことも少なくない。そもそも子ども食堂の理念は、子どもの貧困の深刻化への対応だけではなく、コミュニティづくりでもあった。最終的には「子ども食堂」から誰でも入れる「公衆食堂」へと移行していくことが、本来的に望ましいだろう。
5 独食の可能性
『朝日新聞』の元旦の企画で、「孤独のグルメ」の主人公を演じる松重豊さんと対談をした。松重さんは、『給食の歴史』『食べるとはどういうことか』に加え、『縁食論』を読んできてくださった。そのときに松重さんが披露した概念が、「独食」である。「孤食」は一人で食べて孤立しているが、「独食」は一人で食べても孤立していない。キッチンに立つ料理人と、フロアに立つアルバイトと、同じ空間で食事をしている別の客と、会話は少なくても、空気を共有している。その中で、一人黙々と食べることの充実もあるのではないか。そういう問いかけであった。
「孤食」と「独食」を分けて論じる、という発想は私にはなかったが、たしかに、一人でも孤立していないで食べる場所としての設計も必要ではないかと考えた。無理に話しかけたり、話しかけられなくても、他者たちの無数の視線が漂う空間で、一人で料理と向き合える場所。一人の時間を心の充実とともに過ごせる場所。一人でいることが好きなことが、「友達がいない」「愛想がないやつ」と同義にされてしまう学校の息苦しさはたしかに危険である。他方で、「ぼっち食」と言われたくなくて、トイレで食事をすることについても、もっとその人の感覚に寄り添って考えてみたいと思うようになった。
6 人はパンのみにて生くるにあらず
イエス・キリストが『縁食論』を読んだという報告はまだ届いていないが、もしもキリストが批判するとすれば、「人はパンのみにいて生くるにあらず」と答えるのかもしれないと予想している。パンだけではなく、信仰に代表されるような精神の糧を得ることがなければ、生きているとは言い難いという指摘である。
これに対しては、すでにルートヴィヒ・フォイエルバッハが「人は、食べるところのものである」と、イエスの向こうを張っている。
「生命の糧」と「精神の糧」。
そこで私が考えたのは、公衆食堂を組み込んだ公衆図書館である。本を借りに来ることは、老若男女、貧富を問わず、誰もが遠慮なくできる行為である。本を借りに来る人と、ご飯を食べに来る人が交わる空間。
そういえば、『北海道新聞』の書評で平川克美さんが「公衆浴場」つまり、銭湯で風呂に入り、「カフェ」で仕事をするという生活をしていると書いていた。この渡り歩く感じが、縁食空間に似合うかもしれない。
7 まとめ
『東京新聞』の書評で玄田有史さんは「自助でも共助でも公助でもない縁助だ」と縁食のあり方を評した。「縁助」とは思いもつかなかった概念で、関係性がどうしても固定化されてしまう「援助」「支援」「援護」よりも「縁助」「支縁」「縁護」の方が、隙間が生じて、風通しが良いかもしれないと思った。
中央集権による規制緩和路線と合理化路線が新型コロナウイルスのテストに耐えられなかった以上、自治の見直しが今後進んでいくだろう。自治といってもそれは都道府県の規模の自治ではない。もっと小さなサイズの地方自治だ。食べもの、水、広場、森などの市場に馴染みにくいものを共用できる場所。そこで、縁食は縁助へとゆるやかに接続していくだろう。
編集部からのお知らせ
【3/1(月)】ちゃぶ台編集室 第2回 藤原辰史×伊藤亜紗対談「『ふれる、もれる』社会をどうつくる?」開催します!

<出演> 藤原辰史、伊藤亜紗
<開催日時> 2021年3月1日(月)19:00~20:30(途中休憩5分あり)
※イベント翌日に1ヶ月間視聴できるアーカイブ動画をお送りします。
『ちゃぶ台6』の対談「分解とアナキズム」において、藤原さんは著書『分解の哲学』を「生産と消費の二項対立への批判として書きました」と語られています。分解に携わる微生物たちは、ある目的のために統一されて頑張っているわけではない。世界の見方を地中からひっくり返すことで、違う景色が見えるのではないか、というお話もありました。
一方、伊藤さんは「みんなのミシマガジン」での往復書簡連載のなかで、「利他は、『自分がする行為の結果は自分には分からない』ということから始まるのではないか」と書かれています。人が生きて死んでゆく過程を、分解という生命全体の営みから考えれば、結果や目的から離れた「利他」を考えることもできるかもしれません。
「もれる」と「ふれる」。「分解と利他」のヒントはそこにある!? お二人の思考の先端に触れる対話を、どうぞお楽しみに!!
藤原さんが出演しているイベントのアーカイブ動画を販売中です!
本文にも登場する、藤原さんが出演された2つの「MSLive!」対談のアーカイブ動画を、期間限定で配信中です!
①藤原辰史×松村圭一郎「縁食から世界を変える」
こちらのイベントのアーカイブ動画を2/28(日)までの期間限定で販売中です。
◎対談の内容
・社会の歪みが家族に丸投げされている
・なぜ「無料食堂」なのか?
・お互いが「ありがとう」と言える場
・生命の根源にある「もれ」
・「もれ」は経済活動にカウントされない
・食の特殊性は「余る」と「腐る」
②光嶋裕介×藤原辰史対談「あいだ」のつくり方、ひらき方

こちらのイベントのアーカイブ動画を3/12(金)までの期間限定で販売中です。
◎対談の内容
・光嶋裕介は押し出し相撲
・藤原辰史が読む! 『つくるをひらく』
・自分をどう裏切っていくか
・つくるをひらく↔︎ひらくをつくる
・スティグマを感じない公共建築とは?
藤原辰史さんと赤坂憲雄さんの共著『言葉をもみほぐす』(岩波書店)が刊行しました
民俗学・歴史学という各々の専門分野からの越境を厭わず、知力をふり絞り、引き裂かれながら現実に向き合う二人。同時代を生きてあることの歓びを感じながら、言葉を揉(も)み、解(ほぐ)し、思索を交わした、二〇一九年から二〇年にかけての往復書簡を、銀板写真(ダゲレオタイプ)とともに書籍化。この期に及んでなおも言葉の力を信じて。
(岩波書店『言葉をもみほぐす』書誌ページより)



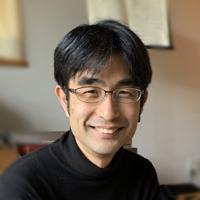




-thumb-800xauto-15803.jpg)


