第3回
パンデミックの孤独ーー「居心地のよい空間」をめぐる人文学(2)
2020.05.04更新
「サードプレイス」について
「居心地がいい」と感じるポイントは多彩だろう。人にとって異なるからだ。ただ、多くの人にとって居心地よく感じる場所があるだろうという前提で、社会の設計について考えた書籍がある。レイ・オルデンバーグの『サードプレイス――コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』(忠平美幸訳、みすず書房、2013年、原典は1989年)は、「三番目の場所」についての社会学の論考である。一番目は家庭、二番目は職場。これら二つの場所は、これまでよく論じられてきたし、考えられてきた。だが、カフェ、居酒屋、バーやパブのような、家族以外の人と好きな時に気兼ねなく集まって、おしゃべりができるような場所については、それほど考えられてこなかった、というのがオルデンバーグの1989年段階での先行社会学研究に対する批判であった。気兼ねがない。つまり、いちいちイニシエーションがいらない。ここがポイントである。多くの研究論文でこの概念は引用されてきた。
オルデンバーグのキーワードは、「とびきり居心地よい場所the great good place」である。見知らぬ人同士でも一緒にいられ、食べものや飲みものを共有しつつ、情報を交換したり、意見を交わしたりできる場所である。この場所の常連になれば、いつ入っても、我が家のように自由に動けて、自由にくつろぐことができる。狭い場所である場合が多いので、すでに述べたように、ウイルスや病原菌にとっても「とびきり居心地のよい場所」にほかならない。
最良のサービスを最大限に提供するサードプレイスは、人が昼夜を問わずほとんどいつでも、きっと知り合いがそこに居ると確信して一人で出かけて行けるところだ。そんな場所が用意されているのは、孤独や退屈に見舞われたときや、その日に受けた重圧や不満を解消するために良い仲間たちに囲まれてくつろぐ必要があるときの強い味方だ(『サードプレイス』82頁)。
一軒家の中に一通りの娯楽が揃い、テレビ番組が発達し、移動を自動車に頼るしかない郊外住宅を典型とするアメリカでは、このような場所が少ない、とオルデンバーグは嘆く。日本ではまだ残っているとはいえ、スラムクレンジングや大規模都市再開発によって徐々に店をたたみ、ショッピングモールや、大型の自動車専用道路や、チェーン店の飲食店によって消えていく。アメリカ社会が、都市近郊の個別住宅で、自由に個人的に過ごすスタイルを確立してしまったため、たとえばパリやウィーンのカフェやイギリスのパブのような公共空間が存在していない、これは都市計画の失敗だ、という痛烈な批判を繰り返す。興味深いことに、オルデンバーグの「サードプレイス」は出版当時のアメリカで、一つの社会現象となり、アメリカ各地でこの理念に賛同した人たちが、そのような人たちのコミュニティの中核になるような場所を作ったという。
オルデンバーグは、イギリスのパブ、フランスのカフェ、ウイーンのコーヒーハウスなど、さまざまなケーススタディーを調査し、それぞれの「くつろげる」理由について考えている。
「サードプレイス」はシングルマザーを排除するのか
だが、読者の思考を喚起させるような彼の議論には、他方で思考が行き届いていない点があることも看過できない。それは、単に、アメリカにもそのような場所がたくさんあるという点だけではない。これまでも指摘されてきたが、「サードプレイス」がもつ排除性についての考察である。オルデンバーグによると、このような空間には、どうしても常連意識が生まれ、その意識こそが、肩書きを外し、自由に振る舞えることを可能にしている。それはその通りである。が、その排除性について、オルデンバーグは、排除される側の空間が社会的に形成されてきた歴史については、極めて鈍感である。とくに、オルデンバーグはサードプレイスから女性が排除されるのは致し方ない、この居心地の良さを求める男性たちを女性たちはあたたかく見守ってきた、ということを臆面もなく述べている。本書の解説を担当しているマイク・モラスキーも、この点については「著者の女性に対する認識が『古い』としか言いようがない」と苛立ちを隠せない。また、人と群れることが嫌いな人も、「サードプレイス」からは除外されている。
私がこれまでの論考で考えてきた「縁食」という食の形式は、男性たちが家族と仕事のしがらみから離れて、ある程度のルールを守り、言語ゲームを楽しむという「サードプレイス」モデルとは異なる。たしかに、「居心地のよさ」や「空気づくり」といった点に注視するのは共通しているが、決定的な違いは、これまで述べてきたシングルマザーの視点の欠如、逆にいえば、近代的古典的家族観への彼のノスタルジーが、その「居心地のよさ」の社会的機能に向かわずに、単にコミュニティーの「活性化」という内向きの議論に落ち着いてしまっていることだ。
「サードプレイス」が持つ機能の中で、オルデンバーグは重要な機能を見落としている。それは、排除的な社会をほぐしていく機能にほかならない。パンデミックの孤独を生きるひとり親たちは、オルデンバーグの「サードプレイス」に浮上するきっかけはあらかじめ閉ざされている。彼女たちに向けられる冷たい眼差しを再生産することはあるだろうが、それを解体していくことはできない。「サードプレイス」の「居心地のよさ」は、こうした眼差しに支えられることになる。
だが、本来の縁食的「サードプレイス」とは、そうではない。逃げ場であり、異議申し立ての場であり、異種混交の場であるのだが、それら以前に、とりあえず食べものにありつける場所である。人と群れることが嫌いな人でも、少なくとも居ることを阻害されない場所である。そこで食べものをもらっても、先ほどのサイトへのコメントにあったように、「くれくれ、ばかりいってないでもっと自分でできることを探したら?」とは誰も言えない空間である。なぜなら、誰もが「くれくれ」と言っているからである。
縁食的サードプレイスは、仲間意識や同一性を確認するだけの、ナルシズムの共同体だけではなく、ナルシズムが分解されていく場所でもありえる。なぜなら、誰もが食べものをねだれる場所だから。食べものも欲しがっている人が、別の人に対して「くれくれというな」とは、さすがに恥ずかしくて言えない。恋人と別れた人や、障害があるからと言って相手にされなかった人や、異議申し立てを適当にあしらわれた人や、職を失った人たちや、テストに失敗した人や、家庭内暴力や共同体の暴力から逃れてきた人や、就職活動で人格を否定された人や、そんな人たちが、面倒な手続きと言い訳と顔色の伺いと差別の眼差しと、できれば金銭支払いも全てカットして食べものにありつける場所が、国や地方の政府が経済的に支えるだけで、口を出さず、作られていくならば、すくなくともそこは「居心地よい場所」と名乗ってよいだろう。日本の福祉制度は、「ありがたく思いなさい」という自動音声が組み込まれたシステムが強すぎる。
残念なことに、パンデミックの時代、私たちはこのような場所を増やすことができない。不況と失業がこれから怒涛の如くひとり親世帯の生活を襲うのにあわせて、各国の輸出制限による世界的な食料危機の可能性も、すでに国連諸機関から警告されている。泣きっ面に蜂である。まさに縁食が必要な時にかぎって、すでに述べたように、ウイルスが感染しやすい場所としてサードプレイスが忌避されている。「自粛を要請する」という、まるで「フリーの練習を強制する」という部活動のような自己責任に落とし込もうとする矛盾した日本語で、閉じられようとしている。ほかならぬ、日本政府の失敗を補う空間であったのに。
それでも上記のようなフードバンクや、子ども食堂が弁当を作るという方法で、あるいは、ただでさえ生計が苦しい飲食店が、給食や弁当のない子どもたちに安価な、あるいは無料の弁当を提供して、弱い場所へと追いやられていく人たちを救い続けている。コロナ前から始まっていたこうした場所は、すでにコロナ後を見据えた先駆的試みと言わざるをえない。実は「居心地が悪い」世の中だとこの世界を感じてきた人びとや、今回の災厄で感じた人びとは、もはや、コロナ前の世界にノスタルジーを感じることはないからである。
アウシュヴィッツの縁食
アウシュヴィッツ強制収容所からの帰還者のイタリア人であるプリーモ・レーヴィの『これが人間か』(竹山博英訳、朝日選書、2017年)には、アウシュヴィッツ強制収容所での不思議な食の光景が描かれている。アウシュヴィッツで栄養価の低い食べものを食べるしかない収容者たちの食べ方は、まるで動物である。
立ったまま、口と喉がやけどをするのもかまわずに、息をする間も惜しんで、がつがつとむさぼる私たちの様は、本当に「餌を食らう」という動物の食べ方なのだ。明らかに、テーブルについて祈りを捧げて「食べる」、人間の食べ方ではない。「餌を食らう」とは実にぴったりな言葉で、私たちの間では普通に使われている(『これが人間か』95頁)
ところが、そんな動物たちのような収容所の食事の風景に、束の間の「サードプレイス」が浮上するのである。まさに「居心地よい空間」だ。それは、レーヴィが属すコマンドーのテンプラーという男が、どこからともなくくすねてくる50キロの濃くて熱いスープを、15人の構成員で山分けした、という経験である。ひとり3リットルの濃くて熱いスープを飲むことができるのだ。これはアウシュヴィッツではほとんど奇跡に近い食事である。そして、テンプラーが飲む番になったとき、「全員一致で、鍋の底から汲んだ濃いスープが5リットル与えられる」。ドイツ人の監督もスープにありつけるので、黙認している。
皆はテンプラーに感謝の言葉を投げかける。それから、「テンプラーは少しの間便所にこもり、準備を整え終えた、晴れ晴れとした顔で現われ、すべてのものが笑顔で迎える中、自分の手柄の果実を味わいに向かう」。監督はいう。「どうだ、テンプラー、スープを入れるのに十分な場所をひり出せたのか」。
つまり、テンプラーの胃袋は、収容者と監督の、感謝とユーモアの共有スペースである。全員が同意をして感謝を流し込む場所なのである。人間と人間が安定した社会的条件で対面するところではなく、人間が動物との境界領域が危うくなってほどけてきたところから、逆に強烈な「人間的なるもの」が漂ってくる、という点が興味深い。「日暮れ時に仕事仕舞いのサイレンが鳴る。私たちはみな、あと何時間は満腹状態だから、上機嫌で喧嘩も起こらない」。「そしてめったにないことだが、私たちは母親や妻のことにも考えをめぐらすことができる。今は、しばらくの間、自由人に帰ったかのように、不幸な気持ちを味わえるのだ」。
よく知られているように、レーヴィは多くの作品を解放後に残した後、1987年に自殺を遂げている。このスープを飲んだ被収容者たちも、どれほどの人間がこの後に殺されたのかわからない。しかしながら、50キロのスープが、これほどまでに荒んだ心を、荒んでいることを味わえるまでには回復させる事実、そして、極限の状態であっても、スープに集まる人びとに、他者を気遣い、他者と言葉を交わし合う「居心地よい空間」を味わわせた事実は、いまもなお、殺されていないはずだ。
編集部からのお知らせ
「パンデミックを生きる構え」イベント動画 期間限定配信中(4/30〜5/10)
4/25(土)に配信された「パンデミックを生きる指針」動画視聴チケットを販売しています (動画では「パンデミックを生きる構え」にタイトルを変更しました) 。今こそききたい藤原辰史さんのお話を期間限定配信します!
出演:藤原辰史(京大准教授)、鈴木潤(メリーゴーランド)、三島邦弘(ミシマ社)



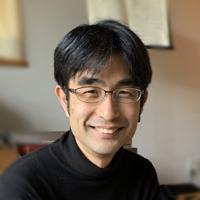


-thumb-800xauto-15803.jpg)


