第2回
「普通」というなめらかな世界との向き合い方Ⅰ(前編)
2024.05.06更新
#エピソード1
かつて『白い巨塔』というドラマの韓国語リメイク版を面白く観ていました。このドラマを観終えてから「日本オリジナル版」も気になってケーブルテレビで一晩中最後まで観てしまいました。当時日本語の勉強もかねて観ていたので、記憶に残る役者たちのセリフはけっこうメモをとっておきました。そのセリフの中で、主人公の
里見へ
この手紙をもって、僕の医師としての最後の仕事とする。
まず、僕の病態を解明するために、大河内教授に病理解剖をお願いしたい。
以下に、癌治療についての愚見を述べる。
癌の根治を考える際、第一選択はあくまで手術であるという考えは今も変わらない。
それは、「根治」という単語でした。この単語を覚えていずれ実際に使ってみようと思いました。その後、群馬にいる叔父の家に遊びに行くことになり、たまたま僕も知っている叔父の友人が右足を骨折し、1か月間入院し、最近退院したという話を聞きました。以下はその時の「根治」という単語をめぐっての会話です。
僕:あの人は「根治」しましたか?
叔父:「根治」ってなんだ?
僕:完全に治ったという意味じゃないんですか。
叔父:それはちょっと、お前「完治」って言えばいいんだよ。
僕:でも「根治」という言葉もありますよね。
叔父:そんな言葉「普通」は使わないと思うけどな。ちょっと待って、辞書持ってくるから。
僕:はい、お願いします。
叔父:(辞書で調べて「根治」という言葉があるのを確かめて)辞書にあるのはあるんだけど、こんなの「普通」は使わないよ。
僕:あ、そうですか。でも、『白い巨塔』というドラマにも出てましたよ。
叔父:あ、そう。あのドラマ観た?
僕:はい。あのドラマ今でも韓国のケーブルテレビで観れますよ。
叔父:お前、変な日本語使ってるね。その日本語間違ってるよ。「観れる」のではなく、「観られる」のが正しい日本語だよ。(笑いながら)日本語の文法の勉強、ちゃんとやり直してよ。
僕:え。。。。は~い。わかりました。これから頑張ります。
これで一応会話を切り上げましたが、僕ももちろん「下一段活用の動詞」、たとえば「観る」という動詞を「可能形」にするときには「~られる」をつけるということはちゃんと知っています。そのうえでわざと「観れる」を使ったわけです。でも叔父には受け入れてもらえなかったのです。
しかし、この些事は僕にとって「言葉を発するとはどういうことなのか」や「辞書を使うというのはどういうことなのか」、「間違った日本語ってどういうことなのか」そして、「日本語の『普通』という言葉はいつ使われるのか」などなどについていろいろ考えさせてくれました。
英語の表現で、 「The smallest detail can make a huge difference」というのがあります。つまり、「些事に注目することで大きな違いが生まれる」という意味ですね。僕にとって「日常の些事」に注目するということは、「思考訓練」のための欠かせないルーチンの一つです。この表現は、詩人の高村光太郎が書いた「日常の瑣事にいのちあれ 生活のくまぐまに緻密なる光彩あれ。 」という詩の一節を思い出します。ありふれた日常の些事に真剣に向き合うというのは、それまで自分が知らなかった話型で自分が普段思わずしていることの意味や価値を見つめなおし、それまで自分が知らなかったロジックと視点で自分の普段の行動をとらえなおすことができるようになる、力になると思います。それによって、我々は日常を生きなおすことができるようになるのではないでしょうか。
まず、考えたいのは「言葉を発するとはどういうことなのか」についてです。
ロシアの哲学者のミハイル・バフチンは、「言葉を発すること」についてつぎのような洞察あふれる知見を残しています。
言語の中の言葉は、なかば他者の言葉である。それが<自分の>言葉となるのは、話者がその言葉の中に自分の志向とアクセントを住まわせ、言葉を支配し、言葉を自己の意味と表現の志向性に吸収した時である。この収奪の瞬間まで、言葉は中性的で非人格的な言語の中に存在しているのではなく(なぜなら話者は、言葉を辞書の中から選びだすわけではないのだから)、他者の唇の上に他者のコンテキストの中に、他者の志向に奉仕して存在している。つまり、言葉は必然的にそこから獲得して、自己のものにしなければならないのだ(ミハイル・バフチン著『小説の言葉』67~68頁)
我々は言葉を発するときに「辞書」の中から言葉を選ぶのではなく、他者(ここでは、主人公の財前五郎)の唇の上からそれを奪い取らないといけないということですね。その言葉を僕の志向(日本語の練習)に奉仕させて使うわけです。こうやって「言葉」というのはそれが使われるコンテキストと話者と聴者の志向の絡み合いがあってはじめて意味を持つものです。だから「辞書」は言葉を使うにあたって単なる「リソース」に過ぎないということですね。
それから、我々は「辞書は実際の現在の言語使用を正しくあらわしているのか」と問うべきだと思います。間違いなくいえるのは、「ノー」です。 「辞書」に載っているのは、現在における言語の「正解」の意味ではない。辞書はまた、我々のこれからの未来の言語使用を「正しく」導いているものでもない。 辞書とは、我々が過去においておおよそこのように言語を使ってきたのだ、という「後付け」の書、すなわち、ある種の歴史書です。 そうです。あらゆる「辞書」 は、よく整理された歴史書です。 辞書には「この言葉の意味は~である」と書いてあるわけでもなく、「この言葉の意味は~になるであろう」と書いてあるわけでもなく、「この言葉の意味は~でなきゃなりません」と書いてあるわけでもなく、「この言葉の意味は~であった」と書いてあるだけです。少し丁寧に補足しますと、「この言葉の意味は~であった(しかし現在はそのとおりかどうかは保証しません)」というわけです。
したがって、辞書は現在、「正しくない」。だから、辞書を「正解」として、「あなたの言葉の使い方は間違っていますよ」と言うことはできないわけです。「間違った言語使用」などはどこにもないのですからね。ただし、僕のこれらの言及は、「辞書は使えない」ということと等しくはないです。もちろん辞書は、我々の言語使用の道しるべにはなる。 それは、我々が世界に向かっていくときの有力な資源だからです。しかし同時に、辞書は、つねに書き換えられなくてはならないという義務にさらされています。
そういえば、内田樹思想の主な際立った特徴の一つは、「言葉の意味の書き換え」にあると思います。『いま中学生に伝えたいこと』(信濃毎日新聞、2023年7月11日)という見出しのエッセイでは「友情の意味の書き換え」についてこう書かれています。
中高一貫校では場合によっては12歳時点で設定されたキャラに6年間束縛される。これは悲劇だ。のびのびと変化すべき時期に変化することそのものを制約されるのである。
友だちが変容すること、見知らぬ人になってしまうことを受け入れ、祝福することがほんとうの友情である。そのように友情の定義を書き換えて欲しい。そういう話をした。みんな真剣に聴いていた(と思う)。
「辞書」はあくまでもある種の「歴史書」だという僕の認識からすると、僕の「白い巨塔は観れます」という表現は「間違った日本語」として簡単に切り捨てられるものでしょうか。
日本語学者の
注意してほしいのは、これから考えていく内容は「つまずきやすい日本語」であって、「間違いやすい日本語」ではない、ということです。「間違いやすい日本語」と言ってしまうと、ことばには「正解」「間違い」があることになります。でも、学校のテストと違って、実際の生活の中で使うことばには、「これを覚えておけば、常に正しい」という、絶対的な正解はありません。同じく、絶対的な間違いもありません。(飯間浩明著『つまずきやすい日本語』6頁)
言葉の本質を見事にとらえていると思いませんか。僕は叔父とのやり取りで「間違いやすい」日本語を使ったわけではなく、「つまずきやすい日本語」を使っていたと思います。
しかし、韓国の多くの出版社が出している「日本語の文法の本」を読んでみると、『観られる』が正しい、『観れる』は間違いと書いています。でも、両者は「正しい vs 間違い」という基準でわけられるものではないと思います。「観れる」は、仲間うちの話しことばとしては頻繁に使われていますし、実際にこの『観れる』ということばを使っている日本人を、僕はたくさん知っています。
4月はじめごろに出た内田樹先生の初の「韓国オリジナル本」の『図書館には人がいないほうがいい』には、「やばい」ということばの意味の変化への気づきのエピソードが出ています。
野沢温泉にスキーに行って、露天風呂につかっていたら、あとから大学生と思しき男子が2人やってきて、ドボンと露天に使った瞬間に、「うゎー、やべえー」って言ったんです。
「やばい」というのは犯罪者の隠語で「危険である」という意味です。犯罪者の隠語が市民社会に入ってきて、ふつうに使われるようになった。隠語の市民語化というのは必ず起きるわけですけれども、「やばい」の場合は、それを通り抜けて「たいへん気持ちがよい」にまで転義してしまった。そうか、そういうふうに意味が変わったのかとその時に思ったのですが、それと同時に、どうして意味が変わったことが僕にわかるのだろうか、とその方がむしろ不思議に思えたのです。だって、聞いた瞬間に、「やばい」が「大変気持ちがいい」という新しい意味を獲得したことが僕にわかったからです。事実、いま手元の国語辞典で引くと「やばい」の項目には「若者言葉」として「大変気持ちが良い」「最高である」ってもう登録してあるんです。(23頁)
『やばい』と同じ「若者言葉」として現に韓国の若者の間でよく使われている言葉で、「미쳤다」ということばがあります。「미쳤다」はもともと「気が狂った」「気が狂う」という意味で使われる言葉ですが、現在では「おかしくなるほどすごい」という意味で使われています。歌がうまい、演技がうまい、見た目が美しい、景色が素晴らしい、食べ物が美味しい、・・・などなど、「やばい! 気がくるってるほどすばらしい!」という意味で使われています。やっぱり、言葉の意味は時代とともに変わっていくものですね。
もう一つ考えたいのは、叔父とのやり取りの中で出ていた日本語の「普通」という言葉の使い方についてです。そのとき改めて思ったことですが、「普通」という言葉の使い方は韓国語と日本語ではあんまり変わらないと思います。
僕は幼稚園生のころ、落ち着きがなく、よく先生に怒られました。みんな踊っているときに一人で手足を広げて大字になって床に横になっていたり、先生がみんなの前でなんか説明するときに、先生の真似をしていたり、していました。ですから、先生からいつも「おとなしくしていなさい」「じっとしていなさい」と言われ続けました。これは言われたとおりの意味でよくわかっていましたが、でもわからない言葉が一つありました。それは「普通」という言葉でした。「普通にしていなさい」。「普通」にするとは、いったいどういうことなのだろうかと子ども心ながら思っていました。「普通って何、どうすればいいの?」と先生に聞いても、「普通は普通よ。他の人と変わらないということよ。まわりをみているとよくわかるでしょ。みんなおとなしく座ってるじゃない。」どうすればいいかはなんとなくわかりましたが、でも「普通」は相変わらず霧の中でした。
いま振り返ってみて、このエピソードで「普通になるということ」について一つわかったのは、それはなんか「異質なもの」や「見慣れないもの」を「普通でないもの」として自分の生活世界から遠ざけていく、あるいは、排除していくことによって、ある種の「安心感」あるいは「なめらかさ」を手に入れようとする実践だということです。多くの人はこの「普通」を身にまとったときの安心感は大きくて、「普通」を手放すのは簡単なことではないというだと思います。多くの人がその安心感を手に入れることによって「なめらかな世界」は相変わらず続いていくでしょう。
(後編につづく)


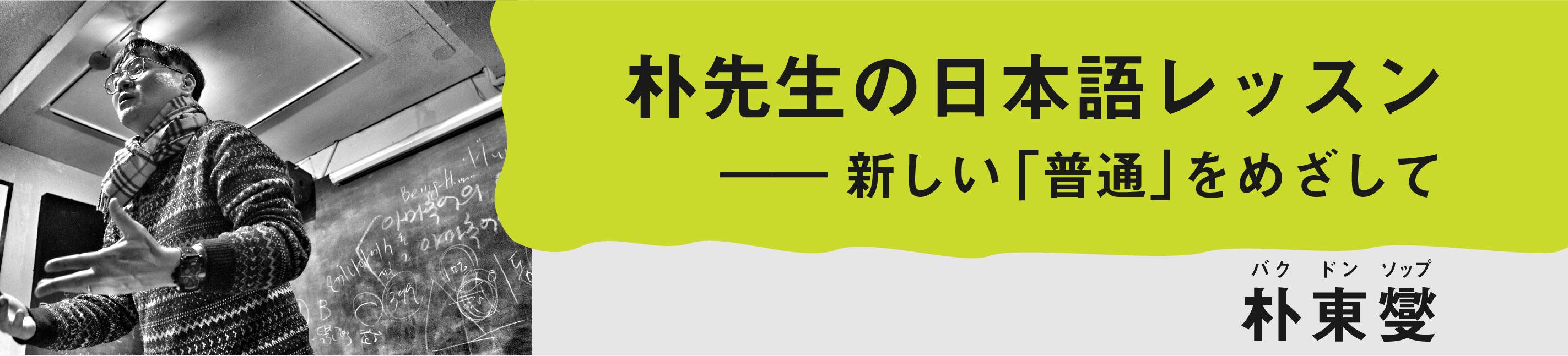



-thumb-800xauto-15803.jpg)


