第3回
「普通」というなめらかな世界との向き合い方Ⅰ(後編)
2024.05.07更新
#エピソード2
日本の留学から戻り、はじめて出席した、ある「教育心理学」の学会で起きた出来事です。開会早々、司会役の教育心理学者が、「心が体に影響を与えるということは我々はよく知ってますが、体が心に影響を与えるということにも我々は注意する必要があります」(あるいは逆だったか)というような発言をしたのを聞いて驚愕したのを覚えています(予想は十分していたのですが)。
これは絵に描いたような、「デカルト的心身二元論」、つまり心身関係を機械論的な身体と、霊的な心にきれいに二分してしまう考え方です。あるいは、後のディスカッションの時間で、心の社会的・歴史的起源について僕が強調したのに対して、別の教育心理学者が「我々はあくまでも心理の研究者なのだから、社会とか制度とか研究してもしょうがないんですよ」と吐き捨てるように言ったのも印象的でした。この発言に加えて彼は「我々の学会では、『心』については精密に研究しているのですが、制度とか歴史とかは『普通』研究しませんよ。」と
こうした発言は、彼らの、「暗黙の理論的前提」を知るのに恰好の手掛かりとなります(もちろん、この心理学者たちは、自分の心の捉え方の「暗黙の前提」を最後まで知らずにこの世を去っていくはずでしょうけどね、多分)。ここらへんの発言を見渡すと、何となく暗黙のイメージが浮き上がってきます。つまり「心」とは「社会」とは対立する、「個体」あるいは「個人」が持っているものであり、そしてそれは身体とは別の仕組みで働く何かである(そしてたぶんそれは、頭のなかにあるかハートのどこかにある)。この「個体心理学的」なイメージは、たぶん我々の常識的なそれに(それこそ「普通」ですよね)最も近いから、それから距離がある僕が考えているような「心」の概念に出会うと、多くの人は違和感にとらわれると思います。
ディスカッションの時間に僕はこう反論したと思います。
しかし、心理学史を紐解いてみますと、我々が囚われている「心のイメージ」、たとえば「箱」としての心、そして「金庫」としての心ではなく、「行為としての心」(@ジェームス・ワーチ)あるいは「心は社会文化歴史の地平でその地平とともに変化し続けてきた」という、「心の歴史性や状況性や身体性」についての議論もちゃんとあります。ですから、「人間の心」だけに焦点を当ててしまうと、かえって「人間の心」さえ分からなくなってしまいます。「社会」や「制度」、そして「文化や歴史」と「心」との絡み方を視野に入れないと、「心」の究明になりません。
しかし、その学会に参加していた会員の中で一人も僕の話を相手にしてくれませんでした。しかもそのあと「同じ言葉遣い」で一般人向けの講演も何回かしましたが、なかなか僕の考え方を受け入れてもらえませんでした。今こうやって自戒の念を込めて当時の出来事を振り返ってみると、僕が発言した言葉が十分に「当たり前の世界、あるいはなめらかな世界(メインストリーム<普通>の心理学の世界と街場の世界)」を形にできていなかったことでした。つまり、その言葉の性能が「普通」を突き詰めるにはちょっと(どころか、ものすごく)足りなかったということです。(彼らにとって)何の問題もなく過ぎていく「普通というなめらかな」世界から、その言葉が十分な距離をもっていないから、「普通」をなぞるだけで、新しいことがなにかわかった感じがしなかったわけだと思います(たぶん)。
しかし、おそらく、彼らは当時もう一つの感じも受けたはずです。それは、僕の言葉が「難しすぎる」という感じだったでしょう。つまり、そこで用いられている言葉づかいが普段彼らが使っている言葉づかいとあまりにもかけ離れた気がして、そこで開かれている世界が伝わってこない、という感じだったんじゃないでしょうか。もしかしたら、この人は言葉遊びをしているのではないか、ただ難しいことを言いたくて言っているのではないか、と思わせさえするような感じだったと思います。
つまり、こういうことだったと思います。世界を描くための言葉作りが、それ自体目的になってしまって、 世界を描くことに手が回らなくなってしまう、ということ。また、ときには、その見事な言葉で世界を浮き彫りにしているのだが、切れ味鋭い言葉であればあるほど、なめらかな言葉しかもっていない人には伝わりにくくなる、ということです。
これは僕が研究者として参加している「ヴィゴツキー心理学」 にとってもったいないことであり、大きな危険であると思います。 それは「ヴィゴツキー心理学」 という切れ味のいい道具が「ヴィゴツキー心理学研究者」 だけのものになってしまう危険です。もちろん、すべての言葉が「ヴィゴツキー心理学」の外に伝えられる必要はないでしょう。しかし、それが「ヴィゴツキー心理学」だけに閉じられた世界だけで流通するようになったとしたら、「ヴィゴツキー心理学」を語る言葉が仲間同士だけに通じる「内輪の語法」だけで成立しているとしたら、そうした言葉は存在してもしかたない。なぜなら、その場合、「ヴィゴツキー心理学者」がいてもいなくても、それ以外の世界は痛くもかゆくもないままでなめらかにつづいていきますから。
言い換えてみましょう。社会のあっちこっちで「普通」というなめらかな世界が広がっている。それに切り込もうとする言葉。ところが、それがあまりにもなめらかな世界に近すぎるとき、それはなめらかな世界に呑み込まれてしまいかねない。 そうすると、「ヴィゴツキー心理学」は「学知」でもなんでもなく、なめらかな力のなかに落ち込み、なんの痕跡も残さなくなってしまう。これだったら「どうしようもないヴィゴツキー心理学」だと言わざるを得ない。
逆に、それがなめらかな世界から離れてくっきりと何かを描くが、なめらかな世界に伝わらなくてなんの痕跡も残さないことがある。 いわゆる僕がかつておかしてしまった「難しすぎるヴィゴツキー心理学」ですね。しかし、この評価は実に難しいと思います。だって、ほんの少数の人には明確にわかる発見をしているかもしれないんですから。それでよいという考えもあるでしょう。しかし、次のことを忘れてはいけないのではないでしょうか。そのとき、「普通」というなめらかな世界は、なにごともなかったようにつづいていく。 ある「ヴィゴツキー心理学者」がなにかいった。しかしそのことは、なめらかな世界にいわば撥ね返されてなんの力ももたない。
「普通」という「なめらかな世界」はそれだけに強い力をもっているものだと思います。自分たちの世界に近いと思われるものは呑み込んでなにも変わらずなめらかに続いていくようにする。逆に自分たちの世界から遠いものは撥ねつけてなにも変わらずなめらかに続いていくようにする。前者の場合は、「ヴィゴツキー心理学」は「普通」になにも突きつけず、そのまま「『普通』心理学会の社会」や「生活世界」は生き延びる。後者の場合は、ヴィゴツキー心理学は「ヴィゴツキー心理学者」のサークルのなかではすばらしい力を持ちながら、 「メインストリーム心理学会の社会」や「一般の社会」には入れないまま生き延びてしまう。
ときにはこんなことさえあると思います。 「ヴィゴツキー心理学」が創り上げた「言葉」はそれぞれの「社会」の「言葉」から人を自由にする方向に働くはずだという考え方です。なめらかな世界で区切らない仕方で世界を区切り、別の見え方を可能にしていく。しかし、ときどき、それが「ヴィゴツキー心理学者」にとってのなめらかな安全地帯になってしまうことがあります。つまり、その「ヴィゴツキー心理学」の言葉に守られて、「社会」に接しなくていい、あるいは「社会」に出会えない地点に「ヴィゴツキー心理学者」は自分の居場所を見つけてしまうことがあると思います。
「普通」というなめらかな世界と反対の場所に、「ヴィゴツキー心理学者」の安全な世界、 「ヴィゴツキー心理学」の「内輪の話法」が「普通」に通じる「社会」というもうひとつの動かない世界が生じてしまいます。 「ヴィゴツキー心理学」がひとつの閉じ込めれらた「社会」をつくる 「普通」になり、いわば、考えを始めるための道具が、考えをやめるための道具に変身してしまいかねない。そしてそういう動かない姿勢がいつのまにか「普通」になってしまう。あらためて「普通」って本当に手強い相手だと思います。
「普通」という名の迷宮の前門に頭を打ちつけ、そのとば口できびすを返してしまう。覚醒のあとにふたたびまどろみの時が訪れるように、「普通」への問いはやがて「普通」のなかにひきずりこまれ、当初の起爆力を消失させてしまいかねます。
「普通」への問いは停滞し、繰り延べられる。先へ先へとひきのばされる問い。「普通」への問いはどこまでも未発の爆薬でしかありえないのでしょうか。
ですから、僕のような「ヴィゴツキー心理学者」は、その動かない世界から 「ヴィゴツキー心理学」を自由にしなければならないと思います。 「普通」に居着いている「ヴィゴツキー心理学」を外に連れ出し「普通の心理学と我々の生活世界」ともう一度向き合わねばならないと思います。「普通」というなめらかな世界に向き合うために 「ヴィゴツキー心理学」の言葉を、つねに更新し、洗練しなければならないと思います。
せっかくなのでここで「ヴィゴツキー心理学者」が好んで使っている「話法」を一つ紹介してみましょう。「後期ヴィゴツキー心理学者」の一人であるジェームス・ワーチ(James Wertsch)は「皮膚を超えて拡がった精神(beyond skin extended mind)」というユニークな表現を使いながら「人間」と「社会」をきれいに分けてとらえる従来の心理学(いわゆる「普通」の心理学)の考え方を批判しています。
ワーチはこう言っています。
分析に際して、「行為」を優先するということは、人間を、行為を通して自身はもとより、「環境」と接触し、創造するものとみなすということなのである。このように行為は、人間や環境をバラバラなものとしてとらえるのではなく、それらを一つの単位(Unit)としてとらえて分析をはじめていく際の入り口をあたえてくれている。これこそ私が創り上げた「媒介手段を用いて行為する主体 (agent acting with mediational means) 」という概念が開いてくれる世界である。この考えは、人間を環境からの情報を受動的に受け取る存在として考える立場や、他方、個にのみ着目して「環境」を二次的にしか扱わず、環境は単に発達の過程を刺激するだけだと考えるようなアプローチとは、いずれも対比されるものである。(James Wertsch, 1991, 『Voices of the Mind』p.18)
みなさん、読んでみていかがですか。ジャーゴンともいうべき専門用語に満ちており、何を言っているのかは容易には読めないと思います。
「人間」と「社会」をきれいに分けてとらえる「メインストリーム心理学」の考え方にとってかわれる「ヴィゴツキー心理学」の考え方を説明しているものの、使われている「言葉遣い」がいわゆる「普通の心理学」の視点や「普通の人が持っている『心の視点』や『人間観』など」を反省的にとらえなおすのに十分な性能を持っていないと思いませんか。
およそ「ヴィゴツキー心理学」という「学知」は「メインストリームの心理学の考え方」や「一般人の眼」や「通念」、つまり「普通」や「あたりまえ」と異なったものの見方をさせ、それに逆らい、戸惑わせるものでなければならない。さらにいえば、それを疑い、揺るがし、問い直すものでなければならない。そのうえで、「ヴィゴツキー心理学」を専門にしない人にも届くように諄々とことの理を説き、話の筋目を通し、カラフルな喩えを駆使し、響きのよい言葉を選び、そして読者の袖をつかんで離さないような書き方を工夫しなければならないと思います。
ですからここで一人でも多くの人に「ヴィゴツキー心理学」の魅力を届けるために「ヴィゴツキー心理学のジャーゴン」を我々の身近な日常生活に落とし込んで読み直してみましょう。
たとえば、「台所」という「環境」について考えてみましょう。身の周りを眺めてみると、そこは、調理用具、材料、調味料など、私たちにとって有用な様々なものに満たされている。台所という場所そのものもそうですが、いろいろな道具、材料も、私たちのために何がしかの役割を果たしてくれているし、また果たしうる。逆に考えれば、そうした環境において私たちが演じるにふさわしい「はまり役」があると言うこともできるでしょう。
さらに、当り前すぎて日常は意識にものぼらないことですが、台所は、ある仕方で整理されています。調理用具、材料、調味料やレシピは、それにふさわしい場所に別々に置かれているでしょう。さらに調理の材料一つとっても、野菜は冷蔵庫のどこ、肉はどこといった具合にあらかじめ分類され貯蔵されている。また、私たちは、調理が終わった後では、再びこうした様々な道具、材料をもとのところに片づけておくと思います。
このように、日常の環境は、たとえば台所にある調理器具、材料、調味料といった「機能的な資源」とでもいうべきもので満たされています。しかし、そうした「環境」は、それとしてあらかじめそこにあるのではなく、「料理」という行為(これこそヴィゴツキー心理学者がよく使う概念ですね)を通してはじめて人は「料理人」という「主体」になり、ネギと玉ねぎなどは「料理の材料」になり、器などは「調理器具」になり、それに伴って「台所」という世界が立ち上がるわけです。
つまり、人はある場所(環境)である道具を持ってある行為をすることによって「料理人」という「社会・文化的サイボーグ」になっていくわけです。
さらにある状況(ここでは台所)における私たちの認知過程をどのように考えるべきなのでしょうか。たとえば、こうしたきわめて日常的な状況での「想起」ということを考えてみましょう。私たちが行うことは、こうした人間的なものに作り替えた環境を前提にしています。たとえば、包丁を探すというときには、迷わず包丁、ナイフといった類のものが置いてある場所を探すでしょう。これは、ある意味では、もっぱら自分の頭だけを頼りにして問題解決しなければならないような実験室的な記憶課題と対照的です。たとえば、対象のクラスタリングの構造は、頭の中にあるのではなく、環境の中にすでに与えられている。あるいは、私たち自らが、台所という環境をあらかじめ、そのように構成しておいてあると言った方がふさわしいかもしれません。しかし、ここでも、クラスタリングは、頭の中の構成物ではなく、あくまで環境の構成の仕方の中にあるものなのです。
こうした状況では、むしろ、実験室的な記憶課題が生じないようになっています。あるいは、むしろ、私たちは、実験室的な記憶課題が生じないように環境をつくりかえようとするのではないでしょうか。少なくとも、みずから積極的に記憶課題を変えて行こうとしていると言えるのではないでしょうか。そして、このように課題を変えて行く中で私たちの「認知的役割」も変わって行くと思います。たとえば、「思い出す人」から、「見る人」へと。あるいは、その状況で必要とされる認知過程や知識も変わって行くでしょう。
以上のようなことを見るなら、台所の様々な資源やその配列のされ方を、「外部記憶」の補助的な性質と片付けることはできないに違いない。「外部記憶」という言い方は、あくまで内部記憶という言い方を前提としたものですからね。さらに、「外部記憶」の補助という言い方には、「内部記憶」が固定された認知能力の一種であるという暗黙の前提が存在している。そして、外部記憶によって、たんに記憶課題が軽減されるというわけです。
しかしながら、環境をつくりかえることによって生じることは、むしろ、課題の変容、記憶課題から別の課題への変容ではないでしょうか。つまり、その状況で、私たちが認知的に果たす役割が変わっているということであって、たんに固定された記憶能力や記憶課題への外部の援助があるというわけではありません。
このようなことを考えるなら、みずから構成する環境との対で私たちの認知過程、たとえば記憶といったものを考えて行く必要があるように思われます。
料理ができること、また、料理に関連した認知過程は、こうした台所という環境の存在をぬきに語ることはできないと思います。あるいは、私たちの認知過程、能力といったものはこうした状況ぬきに考えることはできません。
環境は、私たちの認知的な役割を定める。あるいは、ある環境のもとでの私たちの認知的な役割、あるいは、「はまり役」といったものが存在する。逆に、ある認知的な役割を果たそうと思えば、ある環境が必要になるとも言えますね。
しかし、環境は、たんに与えられたものではない。むしろ、私たちは、環境をつくりかえることによって能動的に自分の「認知的な役割」を変えて行こうとするのです。
まとめてみましょう。最初は何もない「環境」(空っぽの世界)に人や道具(包丁やまな板や野菜そして魚など)が揃い、それらが一緒に動くことで一つの世界が成り立ちます。つまり人がそこに電気をつけたり、包丁で鯖をさばいたり、鯖を焼いたり、味噌煮したり、揚げ物にしたりするような行為が生じることで、 その束の間、「料理人」という「社会・文化的サイボーグ」とその行為で開かれる世界(台所)が同時に立ち上がります。そしてご飯を食べ終え片付けが終われば、その世界はたちまちのうちに消えてしまいます。
「台所」は一般に料理のための装置でありますが、台所の使われ方は常にオープンで、台所らしく使われることも可能性にすぎず、子どもたちの遊び場や宴会場にもなりうる。そこに遊びやお酒を飲んだり雑談をしたりするような行為がはじまり、ふいに空っぽの世界が人間的な意味に満ちた一つの世界が動き出す。だから人間のどんな行為も「野球のグローブ」ではなく、「ボクシンググローブ」をしてする、ある種の運動だと言えるでしょう。
いままでの議論をちょっと抽象度を上げて書き直してみましょう。
人間は自分が作り替えた世界と構成的に相互依存関係を結ぶわけです。「長安一片月:長安の空に浮かぶ一片の月」(李白)もすでに詩的話者から離れた客観的外部に存在するわけではないんですよね。人間という主体は「ある行為」を通して外部を「(人間的な)世界」に作り替え、対象を意味の焦点に変えます。私のある選択によって、私の世界は風景が変わり、世界の変化は、今度は私の主体的介入を促し、また、この介入は私の主体の性格と指向を再構成します。
たった今見てきたように「ヴィゴツキー心理学」の考え方を通して「メインストリーム(普通)の心理学」や「人々の普通の心理学:folk psychology」の考え方を浮き彫りにし、相対化し、そして我々の「生の編まれかた」を精緻に記述し、多くの人に届けるためにはやはり手触りのやさしい「言葉づくり」が必要だと思います。
言い換えれば、様々な「普通」を揺さぶることは、呑み込まれるのでも、撥ねつけられるのでもなく、「あわい」で動きつづける運動にほかならないのではないでしょうか。


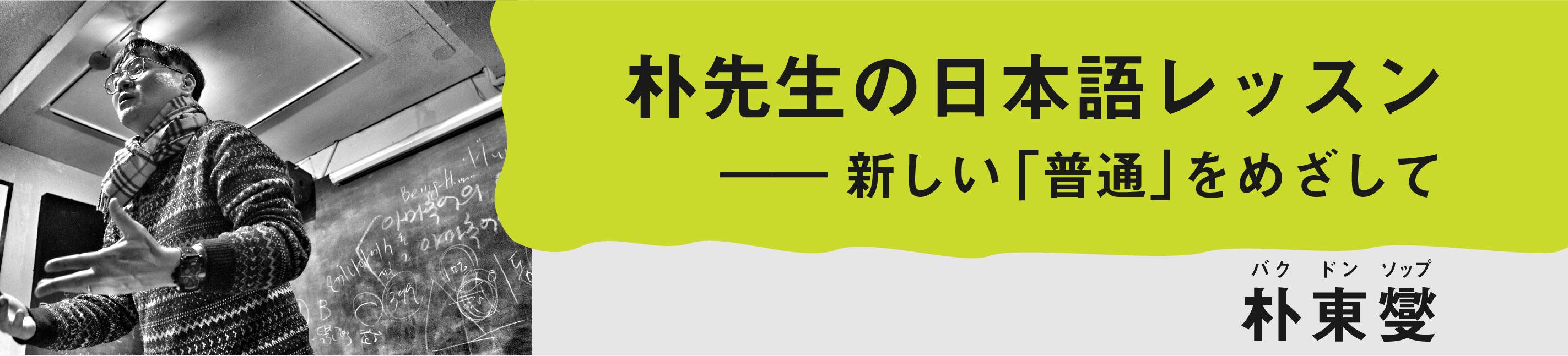



-thumb-800xauto-15803.jpg)


