第21回
僕はなぜ通訳するときにメモを取らないのか
2025.07.04更新
5月28日にソウルLGアートセンターホールで「UCHIDA TATSURU MOVEMENT」というカンファレンスが行われ、内田樹先生とその関係者たちが講演をしました。会場には、ふたりの通訳者がいました。
一人は元朝日新聞記者の成川彩さん。韓国語を日本語に通訳しました。僕を含めて三人の韓国人スピーカーの話を内田先生と日本人の聴衆向けに日本語訳したり、韓国の聴衆からの質問などを内田先生に日本語で伝える役割でした。
もう一人の通訳者は僕で、役割は日本語を韓国語に通訳すること。僕は内田先生の日本語を、韓国の聴衆と韓国語がわかる一部の日本人の聴衆に向けて韓国語に通訳しました。
僕はいままで10年以上、内田樹先生の韓国のご講演で日→韓と韓→日の通訳を同時に自分一人でやってきたので、今回はずいぶん気楽でした。その分、日→韓通訳に全力投球することができたと思います。
このイベントに参加していた韓国のとある新聞記者は、
「両国の言語が自然にありのままに訳されることより、「内田先生を愛する日韓ファンの集まり」において温かい「文化の翻訳」がなされたとでもいうべき、不思議な雰囲気が醸し出された。韓日の武道人、読者、記者たちが互いに融合・複合したようなイベントだった」
と感想を述べてくれました。
そのカンファレンスに参加していた僕の日本人の友人(Tさん)が、成川さんと僕の通訳を間近で見て、つぎのような面白いご質問をしてくれました(ちなみに、Tさんは日本語と韓国語、両方できる方です)。
「成川さんは韓国語を日本語に通訳する際にメモをたくさんとっていましたが、朴先生はメモを全然せずに、長くて複雑極まる内田先生の話を通訳していたの不思議でした。そういう離れ業ができるコツがあるんですか?」
僕は「なるほど!」と思いながら「僕はなぜ通訳するときにメモをとらないのか」について少し考え込んでしまいました。
これはある種の営業秘密なのですが、僕ももちろん、通訳のときにメモをとることもあるんです。しかし、メモをとったからといって、それを読んで通訳をするわけではありません。僕のメモはじつは殴り書きで、書いた本人も読めないからです。
ただ、通訳のときにメモをとっておくと、なんだか安心できるんです。
落ちたら死ぬという条件で綱渡りしている人と、落ちても「セーフティネット」が張ってあると思って綱渡りしている人では、リラックスの程度が違いますよね。リラックスしている人の方が運動精度は高いと言われています。
「自分にはアジールがある」と思っている人ほど、アジールが要るような状況に陥らない。 アジールというのは、そういう逆説的な制度です。
僕にとって「メモをとる」という行為はある種のアジールのようなものです。
これはある脳科学者の本で読んだ話ですが、メンタルストレスについてこんな実験結果があるそうです。
メンタルストレスを受けると、人間の脳内にはある種の化学物質が合成されます。 それがつよい心身の不快をもたらします。 この化学物質を点滴で体内に送り込む実験をしました。ただし、被験者を二つのグループに分け、一つのグループにはただひたすらに点滴で不快をうみだす物質を送り込み、もう一つのグループには点滴装置にオン・オフのスイッチをつけて、心身の不快が限度を超えて 「もう、だめ」となったときにはスイッチをオフにすることができるようにしました。
そうやって実験をしてみたら、驚くべき結果が出ました。 オン・オフのスイッチを与えられたグループは、心身の不快をそれほど感じず、誰もスイッチを使わなかったのです。
ひどく気分が悪くなるだけの量の化学物質を投与したはずなんです。 でも、自分がスイッチをオフにしさえすれば悪い気分は消え去ると思っていると、それほど気分が悪くならない。つまり、 メンタルストレスというのは単体で存在する不快ではなくて、「メンタルストレスに対処して打つ手がない」という無力感とセットになったときにはじめて発動するということがわかった。
この実験結果は、僕の「後で読みもしないのにメモをとっておく論」を薬理学的に傍証してくれるものだと思います。
通訳というのは、多かれ少なかれ「ネイティブスピーカーに憑依されること」だと僕は思います。 憑依されることなしに通訳は果たせません。
外国語でなにかしゃべっているが、いったい何を伝えようとしてそれをしゃべっているのか、その「欲望」に焦点化すると、何となく身体的な「同調」が起こる。これを「憑依」と言わないでなんと言うんでしょう。今回のカンファレンスに参加した僕の韓国の友人は「いつのまにか内田先生の話が釜山弁(僕の韓国語は釜山弁です)に聞こえてしまった」と言っていました。
ネイティブスピーカーに憑依するためには耳と目だけでなく皮膚などを含めて全身を使わないといけないので、そもそもメモなんかとる暇がありません。
通訳をやったことのない方にはちょっと説明しにくいのですが、憑依すると言っても、相手の脳にいきなりアクセスするわけではありません。 それはできないんです。 アクセスできるのは、 相手の身体だけです。 これならできる。言葉を運ぶときの呼吸とか、しぐさとか、リズムとか、グルーブ感とか、アクセントとか、間合いとか、僕はそういう「息づかい」 のようなものにはわりとすぐに同期することができます。相手の話を浴びるほど聴いていると、聴いているうちに「あ、この名詞が来ると次はあの形容詞が来るな」 ということが予測されるようになるんです。 この言い回しが来たら、次はあの言い回しが来るなとかいうことが、わかる。中身とは関係なく。中身じゃなくて、しゃべり方がわかるのです。
それは知らない外国語で上演される芝居や、オペラ、あるいは古典の言葉で上演される能や歌舞伎を見ているのに似ています。 最初は意味がまったくわからない。 でも、同じ芝居を何回も見ているうちに、わからないなりに、この役者が出てくると、こんな声を出して、こんな身振りをして、こんなふうに引っ込むということはわかるようになる。そのうちに、ひいきの役者や、気に入ったフレーズや、身振りが増えてくる。 身体的に舞台と同期してくるんです。 そして、身体的に同期してくると、自分の身体が「これまで思ったことがないことを思っている」という現象が起きる。
身体が思考に先行するわけです。 ぞくっと寒気がしたあとに「熱があるのかな?」というふうに考えるのと一緒です。 まず体感がある。 それから、 その体感を説明する言葉が浮かんでくる。
通訳でも同じことが起こります。まずスピーカーと通訳者の呼吸が合ってくる。体温が合ってくる。皮膚の肌理が合ってくる。体性感覚が同期してくる。そして、同期した体感の中には「前代未聞の体感」が含まれている。 自分の内部には決して起源を持たない未知の体感を感知します。 この体感は僕のものじゃない。とすると、これはスピーカーのうちに起源を持ち、そこから通訳者である僕のうちに入り込んできたものだということです。 出自は外来のものではあるけれど、 今では僕の体感です。そうである以上、手立てをつくせば、それを「自分の言葉」に置き換えることができるはずです。 そういうふうに通訳プロセスは進行します。
語の意味がわかったので、「何が言いたいのか」が分かるのではなく、「何が言いたいのか」がわかったので、語の意味がわかってくるのです。僕たちがふだん母語でしていることと同じです。
「人類にとって最古の職業とは通訳である」と言われることがあります。通訳にも色々ありますが、おそらく最古の通訳とは、 神の言葉を人間に伝える役割をもっていた「オラクル(oracle: 巫女)」のような存在のことを言ったのでしょう。
神の言葉は雷鳴や地鳴りや暴風のような、音声としての具体的な形を持たないものであるので、巫女がそれを感じ取って伝えるということになるのですが、僕の通訳においても、この「感じ取って伝える」という要素は非常に重要だと思います。
通訳は「縦のものを横にする」だけだから、二言語の文法に精通していて、良い辞書があれば簡単にできる仕事だと思い込んでいる人も多いようです。でも、それは大きな間違いです。人間のコミュニケーションは、表面に表れる言葉だけで成り立っているのではないからです。
韓国語と日本語は主語や目的語が省略されることが多いし、物事をはっきり言わずに聞き手の解釈に任せる、いわゆる「ハイ・ コンテキスト」の言語なので意味の伝え方が曖昧だとよく言われます。通訳者の立場からすると、前後の文脈からたいていの状況は把握できますが、やはり英語などに比べると聞き手の判断に委ねる部分が多いのも真実です。
韓国語-英語の通訳をしている友人から聞いた話ですが、彼女が20年前に国際会議のレセプションで通訳した時、会議に出ていたアメリカ人代表者の奥さんが「私は今年で60歳ですよ。」と言ったのに対して、韓国側の女性の一人が「お若いですね。」と言ったそうです。通訳をしていた友人が"You are young." と訳すと、そのご婦人はムッとしてしまいました。 しばらくして、彼女は"You look young." と訳すべきだったと気づきました。 "You are young." だと、 「あなたは(見かけよりも実際は)若いのですね」と受けとることもできます。 "You look young." であれば、「あなたは(実際よりも若く見えますね)」という意味になる。訳し方によってまったく逆の効果を生むことになるのですね。その時の韓国人女性はもちろん相手をほめるつもりで言ったのですから、 友人は後者の訳し方をすべきでした。
通訳者はまた、異文化コミュニケーターでもあります。互いに異なる文化的背景を持つ両者の間で、言葉だけでなく文化の懸け橋の役割も果たすことが期待される。
法廷通訳についてのドキュメンタリー番組で、こんなエピソードを観たことがあります。 妻を殺害したとされる韓国人の被告人が、公判での証言の中で 「お兄さん」「お姉さん」という言葉を何度も使いました。 韓国では知人で年上の人を「お兄さん(형)」や「お姉さん(언니)」と呼ぶことが多く、実際その被告人は、血縁関係のない事件関係者のことをそう呼んでいた。ところが、通訳者はその発言をすべて証言者の実の兄や姉として訳してしまい、そのおかげで、もともと事件に関係のなかった人たちが突如ストーリーの中に出現し、法延関係者たちは非常に混乱させられました。
言葉の裏にある真の意味を汲み取らなければ、通訳はできません。
言葉というものは、その民族の属する文化によって規定されます。つまり、この世界に無限に存在する事象を記号として切り取っていくのが言葉だとすれば、その切り取り方は、民族の世界観や感性、そして美意識などによって異なったものとなります。
例えば、英語の"justice" という言葉には、韓国語と日本語の「正義」の意味も「司法」の意味も含まれます。 "miscarriage of justice" という表現が出てきた場合、それは「正義が実現されないこと」という意味にも「司法がうまく働かないこと」という意味にも受け取れるのです。そういう広い意味を同時に表せるような訳出表現は韓国語や日本語には存在しないので、通訳者は非常に困ることになる。何とかして、状況に応じた最善の訳出表現を考え出す必要があります。
世界に存在する言語の多くが、それぞれ何十万もの単語を持っているといわれています。でも、たかが数十万です。人間の思想や感情やしぐさは、無限の意味合いやニュアンスを持ちます。 記号にすぎない言葉や表現の数は、そのような人間の想念を表すにはあまりにも限りがあります。 さらに文化の違いという要素が加わると、人間が言葉を駆使し伝えることのできる範囲は何と限られているのだろうかと嘆息せざるを得ません。
そういう意味では、通訳者は現在でもやはり、「オラクル(巫女)」のような存在にならないといけないかもしれません。ですから 、僕にとって通訳というのは巫女のように、「他人の頭に自分の身体を繋ぐ」ような感じのものなんです。 「カチャッ」と音を立てながら装着するイメージです。
他人の頭に自分の身を繋いで、他人の頭が考えていることを自分の身体が受けとめる。頭ではなく、身体で受けとめることがポイントです。頭に比べて、身体のほうは割と入り口がゆるくて、ずるずると異物が入ってこれるからです。 そして「身体の機能がいい」状態であれば、異物に対して非常にオープンになれると僕は思います。
この文章を書き終えて、内田樹師匠が僕の通訳を「憑依型通訳」と名付けていらっしゃるわけがなんとなくわかったような気がしてきました。


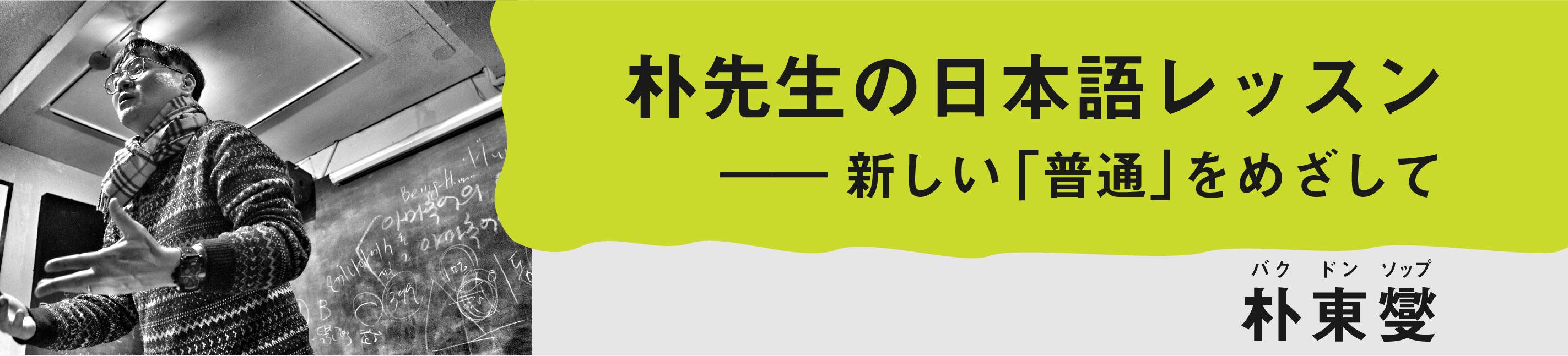



-thumb-800xauto-15803.jpg)


