第23回
僕はバイリンガルではありません(後編)
2025.08.12更新
ヴィゴツキーは、私たちが普段の生活で自然に身につける考え方(これを「生活的概念」と呼びます)と、学校などにおいて知識として学ぶ考え方(これを「科学的概念」と呼びます)では、その発達の仕方が違うと考えました。
「生活的概念」は、例えば「自転車に乗っていて転んだ」という具体的な経験から始まります。そして、その経験を通して「なぜ転んだのか」をだんだん意識して理解できるようになる、というように下から上へと発展していきます。つまり、具体的な経験がまずあって、そこからだんだん意識的にその経験について考えるようになる、という流れです。
一方、「科学的概念」は、これとは逆です。例えば、学校で「
このようにして身についた「科学的概念」は、子どもたちが物事を見直したら、これまでの経験を新しい形で理解したりする手助けになります。「科学的概念」は、実際に物に触れることから始まるのではなく、「まず概念を理解し、それから物事を理解する」というように進むのです。ヴィゴツキーは、この「科学的概念」の発達を、「生活的概念」とは反対に、「より複雑で高度な理解から、より基本的な理解へと」進むものだと説明しています。
学校で学ぶ「科学的概念」は、まるで、遠い国から届いた美しい絵葉書のようなものです。きれいだけど、どこか他人事。自分の目で見た景色や、自分の手で触れたものとは違って、心からの感動や深い思いを語ることは、なかなかないですよね。たとえば、歴史の授業で習う「アメリカの南北戦争」の話も、最初はただの文字の羅列に過ぎないかもしれません。
でも、その絵葉書を本当に自分のものにするには、ただ眺めるだけでなく、「自分の旅の思い出」に書き換えるような工夫が大切なんです。それは、教科書に載っている科学的概念という名の「大きな地図」を、自分の個人的な経験という名の「足跡」で埋めていく作業に似たようなものです。漠然とした知識の地図に、あなたが歩いた道や、心に残った風景を書き加えていく。そうすれば、その地図はあなただけの「宝の地図」に変わります。
もし、自分が南北戦争という大きな出来事を、自分の家族の話や、何か個人的に感じたことと重ね合わせ、「私だったらこう思う」という自分のヴォイスで語れるようになったとしたらどうでしょう? それは、ただの絵葉書だった南北戦争が、自分の「心のアルバムの一枚」になる瞬間です。自分だけの感情や視点が加わることで、その概念は生き生きと輝き始めます。
一方で、私たちが普段の生活で自然に身につけた「日常的概念」(例えば、「兄弟ってこういうものだ」、というあなたの感覚)も、学校で学ぶ「科学的概念」(兄弟の一般的な定義や、複雑な関係性)と出会うことで、まるで魔法にかかったように、新しい命を吹き込まれます。
それは、例えるなら、きらめく絵の具が、自分の真っ白なキャンバス(日常的概念)に鮮やかな色を添えてくれるようなものです。これまではただ「兄弟」と漠然と感じていたものが、「姉の兄弟は誰?」「兄弟の兄弟ってどういうこと?」と、より深く、意識して言葉を操りながら、考えられるようになるんです。日常的概念は、まさに「具体(目の前の体験)」から「抽象(次数を一つ繰り上げて物事を考えること)」へと、ぐんぐん伸びていくツル植物のように発展していきます。
ヴィゴツキーは、 生活的概念は、科学的概念とは逆に、具体(下)から抽象(上)へと向かって発達しているという言い回しを使っています。
つまり、私たちの知性が育っていく過程は、この「日常的概念」と「科学的概念」が、まるで二つの川が合流して、さらに大きく豊かな流れになるように、絶えず影響し合い、混じり合っていく「たゆまぬダンス」のようなものなのです。
ヴィゴツキーは、私たちの「日常的概念」と「科学的概念」の関係にそっくりなパターンを、なんと「母語」と「外国語」の間にも見つけました。
考えてみてください。みなさんは日本語を話すとき、いちいち「助詞の『は』は主語に使う」とか「動詞の活用はこうだ」なんて文法規則を意識しませんよね。赤ちゃんが言葉を学ぶときも、まず文字を覚えたり、辞書で単語の意味を調べたり、文法のルールを学んだりすることはありません。まるで、森の中で迷わず進む動物のように、自然に言葉の道をたどっていきます。つまり、「母語」は、感覚と経験を通して自然に身につく「日常の考え方」の道をたどって育っていくんです。
僕が以前、日本の保育園で遊んでいる子どもたちを観察していたときも、そんな不思議な光景を目にしました。小学校に入る前の子どもたちは、もう日本語のルールをバッチリ使いこなしています。例えば、「水をのむ」「水をのもう」「水をのんだ」「水をのまない」「水をのめば」といった言葉の形を、会話の中で完璧に使い分けているんです。
でも、その言葉の使いこなしは、まるで呼吸をするように無意識で、「よし、この言葉を使うぞ!」とわざわざ考えているわけではありません。生活の具体的な場面の中で、まるで自動販売機からジュースが出てくるように自然に出てくるんです。だから、もし「『のむ』っていう動詞を変身させてみてごらん?」と、具体的な状況から切り離して聞くと、子どもたちは「え、どうすればいいの?」「そもそも、『動詞』ってなんだ」と困ってしまいます。
まるで、水面に映る自分の顔を初めて見るように、子どもたちは学校で読み書きを学んだり、文法を習ったりする中で、初めて「あれ? 自分はこんなに日本語を使いこなしていたんだ!」と気づきます。そして、その気づきをきっかけに、ようやく自分の意思で言葉を自由自在に操れるようになるわけです。
一方、外国語を学ぶことは、まるで精密な設計図を最初に手に入れることから始まります。「ふーん、言葉ってこんな風に組み立てられているんだ!」と、文法という名の「骨組み」や「仕組み」を意識して、頭で理解しようとしますよね。だから、母語が「足元から自然に伸びていく草木」のように育つのに対し、外国語は「空から降りてくる雨粒」のように、まず理論やルールといった「上」から、私たちの心や感覚といった「下」へと染み込んでいくと言えます。
最近、僕は日本のニュースを見ていて、「えげつない」という言葉に偶然出会いました。僕にとって日本語は外国語なので、「えげつない」はまるで初めての土地で見つけた不思議な植物のようでした。辞書で調べてみると、「やり方や言い方が意地悪で、人情がない」と書いてあります。最初は「なるほど、そういう意味か」と、辞書の通りに受け止めていました。
でも、この言葉を耳にする機会が増えるにつれて、「あれ? 辞書に書いてある意味と、ちょっと違うんじゃないか?」と、だんだん気づき始めたんです。たとえば、MLB(メジャーリーグベースボール)の公式ツイッターが「球界で最もえげつない球を投げるのは誰?」と問うていたり、あるピッチャーが「えげつないカーブボールがすごい」と褒められていたりするのを見ました。そこでようやく、「ある野球選手が『えげつないピッチャー!』と言われるときは、その人がとてつもなくすごい実力を持っていることを意味するんだな」と分かってきたんです。
面白いことに、それだけではありません。「えげつないカーブ」というときには、投げられた側が思わずのけぞってしまうほど、ものすごく曲がるというニュアンスもあれば、同時に、相手からしたら手も足も出ないような、とんでもなく厳しい、容赦ない一球という意味も含まれている気がしました。
この「えげつない」という外国語の例では、まず頭で理解しようとする「意識的で複雑な特徴」(辞書の意味や、文脈から推測する応用的な意味)が先に育ちます。その後に、その言葉が、まるで体の一部のように自然に、そして自由に使えるようになる「より基本的な感覚」が生まれてくるんですね。
いわゆる「バイリンガル」と呼ばれる人は、まるで二つの異なる道(言語)を、どちらも意識せず、自然に駆け抜けることができるランナーのような人なんです。日本語の道も、韓国語の道も、いちいち「次は右足を出して・・・」とか「ここで息を吸って・・・」なんて考えずに、スイスイと走れる。どちらの言葉も「母語」みたいに、頭で文法ルールを組み立てる手間なしに、感覚で使いこなせる人のことなんです。
だから、僕はバイリンガルではありません。
一方で、バイリンガルは、二つの言葉をまるで呼吸をするように自然に、無意識のうちにスラスラと操れるという素晴らしい能力を手に入れる代わりに、僕のように二つの言葉を意識して、自分の意思でじっくりと選びながら使うという機会は、もしかしたら永遠に訪れないかもしれません。
それはまるで、野生の鳥が空を自由に飛び回るように、何の迷いもなく言葉を紡ぐバイリンガルと、一つ一つの言葉の羽根をじっくりと見つめ、「この羽根はどこへ向かうだろう?」と意識しながら、自分の手で組み立てていく僕のような人間の違い、とも言えるでしょう。僕にとっては、その「組み立てる」という行為自体が、言葉を深く味わう旅の一部なんです。
母語をベースに外国語を学んでいくことは、まるで目の前にあった霧が晴れて、言葉の全体像がはっきり見えてくるようなものです。外国語のルールを知ることで、「ああ、自分の母語も、実はこんな仕組みで動いていたんだ!」と気づかされます。これは、母語を意識的に、自分の意思で使いこなせるレベルへと引き上げることを意味します。
反対に、外国語を学ぶことは、まるで母語という木の横に新しい道を通すようなものです。その道を通ることで、私たちは自分の母語が、世界中に広がるたくさんの言葉の庭園の中の、ユニークな「一本の木」に過ぎないんだ、ということを理解できるようになります。
昔の偉い詩人ゲーテが言ったように、「外国語を一つも知らない人は、母語も本当には知らない」というのは、まさにそういうことなんです。まるで、一つの窓からしか景色を見たことがない人は、その部屋の本当の広さや、外の世界の多様さに気づけないのと同じですね。
最後にふっと思いついたことですが、 同じ言語であっても、地方(たとえば釜山)からソウルに上京してイントネーションをそっくり入れ替えたひとは(僕の友人にいます)、腹から立ち上がることばを失ったという意味では、一度は死んだといってよいでしょう。
韓国語の「김치」を「キムチ(Kimchi)」となんの苦労もなく母語の限られた音韻で発音するように、どこに行ってもイントネーションを変えない人間は、言葉という次元ではたしかに死を一度も経験していないのかもしれません。けれどもほんとうは、そのこと自体がひとつの死なのかもしれません。なぜなら、 外国語に接してみずからの母語が根底から揺らぐという経験を受けつけてこなかったのだから。
不器用でも、別の言葉、別のイントネーションや統辞法そしてロジックを口にできるほうが、自分を開くにはいいに決まっていると思います。 僕は日本語を学ぶことによって、その言語がなければ僕がついに気づくことのできなかった考えや感覚を知ることになりました。
それと同時に、僕は日本語という、外国語を学ぶことによって、母語である韓国語をより表情豊かで、多声的で、厚みのあるものにできるようになったと思います。母語運用の自由度が外国語の学習によって一層高まったと思います。
みなさん、ぜひ外国語を勉強しましょう。


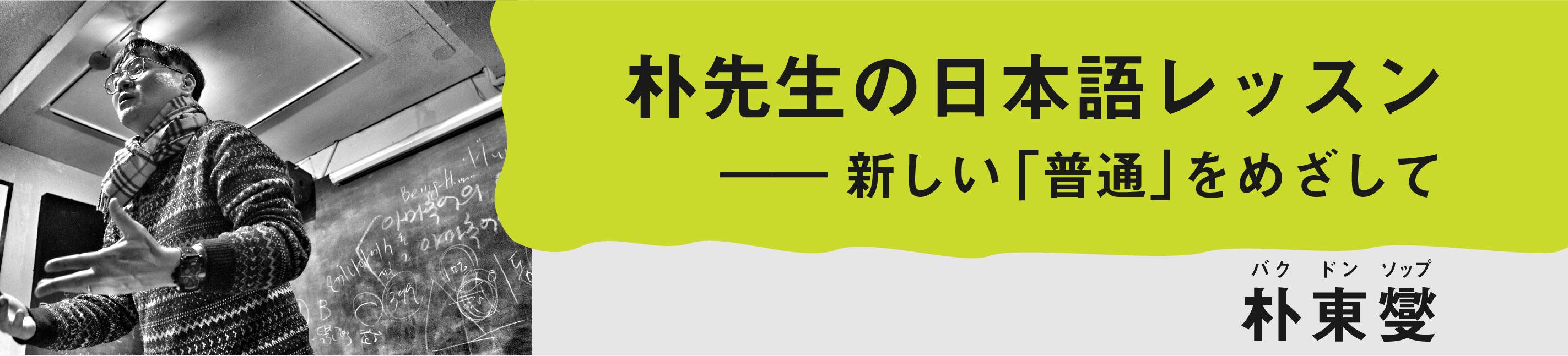



-thumb-800xauto-15803.jpg)


