第25回
家から出ない「独立研究者」
2025.09.24更新
MBSの西靖アナウンサーが、思想家・武道家の内田樹先生を評して口にした「家から出ない『知の伝道師』」というフレーズは、至高の言い回しです。このキャッチコピーには、知性が特定の場所に深く根を張り、そこから世界全体を透かし見るという、ある種の理想的な研究者像が凝縮されています。
この言葉の魔力に引かれ、私はいつしか自らを「家から出ない独立研究者」と密かに名乗るようになりました。かつては筑波大学の大学院で質的研究に勤しみ、山形県の庄内地方などを駆け巡るフィールドワーカーの端くれでした。しかし今、私のフィールドは釜山・
社会学の世界には、かつて「安楽椅子の理論家(アームチェア・セオリスト)」という、やや軽蔑的な言葉がありました。これは、現場の泥臭い現実から目をそらし、書斎の安楽椅子にふんぞり返って、観念的な理論だけをこねくり回す研究者を揶揄する言葉です。彼らは、社会を「向こう側(out there)」にあるものと捉え、自らの身体性を伴った参与を放棄します。
私は、この旧来の「安楽椅子の理論家」を擁護するつもりは毛頭ありません。しかし、その「安楽椅子」という装置を、思索のためだけでなく、観察のための特等席として再定義し、人文科学的な調査研究の新たな地平を切り拓くことを提案したいのです。ここでまず、「独立研究者」という存在について触れておく必要があるでしょう。
独立研究者とは、大学や公的な研究機関といった制度(アカデミア)の庇護の外に立ち、自らの知的好奇心と問題意識だけを羅針盤として研究活動を行う者です。彼らは(僕も含めて)、組織の論理や研究費獲得のための流行、学閥の力学から自由である代わりに、経済的な不安定さや知的な孤独という荒波を自力で乗り越えなければなりません。この自由と孤独の狭間で、独立研究者は必然的に、最も身近で、最も低コストで、そして最も誠実に向き合える研究対象――すなわち「自分自身」と「自分の日常」――に目を向けることになります。安楽椅子は、制度から解放された研究者の、いわば司令室であり、観測基地なのです。
では、この司令室から、具体的にどのような「データ」を拾い上げ、人文学的な洞察へと昇華させることができるのでしょうか。私の日常を例に、いくつかのケーススタディを挙げてみましょう。
<ケーススタディ1:小さな傷>
ある朝のこと。イルグァン(日光)の海辺を走ったあとにシャワーを浴びていたら、シャンプーの泡が目に入り、慌ててシャワーヘッドを探ろうとした瞬間、左手にチクリと鋭い痛みが走った。シャワーを終え、体を拭いていると、タオルにぽつりと赤いしみが――。見ると、左手の薬指の先が少し裂けていた。
シャワーヘッド。引っ越してきて五年、初めて私はこの浴室の道具をまともに見つめた。一体どの部分で手を切ったのだろう。よく見ると、我が家のやや時代遅れのシャワーヘッドには、水の流れを切り替えるノブが1センチほど突き出している。どうやら、泡にまみれたまま手探りしていた私の手が、ここに引っかかってしまったらしい。
「シャワーが人を傷つけることがあるのか・・・!」という驚きと、「それでも五年間無傷でいられたのか・・・!」という妙な感謝が、同時に胸をよぎった。近いうちに安全なものに替えよう。そう心に決めてシャワーヘッドに目をやると、それはまるで長年独立研究者という新たな人生を見守ってきた同志のように、ふと日常の秩序からはみ出して、こちらをじっと見返しているようだった。
その朝、私は釜山のある高校で講演の予定があり、久しぶりに家を出ることになっていた。出かけるまでのわずかな時間、小さなこの傷によって暴かれていく「日常の秩序」の数々に、私は次々と向き合わされる羽目になった。
たとえば――ワイシャツのボタンを留めるには、薬指の協力が必要であること。外出のたびに、ドアノブや玄関のドアを開けねばならぬこと。靴べらがあると意外に助かること。エレベーターの中でカバンを何度も持ち替えること。そして何より、右利きの私は、なぜか車のドアだけは左手で開け、運転中もハンドルを無意識に左手で操作しているという事実・・・。
どれもこれも、これまで一度たりとも意識されたことのない、小さくて大きな「当たり前」だった。
だが、真の試練は仕事だった。なんと運の悪いことに、その日私は、釜山のとある歴史ある市民団体に講演原稿を送らねばならず、締切という名の怪物に追い詰められていた。仕上げの作業のためにパソコンを立ち上げ、キーボードに手を置いたその瞬間――「あいたっ!」と思わず声が漏れた。
ちょうどその傷が、キーの打面にピンポイントで触れる場所だったのだ。しかも痛みは、指先からというより、全身から分泌されているかのように広がっていく。私はそのとき、朝ごとにボタンを押して始まるこの作業が、実はこの左手の薬指一本に支えられていたのだと、初めて思い知った。
もしパソコンのない生活が考えられないのなら、左手薬指のない生活もまた、考えられないではないか。これこそが、この小さな傷が私に暴露した、決定的な真実だった。
そんなこんなで3日ほど、まるで「私の人生は左手の薬指にかかっている」かのような幻想を抱く頃には、傷はゆっくりと癒えはじめ、そして私は、再び自分の人生を満たしていたあの崇高なる日常の真実たちを、徐々に忘れていったのである。
<ケーススタディ2:「ない」ものが見える:会話のなかの「超能力」>
2025年8月、
事件が起きたのは、今日の昼下がり。研究素材は、私の母と、スマホに魂を抜かれた私の娘のギョンリョン(17歳)だ。祖母=ハルモニと孫娘=ミンジュンの会話を聞いてみよう。ハルモニは、見るからに涼しげなスイカのファチェ(화채、韓国の伝統的なフルーツポンチ)を手に、リビングに現れた。
01 ハルモニ: ミンジュナ〜、ファチェ食べるかい? 《スマホ画面に釘付けの孫に》
02 : 《2秒の沈黙》
03 ミンジュン: あ、うん。食べる。
さて、ここで問題です。この会話の02行目、2秒の沈黙。この沈黙の主は誰だったでしょう?
この問いに、あなたはおそらく一瞬も迷わず「ミンジュンだ」と答えるはずだ。素晴らしい。あなたもまた、会話における「超能力」の使い手である。
文字通りに考えれば、02行目で声を発していないのは、ハルモニもミンジュンも同じだ。しかし、我々は決して「ハルモニが黙っている」とは感じない。それどころか、ミンジュンが01行目で黙っていることにも、我々は何の不思議も感じない。我々が見ているのは、こういう光景だ。
01 ハルモニ: ミンジュナ〜、ファチェ食べるかい?
→ 02 ミンジュン: 《沈黙》
このとき、我々の「超能力」はさらに鋭さを増す。我々には、この場に「ない」ものが見えているのだ。それは「ミンジュンの応答」である。
このリビングには「ない」ものが無数にある。例えば、キリンも、宇宙戦艦も、フランス大統領もここにはいない。だが、我々の目にはただ一つ、「ミンジュンの応答がない」ことだけが、くっきりと、まるでそこに存在するかのように見えている。
これこそが、会話分析で言うところの「隣接対(adjacency pair)」が引き起こす奇跡である。
「隣接対」とは、「提供-受諾/拒否」のような、ペアで機能する社会の偉大な発明品だ。第一対成分(ハルモニの提供)が発せられれば、その直後には第二対成分(ミンジュンの応答)が来るべきだ、という規範的な期待が、我々の脳内に自動的にインストールされている。
ハルモニは、この装置の力を借りて「ミンジュンに応答させる」というミッションを遂行しようとした。彼女は「ファチェを食べるかい?」というボールを投げたのだ。ミンジュンがすべきことは、それを「食べる」と受け取るか、「いらない」と打ち返すか、ただそれだけだった。
しかし、ミンジュンは2秒間、このボールを無視した。スマホという名のブラックホールに吸い込まれていたからだ。この2秒間、リビングの空気は奇妙に張り詰めた。それは単なる「無音」ではない。「応答が来るはずの空間が、空っぽのまま放置されている」という、非常に意味のある沈黙だったのだ。
この「応答不在」が見える能力こそ、我々が社会生活を円滑に(あるいは時々、気まずく)営むための根源的な力なのである。挨拶をすれば挨拶が返ってくる。質問をすれば答えが返ってくる。そして、釜山のハルモニがファチェを差し出せば、孫は感謝と共にそれを受け取る(べきである)。この期待があるからこそ、我々はコミュニケーションの海で溺れずに済んでいる。
安楽椅子から一歩も動かずとも、かくも深遠な社会の仕組みが、スイカの浮かんだ器一つを巡って展開されている。今日のフィールドワークは上出来だ。さて、私も自分の分のファチェを確保せねば。なにせ、ここでも「提供―受諾」の隣接対が、いつ不発に終わるとも限らないのだから。
<ケーススタディ3: 台所という名のエコロジカル・ニッチ>
台所について、ちょっと真面目に考えてみたことはあるだろうか?
そう、あの毎朝バタバタと卵を焼いたり、コーヒーをこぼしたり、時には人生の愚痴をこぼしたりする、あの場所のことだ。冷蔵庫、調味料、鍋、まな板、時には謎の賞味期限切れの何か──そこはまるで「日常という舞台」の大道具小道具がすべて揃った裏方のような空間である。
だが、よくよく目を凝らしてみると、台所とは実は、ヴィゴツキー心理学がいうところの「エコロジカル・ニッチ(生態学的なすき間)」として機能している、というとちょっとカッコつけすぎだろうか。でもまあ聞いてほしい。
私たちは台所で料理をする。だがそれはただ食材を切って炒めるという動作以上のものだ。包丁はいつも同じ場所にあり、塩と胡椒は夫婦のように隣り合い、レシピは冷蔵庫に貼られたマグネットの下でじっとこちらを見つめている。気づかぬうちに私たちは、この空間に「秩序」という名のリズムを与え、そこに「私たちの役割」を埋め込んでいるのだ。
この「秩序」は、頭の中にある理屈ではない。台所という現場そのものが、すでに記憶の構造を代行してくれている。包丁を探すとき、私たちは脳内の記憶引き出しをゴソゴソ開けるのではなく、まっすぐに「包丁がいつもいる場所」へと手を伸ばす。これは記憶ではない。場所が私たちに思い出させてくれるのである。
心理学の実験室では、たとえば被験者に「バナナ・りんご・ドライバー・ピアノ」というリストを覚えさせては、「さあ、何があったか言ってごらん」と試す。でも台所ではそんなことは起きない。りんごは冷蔵庫の野菜室に、ドライバーはなぜか引き出しの奥で眠っている。バナナは、子どもがもう食べたかもしれない。すべてが意味のある場所にあり、私たちはその配置とともに思い出すのだ。
つまり、台所というのは、私たちの脳の外側にあるもうひとつの「記憶装置」なのである。いや、これではまだ言葉が足りない。これは単なる「外部記憶」などではない。環境それ自体が、課題そのものを変えてしまうのだ。
たとえば、包丁を思い出す必要があるか? いや、目の前に置かれていれば、「思い出す」という動作そのものが不要になる。記憶というより、出会いに近い。私たちは、記憶しないことで、むしろスムーズに生きている。
このように、環境を変えることで、私たちの「認知的な役回り」も変わっていく。探す人から、見つける人へ。思い出す人から、ただそこにいる人へ。
私たちはいつの間にか、「記憶」そのものを最小限にして生きている。レシピは壁に貼り、冷蔵庫にはメモを貼り、スマホにはリマインダーをセットする。記憶するより、忘れても困らないように環境を整える──これが私たちの賢さであり、ズボラさであり、そして人間らしさでもあるのだ。
こうして見ると、「料理ができる」というのは、単に腕前の問題ではなく、「台所というニッチ」との連携プレーなのだ。私たちの認知も、能力も、ぜんぶ台所という舞台装置あってこそ踊れるダンスなのである。
「安楽椅子の理論家」という言葉が揶揄したのは、現実から遊離した観念の遊戯でした。しかし、私が提唱する「安楽椅子の調査研究」は、それとはまったく逆のベクトルを向いています。それは、自分自身の生という、最も否応なく突きつけられる現実(リアリティ)に深く潜っていく営みです。
社会的世界は、「向こう側」にだけあるのではありません。「ここ」にこそ、その凝縮された姿があります。社会のメンバーとして、私たちはすでにその世界の複雑なルールや文脈を熟知した「ネイティブ・インフォーマント」(フィールドワーカーに情報を提供する現地の人)なのです。ならば、最もアクセスしやすい観察対象である「自己」と「日常」を研究の出発点とすることに、何の躊躇が必要でしょうか。
今日も私は、
かつての社会学者が、遠い異国の村に参与観察のフィールドを求めたように、私は「私」という名の部族が暮らす、「日常」という名の村を参与観察します。データが必要なら、私の経験と活動のすべてがデータです。研究に必要なものは、すでにすべて用意されています。
かくして、私の一日は、私自身の生きた人文学の教科書となります。そしてこの安楽椅子こそが、世界で最もアクティブなフィールドなのです。


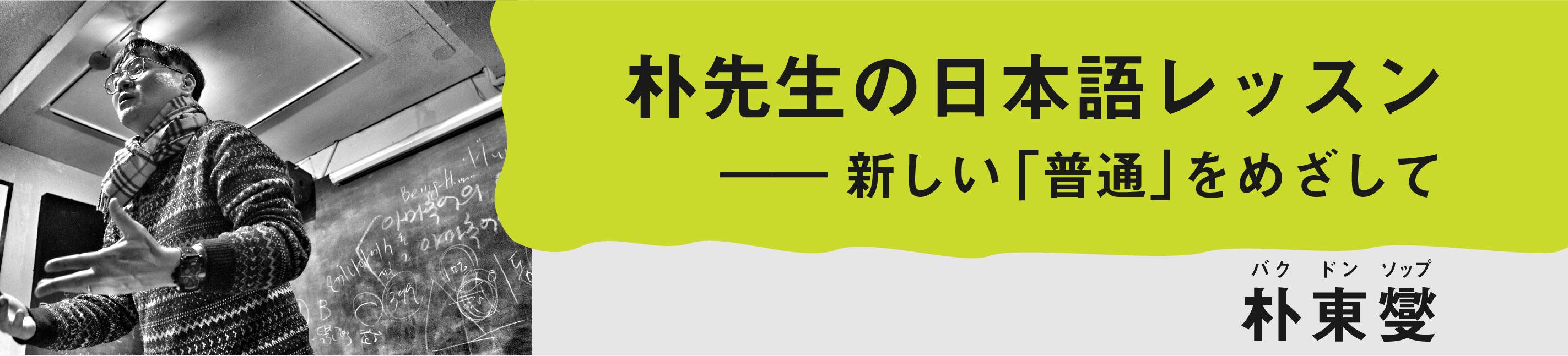



-thumb-800xauto-15803.jpg)


