第24回
ラブをしようぜ!――『ミスター・サンシャイン』から学ぶ愛のトリセツ
2025.09.12更新
「ラブが、したい」
かの有名な韓国ドラマ『ミスター・サンシャイン』で、李氏朝鮮時代末期の高貴な令嬢エシンは、アメリカ人将校ユジンにそう宣言する。もちろん、英語にも西洋文化にもほとんど触れたことのない彼女は、「ラブ」が何なのか、まったく知らない。だからユジンは、ちょっと意地悪く、でも本当のことを言う。
「一人ではできない。相手が必要だ」 「ならば、私としよう」 「・・・それは、銃を撃つより難しく、それより危険で、それより熱いものだ」
いやあ、シビれますね。最近、このドラマにハマっていてついにイビョンホンの大ファンになってしまったという編集者のSさんの話を聞いて、僕も改めて見直しているんですが、このやりとりは最高に面白い。なぜって、これはただの恋愛ドラマのワンシーンじゃない。僕たちが毎日当たり前のように使っている「ラブ」や「恋愛」という言葉が、かつては存在すらしなかった「謎の輸入品」だったという、壮大な歴史の秘密を暴いているからです(希望的観測)。
実は、この「ラブ」の話、僕が今度の高校での講演でやろうと企んでいるネタなんです。
事の経緯を話すと、去年、釜山のある高校で「ヴィゴツキー心理学」について講演したんです。そうしたら、「3時間じゃ短すぎる!」という、嬉しいんだか困るんだか分からないクレーム(?)が届きまして。ありがたいことに、アンコール講演が決定したわけです。
そこで何を話そうか。そうだ、『ミスター・サンシャイン』のエシンのように、「ラブって何?」という根源的な問いから始めてみよう。ヴィゴツキーの言う「歴史的なものの見方」――つまり、「普通じゃん」って思うことこそ、「それ、いつから普通になったの?」と疑ってみる知的冒険に、高校生たちを誘ってみよう、と。
「恋愛」という名の、ピカピカの輸入品
考えてみてください。今でこそ「恋愛」という言葉を何の不便もなく使っていますけれど、柳父章の名著『翻訳語成立事情』によれば、昔の日本には「love」にピッタリくる言葉がなかった。もちろん、「恋」とか「色」とか「情」はあった。でも、それらはちょっと意味合いが違う。
当時の感覚を、スマホのアプリに例えてみましょうか。 江戸時代の日本人が持っていたのは、「恋アプリ(切なさ、憧れ機能特化型)」と「色アプリ(ちょっとオトナ向け、遊郭エリア限定)」の二つ。結婚は家と家との契約、つまり「家業経営シミュレーション」みたいなもので、個人の感情は二の次でした。
そこへ、西洋から「LOVE」という、とんでもなく多機能で高性能な、最新アプリがやって来た。さあ大変だ。既存のアプリじゃこの「LOVE」の概念は処理しきれない。そこで当時の頭のいい知識人たちは、「恋愛」という、まったく新しい国産アプリを開発したのです!
巌本善治のような思想家は、この「恋愛」という、当時としてはまだ新品の輸入コンテナに、これまで誰も詰めたことのない中身――つまり「魂から魂へと響き合う深い愛情」という希少で芳醇なワイン――を満たそうとしたのです。
それは、遊郭の暖簾の奥で交わされる刹那的な色恋とは似ても似つかない、社会的にも公に認められる、対等な男女の精神的結びつきでした。言ってみれば、これは恋愛という「新型の精神的ツール」を使った、心の働きの革命だったのです。
ヴィゴツキー風に言えば、この「ラブ」という輸入語は、単なる異国情緒の飾り物ではなく、当時の日本人の思考を変形させ、感情の回路を作り替える「心理的道具」だったわけです。その道具を手にした人間は、その道具に合わせて手の形を変えるように、その言葉に合わせて心の形を変えていく――まるで初めて箸を使う子どもが、手の動かし方を覚えていくように。
そして、このドラマの舞台である1900年代の朝鮮でも、それは同じでした。
エシンには親が決めた婚約者がいます。しかし二人の間には「ラブ」など影も形もない。結婚は家のための取引であり、個人の心はまるで包丁で切り落とされる大根のヘタのように脇に置かれていました。
そんな時代に、この「ラブ」という未知の言葉が、まるで黒船が港に現れるように――いや、黒船の甲板から降ろされた西洋製の不思議な機械のように――エシンの前に突然現れたのです。その瞬間、彼女の精神世界には、新しいレバーと歯車が組み込まれ、古い仕組みでは動かなかった感情の時計が、静かに、しかし確実に動き出したのでした。
愛は名詞じゃない、動詞だ!アクションだ!
じゃあ、その「恋愛」って一体何なのか。辞書を引けば定義は書いてあります。でも、そんなものを読んでも、恋愛は実践できません。
では、ちょいと「辞書」というやつについて考えてみましょうか。
「辞書は、いまこの瞬間の言葉づかいを正確に写し取っているのか?」――これ、答えはもうカンタン。「ノー!」です。
なぜって、辞書というのは「言葉の生放送」じゃないんです。あれは録画放送、いや、もっといえば歴史のアルバムです。「この前の夏、こんなふうに話してましたよ」みたいな集合写真のようなもの。
だから、辞書は未来の我々を正しく導く魔法のコンパスでもなければ、「はい、これが唯一の正解です」と金ピカのスタンプを押してくれる裁判官でもありません。あれはむしろ、「いやぁ昔はこういう意味だったんですよ・・・今はどうか知りませんけどね」と、ちょっとお節介な古老のような存在なんです。
つまり辞書に書いてあるのは「この言葉の意味は〜であった(※ただし現在もそうだとは限らない)」という、いわば「注釈つき過去形」なんですね。
そう、辞書はいつだって「現在」に対してはちょっと不正確。ですから、辞書を盾に「おやおや、あなたの言葉づかいは間違ってますよ」なんて言うのは、まるで江戸時代の地図でスマホのナビを論破しようとするようなもの。そもそも「間違った言葉づかい」なんて、この世には存在しないんです。
とはいえ、「辞書は役立たず」と言っているわけじゃありません。辞書はちゃんと我々の旅の道しるべになります。世界という広大な森を歩くとき、ポケットに忍ばせておくと頼もしい「古地図」のような存在です。
ただし――この古地図、川の流れが変われば線を描き直し、道が増えれば書き足し、山が消えれば消しゴムでこすらなきゃいけない。そういう宿命を背負っているのです。
辞書は「正解の石板」じゃなくて、「日々書き換え必須の歴史絵巻」。だから、ページをめくるたびに、ちょっとしたタイムトラベル気分を味わえるのです。
昔読んだ小説に、面白い青年がいました。彼はガールフレンドとセックスする前に、まず「愛とは何か」「現代人は愛しうるか」というテーマで徹底的に討論し、合意形成に達してから事に臨むという。
・・・アホでしょう? そんな議論を百万語費やすより、議論で乾いた喉に、そっと冷たい水の入ったグラスを「はい」と差し出す行為の方が、よっぽど「愛とは何か」を教えてくれる。僕の直感ですが、具体的なもの、断片的なものの方が、かえって物事の本質を「腑に落ちる」かたちで示してくれるんです。
もちろん、ここには定量的な分岐点がありますよ。 例えば、そのグラスが指紋でベトベトで、中の水は昨日から汲み置きしたぬるま湯で、しかも渡すときにビシャビシャこぼしながら「ほらよ!」って感じで突き出したとしたら・・・。それは、あまり「愛」については教えてくれないでしょうね(笑)。どこかの分岐点を超えると、その行為は「愛の印」とは解釈されなくなる。
つまり、「愛」や「恋愛」は、美術館に飾られた彫刻のような「名詞」じゃない。絶えず動き続ける「動詞」であり、具体的な「アクション」なんです。
人間というのは、社会的動物である――なんて、心理学の教科書に書いてあることを改めて言うまでもありませんが、実際はもっとややこしい。私たちは放っておくと、勝手に他者と関係を作り、そこに感情を流し込み、ドラマを組み立てるクセがあります。そして、その舞台装置としての「人工物=メディア」抜きには、現代の恋愛はほぼ成立しません。
たとえば、LINE。あの小さな緑のアプリは、感情の宅配便です。「おはよう」のスタンプひとつに胸を躍らせ、「既読」のまま放置されては胃を痛める。もし宇宙人が地球を観察したら、カフェの隅でスマホを必死にタップする二十代女性を、まるで未知の呪文を打ち込む技術者か、銀河戦争の司令官だと勘違いするかもしれません。でも実際に彼女が操っているのは、冷たい機械ではなく、沸騰寸前の恋心そのものなのです。
文化が違えば、この「感情の伝送装置」も多種多様。ある民族の男性は、美しい彫刻を施した小刀を女性に贈り、それが求愛のサイン。女性がそれを腰に下げれば「オーケー、交際スタート」。まるでBluetoothペアリング成功の合図です。
ドラマ『ミスター・サンシャイン』では、まず握手、次にハグ、と西洋式プロトコルで関係がアップデートされていきます。
一方、現代日本と韓国の恋愛プロトコルはもっと長い取扱説明書を持っています。
まず「告白」というセキュリティ認証を通過し、付き合いが正式稼働。週末デートという定期メンテナンスを行い、LINE(韓国ではカカオトーク)でメッセージというデータ通信を交わし、誕生日にはプレゼントというファームウェア更新、そして最終的にはキスやセックスという高次互換モードへ移行します。
この一連の儀式ややりとりは、恋愛感情という「ソフトウェア」を媒介しながら、逆にその感情の仕様書を書き換えていくテクノロジーでもあります。
だからこそ、「キスの前に告白しなきゃ」とか、「付き合って半年なのにまだ手もつながない」とか、「LINEで既読になってるのに返事がこない」なんて心配は、この人工物とプロトコルの組み合わせから生まれる「副作用」でもあるわけです。
こうして恋愛感情は、確かに個人の心の中に存在するようでいて、実は具体的な人工物の配置や相互行為の様式を土台にした、れっきとした社会的現象なのです。
つまり、恋愛とは――Wi-Fiなしではつながらない、しかしつながったら最後、感情データが無限に流れ続ける、極めて人間的で、極めてテクノロジー的な「心のインフラ」なのです。
僕らはみんな、物語づくりの天才だ
先日、講演に向かう電車の中で、テスト終わりらしい男子高校生二人の会話が聞こえてきました。これがまた、最高のネタ提供だったんです。
A君:「なあ、付き合って数ヶ月の彼女、最近なんか素っ気ないんだよ。インスタのプロフ画、前は俺とのツーショットだったのに、この前友達と旅行行ったときの写真に変わってたしさ・・・。俺、振られたのかな?」
B君:「バカ! そんなんでビビってどうすんだよ! 『プロフ画変えたくらいで動揺してんの?器ちっさ!』って思われるぞ! 男ならドーンと構えとけ!」
いやあ、感心しました。彼らの「お話を思いつく能力」に。 僕たち人間は、どんな断片的な情報からでも、瞬時に物語を紡ぎ出す天才なんです。コンピュータ科学者が「データを無視する能力」と呼ぶ、人間だけのスーパーパワー。バラバラのデータ(彼女の素っ気ない態度、プロフ画の変更)を、瞬時に一つの「物語」(①俺はもうすぐ振られる物語、②ここで動揺したら負けだ物語)として編成してしまう。
明治の知識人たちが、「love」を崇高なもの、「色」を卑俗なものとする「物語」を作ったのもこれと同じ。そうやって「自分自身に何かを説明すること」、それこそが「知る」ということの本質なんです。
でも、忘れてはいけない。その「物語」の作り方自体が、自分が生きる時代や歴史に、がっつり縛られているということを。僕が大学生の頃なら、彼女と連絡が取れなくなったら「家の電話に出るのがお父さんだったら気まずいからな・・・」なんて物語を作っていたかもしれません。今なら、まず「LINEの既読スルー」というデータから物語が始まりますよね。そして、そのような 「主体の時代性や歴史性の見落とし」についての反省的な知(なんならそれを「哲学」 と呼んでもいいと思います)もまた、僕が今回試みたように「ある話を思いつく」というかたちをとる他ありません。そしてまた・・・
発酵するラブ
さて、最後にユジンとエシンの話に戻りましょう。
エシンは、その日、生まれて初めて「ラブ」という言葉を耳にしました。
意味は――皆目わからない。形も色も匂いも想像できない。
辞書をめくっても出てこないし、出てきたとしてもきっと「へぇ〜」で終わる程度。
けれど、その言葉を口にしたユジンの眼差し、やわらかくも熱のこもった声の響き、その瞬間を包み込む空気の温度、ほんのかすかな花の香り、胸の奥をチクリと刺すような痛み・・・そうした五感の残像が、ゆっくりと、湖の底に沈む
その澱は、じっと動かず、しかし時間をかけて変化します。まるで台所の隅に置き忘れられた梅酒(僕、これ大好きです)が、知らぬ間に黄金色へと熟していくように。
いや、それはパン種かもしれないし、壺の中で静かに息をしている味噌かもしれない。いずれにしても、「ラブ」という名の微生物は、エシンの心の中で密かに繁殖を始めたのです。
やがて、その発酵は静かな泡立ちを見せます。
ある日――それは洗濯物を干している最中かもしれないし、寝ようと布団の中に入っているときかもしれない――ふと「ぽこっ」と、一つの泡が表層まで浮かび上がってくるのです。その瞬間、エシンは胸を衝かれ、思わず息を呑むでしょう。
「ああ・・・ラブって、そういうことだったのね」と。
その気づきは、誰かに「はい、これが答えです」と手渡されるものではありません。教科書の脚注にも載っていなければ、試験問題にも出ない。
それは、じっと自分の内側で熟成され、ある日、自分の手でそっとふたを開けて見つける宝物のようなものです。
まるで古い押し入れの奥から、子どもの頃に描いた落書き帳を見つけてしまったような、懐かしさと照れくささと、ちょっとした感動が同時に押し寄せてくる。
そして思うのです。
「知る」ということは、もしかしたらこういうことなのかもしれない、と。
・・・だから、僕たちの「ラブ」もまた、今日も誰かの胸の奥で、味噌壺のように静かに、しかし着実に発酵しているのです。
時折ふたを開ければ、甘酸っぱい香りがふわっと広がり、まだ見ぬ誰かをほろ酔い気分にさせる――そんな「ラブ」が、あちこちの心の中で、しずしずと育っているのです。


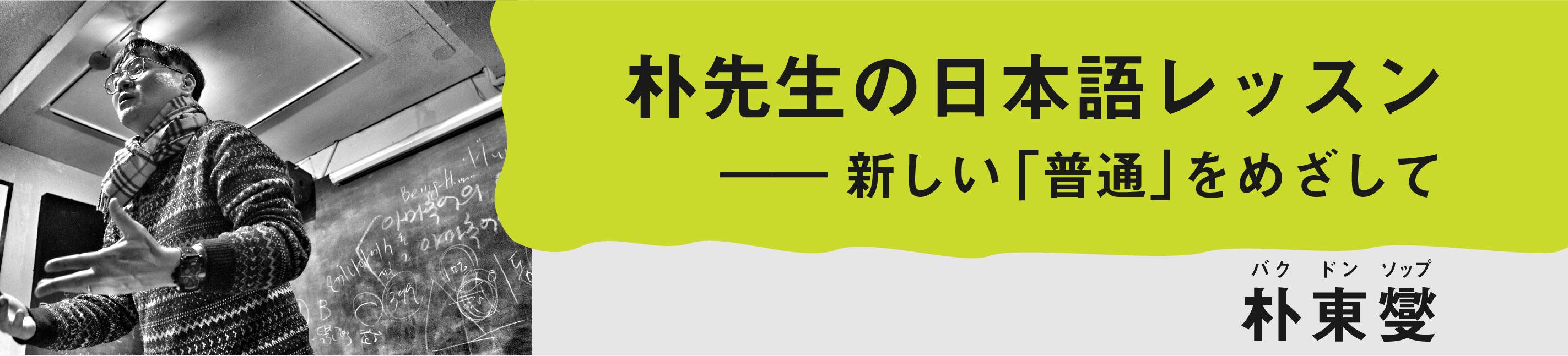



-thumb-800xauto-15803.jpg)


