第27回
ラブをしようぜ!3――「握手」から愛をデザインする
2025.10.23更新
はじめに:金曜21時の「既読」
ある韓国のドラマの一コマです。
金曜日の夜、時計の針が二十一時を指した瞬間、彼女のスマートフォンが静かに震える。画面に浮かび上がったのは、マッチングアプリで知り合い、三度目のデートを約束していた男からのカカオトーク(韓国でよく使われているメッセージアプリ)だった。
「ごめん、急な仕事で行けなくなった」――短い文字列。その後に続くのは、眉を下げた愛らしいキャラクターのスタンプ。
わずかな電子の震えと、無機質な光の中に、約束の夜が淡々と終わっていく。まるで、観客の前で小さな幕が音もなく降ろされるかのように。
最近の恋人同士のコミュニケーションは、これで終わりです。そこに、かつて恋人たちが交わしたであろう手紙のインクの匂いも、長電話で熱くなった受話器の温もりもありません。あるのは、デザインされた定型文と、デザインされたキャラクターが代弁する、軽やかで、そして少しだけ空虚な感情のやり取りです。
私たちは、いつからこんなにも「デザインされた」愛の形に慣れ親しんでしまったのでしょうか。Instagramで「映える」デートスポットを探し、食べログの評価でレストランを選び、カカオトークの返信速度で相手の好意を測る。まるで、あらかじめ用意された設計図の上を、間違いのないように慎重に歩いているかのようです。
しかし、この「恋愛」という名の設計図は、一体誰が、いつ描いたものなのでしょうか。
考えてみてください。カカオトークやInstagramがなかった時代の「親友」と、今の「親友」が違う意味を持つように、私たちが当たり前だと思っている「恋愛」という観念もまた、時代と共にデザインされ、その形を変え続けてきたのかもしれません。友情という根源的な関係性でさえ、テクノロジーによってその「味」をデザインされ続けるのですから、愛もまた然りでしょう。
この壮大な設計図の起源を求め、そしてその意味を問うために、私たちは少しだけ時間を遡る旅に出る必要があります。旅の始まりは、西洋から「love」という未知の言葉が、初めてこの国にたどり着いた時代。そう、明治の日本です。
第一章:明治の翻訳者が見た夢 ―「恋愛」の誕生秘話
時は明治維新の真っ只中。西洋からの新しい知識や文化が、まるで堰を切ったように日本へと流れ込んでいました。蒸気機関車が煙を上げ、レンガ造りの建物が空を目指し、人々は断髪して洋装を纏う。その変化の奔流の中で、一人の翻訳者が頭を抱えていました。彼の名は、仮に「森口亮介」とでもしておきましょう。
森口は、当代随一の知識人として、数々の西洋文学の翻訳を手掛けていました。シェイクスピアの悲劇、ジェイン・オースティンの機知に富んだ会話、ブロンテ姉妹の荒野に響く情熱。物語はどれも、彼の心を強く打ちました。しかし、その感動を日本語に移そうとするたび、彼は巨大な壁に突き当たります。その壁の名は「love」でした。
辞書を引けば、「愛」「恋」「情」「色事」といった言葉が並びます。しかし、どれもしっくりこないのです。物語の中で描かれる「love」は、男女が互いの魂に惹かれ、身分や家柄といった社会的制約を超えて結びつこうとする、対等で、理知的で、そして何より強烈な意志を伴う関係性でした。それは、親が決めた相手と添い遂げるのが当たり前だった当時の日本において、ほとんど存在しない概念でした。
「これを、どう訳せばいいのだ・・・」
森口は、ランプの揺れる灯りの下で、インクの染みがついた指で何度も髪をかきむしりました。
「色恋沙汰」と訳せば、それは単なる浮ついた遊びのように聞こえてしまう。物語の主人公たちが命を懸けて貫こうとする、その精神的な崇高さが消え失せてしまいます。 「夫婦の情」と訳せば、そこにある燃えるような情熱や、結婚に至るまでの葛藤が抜け落ちてしまう。あまりに穏やかで、静的すぎるのです。 「愛」という一文字は、あまりに広範でした。親子や兄弟の愛、主君への忠愛、神への愛。そのすべてを包み込む言葉では、男女間の特別な結びつきを表現するには、焦点がぼやけてしまいます。
彼は、西洋の男女が「I love you」と囁き合う場面を想像しました。それは、決して一方的な感情の吐露ではないはずです。そこには、相手を尊重し、理解し、共に人生を歩もうとする双方向の意志がある。個として自立した「私」と「あなた」が、自由意志によって結びつく、近代的な人間関係の形なのです。
「これは、単なる言葉の問題ではない。新しい『人間関係の形』そのものを、この国に紹介するということなのだ。」
そう思い至った時、彼の脳裏に一つの光が差し込みました。 情熱的な側面を持つ「恋」。 そして、慈しみや精神的な結びつきを意味する「愛」。
この二つの漢字を組み合わせるのはどうだろうか。
「恋」と「愛」。 「恋愛」。
その二文字を紙に書きつけた瞬間、森口は小さな戦慄を覚えました。それは、まるで新しい生命を産み落としたかのような感覚でした。この言葉ならば、西洋文学に描かれた、あの複雑で、情熱的で、そして崇高な男女の関係性を、日本の人々に伝えることができるかもしれない。
もちろん、それは完璧な翻訳ではなかったかもしれません。しかし、森口亮介という一人の翻訳者が、苦悩の末に「デザイン」したこの「恋愛」という言葉は、これから日本の男女の心の中に、全く新しい世界を創造していくことになるのです。それは、未知の感情に名前を与えることで、その感情そのものを人々の心に芽生えさせる、壮大な文化的実験の始まりだったのでした。
第二章:言葉が心をつくる時 ― ヴィゴツキー心理学で読み解く「新しい感情」の芽生え
森口亮介が産み落とした「恋愛」という言葉は、やがて活字となり、人々の間に静かに、しかし着実に広がっていきました。それは、まるで無色の水に一滴の絵の具を垂らしたかのようでした。最初は小さな点でしかなかったその色は、ゆっくりと溶け出し、水全体を鮮やかに染め上げていきます。
20世紀の心理学者レフ・ヴィゴツキーは、「言葉は思考を形成する」と述べました。私たちは、言葉という道具(記号)を使って世界を理解し、他者と関わり、そして自分自身の内面、つまり心を構築していく、と考えたのです。彼によれば、言葉の無いところに、明確な思考や感情は存在しにくいのです。
明治の日本で起こったのは、まさにこの「言葉による心の創造」でした。 「恋愛」という言葉が生まれる前、男女間の個人的な強い惹かれ合いは、名前のない感情でした。それは「みだらなこと」として社会から非難されるか、あるいは文学の世界の中だけの「儚い夢物語」として処理されるしかありませんでした。人々は、その感情を表現するための共通の語彙を持たなかったのです。それは、色の名前を知らない人が、夕焼けの空を見ても「なんだか燃えるような感じがする」としか言えないのと同じです。
しかし、「恋愛」という新しい文化的道具が人々の手に渡ると、世界は一変します。
それは、真っ白なキャンバスに、「恋愛」という名の全く新しい絵の具セットが与えられたようなものでした。人々は、その絵の具を使って、これまで描くことのできなかった新しい人間関係の絵を、少しずつ描き始めたのです。
女学生たちは、西洋の小説を読みながら、自分たちの胸の高鳴りに「恋愛」という名前を付けました。それまで「はしたない」と抑圧してきた感情が、美しく、追い求めるべき価値のあるものとして肯定された瞬間です。 青年たちは、「恋愛」の名の下に、家柄や身分を超えて意中の女性に想いを伝えることの正当性を得ました。「家」のためではなく、「自分」の気持ちのために行動するという、近代的な自我の目覚めです。
「恋愛」という言葉は、人々に新しい視点を与えました。「私の気持ちは、どうなのだろうか?」「あの人は、私のことをどう思っているのだろうか?」。家と家の結びつきという大きな物語から、個人の内面という小さな、しかし切実な物語へと、人々の関心がシフトしていったのです。
まるで、それまでモノクロームの世界に生きていた人々が、突然「赤」や「青」や「黄」という色の名前を教えられ、世界がどれほど色彩豊かであったかに初めて気づいたかのようでした。公園のベンチも、街灯の灯りも、交わす視線の一つひとつも、「恋愛」というフィルターを通すことで、特別な意味を帯びて輝き始めたのです。
もちろん、この新しい絵の具は、すぐに誰もが使いこなせたわけではありません。古い価値観との間で板挟みになり、悲劇に終わった恋も数多くあったでしょう。しかし、一度手にした新しい心の道具を、人々が手放すことはありませんでした。
こうして、「恋愛」は単なる翻訳語であることをやめ、人々の心の中で実際に生き、呼吸し、時には痛みさえもたらす、リアルな感情へと姿を変えていきました。それは、一人の翻訳者の苦悩から始まった、壮大な心のデザイン革命だったのです。
第三章:握手から始まる愛 ―『ミスター・サンシャイン』に見る「原初的デザイン」の輝き
さて、ここで私たちの旅は、もう一つの物語へと向かいます。明治の翻訳者が「love」という概念の設計に苦心していたのと、ほぼ同じ時代。朝鮮の地で出会った、一組の男女の物語です。アメリカで育った米軍将校ユジン・チェと、朝鮮の名家の令嬢コ・エシン。彼らの対話は、言葉が生まれる以前の、愛が「デザイン」されていくまさにその瞬間を、鮮やかに切り取っています。
まず、彼らの心を揺らした、あの印象的な会話を、日本語で再現してみましょう。
ユジン:「考えはまとまった。やりましょう、ラブを。俺と。一緒に」
エシン:「よろしい。・・・返事が遅れた分、その決断が慎重なものであることを願う」
(少し間があって)
エシン:「それで、次は何をすればよいのだ?」
ユジン:「まずは、自己紹介から」
エシン:「ああ・・・。私はコ・エシンだ。あなたの名前は、かねがね聞いている」
ユジン:「すぐに、読めるようにもなるでしょう」
(ユジンは、自分の名前を綴った紙を見せる)
ユジン:「チェ・ユジンだ」
エシン:「朝鮮ではチェ姓だったのか?」
ユジン:「アメリカでもチェという苗字だ。アメリカ人は『チェ』を『チョイ』と発音するが」
エシン:「ああ・・・。学べど学べど、まだ遠い道のりだな。・・・それで、他に何をする?」
ユジン:「握手」
エシン:「握手・・・?」
(ユジンが手を差し出す)
ユジン:「握手は、アメリカ式の挨拶だ。この手には、あなたを害する武器を持っていない、という意味がある」
(エシンは、その意味を聞き、ゆっくりと彼の手を握る)
エシン:「その意味、たいそう気に入ったわ。ラブとは、思ったよりもたやすいのだな。始まりが半分、と言うからか。・・・ところで、この手はいつ離すのだ?」
ユジン:「あなたが、その手に武器を持ちたいと思った時に」
エシン:「・・・少なくとも、今ではないようだな」
この会話の、なんと豊かで示唆に富んでいることでしょう。 ここには、現代を生きる私たちが当たり前のように使っている「恋愛の設計図」が一切存在しません。
ユジンは「love」という言葉と、それが示す関係性の完成形を、知識として知っています。彼は、いわば「愛の設計図」を頭の中に持っている建築家です。一方、エシンはその言葉も概念も知りません。彼女にとって、それは全くの未知の領域。彼女は、設計図のない土地に立っているのです。
この状況で、ユジンが取る行動は、現代の私たちのそれとは全く異なります。彼は「好きです、付き合ってください」という、パッケージ化された告白の言葉を使いません。なぜなら、そのパッケージを受け取る文化が、エシンにはないからです。
代わりに彼がしたのは、「love」という壮大な建築物を、その構成要素であるレンガの一つひとつから、エシンと共に積み上げていく、という途方もない作業でした。
その最初のレンガが、「握手」だったのです。
彼は、ただ「これが挨拶だ」と手を差し出すのではありません。「この手には武器がない」という、その行為に込められた「意味」を丁寧に説明します。これは、関係性を築く上での最も根源的な要素、すなわち「信頼」の表明です。 物理的な接触を通じて、まずは心の武装を解く。それが、彼のデザインした「ラブの第一歩」でした。
エシンの「ラブとは、思ったよりもたやすいのだな」という言葉は、実にユーモラスで、本質を突いています。これは、最高級レストランの複雑なフルコースを知らない人が、シェフが心を込めて握った熱々の塩むすびを食べて、「こんなに美味しいものがあるのか!」と心から感動するのに似ています。余計な装飾や手順がないからこそ、その行為の持つ温かさや誠実さが、ダイレクトに心に響くのです。
現代の私たちの恋愛を、家具量販店の組み立て説明書通りに作るお洒落な棚だとすれば、ユジンとエシンのそれは、森で木を切り倒し、道具も十分にない中で、手探りで一脚の椅子を作り上げるようなものです。完成した椅子は、少し不格好かもしれません。しかし、そこには木の温もりと、二人の息遣いと、試行錯誤の跡が、確かに刻まれているのです。
私たちは、いつしか「恋愛」という完成された設計図に頼りすぎるようになりました。相手の気持ちを確かめる前に、カカオトークの返信パターンをネットで検索する。二人だけの特別な場所を探す代わりに、Instagramで「#デートスポット」を検索する。失敗を恐れるあまり、マニュアル化された安全なルートばかりを選んでしまう。それは、効率的かもしれませんが、ユジンとエシンが体験したような、関係性をゼロから「創造」していく根源的な喜びやスリルを、どこかに置き忘れてはいないでしょうか。
ユジンが差し出した手は、単なる挨拶ではありませんでした。それは、言葉も文化も違う相手に対して、「私はあなたを理解したい」という意志そのものでした。そしてエシンがその手を握り返した時、そこには、まだ名前のない、しかし確かな信頼と好奇心に満ちた、新しい関係性が誕生したのです。それは、誰かが作った設計図の上ではなく、二人の間にだけ存在する、世界でたった一つの「愛の原初的デザイン」でした。
終章:あなた自身の「愛」をデザインするために
再びドラマの世界に。
画面の中では、主人公が既読スルーされたトーク画面をじーっと眺めています。
その真剣な眼差しを見ていると、まるで国家の命運でも背負っているかのよう。
でも実際は――ただの既読スルー。
「この軽やかな感情のキャッチボールは、果たして二人を繋げているのか?」
明治の翻訳者が、西洋の「love」という巨大な概念を前にして、一つの言葉を「デザイン」したように。 朝鮮の地で、ユジンがエシンのために、握手から始まる「ラブ」を一つひとつ丁寧に「デザイン」したように。 「愛」とは、元来、完成品として与えられるものではなく、自分たちで悩み、考え、築き上げていく、極めて創造的な営みだったはずです。
テクノロジーは、私たちのコミュニケーションを驚くほど便利にしました。SNSは、かつては出会うはずのなかった人々を結びつけます。しかし、その「デザインされた便利さ」は、時として私たちから、関係性を手作りする喜びや、相手と真摯に向き合う時間、そして言葉にならない感情を伝えようとする努力を奪ってしまうのかもしれません。
友情が「いいね!」の数で測られるようになり、愛が「既読」の速さで推し量られる時代。私たちは、もう一度立ち止まって考える必要があるのではないでしょうか。私たちが今歩いているこの「恋愛」という名の道は、本当に私たちが望んだ道なのか、と。
ユジンとエシンのように、時には既成の設計図から自由になって、相手の前に、誠実な、裸の手を差し出してみる。そして、その手に武器がないことを、自分自身の言葉と態度で伝えてみる。それは、とても勇気がいることで、効率の悪いやり方かもしれません。
しかし、そうして手探りで築き上げた関係性の中にこそ、誰にも真似できない、あなたと、あなたの愛する人だけの、本物の「愛のデザイン」が宿るのではないでしょうか。
スタンプ一つで終わる関係もあれば、一つの握手の意味を、生涯をかけて分かち合っていく関係もある。どちらが良いという話ではありません。ただ、私たちが忘れてはならないのは、「恋愛」という設計図は、あくまで先人たちが遺してくれた一つの見本に過ぎない、ということです。
その設計図をどう使い、あるいは、全く新しい設計図をどう描くのか。 最終的なデザイナーは、いつの時代も、他の誰でもない、私たち自身なのですから。


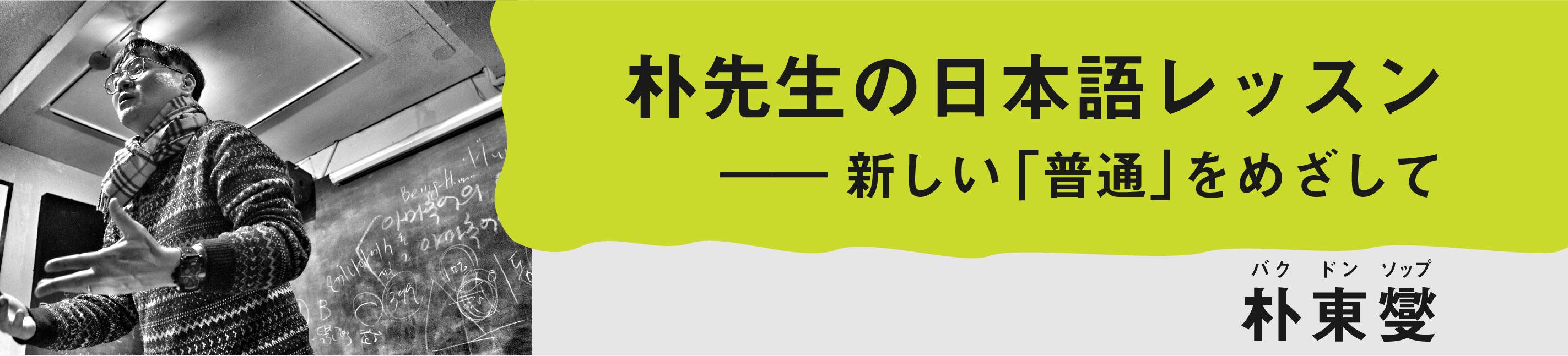



-thumb-800xauto-15803.jpg)


