第26回
ラブをしようぜ!2――言葉が魂に火を灯すとき
2025.10.07更新
はじめに:ある高貴な令嬢の素朴な問い
「러브가 무엇이오?」(ラブとは、何ですか?)
三度目の正直――とでも申しましょうか。「ラブをしようぜ」というテーマで文章を書くのは、これでもう三回目になります。
最初はこの「朴先生の日本語レッスン」の第24回に、二度目は韓国の人文学雑誌に。そして活字だけにとどまらず、高校生相手に二度ほど講演でも語ってしまったのですから、ここ最近の私は、どうやら"ラブ推し"の説教師と化しているようです。
さすがにこれだけ繰り返して語るとなると、自分でも不思議に思うのです。
「どうして私は、こんなにも同じ題目に執着しているのだろう」と。
もちろん、単にこのエピソードが便利で"話のネタ"として重宝するから――というだけではない。
むしろ逆に、同じ話を何度持ち出しても、そのたびに気持ちはどこか置き去りにされ、必ず「まだ言い残したことがある」という不完全燃焼の感覚だけが残るのです。
だから、Aで語った「同じ話」とBで語った「同じ話」は、表面上は瓜二つに見えても、実のところ微妙にずれている。話は同じでも、そこから私が掬い取る知見は、少しずつ、けれど確実に変わってきているのです。
その"ずれ"のおかげで、読者の皆さんが味わう愉しみもまた、モザイク画のように色彩を増していく。
――というわけで、今回もまた「同じテーマ」を抱えて筆を執ることにしました。
ただし、同じ川を二度は渡れぬように、この三度目の「ラブをしようぜ」もまた、別の色合いを帯びて流れていくはずです。
さて、第24回でも取り上げたドラマ『ミスター・サンシャイン』の世界に再び戻りましょう。1900年代初頭の朝鮮。西洋の文物と思想が怒涛のごとく押し寄せる激動の時代。固く閉ざされた伝統の中で、国の未来を憂う高貴な令嬢、コ・エシンが、異国の文化で育った米軍将校、ユジン・チョイに問いかけます。彼女にとって「Love」とは、意味の分からない異国の言葉、まるで遠い国の珍しい蝶の標本のようなものでした。
しかし、彼女の「하고 싶어 그러오(やってみたいのです)」という言葉には、単なる知的好奇心を超えた、自らの意志で新しい世界に触れたいという、魂の渇望が込められていました。それに対するユジンの答えは、辞書的な定義ではありませんでした。「Love」は「銃を撃つことよりも難しく、それよりも危険で、それよりも熱くなければならない」。この詩的で、謎めいた言葉は、エシンの心に小さな火種を落としました。
この二人のやり取りは、単なるドラマの一場面に留まりません。それは、西洋の「Love」という概念が、漢字文化圏である日本と韓国に初めて根を下ろそうとした瞬間の、歴史的な「概念の衝突」を見事に描き出した、一つの寓話と言えるでしょう。
本稿では、この感動的なシーンを道標としながら、時を遡り、壮大な旅に出たいと思います。まずは、日本で「Love」がいかにして「恋愛」という言葉に結晶化したのか、その劇的な翻訳の物語を紐解きます。次に、「恋愛」以前の日本と韓国で、男女の「情」や「色」がどのようなグラデーションを描いていたのかを探ります。そして再びエシンの心の内側に戻り、固く閉ざされた世界に生きた一人の女性が、未知の感情「Love」と出会ったとき、その魂の中で何が起こったのかを、色彩豊かな比喩を交えながら、ドラマティックに描き出してみたいと思います。
第一章:「恋愛」の劇的な誕生―ある翻訳の物語
明治維新。西洋への扉がこじ開けられた日本には、蒸気機関車や煉瓦造りの建物と共に、目に見えない無数の「概念」が上陸しました。「自由」「権利」「社会」「個人」...。当時の知識人たちは、これらの新しい思想にふさわしい日本語を、まさに産みの苦しみを味わいながら創造していきました。その中でも、最も翻訳が困難を極めた言葉の一つが「Love」でした。
なぜなら、以前にも触れましたが、当時の日本語には、西洋の「Love」が持つ複雑なニュアンス―すなわち、個人の自由意志に基づき、精神的な結びつきを重んじ、時には自己犠牲さえ厭わない、人格的なパートナーシップとしての愛―を的確に表現する言葉が存在しなかったからです。
もちろん、愛に類する言葉はありました。例えば「恋(こい)」。これは多くの場合、片思いの切なさや、相手への強い思慕の情を指しました。『万葉集』の時代から、日本の文学は「恋」の歌に満ちていますが、それは成就しないからこそ美しい、という美学さえありました。
また、「愛(あい)」という言葉もありました。しかし、これは仏教的な「慈愛」や儒教的な「仁愛」のように、親子や主君と家臣の間の情愛、あるいはもっと博愛的な、普遍的な愛を指すことが多く、男女間の情熱的な感情を指す言葉としては一般的ではありませんでした。
そして、より官能的な側面を担っていたのが「色(いろ)」です。遊郭などの色町で使われたこの言葉は、男女間の性的な駆け引きや、粋な遊びとしての情事を意味しました。「色好み」といえば、そうした世界に精通した通人を指したのです。
このように、「恋」は精神的だが一方的、「愛」は広範で非個人的、「色」は肉体的だが遊戯的。西洋のキリスト教文化を背景に持つ、精神的かつ人格的で、相互的な「Love」の概念を、これらの既存の言葉で受け止めることは不可能でした。
この知的な格闘の中で、一つの新しい言葉が生まれます。それが「恋愛」です。
この言葉を近代的な意味で社会に広めた立役者の一人が、夭折の天才、北村透谷でした(柳父 章、 1982年『翻訳語成立事情』)。彼は、キリスト教の影響を受けながら、西洋文学を深く読み込み、「Love」の本質は「人世の秘義」であり、精神的な合一にあると考えました。彼は、単なる情欲である「色」や、一方的な思慕である「恋」を批判し、男女が互いの人格を尊重し、魂と魂で結びつくことこそが真の「Love」であると主張しました。そして、その崇高な概念の受け皿として、「恋」と「愛」という二つの漢字を組み合わせた「恋愛」という言葉に、新しい命を吹き込んだのです。
「恋愛」は、単なる翻訳語ではありませんでした。それは、封建的な「家」制度からの個人の解放を願う、近代日本の知識人たちの「宣言」でした。結婚が家と家の契約であり、個人の感情が抑圧されていた時代に、「恋愛」は、自分の意志でパートナーを選び、精神的な幸福を追求する権利があるのだ、という新しい価値観の象徴となったのです。
それはまさに、言葉による革命でした。たった二文字の漢字が、人々の生き方、幸福の形、そして人生の意味さえも、根底から変えてしまうほどの力を秘めていたのです。この「恋愛」という名の船は、やがて海を渡り、朝鮮半島にも新しい時代の風を運んでいくことになります。
第二章:「恋愛」以前の風景―情と色のグラデーション
では、「恋愛」という言葉が生まれる前、あるいはそれが社会に浸透する前の日本と韓国で、男女の心はどのような風景を描いていたのでしょうか。そこには、現代の私たちが考える「恋愛」とは全く異なる、しかし豊かで複雑な「情」と「色」の世界が広がっていました。
【日本の風景:『家』の秩序と『遊郭』の夢】
江戸時代から明治初期にかけての日本において、男女関係を理解する鍵は、「内(いえ)」と「外(そと)」の厳格な区別にありました。
「内」、すなわち武士や商人の「家」における結婚は、個人の感情が入り込む余地はほとんどありませんでした。それは、家の存続と繁栄という至上命題のための、極めて実務的な契約でした。妻の最も重要な役割は、跡継ぎを産み、家を切り盛りすること。夫にとって妻は、共に家を守る「戦友」あるいは「経営パートナー」であり、そこに燃えるような情熱やロマンスが求められることは稀でした。夫婦の間には、長年連れ添ううちに育まれる穏やかな「情愛」や「信頼」はあったかもしれませんが、それは現代の私たちが「恋愛結婚」に期待するものとは、明らかに異質のものでした。
一方、男たちが情熱やロマンス、そして癒しを求めた場所が、「外」の世界、すなわち吉原に代表される「遊郭」でした。遊郭は、単なる売春の場ではありません。そこは、洗練された文化サロンであり、一種の劇場空間でした。最高位の遊女である「太夫(たゆう)」は、美貌はもちろんのこと、和歌、書道、茶道、楽器など、一流の教養を身につけたアーティストであり、男たちは彼女たちとの擬似的な「恋愛」を楽しみました。
ここで交わされる関係は「色」と呼ばれ、そこには「粋(いき)」という独特の美学が存在しました。金銭に物を言わせる野暮な振る舞いは軽蔑され、客と遊女の間には、本音と建前、嘘と真実が入り混じった、繊細でスリリングな心理戦が繰り広げられました。客は遊女の気を引くために財を注ぎ込み、遊女は客の心を見抜きながら巧みにあしらう。時には、本気の「情」が芽生え、駆け落ち(心中)に至る悲劇も生まれましたが、それはあくまで例外的な逸脱でした。
この時代の男性の心は、家の秩序を守る「妻」と、夢と幻想を見せてくれる「遊女」との間で、巧みに分割されていたのです。結婚は「現実」、遊郭での恋は「非日常」。この二つが交わることは、基本的にはありませんでした。「恋愛」という、唯一のパートナーと精神的・肉体的に深く結びつき、現実の生活を共にする、という概念は、この分割された心の世界には、まだ生まれる余地がなかったのです。
【韓国の風景:『儒教』の規範と秘められた『情(정)』】
一方、李氏朝鮮時代の韓国では、より厳格な儒教の規範が、男女関係を鉄の規律で縛っていました。「男女七歳にして席を同じうせず」という言葉に象徴されるように、公的な場での男女の接触は極度に制限されていました。
ここでも結婚は、徹底して「家門(かむん)」と「家門」の結びつきでした。当人たちの意思は完全に無視され、親同士が家柄や財産を考慮して決めるのが当然でした。花嫁は、婚礼の日に初めて花婿の顔を見る、ということさえ珍しくありませんでした。
このような状況で、夫婦の間に最初から熱烈な愛情が生まれることは、まずあり得ませんでした。妻に求められたのは、夫への絶対的な服従、舅・姑への献身的な奉仕、そして跡継ぎとなる息子を産むことでした。夫にとって妻は、自らの家門を維持するための重要な存在ではあっても、心をときめかせる恋愛の対象ではありませんでした。
しかし、人間である以上、感情を完全に押し殺すことはできません。この厳格な社会にも、秘められた形で男女の「情」は存在しました。その一つが、韓国文化の深層に流れる「情(정、ジョン)」という概念です。これは、日本語の「情」よりもさらに広く、深く、複雑な意味を持つ言葉です。夫婦が長い歳月を共に過ごす中で、言葉には出さない信頼や憐憫、一種の戦友として育まれる、空気のような絆。これもまた「情」の一つの形です。
そして、社会の規範から逸脱する形で燃え上がる、禁断の恋もありました。ドラマ『ミスター・サンシャイン』の時代より少し前の物語である『春香伝(チュニャンジョン)』は、妓生(キーセン)の娘と両班(ヤンバン)の息子の身分違いの恋を描いていますが、これはあくまで例外的な物語として語り継がれたものです。現実の社会では、そのような関係は「정분(ジョンプン、情分)」と呼ばれ、発覚すれば家門の名誉を汚す、命がけのスキャンダルでした。
このように、朝鮮の男女関係は、表面的には儒教の厳格な規範に覆われていましたが、その水面下では、言葉にならない「情」が静かに流れ、時には禁じられた「情分」が激しい渦を巻いていたのです。しかし、個人の自由な意志で相手を選び、社会的に公認された形で情熱的な関係を築く「恋愛」は、やはり遠い異国の夢物語でしかありませんでした。
第三章:鍵のかかった部屋―ある両班令嬢の心の奥
このような時代に生きた両班の令嬢、コ・エシンの心の中は、どのような世界だったのでしょうか。彼女が「Love」という言葉に出会う前、その魂は、静かで、美しく、しかし外界から隔絶された、手入れの行き届いた庭園のようだったと想像できます。
その庭には、四季折々の花が咲き、決められた場所に植えられた木々が静かに佇んでいます。彼女の人生は、その庭園のように、一分の隙もなく設計されていました。読むべき書物、習うべき作法、着るべき衣服、交わすべき言葉。全ては、両班の令嬢として、そして未来の許嫁の妻としての役割を果たすために、定められていました。
彼女の心の中には、
しかし、ユジン・チョイという男の出現は、その静謐な庭園に、見たこともない異国の鳥が舞い込んできたようなものでした。あるいは、静かな湖面に、突然投げ込まれた一個の石。彼の存在は、彼女の世界の調和を静かに、しかし確実に乱し始めます。彼が話す異国の言葉、彼の立ち居振る舞い、そして彼の瞳の奥にある、彼女が知らない世界の影。その全てが、彼女の心にさざ波を立てていきました。
彼女がユジンに対して抱き始めた、名付けようのない感情。それは、朝鮮の言葉で言うならば「恋慕(연모、ヨンモ)」に近いものかもしれません。しかし、彼女にとってそれは、教科書で習ったどの感情とも違う、熱を帯びた未知の感覚でした。まるで、今まで存在すら知らなかった、自分の心の中の「鍵のかかった部屋」を偶然見つけてしまったかのようです。その部屋の扉の隙間からは、微かに甘い香りが漏れ、聞いたことのない音楽が聞こえてくる。彼女は、その扉を開けてみたいという、抑えがたい衝動に駆られます。
許嫁への道が、陽の光の下にまっすぐに続く、舗装された道だとすれば、ユジンへと続く道は、月明かりだけが頼りの、霧深い森の中の小径のようでした。危険で、どこに続いているか分からず、踏み迷えば二度と帰れないかもしれない。しかし、その道の先には、今まで見たことのない景色が広がっているという、抗いがたい予感がありました。この名もなき感情の正体を知りたい。その渇望こそが、彼女を「ラブとは、何ですか?」という、運命的な問いへと導いたのです。
第四章:「銃よりも危険で、熱いもの」―言葉が魂に火を灯す瞬間
エシンの「하고 싶어 그러오(やってみたいのです)」という言葉は、彼女が生きてきた世界において、驚くほど革命的な響きを持っていました。それは、常に「〜すべき」「〜してはならない」という規範の中で生きてきた女性が、自らの「したい」という純粋な意志を、何の飾りもなく表明した瞬間だったからです。それは、まだ意味も分からない「Love」という行為を、自らの人生の選択肢として能動的に掴み取ろうとする、自我の芽生えの宣言でした。
この純粋で、しかし力強い意志の表明に対して、ユジンは驚くべき応答をします。彼は「Love」を説明しません。彼は「Love」を翻訳します。しかし、それは言葉から言葉への翻訳ではなく、概念から「魂の体験」への翻訳でした。「銃を撃つことよりも難しく、それよりも危険で、それよりも熱くなければならない」。
「銃を撃つよりも難しくなければならない」 エシンは、国を守る義兵として、銃の撃ち方を知っています。狙いを定め、引き金を引く。そこには冷静さと技術、そして覚悟が必要です。ユジンは、ラブとはそれ以上に難しいと言います。なぜなら、銃が狙うのは物理的な「的」ですが、ラブが狙うのは、絶えず変化し、揺れ動く「相手の心」だからです。そして、何よりも自分自身の心という、最もコントロールの難しい的を射抜かなければならないからです。この一言で、ラブが単なる遊びや気まぐれではなく、人生を懸けた真剣な営みであることが、エシンに伝わります。
「それよりも危険でなければならない」 銃は命を奪う危険なものです。しかしユジンは、ラブはそれ以上に危険だと言います。銃弾が傷つけるのは肉体ですが、ラブが傷つけるのは「魂」だからです。裏切られたときの痛み、失ったときの絶望は、時に死よりも辛い苦しみをもたらします。そして、エシンとユジンの場合、二人のラブは、家門、身分、国籍、そして時代そのものに反逆する、あまりにも危険な行為でした。この言葉は、ラブが甘い夢であると同時に、全てを破壊しかねない劇薬であることを、彼女に予感させます。
「それよりも熱くなければならない」 銃口から放たれる弾丸は熱い。しかし、ラブはそれ以上の熱を要求します。それは、理屈や計算、損得勘定をすべて焼き尽くしてしまうほどの、抑えがたい情熱の炎です。常識を、ためらいを、恐怖心を溶かしてしまうほどの熱量。この言葉を聞いた瞬間、エシンの心の中にある「鍵のかかった部屋」の扉の向こう側で、何かが「カチリ」と音を立てて燃え上がったはずです。それは、今まで彼女が経験したことのない、人生の根源的なエネルギーの奔流でした。
このユジンの言葉は、エシンの心の中で、不思議な化学反応を引き起こしました。それまで単なる記号、異国の音の響きでしかなかった「Love」という言葉に、意味と、質感と、温度と、そして命が吹き込まれたのです。
彼女の心の中に湧き上がった感情は、もはや単なる好奇心や憧れではありませんでした。それは、「危険」を承知の上でその炎に飛び込んでみたいという「覚悟」であり、自らの人生を自らの意志で燃焼させたいという「渇望」でした。ユジンの言葉は、彼女の魂に火を灯す、魔法の呪文となったのです。彼女はまだ、その炎が自分自身を、そして愛する人を、やがて焼き尽くすことになるかもしれない運命を知りません。しかし、その瞬間、彼女は確かに、新しい人間として生まれ変わったのです。
結論として
「恋愛」という言葉が、近代日本の知的な苦闘の末に生み出された一つの「発明」であったように、コ・エシンの心に芽生えた「ラブ」への理解もまた、ユジン・チェという翻訳者を得て、彼女自身の魂の中で行われた、きわめて個人的で、創造的な「発明」でした。
言葉は、単なる記号ではありません。一つの新しい言葉との出会いは、私たちの心の中に新しい部屋を作り、新しい感情を発見させ、時には人生の航路を全く変えてしまうほどの力を持っています。日本と韓国が「恋愛」という新しい窓を手に入れたことで、人々の幸福観が大きく変わったように、エシンもまた、「ラブ」という窓を通して、全く新しい世界、そして全く新しい自分自身を発見したのです。
ドラマ『ミスター・サンシャイン』のあの美しい場面は、私たちに教えてくれます。真のコミュニケーションとは、言葉の意味を正確に伝えることだけではない。相手の魂に火を灯し、新しい世界の扉を開ける手助けをすることなのだ、と。そして、その出会いは、時に銃よりも危険で、しかし何よりも熱く、私たちの人生を根底から揺さぶるほどの価値を持っているのだ、ということを。


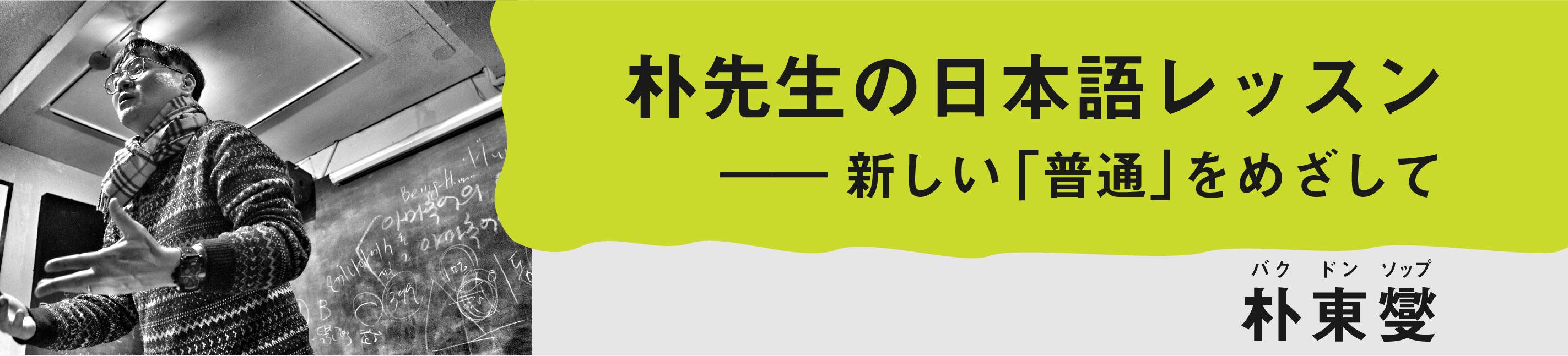



-thumb-800xauto-15803.jpg)


