第22回
僕はバイリンガルではありません(前編)
2025.08.05更新
ときどき、日本語話者と日本語で会話をする機会に恵まれています。そのときに必ずといっていいほど彼/彼女らから言われるのが「朴先生、日本語がほんとうにお上手ですね。」という言い回しです。そういわれるたんびに照れた顔で「いえいえ、まだまだです。頑張ります!」と、どうみても「日本語話者がいいそうな」フレーズで対応することにしています。あるいは、たまには「語学の天才だから、しょうがないんです」という、とんでもない発言をして、相手を当惑させたりする時もあります。
日本語に堪能になるというのは、要するに、日本語のストックフレーズをたくさん覚え込んで、日本語話者が「いいそうなことを」タイミングよく同じような口調とイントネーションとしぐさで復唱することになるということだと僕は思います。つまり、日本語で語るということは、日本語話者たちの思考や生き方、そして身体の使い方までを身につけ、承認し、それを受けいれるということ。逆にいえば、韓国語で思考したり表現したりするということは、韓国語話者に固有の思考のパターンと身体の使い方、韓国人のある種の「種族の思想」を受け入れるということです。
つい最近、日本語話者からこんな誉め言葉をいただきました。
「日本語が母語の人以上に濃やかで美しい日本語を話される朴先生。感嘆するばかりです」
僕の最新の美談です。
ところで、なぜこの友人は、「『母語の人以上に』濃やかで美しい日本語」という表現を使ったのでしょうか。僕はそのことがすごく気になりはじめました。
おそらく、僕が一つの日本語のセンテンスを発するときのしぐさや、発声に深くしみ込んだ日本語特有の言語的リズムや抑揚を高く評価してくれたからでしょう(たぶん)。また、正しい日本語の文法をベースにした豊かな語彙力と表現力があったからかもしれません。ひとつひとつの日本語に織り込まれている「文化」を僕が身をもって体現しているということも関係がありそうです。
ある活動しているとき、その活動について「自分を含む風景を上空から俯瞰する想像的視座」に立つことを、「メタ」と言います。野球をしていて、冗長な展開になってしまい、ルールを変えよう、なんて話し合いを始めたとすると、それは野球のプレイそのものではなく、野球のプレイについての話し合いだから、「メタ野球」と言えるでしょう。
子どもの頃、遊び相手の人数、空き地の広さ、ピッチャーの力量などに応じて、ストライクやボールの定義を変えたということはないでしょうか。たとえば、ピッチャーのコントロールがひどく悪いとき、通常のルールに従っていては、ゲームはフォアボールの連続で、およそしまりのないものになる。こんなとき、ストライクゾーンに入らないボールをボールとカウントしないというようなことが行われるのではないでしょうか。あるいは、人数や道具のそろい方に応じて、ベースを二つにしたり、三つにしたりということは、素人の野球においては日常茶飯事でしょう。このように一連のプロセスを俯瞰的に考えるのが「メタ野球」です。
自分が普段なにげなく使っている「言葉」についても、「この言葉の使い方はどういうルーツがあるのか」と考え始めたら、それは「メタ言葉」であり、さらには「なんで僕は普段使っている言葉のルーツなんて考えちゃうんだろう」などと考えだしたら、それは「メタメタ言葉」ということになる(と思います)。
自分が普段なにげなく使っている「言葉」についていろいろ「メタ」的に思考するということは、いかにして可能となるのでしょうか。そして「日本語を母語話者以上に使いこなす」原動力はどこからくるのでしょうか。 今回はこの問いに答えていきたいと思います。
ロシア―の心理学者のヴィゴツキー(1)の議論の一つに、「科学的概念」と「日常的概念」というものがあります。言葉の意味の発達に関して、子どもがどんなふうに発達過程を経過していくのかという議論です。
日常的概念(生活的概念)とは、簡単にいうと、子どもが、日常生活の中で単語と対象物を見ることによって学ぶ概念です。これに対して科学的概念とは、学的な、つまり学校で知識として学ぶような概念です。ヴィゴツキーは概念の学び方にはこの二つがあるとし、その間の内的な緊張関係を考えています。
具体的にいうと、こんな接続詞の用法の発達の研究があります。
たとえば、次の括弧を埋めて文章を完成させてください。
「男は自転車から落ちた。なぜなら( )」
「計画経済はソビエトにおいて可能になった。なぜなら( )」
このうちどっちの穴埋めが子どもにとって易しいかむずかしいかを、ヴィゴツキーたちは研究したのです。
日常生活の場面でよく出会うという意味では、「男は自転車から落ちた」は生活的概念で、「計画経済はソビエトにおいて可能になった」は、学校で出会うことが多い科学的概念を使った文章、ということになりそうですよね。
そういう考え方をすると、前者の穴埋めほうが易しくて、後者の計画経済云々というほうが難しいということになりそうですが、実はヴィゴツキーたちが見い出した結果というのは逆です。
ヴィゴツキーたちは、子どもたちにとって穴埋めすることが難しいのは「計画経済」の文章よりも「自転車」の文章のほうだというのです。
この子どもたちは日常のなかで「なぜなら」という言葉を問題なく使いこなせていました。しかし、この言葉を「接続詞」として捉え、その機能や文の中での位置づけを理解して「意識的」に使うことはできなかったのです。自然に使えていた「なぜなら」を意識的に使おうとすればするほど、そのやり方がわからなくなってしまう。一方で、「計画経済はソビエトにおいて可能になった、なぜなら」という言い回しは、学校の授業やテストで何度も目にする機会があり、いわば丸暗記していたから、難なく穴埋めができる子が多かった。
子どもたちにとって、日常会話で「なぜなら」を使うのは、自転車に乗るようなものでした。一度乗り方を覚えてしまえば、ペダルを漕ぐ順番やハンドルの角度なんていちいち考えなくても、スイスイと目的地に着ける。ごく自然で、無意識のテクニックです。
ところが、先生が「その自転車の乗り方を、力学の法則や筋肉の動きから説明しなさい」と言った途端、彼らはパニックに陥ります。今まで自然にできていたはずのペダルの踏み込み方さえ、分からなくなってしまうのです。
一方で、「計画経済はソビエトにおいて可能になった、なぜなら...」という文章は、補助輪付きで、決まったコースを走るだけの一輪車ショーのようなもの。これは「乗りこなしている」のではなく、「決められた手順を暗記して、その通りに体を動かしている」だけ。だから、テストで穴埋めをするのは簡単だったのです。
この点をさらに検証するため、ヴィゴツキーたちは、自然な会話では問題なく「ので」という接続詞を使いこなしている小学二年生の子どもたちに、日常の経験に関連する内容で文を完成させる課題(たとえば、「~~ので、自転車に乗っていた人が自転車から落ちた。」「~~ので、貨物船が海に沈んだ。」)を出しました。
その結果、子どもたちはこうした課題をうまくこなせないことが多く、「かれは自転車から落ちて足を折った。かれを病院へ運んだので。」といった不自然な文章を答えてしまうことが分かりました。
この面白い実験の結果をヴィゴツキーは次のように説明しています。
自分の自然な会話では申分なく正しく「ので」という言葉を使用するこの子どもが、「ので」の概念そのものはまだ「自覚」していないのである。子どもは、この関係をそれを「自覚」する前から利用する。彼が適当な状況の中で習得したこの構造を「随意」に使用することが、彼にはまだできないのである(2)。
この課題は、子どもが日常いくらでも「無意的」にできることを「随意的」に行なうことを子どもに要求するから、むずかしいのです。
日頃よく子どもと接する人なら、小学二年生の子どもが「ので」という接続詞を状況にあわせて正しく使用することを知っているでしょう。自転車に乗っている人が街路で倒れるのを子どもが目撃したとすれば、子どもは決して「彼を病院へ運んだので、彼は足を折った」とは言わない。ところが、テストではそのように言うのです。
「なぜなら」という言葉をうまく使えない子どもたちに足りないのは、言葉や考え方を「意識して、自分の意思で使いこなす」力だと言えます。ヴィゴツキーはそういう現象のことを 「自覚性」とか「随意性」が足りないという言い方で説明しています。
(後編につづく)
(1)ヴィゴツキー/柴田義松(訳)『思考と言語(下)』明治出版、1962年。
(2)同上、52頁。


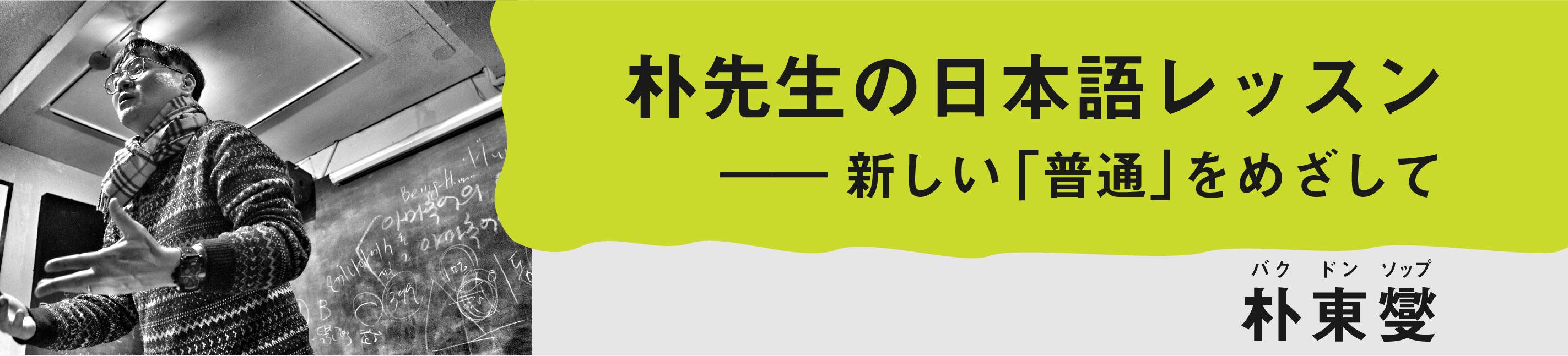



-thumb-800xauto-15803.jpg)


