第13回
春の綺麗な花のこと
2025.04.23更新
桜が嫌いだった。
甘い桃色の泡があふれるように咲く春のシンボルは、あまりに綺麗で、完璧なまでに美しく、それが気持ち悪かったのだ。
また、出会いと別れのセンセーショナルな季節にあわせてここぞとばかりに咲き誇り、忘れようのない鮮烈な色あざやかさで数多くの重要なシーンを彩ったかと思えば、たった数日で儚く散り去ってしまう......という壮麗な物語性も、計算され尽くしていて小賢しく、いけすかない感じがした。
まるでただ愛されるためだけに生まれてきたかのように完全無欠なその存在は、生き物としてそなえておくべき必死さや泥臭さ、なりふりかまわぬ胆力のようなものがまるで感じられず、なんだか傲慢で狡猾な性格を有するように思われたのである。すましこんでちやほやされるのを待つばかりの一生なんて、ずいぶんいい気なもんだなと、腹立たしさすら覚えた。
もともと春が苦手で、だから桜を愛せないというのもあるかもしれない。環境の変化にとことん弱いので、多くの人々がいっせいに新しいことを始めるこの季節が、とにかくストレスフルでたまらないのだ。青息吐息の生活をして、ぼろぼろにくたびれた帰り道などにふと桜の木を見ると、「自分はこんなに大変な思いで生きているのに、たまたま綺麗な花に生まれたからって調子に乗るなよ」と、わけのわからぬ理不尽な憤りにかられてしまうのである。
みんなが好きな花をどうしても愛せない。頭がおかしいのだろうか、とうんざりもする一方で、しかし、それこそが持って生まれたパーソナリティの核たる部分だとも思えた。面倒くさいところこそ、自分を自分たらしめる大事な部分、と考えていたはずである。
それなのに、今年の春。
桜を綺麗だと思ってしまった。
それは簡単なことだった。綺麗な花を見て、ただ「綺麗」とたった一つの形容動詞にまとめてしまえばおしまいだったから。以降になんの感想も主張も浮かばなかった。
そして、胸に寂しい微風が吹いた。別に私じゃなくてもいいな、と思った。花を見て、たったこれっぽっちの言葉しか出てこないなら、この人生はもう私がやる必要はないような気がしてしまった。
そろそろ生き方を真剣に考えなければ、とここ数年ずっと思い続けている。
キャリアというほど立派なものはまったく持っていないのだが、だからこそ、現実的なことを一つずつ見極めて、将来へ備える必要がある。
自分はいつまで文筆の夢を追うのか。また、それと並行して、日々の食い扶持をどのように稼いでいくべきか。業種は、雇用形態は、資格は、それにともなうライフプランは......など、思案しだすときりがない。
あれこれ必死で考えたつもりで、この四月に転職をした。慣れない職場へ通う日々の中、一番大好きで、なにより大切にしてきたはずの「書きたいもの」のことを考える体力や気力のゆとりはほとんどなく、毎日、何を食べていつ眠るかを考えるだけで精一杯。
桜を綺麗だと思ったそのとき、あ、世界は終わってしまったのかもしれないなと思った。
もちろん、形は何も変わっていない。去年と同じような春が、同じような時期にやってきて、同じ桜が同じ場所で開花する。そして、同じはずの自分がそばを通り過ぎるのだけれど、その肉体の中に、これまでと同じ自分はもういないのである。
かつて念入りに耕してきたはずの感性は、必死で社会生活に食らいつくうち、みるみる優先順位を下げて、そのうちに痩せ、あまつさえ滅びかけてしまっているような気がする。
自分自身の不在。こんなに心細いことはなかった。しかしもう、なにもかもどうでもいいとも思った。いかんせん本当に疲れているのだ。いっそこのまま全部を手放して、根なしの草がとりとめもなく風に運ばれ、名もないどこかへ移動していくみたいに、実態のない人生を、白目でも剝きながらやりすごしていくだけでいいか、などと投げやりなことを考えたりした。
毎晩、寝る前に台所に立ち米をとぐ。翌日の弁当に詰めるための米。
しかし、その日はシンクに洗い物がたまっており、まずそちらを片付ける必要があった。
アルミのざるを洗っていたら、針金が一部、ぴょんと飛び出ているところがあったらしい。それにまったく気が付かず、勢いよくスポンジを動かしたせいで、右手の人差し指にぶすりと刺さってしまった。
ゆっくりと血が出てきた。かなり深く入ったので、やがて指先は真っ赤に染まった。
最悪。こんなところを怪我したら、傷口がふさがるまで、もう数日は米をとげない。数少ない趣味である弁当作りまで封じられてしまったら、この日常に安らぎの時間などもうなくなってしまう。
ひどく落ち込みながらも、指先に血がにじんでいくさまには、なんだか既視感があった。
しばし考えて、「オーロラ姫だ」と思い至る。ディズニーのアニメーション映画『眠れる森の美女』に、これと似たようなシーンがあった。主役のオーロラ姫は、呪われた糸車の針に指先を刺してしまい、そして眠り続けるのである。幼いころに見たきりなのでストーリーの記憶はかなりおぼろげだが、その場面は物語の山場だったのでよく覚えている。
え、山場で寝たんだっけ? 主役が? そんなことありえるのか?
たしかめるため、家事のついでに映画を見返してみた。
そして結論からいえば、オーロラ姫は作中、本当に寝ていた。寝る以外、ほとんどなにもしていなかった。
彼女がお話の中でとった行動といえば、にわかには信じがたいほどごくわずかで、①いちごを摘みに行く ②王子と出会って恋をする ③寝る という、まったくただそれだけなのだった。
それなのに、ただ美しい見た目を有するキャラクターだからという大きすぎるバリューによって、ディズニープリンセスの中でも特にメジャーなフロントメンバーのうちの一人として、長年人気者の座に君臨している。
オーロラ姫もまた、桜なのである。
特になにしなくても、その美しさと物語の麗しさだけで、永くみんなから愛される。
指先に針が刺さっても、彼女はきっと痛くなかっただろう。すぐに眠ってしまったのだから。
一方で自分は、このたまらないみじめな痛みを常に感じて、また一つ枷が増えた日常を強いられるのだ。美しくもドラマチックでもない存在として生まれてしまったがために。
新生活に翻弄され、めちゃくちゃに散らかった暮らしの中へ、一輪のバラが迷い込んできた。たまたま知人にもらったそれは、特にこれといった意味を持たない、本当に偶然うちへ流れついただけの花であった。
それに関心を持つ余裕すらまるでなかったから、そのバラはとりあえず、帰宅したまま玄関の床に放り出された。そうして一晩が過ぎた。
翌朝、また弁当を作るために台所へ立ったとき、バラが死にかけていることに気が付いた。花弁はすっかり生気を失い、萎んで、まるでくしゃくしゃに丸めたティッシュペーパーのような姿に変貌してしまっていた。
にわかに気の毒に思い、とりあえず間に合わせの紙コップに水を入れた。机の引き出しを探ると、大学生のころに思いつきで買った植物用の栄養剤が出てきたので、それも数滴垂らす。ぐったりした花の茎を適当にカットして、即席の花瓶へさしておいた。
その日の夜、仕事から帰ってくると、バラは見事に復活していた。
薄桃色の花びら一枚一枚がはりを取り戻し、誇らしげにしゃんと開いて、すっかり見違えるようだった。
それを見て、綺麗だと思った。本当に綺麗だと思った。
映画の中のオーロラ姫も、眠りながら、胸にバラを抱いていた。酒を飲まずともすんなり入眠することができ、将来への不安などなにもないまますやすや眠り、その間にすべてが解決していたというあの羨ましいお姫さまが華奢な両手で抱いていたのと同じ花。
それは、雑然と散らかった狭いワンルームの中で、しかしたしかに美しかった。一度は萎れてしまったとしても、再び水を吸って再生し、自分で生気を取り戻した特別なその命にしか宿らない、無二の美がはっきりと見てとれた。
春風に揺れる満開の桜より、物語のプリンセスが抱いていた真っ赤なバラより、我が家の暗い台所で咲いた花が一番綺麗だった。
よみがえったバラを見て、かくありたいと思った。まだ生きられるような気がした。
今年はそういう春だった。


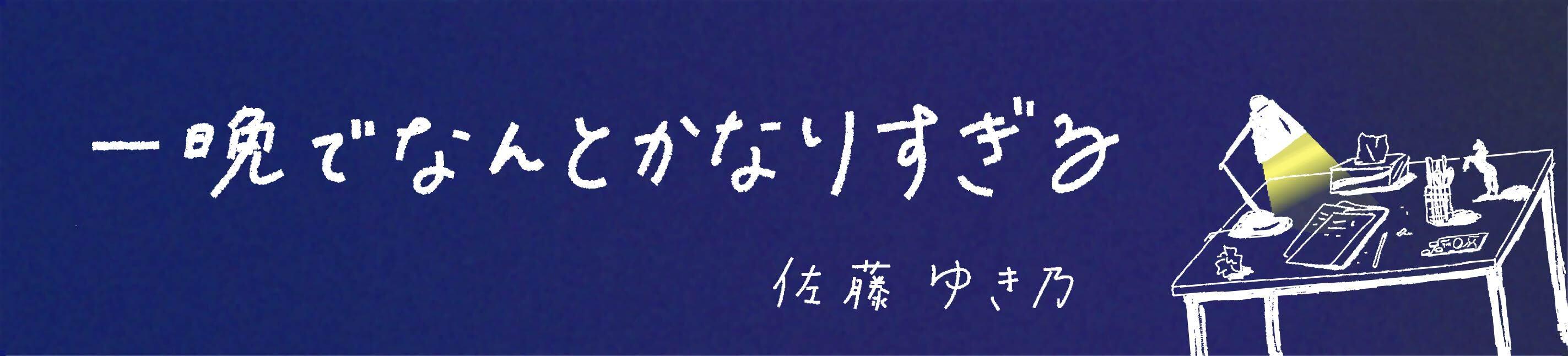

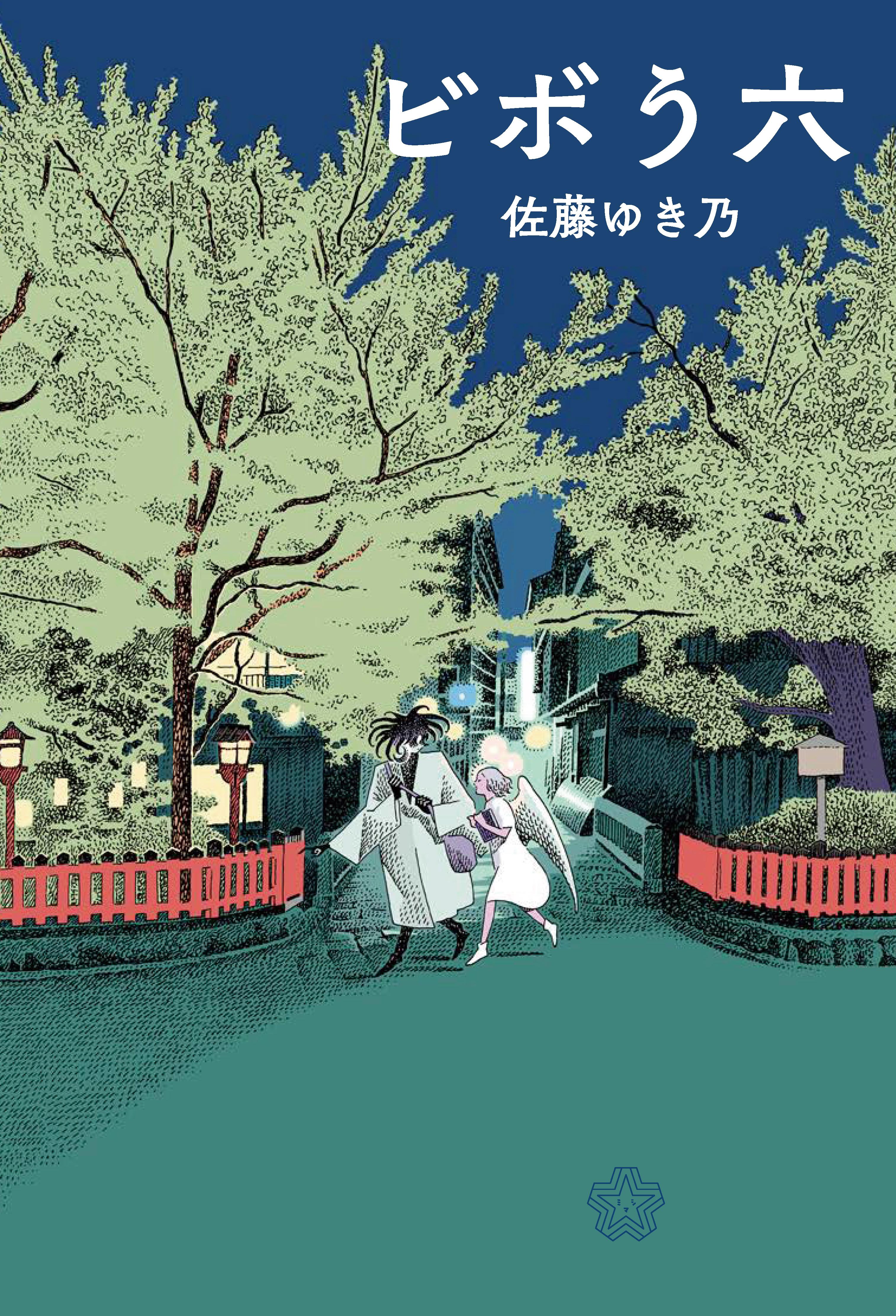




-thumb-800xauto-15803.jpg)
