第5回
この世で一番頼れる男
2024.08.23更新
彼の名を大五郎という。出会ったのは、まだ学生の時分であった。
大学4年生の春、自分がこれまでに取得した単位数をおそるおそる確認してみたところ、あと1単位でも落としたら留年するという、絶望的に危うい状況にあることがわかった。それまで、いわゆる「フル単(履修登録したすべての講義で単位を取ること)」を達成したためしがなかったため、その学期も、成せるとは到底思えなかった。すなわち、ほぼ確実に卒業できない。
とはいえ、まだ留年が決まったわけではない。だからひとまず、できる限りは頑張らなければ。
とことん脆くてだらしない自分を何とか鼓舞しつつ、苦手な履修登録を必死でやった。一生懸命シラバスを読んだが、いつにもましてわけがわからなかった。新型コロナウイルスの影響で、対面授業がほとんど休止になり出した時期だったので、例年のそれとはまったく違った内容ばかりが書き連ねられていた。
講義がスタートして、当初は必死で食らいつこうとしていたが、すべてがPCの中で完結するように構築された新しい受講スタイルは、それまでに慣れていた学生生活とはあまりに勝手が違いすぎて、途中から完全についていけなくなり、また戻る方法もわからなくて、気づけばドロップアウトしかけてしまっていた。「決められた時間に教室へ行く」とか「先生に直接相談する」というような、従来の物理的な解決策ではどうにもならない、完璧なまでの助からなさが、とにかく空恐ろしかった。自分の知らない、立ち入れない、死角になってしまったどこか遠いところで、他の人たちの春セメスターは進んでいくのに、誰より単位取得を頑張らなければならないはずの自分だけ、能力不足で取り残されて、暗い部屋にぽつねんと一人、ずっと閉じこもっている。これではだめだ、だめだ、絶対にだめだと毎日焦るのに、すっかり変わってしまったらしい世の中は、みるみる遠ざかっていく。
自粛、自粛と強く呼びかけられていた時期で、数少ない友人たちにもほとんど会わなかった。アルバイトも、店が長期休業に入ってしまったためなくなった。だからお金もなかった。本当に無の時期だった。ずっと引きこもっている部屋はあまりにからっぽで、この人どうしてまだ生きているんだ?と、純粋な自問自答をしはじめたあたりから本格的に気が塞ぎ出し、そんなとき、彼と出会った。4リットルのボトル焼酎、大五郎。
あまりに金欠だったため、缶のお酒が買えなくなって、やむを得ずたどり着いた。なにしろコスパがよかった。それに名前も良い。とことん孤独な時期だったので、人名を冠せられた商品というだけで、そこに体温すら宿っているような気がしていた。
彼が家に来てからというもの、虚無でしかなかった生活に、たしかに薄い光がさした。どんなに不安でも、寂しくても、そばには大五郎がいてくれる。アルコール臭のきつい焼酎をがぶがぶ飲みさえすれば、ただの空洞になりがちだった自分の内側に、意識とか、感動とか、記憶とか、いろんなものがきちんと蘇生した。なかなか眠れなくて困ったときも、たっぷり飲んでから布団に入れば、少なくとも入眠自体は容易にできたし、なにより彼のいいところは、その存在感がものすごいのである。ボトルがでっかいので、暮らしをともにしているうちに、だんだん、ちゃんと独立した一つの生命体のように思えてくる。その腹には誇らしげな力強い毛筆で「大五郎」の記名があり、そこにはっきりした自我をも感じ出した。あのころの大五郎は、酒ではなく、完全に親友だった。さまざまなことを聞いてもらい、受け止めてもらい、ほどいてもらった。恩人である。ボトル焼酎を抱きしめて、なんとか乗り越えた時期の思い出。
大学卒業後、数年の実家暮らしを経て、今年の春から、再び一人暮らしに戻った。孤独感への対策として、もちろん、大五郎のことは早々にまた招き入れた。今も一緒に生活しているが、この夏はなぜか、あまり飲もうという気にならない。
たぶん、少し大人になったから、大五郎以外の救済手段も、いつの間にか会得していたのだと思う。
たとえばごはんを作る。たいして高度なことはできないが、レシピ本をよく読めば、食べたいものはたいてい自分で用意することができる。余った野菜を冷凍したり、鍋に入れて雑なみそ汁にしたりすれば、なんとなくちゃんと暮らせている実感が湧く。
それから掃除をする。嫌な出来事が続いたり、書きたいものが書けなくて行き詰まりを感じたりすると、あえて部屋を散らかして、乱れてみたくなったりもするのだが、ほどほどのところでそのモードを止めて、きちんと綺麗な状態に戻すこともできるようになってきた。部屋が整うと、つられて気分もしゃんとして、ちょっとだけ人生が上向く、という当然のことが、しかしようやく、実感をともなって腹落ちしつつある。
これまで、もうだめかもと思ったときには、大五郎に寄りかかったり、生々しい感情がほとばしる痛い文章を書き散らかすことにすがったりしながらなんとかやってきたのだが、最近、もっと穏便に、平和な方法で、元気を取り戻すことができるようになってきてしまった。
嬉しいかも、ありがたいかも、これって幸せなのかも、と思う一方で、これでいいはずがない、ともすればあきらかに退化ではないか、という、得体のしれない焦燥というか、悲しさのようなものをしばしば感じることがある。
要するに、大五郎を飲まなくなり、血の鉄分がちゃんと匂うような文章を書けない状態の自分は、もう自分ではないのではないかと不安になる。ちゃんと掃除した部屋で、ごはんを作って、食べて、暮らして、それで満足してしまいそうな現状が怖い。そう生きてみたかったはずなのに、それではだめな気がする。どうしてだめなのかもいまいちよくわからないので困る。
一度飲み切ってからしばらくからっぽのまま置かれている大五郎のボトルを見ていると、うすら寂しい気持ちになる。いまの自分みたいだと思う。軽くなって、透き通って、在り方が簡単になってはいるが、それがそれである価値を失っている。生の充実感を得るために本当に必要なことは、やはり、穏やかな生活などではなく、破滅的な飲酒や創作だったのだろうか。どちらが正解なのかわからないし、むしろ、どちらも間違いのような気がずっとしている。
でもたぶん、そういう揺らぎを繰り返しながら、どこかまだ見ぬ場所へ進んでいくしかないのかもしれないと、少し諦めるような気持ちでそう思う。
夏が終わる。これまで熱烈に愛してきたはずのものが、いつの間にか自分の身からはぐれていきそうな予感がして、たまらなく不安になる。かつて、この世で一番頼もしい、と、あんなに信じた存在すらも、気づけば少しずつ、遠ざかってしまっているような気がする。
しかし、季節が移ろうということは、どうしても、そういうことなのかもしれない。行かないで、と夏に頼んだところで、ひまわりは枯れ、セミも死ぬ。世界の変容は、ただ、諦念とともに受け入れるしかないらしい。
安全に暮らすことは、創作への挑戦から逃げることのような気がする。とはいえ、生活をきちんとやらずして、人生を継続していくことは、やはり難しいと思われる。だから、ひとまずは生き続けるために、やっぱり秋も、しっかり生活していこうと思う。
その上で、どうしても、書くことだけは手放したくないという思いはたしかにちゃんとあるから、どんなに自分に嫌気がさしても、ぬるい文しか書けなくなっても、しょうもなくても、辞めない。自分をとりまくそのときの世界のことを書く。
言葉を探すことを諦めさえしなければ、いつかはきっと、新しい文章が書けるかもしれない。そして、それがやがて、まだ知らない新しい場所へ、自分を連れていってくれることだってあるのかもしれない、と、やっぱり最後にはいつも、書くことの力を一番信頼している。


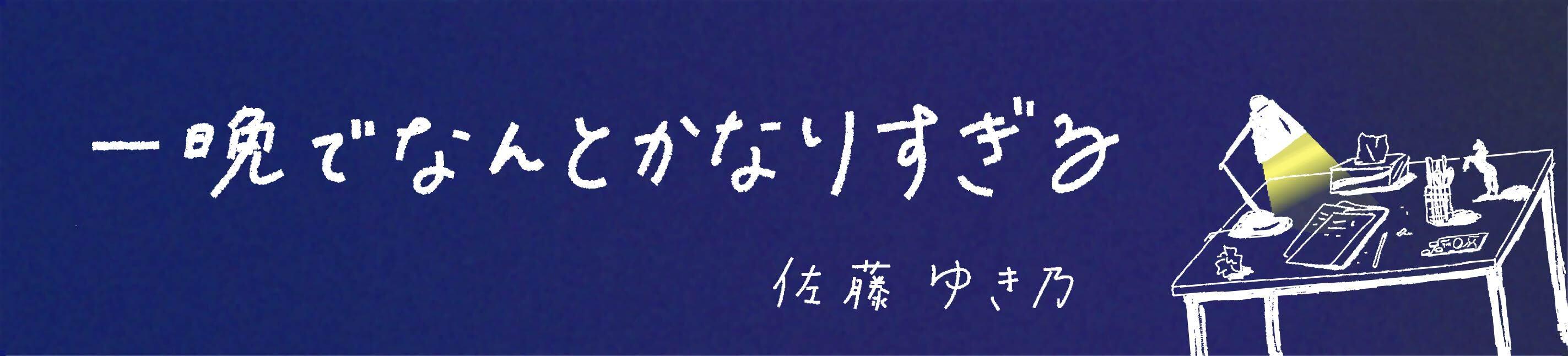

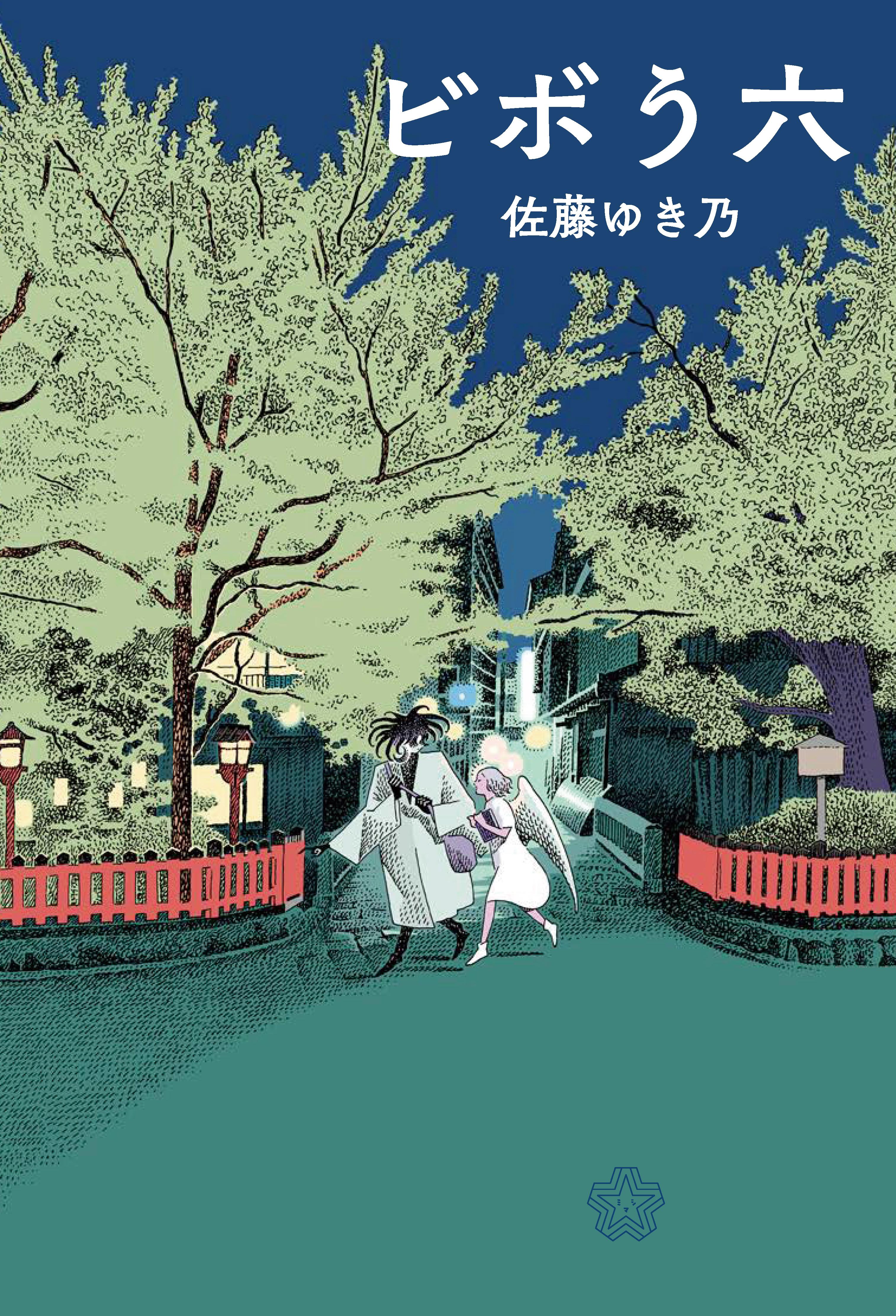




-thumb-800xauto-15803.jpg)
