第20回
27歳で星になる前に
2025.11.24更新
「才能あるロックスターは27歳で死ぬ」という有名な話をはじめて知ったのは、高校生のころだった。
たまたま読んでいた小説にそれが書いてあって、なんというか「スター/死ぬ」という激しすぎるアップダウンの清々しさに感銘を受けた。
そして「27歳」という絶妙な年齢設定が放つなまめかしい本当らしさがすごく印象的で、「じゃあ、自分に才能があった場合、あと10年くらいで死ぬってことか」と、いまになって思えばなんとも17歳らしい傲慢な発想にまで至ったものである。
この「27歳」という期限は、たとえば足首かどこかの見えにくいところに染み付いたワンポイントのタトゥーみたいに、ずっとひっそり残り続けていた。折にふれて「あと何年か」と考える。
それは永遠に訪れない未来のような気もしたし、あるいは、もう明日に差し迫った終着点、あたりまえにあと数時間で迎えることになっている、美容院の予約くらい気楽で身近な予定のような気もしていた。
半年前、いよいよ27歳になった。
別にそれがどうというほどのこともなかった。実際、あの高校生の時分から10年も経つと、人間というのはずいぶん冷静に、現実的に成長するものだなと思う。
自分は27歳で死んだことがステータスになるほど特別な人間ではないし、「27歳で死ぬ」界隈があるからといって、それと己の人生には、なんら相関関係がないことも理解している。
10月、大阪へ行った。野外で行われた音楽フェスを観覧するのが旅の主目的であった。
プログラムの一つに、とある女性アーティストのステージがあった。
よく知らない歌手だったが、ソロシンガーとして舞台に立ち、威風堂々たる素晴らしいパフォーマンスを披露していた。
曲の素晴らしさに感動して聞き入っている最中、ふと、そういえばこの人も、自分と同い年の「27歳」ではなかったかと思い出す。
たしかにそうだった。記憶が鮮明によみがえる。
23歳のころ、ひょんなきっかけから、彼女が作詞した曲を聴く機会があった。
そして、その歌詞があんまり素晴らしかったのだ。仰天するほど胸を打たれた。これほど素晴らしい歌を聴いたのははじめてだ、とまで思った。
こんなに深く美しい詞を書けるなんて、いったい何歳の人なんだろう。どれだけの人生経験を積めば、この神がかった領域にたどり着けるのだろうか......と、軽い興味で調べてみたところ、なんと彼女は、当時の自分と同い年の23歳だったのである。
たちまち猛烈な嫉妬が炎となって噴き上がり、静かな感動などたちどころに消えてしまった。
悔しい、むかつく、許せないと、そればかりが頭を占めて、何日も寝付けないほどだった。たとえ大きく舌打ちをしてみても、怒りに任せて浴びるほど酒を飲んだとしても、苛立ちは少しも和らぐことなく、むしろ無様な自分に対する情けなさが膨れて、よりいっそうみじめな気分になるだけだということをそのときに体感した。
当時の自分といえば、ものを書く夢も、実生活も停滞しており、なにをやってもうまくいかなくて、とにかくくすぶっている時期だった。実家の砂壁に酒の空き缶をぶつけては奇声を上げるのが日課であった(いま考えると、本当にどうかしている)。
だから、当時の自分と同い年のはずの23歳で存分に才能を発揮して、それが世に高く評価され、意気揚々と創作活動をできているその人が、羨ましくてたまらなかったのだ。まったく醜悪で呆れてしまう。
それ以来、久々にフェスで彼女の音楽を聴いた。
やはりとんでもなく歌が上手で、歌詞の内容も素晴らしく、パフォーマンスは圧巻だった。
しかしそれよりも、彼女と自分とを隔てる距離が、妙に際立って長く感じられ、なんだかぽかんとしてしまった。
数万人というありえない人数のオーディエンスを前に、一人きりで堂々と歌っている27歳の歌手。
その遥か遠くで、有象無象の観客の一人として、米粒くらいの彼女を鑑賞している、同じく27歳の自分。
まさかの同い年。同じ年数しか生きていないだなんて、ありえないことだと思った。
そして、どうしてあんなすごい人に嫉妬なんかしたんだろう、とも思った。
彼女は27歳で、正真正銘のスターになったのだ。それは、たとえば伝説のとおり生を諦めて星になるより、ずっとずっとかっこいいとしみじみ思った。
本当に才能があるということは、きっとこういうことなのだ。
11月は和歌山に行った。
「有名な洞窟温泉に浸かりながら海を眺め、しばし現実を忘れよう」という友人の提案をうけて、ほとんどそれだけを目当てに旅立った。
この友だちも27歳である。高校生のころからの親友だが、当時の成績は文字どおり雲泥の差であった。彼女はクラスで一番賢く、私はクラスで一番馬鹿だった。それでも仲はとてもよかった。
友人は堅実に大学を卒業し、堅実に市役所職員になり、そして堅実に5年間、同じ職場に勤め続けている。
どれ一つとして自分にはできなかったことである。本当にえらいと思う。どうしてこんなに違うんだ......と思いながらも、ずっと友だちでいられる理由が一つある。
ちょうど同じくらい、性格が悪いのである。
2泊3日の旅行中、とにかくずっと悪口を言っていた。
自分たちを取り巻く、森羅万象について不平不満を述べ合った。この世界の隅から隅まで、端から端に至るまで、ありとあらゆる語彙を尽くして文句の形に置き換える。キレのいい悪口を放つことができるとたまらなく気持ちがいい。びしりとスマッシュが決まったかのような、たまらない爽快感に震える。こういうとき、国語の勉強を頑張った甲斐があったと大いに満足する。
和歌山旅行の目玉と期待して訪れたのは「ホテル浦島」という温泉リゾートホテルで、なんといっても名物は、「忘帰洞」の名前を冠した洞窟温泉。
まさしく頑強な洞窟の中に、こんこんと湯が沸いている。洗い場も浴槽も、ワイルドな岩肌に囲まれて薄暗い。野趣あふれる湯殿の空気を吸うだけで、自らが自然の循環の中に溶けて混じり出すような心地がした。
細長く伸びる湯舟を最奥まで進むと、やがて洞窟の天が途切れて、穏やかな水色をたたえた秋の空がそこにある。眼下には、壮麗な大海が、広大無辺に広がっている。
熱い湯に浸かりながら、地球がこっそり隠し続けてきた秘宝のような絶景を楽しんだ。ここではさすがに会話は控え、友人と二人、互いに黙って景色に見とれた。
その日、和歌山の海は青かった。自然物にしかありえない、清廉で実直な青色をしていた。美しい水のかたまりを見ると、ただそれだけで胸がときめく。
大小さまざまの波が寄せては岩に当たって砕け、白くきらめくあぶくになって散り散りになる運動を、いつまでも夢中で眺めた。無限に繰り返すうねりの中で、連綿と変形だけがはてしなく続き、それをじっと見ているうちに、みるみる心が楽になる。
形のないものは美しい、と思った。
27歳、その型がいったいなんだというのだろう。自分で勝手に枠を作って、そこへうまくはまれないことに落ち込む日々が、本当に愚かしいと感じた。
それでも、ひとたび日常に戻れば、またすぐに形ばかりが気になる。どうしても有形のものにばかりとらわれる。流体然としていては、現実の社会では生きていけないからである。
仕方のないことだからこそ、ときどきは、形のないものを見に行くべきだなと思った。
「忘帰洞」の名のとおり、帰るのも忘れて、世界がただ巡るさまに見とれ続けたあの時間を思い返すたび、生きていてよかったなと思う。
27歳で星になる前に、見るべきものがきっとまだまだある。


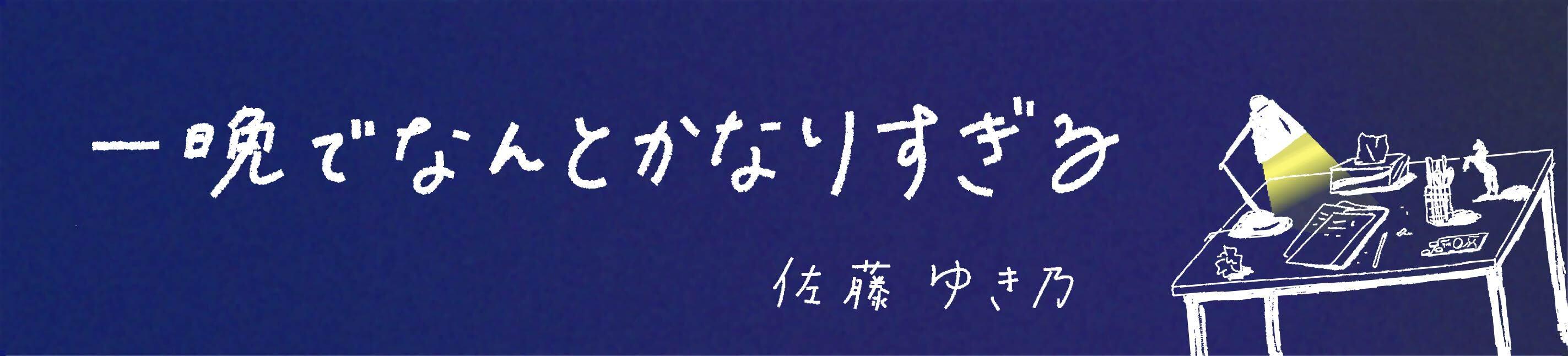

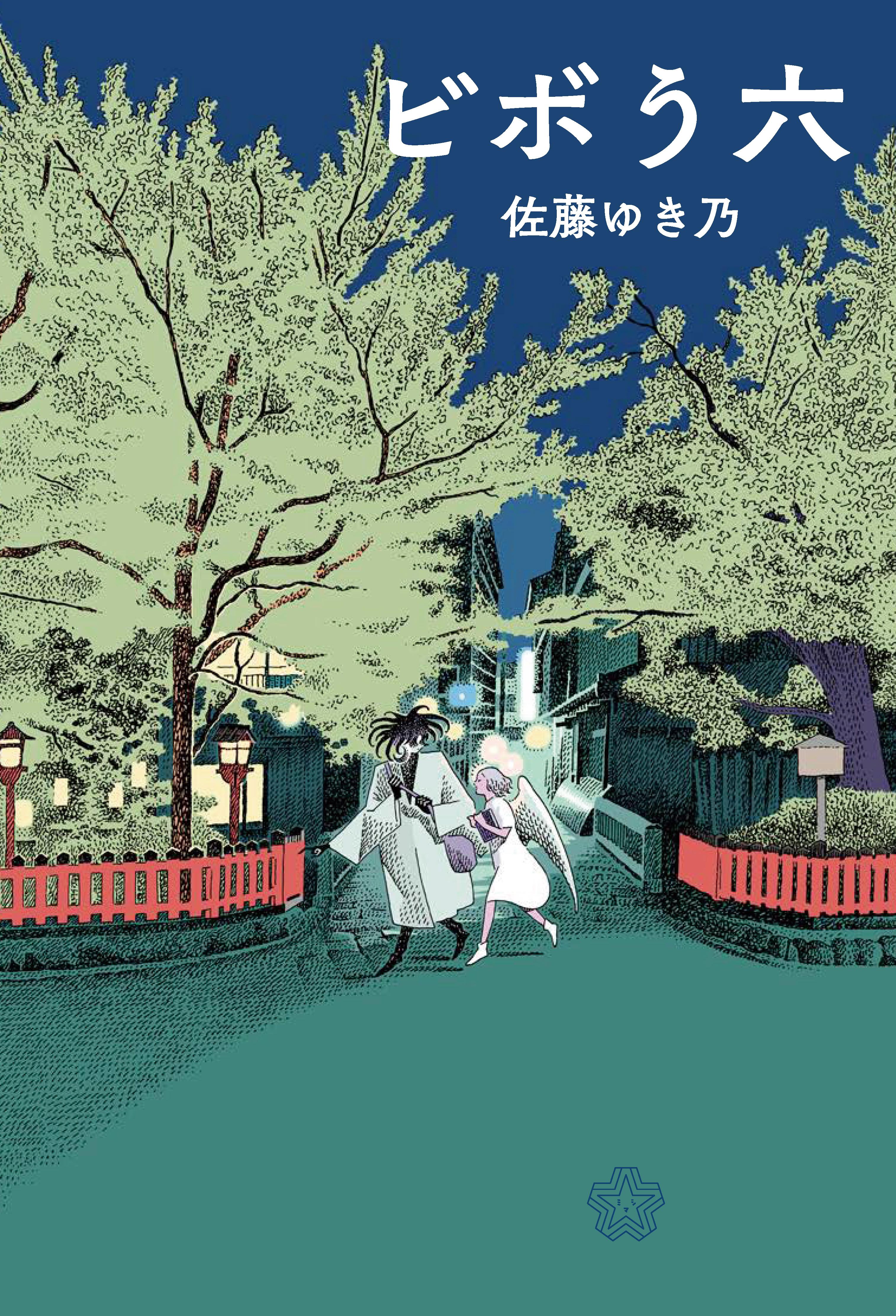




-thumb-800xauto-15803.jpg)
