第1回
この世がでっかい競馬場すぎる
2024.04.24更新
この世がでっかい競馬場すぎる。もう本当に早くここから出たい。
脳のキャパシティが小さい、寝つきが悪い、友だちも少ない、貧乏、口下手、花粉症、知覚過敏、さらには性格が暗いなどの理由で、自分の場合はけっこう頻繁に「あーあ、終わりだ、人生はもうどうにもならない」とお手上げ気分になるのだが、そのような窮地に陥った者のために用意されているたった一つのラストチャンス、それが「公募」である。
このデスゲームにうっかり参加し始めてしまったきっかけは、高校時代までさかのぼる。
1年生のころ、本当にめちゃくちゃ成績が悪く、毎日のように職員室に呼び出されては、とにかく怒られまくっていた。
見かねた担任の先生に、「忙しい運動部は辞めて、文芸部に転部しろ(活動が週2回だけのゆるい部活だったので、そこで勉強時間を確保しろ)」と半ば強制されるような形で勧められる。全然やりたくないなー、と不本意に思いながらも、しぶしぶ文芸を始めた。
それが転機になってしまった。入部してはじめて出した2年生時のコンクールで、随筆が県内1位、小説も2位と、思いがけない好成績が出たのである。勉強では常にビリしかとったことのなかった自分にとって、あまりにも衝撃的な体験だった。
この土俵なら勝てる。1位になれる。しかもこんなに簡単に。たった一晩、ちょっと頑張っただけなのに。締め切り当日の深夜2時をすぎてからようやく手をつけて、心底面倒くさいと思いながらも仕方なく書き上げた随筆が、なぜかやすやすと最優秀賞をとってしまった。全校朝礼で表彰されて、立派な賞状をもらった。
その日を境に、職員室に行くたび、急に褒められるようになった。どんなにひどい点数をとっても、なんとなく許されることが増えて、欠点はむしろ、文才があることの代償というか、非凡な力があることの証左みたいに言われるようにさえなった。
ある一夜を超えたそのとたん、完璧に世界がひっくり返った。こんなにもはっきりした革命を体感した上で、地に足を付けろと言われても無理である。これを機に、すっかり公募中毒になってしまった。
次は全国で1位をとりたい。その一心で、文字通り24時間、コンクールのことだけを考えて暮らし、いつも脳みそが垂涎していた。過去の受賞作品や審査員評を徹底的に読み込んでは、頭がおかしくなるくらい勝ち筋を熟考しまくった。
こうして、気付いたときには競馬場にいたのである。毎日が出走前の心持ちで、次のレースでまた大当たりする未来を妄想するだけで、はちきれんばかりのときめきが胸にあふれ返り、苦しいくらいだった。脳内麻薬がとめどなく出続ける高校生活。いつも虚構の恍惚に支配されていたというのに、誰も止めてくれなかった。
満を持して挑んだ3年生のコンクールでは、小説の全国1位、文部科学大臣賞が無事に叶った。おかげで大学の推薦まであっさり決まって、ずっと学年最下位だったのに、誰より早く進路が定まった。
このような歪んだ成功体験を重ねに重ね、どこまでも加速していく中毒症状。「最優秀賞をとるためだけに生きている」と、真剣に思い込んでいた。というかもはや、公募で勝つ以外の方法で、人生を前に進める方法がわからなくなってしまっていた。
せっかく推薦で入った大学も、持ち前のだらしなさと要領の悪さのために留年してしまった。就活もうまくいかず、ちょうどコロナ禍の時期だったのでアルバイトもできなくなってたんす貯金が1000円になり、「ああやばい、さすがに今回こそいよいよおしまいだ」と絶望していた折、京都文学賞の募集を見つける。「副賞:賞金100万円、出版化」の文言にまたしてもよだれが止まらなくなり、日夜瞳孔を開きっぱなしのまま、2週間、筆を爆走させた。「もし落選したら、ただのろくでなし無職だ、頼む頼む」とこのレースで大勝ちできる未来だけを祈っていたら、結局、また最優秀賞がとれてしまった。
神さまは一体、なにを考えているんだろうと思う。こんな博打頼りの生き方でいいはずがないことは明白なのに、間一髪のところでいつもなんとかなってしまうため、私はいつまでたっても、この巨大な競馬場から脱出することができない。
ところで、この「競馬場」というメタファーにおいて、では「馬」に相当するものはなにか。その正体をようやく知ったのは、京都文学賞をとったあとのことであった。
副賞として「出版化」が約束されていたはずが、自分の場合のみ、これがすぐには叶わなかった。なんの音沙汰もないまま約半年が過ぎて、この期間がとにかく苦難だった。
受賞作がどうなるかわからないために身動きがとれず、先の見通しも立たない。仕方がないので心機一転、また新しい小説を書こうにも、なぜかまったく言葉が出てこなかった。「公募には勝ったはずなのに、どういうわけか負けている」ことへの疑問と困惑、そして不安が、文筆用の筋肉にねっとりと絡みついて、なにも書けなくなってしまった。
だからもうやめる、小説なんかきっぱりやめる、こんなくだらないことはもう絶対に絶対に絶対にやめてやる、と何度も決意するのに、心は全然追いつかないから、気づけば公募ガイドを買ってきて、次のチャンスを探してしまう。結局未練たらたらの自分が、あまりにも悔しくてやるせない。
そのときにようやく気がついた。創作意欲というものは、己の意のままにはならないのである。
だからこれはもう、自分ではない。欲望は馬。才能も馬。私じゃなくて馬。いつも勝手に駆け回る馬。負けず嫌いな性格だから、競走馬っぽく見えすぎるけど、本当はただ、走るのが大好きなだけの馬。
あの時期、一番苦しかったのは、副賞がうやむやになりかけたことでも、そのために敗北感を味わったことでもなかった。「書けない」という状態に、はじめて陥ったことだった。当たったはずの競馬が幻だったのがつらいのではなく、走り方がわからなくなってしまったのがつらいんだ、勝ちたかったんじゃなくて、書きたかったんだなあ、ということが、やっとわかった。
本当はレースがしたいわけじゃない。馬を競わせたいのではない。ただ、のびのびと駆け回らせたいだけ。きっと面白いものが書けると思う。超でっかくて熱い小説ができるといつも信じている、だから、衝動にまかせて走りたいだけ。公募という魅惑のにんじんによだれを垂らすのが楽しかったのではなく、よだれを垂らしながら、次の小説の構想を考えるのが楽しかった。わかっているはずなのに、なぜかすぐに見失う。
公募に勝てば道が開ける。それは自分の経てきた道中において、たしかに一つの傾向ではあるけれど、だからこの競馬場にいるというわけではない。
いろんなことに追い詰められて、完全に絶望して、もう無理だって思った夜に、それでもなにかを「書き始める」ことによって、新しく別の世界が生まれて、詰んでいたはずの駒がまた動き出し、未知の風が吹く。するといつの間にか朝日がさして、そのころにはなんとかなっているのだ。それが嬉しいから、ここに居続けてしまうのだ。
もうやめてしまいたいな、としょっちゅう思うけれど、馬がいる限りは仕方ない。できるだけ仲良く共生していきたいと思う。どんなに苦しい夜を迎えたとしても、この馬が駆け出しさえすれば、きっと、一晩でなんとかなりすぎる。そう信じながら生きられるのは、やはり、とても幸福なことである。


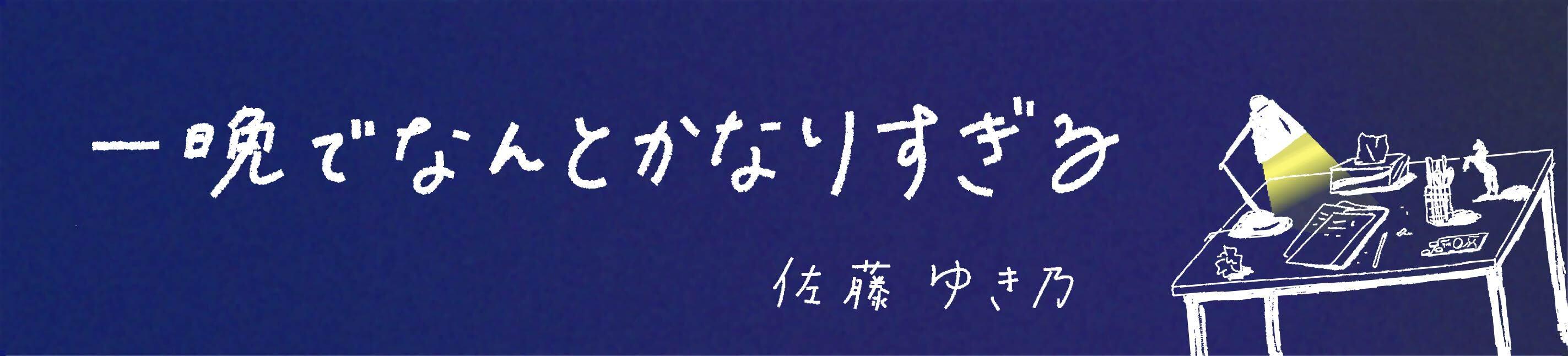

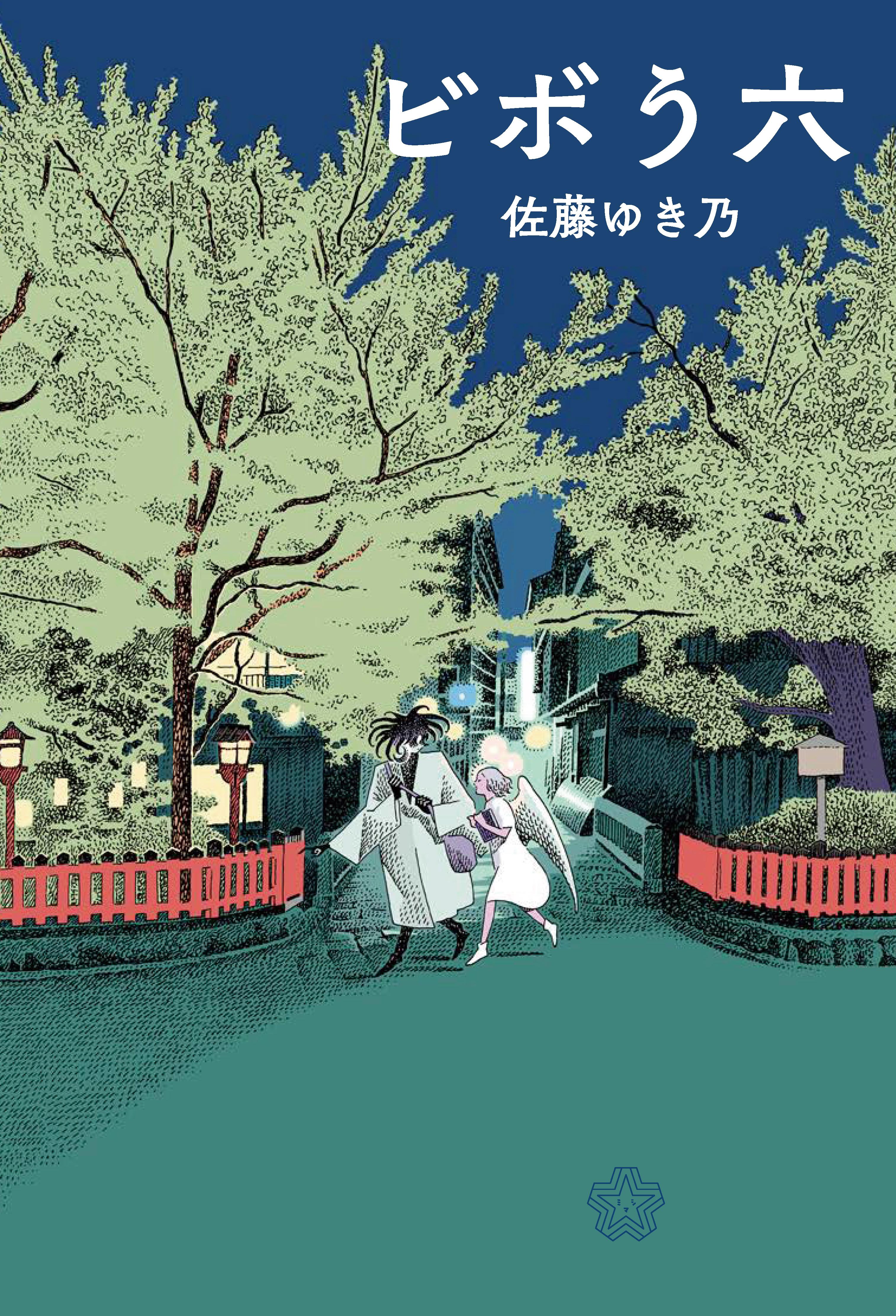


-thumb-800xauto-15803.jpg)


