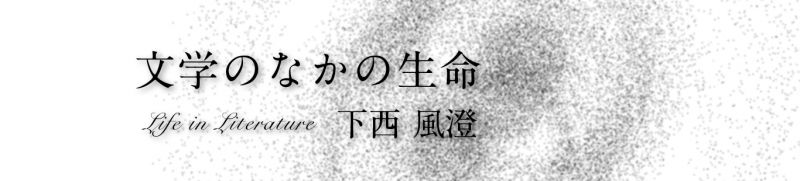第4回
神様と船に酔う
2022.01.14更新
もうずいぶん前のことになるが今でもありありと思い出す出来事がある。
周防大島の地を初めて踏んだ日、僕はとある神社をお参りした。島の中に百ほどもある神社仏閣の中で特にそこを選ぶ理由もなかったが、最初に通りかかった神社でなんとなく目についた。その名を厳島神社といった。かの有名な宮島と同じ神を祀る由緒ある神社らしい。大きな鳥居が浜辺に突き刺さったように建っている。鳥居のはるか向こう、海の彼方に見えているのが四国だということすらわからないほど、この時は島の地理に疎かった。静かな波音を聞きながら、賽銭を投げ入れ参拝した。周防大島に住むかどうかも決まっていなかったこの瞬間に何を祈ったか、そこまでは今となっては覚えていないが、とりあえずご挨拶しておけばなんかいいことあるかも。そんな下世話なことを思っていたのかもしれない。
だけどこのことを思い出すたびに、「因果」なんていう大袈裟な言葉が脳裏に浮かんでしまう。それはその後、周防大島の中で数回の引っ越しを繰り返し、巡り巡って僕ら家族が居を構え、定住したのがまさにこの神社のある集落だったからだ。
ここで何年か飛び越えよう。僕ら家族は今やすっかり根を下ろし、周防大島に暮らしている。
そして神社の話は続く。
今日は年に一度の十七夜の祭り、管絃祭だ。僕は集落の先輩方に言われていた通りに、夕方仕事から帰ってくるや、すぐに集会場に行って着替えた。新品の白いシャツに、白い袴、白い足袋。いわゆる白装束だ。少し遅れてしまったらしく、他の人はすでに着替えた後のようだ。お腹は空いていたが何しろ時間がない。もう神社の方に人影が見える。僕は境内まで急ぎ走った。
僕が到着した時には、やはりすでに神事は始まっていた。
社殿の中で祝詞をあげる宮司。神前には、誰かの手作りであろう特大の丸いお餅や、絵に描いたように立派な鯛、大根などの農作物、それに酒など、様々な食物が供えられている。そのすぐ傍に総代である村の長老たち。その人たちを囲むようにして、神輿の担ぎ手である白装束の若い衆。僕は遅れてその中へそっと紛れ込んだ。
宮司の祝詞の抑揚に耳を澄ませていると、どこか遠いところからこちらへ向かって眠気がやってくる。いったい宮司は何を言っているんだろうか、もちろん何も判りはしないのだけれど、はるか昔から続いてきている大きな時の流れのなかに自分はいるのだと、うつらうつらしながらそんなことを思う。
神事は終盤を迎え、それぞれが神前でお参りする。用意されている榊の枝を持って、順番に祈りと共にお供えしていく。こういう時に限って、腹が張ってきた。なんだか屁を出したい衝動に駆られる。いや出したいわけじゃない、むしろ、というか当然出したくはないのだけれど生理現象なのでどうしようもない。放屁しそうになる生理をなんとか押し殺し、腹の中へ押し返す。と思ったらまた出そうになる。そんな押し問答を体の中で繰り返しているうちに、僕の番がやって来た。
正座していた足を崩し、立ち上がって前に出る。思っていたよりも足は痺れていた。こんなことなら胡座にしておけばよかったと後悔しても時はすでに遅く、少しふらついた足取りで神前にたどり着いた。前の人がやっていたのを思い出すように、頭を下げて神前に座る。手に持った榊の枝をくるり回し、お供えする。自分が立てる物音以外に、なんの音もしない静かな空気が緊張を後押ししてくる。僕は柏手を打ち、再び頭を下げた。
神輿守り全員の参拝が済んだ後に、宮司の合図のもと電気が消された。暗闇の中、甲高い声を発する宮司。どこから声を出しているのか、彼はその奇声とも思えるような声を途切れることなく出し続け、神社の一番奥へ行き、何かを取り出そうとしている。その場にいる全員が深く頭を下げているので、目で見ることはできないが宮司は御神体を神輿へ移そうとしているようだった。いったい御神体とはどんなお姿をしているのか。この目で見たいという欲求がむくむくと湧き上がるが、見てはいけないようだし、何しろ真っ暗で見えない。だけれど、いま目を閉じ、首を垂れているみんなの中にも、片目を開けてなんとか見てやろうと思っている者もいるに違いない。そう思うと見ないのもなんだか損をしているような気になり、僕もつい薄目を開け、首を変な方角へ捻り上げて、なんとか覗き見た。宮司は素早い動きで御神体を手の中から神輿の方へと滑り込ませた。大きく広がった服の袖に隠れて、結局見ることはできなかったが、動きから察するにかなり小ぶりな神様のようだ。
宮司の甲高い声が止んだ。
合図で再び電気がつけられる。
「それでは神輿守りの皆様、よろしくお願いします」
宮司の声で僕らは神輿を担ぎ始めた。
背が高くて困ることはないと、多くの人はそう思っているに違いない。あと何センチか背が高ければ人生は違った、なんていう話を幾度も聞いたことがあるが、何もいいことばかりではないのだ。例えば、僕が学生時分にモヒカン刈りにしていた時など、わりと大きめの自分の身長プラス固めた毛髪分でとんでもない高さになっていた。一番の問題は車に乗れないことだった。天井にぶつかってしまうので車に乗っている間中、ずっと首を傾けて「まだ? まだ着かないの?」と繰り返すハメになることもしばしば。そんな髪型にするからだ、このど阿呆めがと言われればまさにおっしゃる通りなのだが、髪がなくとも具合が悪い時もある。島の古民家に暮らしたときもそうだった。建具や天井など、全てのサイズが昔の暮らしに沿って作られているのだが、どうも僕の身長は昔の人よりも大きいらしかった。引き戸を開けてただ中へ入るだけなのに、頭部を強打する。手洗いで用を足そうと扉を開けては頭を強打する。頭を押さえ畳の上で今まで何度うずくまったことか。
そしてまた、この神輿守りもなかなかに辛い時間であった。
「ちょうさいやー!」
大きな掛け声を上げながら神輿を担ぎ上げて、海沿いの道を練り歩く。なぜこの掛け声なのか、いったいどんな意味があるのか。色んな人に聞いてみたが誰もその答えを明確には教えてはくれなかった。意味などないのかもしれない。「わっしょい」ってどういう意味ですか? もしかしたらそれと同じ質問だったのかもしれない。そんなこと誰も知るわけがない。
僕らの最終目的地は波止場。そこに準備されている船に神輿を載せて神様とともにこれから海へ出るのだ。
「ちょうさいやー!」
誰か一人が大きな声を出し、その後に皆が声を出し続いていく。神輿の前方と後方に分かれて担ぐのだが、背の大きなものはここでもやはり辛い立場だ。飛び出している分、肩に一際重力がかかってしまう。痛みに耐えかね、やや中腰で担ぐ。そうするしかないのだが、見るからに屁っ放り腰となる。格好の悪いことこの上ない。仕方ないから背筋を伸ばし、肩の痛みと向かい合う。痛みに耐えかね、やはり屁っ放り腰に。そんな時に見物客が写真などを嬉しそうに撮り始める。格好悪い。背筋を伸ばす。肩が痛い、屁っ放り腰に。これを延々と繰り返しながら目指す波止場はとてつもなく遠くに感じた。
ところで、何年も前の話になってしまうが、以前うちの家に新聞社の方が取材に来られたことがあった。取材に来た理由はうちの息子が誕生したからということだった。驚くなかれ。もうずっと長いことこの集落で生まれた子供がいなかったから、これは一種の事件だったのだ。大変おめでたいので是非記事にしたいとの話だったが、もちろん息子は何かをなしたわけでもなく、ただ誰もと同じように自然に生まれただけだ。新聞記事に載せるのは気恥ずかしいし、なんだか息子にも悪いような気がしたので丁重にお断りをした。その際、祭りの日取りが近かったのだろう、新聞記者さんは面白いものを見つけましたと古い新聞のコピーを持ってきてくださった。何年前の新聞だったのか、正確な日時は覚えていないが、何十年も前の記事だったことは確かだ。そこにはこうあった。
「厳島神社、管絃祭に周防大島の島民3千人集まる」と。
目を疑った。3千人? もはや頭では理解できない数字だった。今や祭りに集まっているのはその100分の1だ。多くても40人くらいだろう。
いったいそれはどれほどの賑わいだったのだろうか。話をもう一度祭りの日に戻そう。
これが船酔いというものか・・・・。
僕は暗い海の上で航海ならぬ後悔をしていた。初めて味わう激しい不快感と吐き気に襲われ、陸地を羨望の目で見ていた。船は大きな円を描くように湾内を回り、陸地に近づいていったかと思うとまたどんどんと離れていく。それをかれこれ2時間ほど繰り返していた。いっそ泳いで行ってしまおうか・・・。到底できるはずはないのに、そんなことを思ってしまうほどに帰りたかった。晩御飯を食べずにきたのは幸いだった。何かを口にしてきていたら、今頃とっくに海の中に吐き出していただろう。
船の上にあるのは大量の打ち上げ花火。ビール。日本酒。酒のつまみ。太鼓。ばち。大きな鐘。それに鐘をつく木槌だ。
以前、島の学芸員さんが家へ遊びに来た時に祭りについて教えてくれたことがあった。管絃祭は雅な祭りだと。船上で、月を愛でながら酒を飲み、花火に興じる。これを雅と言わずしてなんと言うのかと。
確かに揺れなければそうかもしれない。だけどこの日は、風が吹き、小雨もあった。船は大きく脈を打つように、上がったり沈んだりを繰り返す。
僕らの船は最後尾で前に2隻が連なっている。船といっても、一番前の船だけがエンジンがついていて、後ろに続く2隻はロープで牽引してもらっている御座船だ。すぐ前をゆく御座船には神輿を中心に神主さんや祭りの総代さんたちが乗っている。そして僕らの船は神輿の担ぎ手となる村の若い衆が乗り込み、ゆうに百はあるんじゃないかと思うほど大量の提灯の灯りで飾られていた。月夜の下、いくつもの提灯を乗せた船がゆっくりと湾内を周遊する。確かに離れて見ていたらとても美しいものだろう。
だけど僕の心は全く美しくなく、吐き気でいっぱいだった。何もしていないのも苦しいだけなので、気を紛らすつもりで僕は鐘を打っていた。別の一人が太鼓を打ち、僕が鐘を打つ。これも鳴らすリズムが決まっていて、簡単ではあったが船が出る前に長老の一人に教えてもらっていた。鐘を打っているといくらか気分が紛れた。
一つ前の船から、風に乗って笑い声が聞こえてくる。宮司や長老たちが一緒に酒を酌み交わしているようだ。神輿の神様も一緒に愉しんでいるだろうか。
僕は鐘を叩いた。湾内に響かせるため力いっぱい叩いた。この日ばかりはうるさいなどと思う人間はいないのだ。
長い一年の中でたった一日。この日だけ、暗い神社の奥から出て、月夜の下で波に揺られる。神様にも鐘の音は聞こえているだろうか。船酔いに朦朧となりながら、僕は鐘を打ち続けた。
船が陸の方へと近づいたその時に、かすかに子供の声がした。
「・・・ととー、・・がんばれー・・・」
途切れ途切れだったが、うちの息子の声なような気がした。
その一瞬、思い出せなかった夢を突然思い出したみたいに頭の中にイメージが次々と浮かんできた。
浜辺の道をどこまでも続いていく屋台。色とりどりの提灯で飾られている。子供たちは夜遅い時間でも走り回れるこの特別な一日に興奮を隠すことなどできない。射的、水飴、ポン菓子。熱狂する子供たち。ベーゴマを回しているのだろうか、コマのぶつかり合う音が聞こえる。途切れることのない笑い声。大人たちは酒を酌み交わしている。往来は人の肩がぶつかり合うほど大勢の客で賑わっている。大声で歌を歌い、踊る人々が笑っている。餅を焼いている女性がいる。醤油の焼けたような甘い匂いが潮風の中に漂っている。そして鐘の音が聞こえていた。海に浮かんでいる提灯船からの鐘だ。そして空へ大きく花火が打ち上がった。ひときわ大きな歓声が上がる。皆の目の中には散っていく花火と大きな丸い月が浮かび上がっている。
これは幻影だ。船の上で鐘を打ちながら僕が見た、かつての幻影だ。
今や浜辺の光は僅かな提灯だけであり、人影もまばらだ。出店など一つもありはしない。あの喧騒や笑い声はどこへ行ったのか。あんなにもいたたくさんの人たちはどこへ行ったのか。なぜ島を出て行ったのか。なぜ人は街を目指すのか。
吐き気を打ち消すように僕は鐘を打ち続けた。
長い長い時間を終えて、船が港にたどり着き、陸地に足を踏みついたその瞬間を僕は忘れない。
揺れない。どれほど力を入れて踏んでも揺れない。
まさに揺るぎない安心感が体にじわりと広がった。いつか見た映画で船乗りが砂浜に降り立って、足元の砂浜にキスをしていたシーンを思い出す。僕は本当にそんな気持ちになっていた。キスをするような心の余裕はなかったが、なんと愛すべき大地か。揺れないということがこれほど素晴らしいことだったとは。
「座って飲み直そうやー」
背後から聞こえてくる、長老たちの恐ろしい会話に振り返る余裕もなく、逃げるように家までの道を急いだ。
這うようにしてなんとか帰り着いた家の玄関で、扉を開けた途端に倒れ込み床に突っ伏して動けなくなってしまった。
「大丈夫!?」
気づいた家族が驚いて駆け寄ってくる。ちっとも大丈夫ではなかったけど、この胸の気持ち悪さも、肩の痛みも、年に一度しか動くことのできない神様をお連れして、海の上で一緒に楽しんだのだと思えばそう悪いものではないような気もした。
・・・おええぇっ。