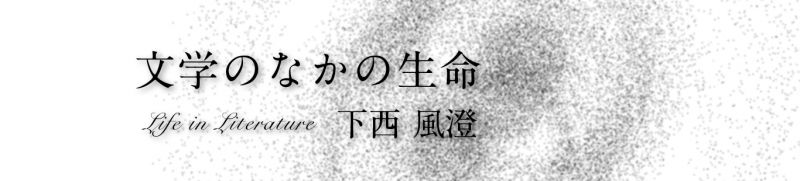第6回
屁みたいな時間
2022.03.17更新
最近息子のおならが臭い。7歳のそれとは思えぬほどに臭い。
いや今に始まったことじゃない。思い返せば、保育園時代からその臭さは群を抜いていた。出る気配を感じたら、素早く保育園の外へ出て放屁。尻を7回振ってから戻ってくるように。そんな変てこなアドバイスを息子に与えるほど、保育士さんたちも臭さに耐えかねていたようだった。
一度、島の料理屋でも気まずい思いをしたことがあった。
家族で温泉の帰りにご飯を食べながら、気持ちよく一杯やっていたが、気がつくと息子の姿が見えない。どこへ行ったのかねえなどと話していたら、通路を挟んだ個室席の扉がバンと開き、中から顔馴染みの大工さんがうちの息子を抱きかかえて小走りに出てきた。どうやら息子は知っている顔の人を見つけて個室へ入り込み、室内で派手にお見舞いしたらしい。
「こりゃすごい! どういうたらええんじゃろう・・・これはほんまにすごい破壊力じゃね」
その臭さに驚いた大工さんの口ぶりには一切の嫌味はなく、本当に感心したという様子で笑顔でそう言った。
この夜は何かの会合があったようで、開いた扉の中を見ると元町会議員の方や、県の職員の方など、数名のお偉い方々が酒の席を打っている。僕の顔を見た1人が個室の中へ呼び、酒を勧めてくれた。断るわけにもいかないので、そそくさと部屋へお邪魔したが、僕は酒を注いでもらいながらも息子の残り香に閉口していた。息子は大事な会合に水ならまだしも、屁を差したのだ。僕は申し訳ない気持ちでいっぱいだったが、何十年も議員を務めてきた主賓の方はさすがであった。そんなことは意にも介さず豪快に笑って酒を酌み交わしていた。
隠さずに書こう。
息子の屁の臭さは僕由来のものだ。
妻に言わせれば、全く同じだという。それどころか、息子のものをさらにギュッと凝縮したのが僕のものだという。おならが原因で離婚した夫婦もどこかにいると思う。いつだったか妻は僕に向かって真顔でそう言った。
なぜこんなに臭いのか。ほとんど同じものを食べて暮らしている妻や娘は臭くないのに、なぜ僕と息子だけが臭いのか。
先祖にスカンクを悪戯に殺し、怨念を受けた者がいるのではなかろうか。いや、スカンクは日本にはいない。だとすると、どこか外国の血が僕たちにも流れているのだろうか。
今までたくさんの失敗をしてきたが、特に忘れられないのはホームセンターでの出来事だ。
僕は仕事柄よくその店を利用している。どうしても手に入らないものは仕方ないのだが、島で手に入るものはなるべく島の中で買うことにしている。そうやって地域の中でお金を回していくことこそ大事なことだと日頃から思っているからだ。
だが、この日ばかりはネット通販で済ませるべきだった。
その日何を買いに行ったのか、詳しくは思い出せないが、多分工具か何かが足りなくなって立ち寄ったのだろう。
体の中から出ていく前から、すでに悪い予感はあった。腹の中に特別熱いものを感じていたからである。こういう時は始末が悪い。確実に臭いことは経験上分かっていた。だが、出口は遠かったし、何よりこの日の客はまばらで少なかった。そして僕のいた通路には誰の人影もない。チャンス。今しかない。僕は思い切って放った。正直自分でも人生のワースト3に入るほどに臭かった。周りの空気が澱みはじめたその直後に、通路に女性がやってきた。話したことはないが、よく見かける店員さんだ。年配の方もたくさんいるというのに、その人だけは若い色白の綺麗な女性だ。どうか近くまで来ませんようにと祈るのも虚しく、事もあろうに、彼女は僕の目の前にある商品を取りに来た。居ても立ってもいられず僕はその場を離れた。僕の後方で彼女の鼻が曲がる音が聞こえた気がした。彼女の色白の肌が黄色に汚染されていく気がした。僕は心の中で何度も謝ったが、神さまは時に手厳しい。僕が辿り着いたレジに立っていたのは彼女その人だった。彼女はいつもと変わった様子はどこにもなく、淡々とレジでの会計作業を進めていく。僕が支払いを済ませている間、彼女が僕の方を見ることはなかったし、僕も彼女の顔を見ることができなかった。
それからしばらくして彼女はホームセンターを辞め、それっきり姿を見かけたことはない。彼女が退職した理由のどこかに僕の屁が関わっているんじゃないかと、僕は今でも本気で思っている。
そういえば島の暮らしの中で、印象に残っているレジでのやり取りがもう一つある。
あれも周防大島に移住してからそんなに月日が経っていない頃だ。
僕はその日初めて入った喫茶店でコーヒーを飲み終え、お代を払おうと店員さんに伝票を渡した。彼は僕よりいくらか年上だが、この過疎の島では確実に若者と呼ばれる年齢だ。正確な金額は忘れてしまったが、多分350円とかそのくらいで、僕は1000円札を渡したのだと思う。彼はレジを打ち込み、お釣りを出した。片方の手で小銭を持ち、もう片方の手にはレシート。僕に渡されるはずのそのお釣りとレシートを持った彼の手が空中で突然止まった。
「あー・・・」と言いながら、彼はなぜか目を見開いてレシートを見つめ始めた。彼のその大きな目から察するに彼は老眼などではない。一体レシートに何が書いてあるというのか。思わず僕は身を乗り出した。彼は口を半開きにしたまま、レシートを上げたり下げたり舐めるように見つめている。なんの変哲もないレシートだったが、彼にしか見えない特別なメッセージでも書かれているのだろうか。長いあいだ目を凝らし、眉間に皺を寄せている彼がミスタービーンに見えてきた。もしかして僕は
驚くほどに長く感じられた時間はせいぜい30秒くらいだったのだろう。口を開けたままレシートを見続けていた彼は突然僕の方へ向き直り、
「650円のお返しです。ありがとうございました」
と、さらりと言ってお釣りをくれた。僕は思わず腹を立てた。
知ってるよ! 1000円札出した時から知ってましたよ! 時間返してくれや!
声にこそ出さなかったものの、つい心の中で叫んでしまった。
そしてこのことを思い出すたびに、ある映画の登場人物もセットで思い出してしまう。それはミスタービーンではなく、「ももへの手紙」というアニメーション映画だ。
映画の舞台は周防大島によく似た瀬戸内海の島で、方言もよく似ている。登場人物の1人に郵便配達の男がいる。彼は都会で商社マンに挑戦したが、それを辞めて島に帰ってきたという。
近所のおじいさんとの会話だけで彼の人物像が滲み出ている。
「まあた隣のハガキが家に入っとったぞ! しっかりしんさい! お前は何をやっても失敗ばっかりで」
「あちゃー、まあたやってしもうた」
うろ覚えなので間違っていたらご容赦願いたいが、こんな会話だったと思う。
自分の失敗を笑いながら頭を掻く彼は、おっちょこちょいな人間だ。都会の商社マンのように素早く、先を読んで行動することはきっと得意じゃない。だけど彼はその人間性において村の人から信頼されている。
田舎で暮らしていてよく思うのは、大事なことが都会とは違うということだ。いくら仕事が素早くこなせても、信頼のできない人間とは一緒に暮らすことはできない。
都会で評価されるのは仕事を素早くこなし、結果を出す人間だろう。何につけてもゆっくりな人ではろくに仕事すら回してもらえない。では世の中にたくさん存在する少しだけゆっくりな人の居場所はどこにあるというのだろう。
僕はレシートの珍事件を思い出すたびに、怒った自分を思い返して恥ずかしくなっている。いったい自分の30秒がどれほどのものだというのか。馬鹿馬鹿しいほどに短い時間だ。僕は多分あの時、自分でも気づかないうちに島の中に都会の時間を持ち込んでいたのだ。
都会の時間感覚と島の時間感覚はまるで別のものだと今なら分かる。
近所の狭い田舎道で、前を走っていた軽トラが突然ピタリと止まる。
運転していたおじいさんと、道路の脇を歩いていたお婆さんがすれ違いざまにイノシシについて話を始めたようだ。あちこちの畑が荒らされて困っているのはみんな同じだ。
「あんたんとこもかね?」
「ほうよ、うちも芋がみな食われたんよ」
話し始めて3分が経過した頃、後ろの僕の車にようやく気がつき、再び車は走り始めた。僕もすれ違いざまにお婆さんに挨拶をする。
「今日はいい天気ですねえ」
「ほんまにいい日和じゃねえ」
向こうも笑顔でこちらを見て手を振っている。3分返してくれや! などと思うことはもうなくなった。
あの喫茶店もなくなってしまったが、レシートを見ていた彼は今も元気にしているだろうか。あの時、僕が感じた怒りはひょっとすると自分に向けていたのかもしれない。彼のレシートを見つめるポカンとした表情は僕が屁を放つ表情によく似ている気がした。