第31回
仲野徹×若林理砂 "ほどほどの健康"でご機嫌に暮らそう
2024.05.22更新
5月17日、『謎の症状――心身の不思議を東洋医学からみると?』が発売となりました。鍼灸師の若林理砂先生が、「病院に行くほどではないけれど、ちょっと困る。なんじゃこりゃ?」という64の症状を、東洋医学の古典を元に解説&アドバイスする新しい健康本です。
また、3月刊『仲野教授の この座右の銘が効きまっせ!』がおかげさまで大好評で、増刷が決まりました! 元・阪大医学部教授の仲野徹先生が、目からウロコの「座右の銘」30本を解説する一冊。生産的に機嫌よく過ごすヒントが詰まった、仕事・人生・学問に生かせるフレーズ満載の教養本です。
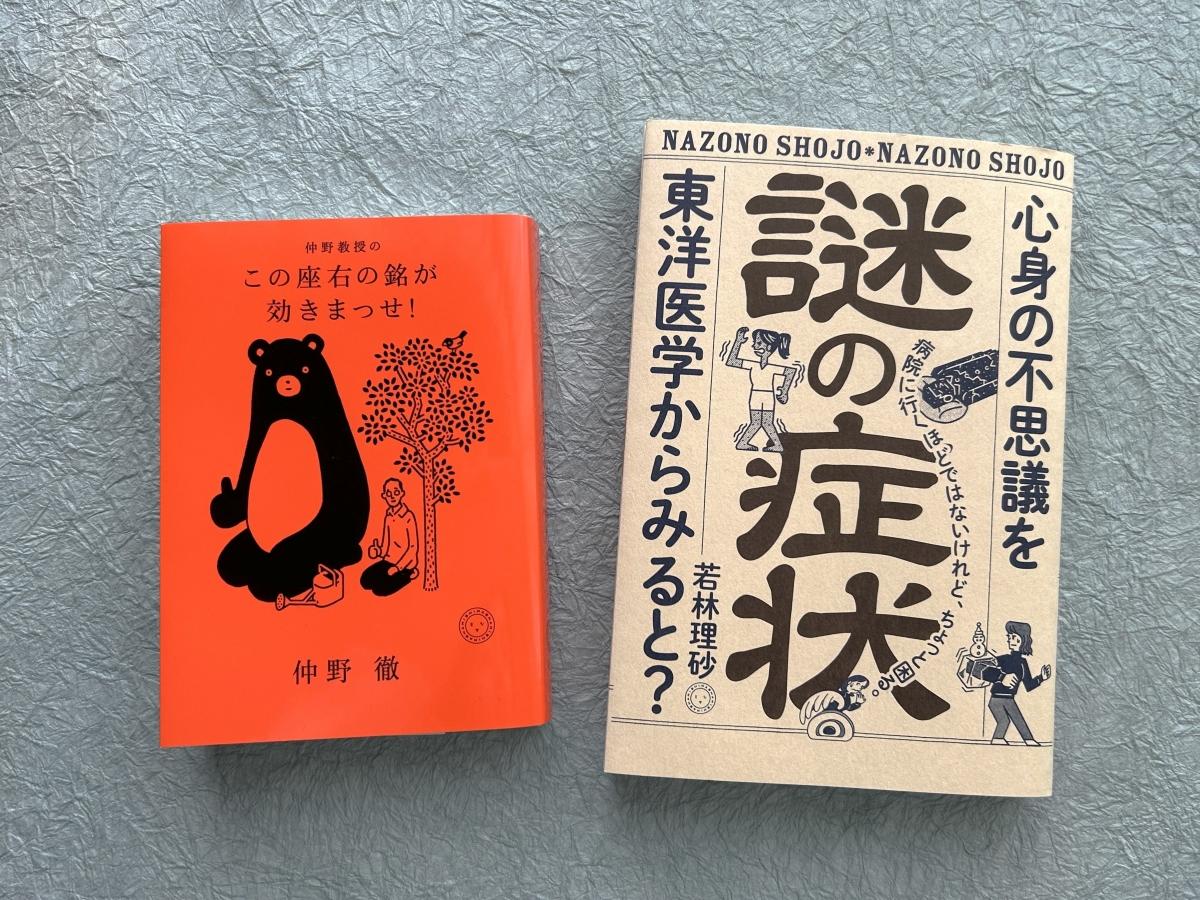
左:『仲野教授の この座右の銘が効きまっせ!』、右:『謎の症状』
東洋医学の臨床スペシャリストの若林先生と、西洋医学の最先端の研究に携わってきた仲野先生。それぞれ医学のプロフェッショナルでありながら、アプローチをまったく異にするお二人は、じつは数年前に対談をされています。
果たして、それぞれが考える「健康」に共通項は見出されるのでしょうか・・・? パワフルで刺激的、会場を爆笑に包んだトークを、本日は復活記事としてお届けします!
(構成:須賀紘也、星野友里、写真:岡田森)

アンチエイジングが嫌いですよね
仲野 若林先生、よろしくお願いします。初対面ではありますが、本日は失礼な質問からはじめようと思います。
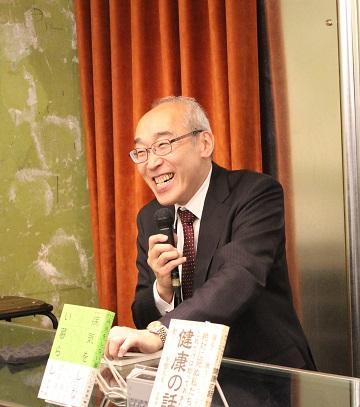
若林 はい(笑)

仲野 鍼灸には効果があるというのは認めます。でも、鍼灸って元になる理屈は無茶苦茶ですよね?
若林 そうですよ。
会場 (笑)
仲野 鍼灸はそういうところが不思議でたまらんのですわ。ミシマ社から「対談をやってくれないか」と連絡が来たとき、最初は断ろうと思ったんですよ。
若林 お医者さんは、鍼灸師の人と話したがらないですから。
仲野 そうでしょうね、わかります。でも、これ(『絶対に死ぬ私たちがこれだけは知っておきたい健康の話』)を読んだら、むっちゃおもろかったんで、引き受けることに。
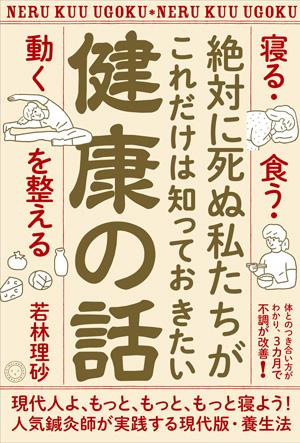 『絶対に死ぬ私たちがこれだけは知っておきたい健康の話』若林理砂(ミシマ社)
『絶対に死ぬ私たちがこれだけは知っておきたい健康の話』若林理砂(ミシマ社)
若林 ありがとうございます(笑)。
仲野 「この人、気が合うわ」と思ったんです。すごくおんなじ匂いがするんですよ。3ページくらい読んだところでおんなじ部類の人やと思いました。まずアンチエイジングが嫌いですよね。
若林 はい。
仲野 僕が『こわいもの知らずの病理学講義』を書いたとき、編集者に「アンチエイジングの悪口を書いてくれ」と言われました。でもね、それは書きにくいんです。アンチエイジングをやっている人が知り合いに結構いるから。でも、無理があるんですよね、アンチエイジングって。考えたらあたりまえですけど、どこかでガクッとくる。
若林 必ずきます。だって歳はとるんですから。絶対身体にガタがきますよね。
玄米を貼りたくなる気持ち
仲野 このまえ肩が凝りまして、家内が、首とか肩に貼る磁気治療のテープを買ってきたんですよ。「こんなもん効くわけないやろ、もったいない」とか文句を言いながら貼ってみたら、あっと言う間に肩凝りが取れて、「・・・効くやんか」とびっくりしました。
若林 鍼やお灸をしなくても、皮膚の表面に圧刺激を加えるだけで、ある程度は効果を見込めます。指圧でも効くのと同じです。
仲野 若林先生は、ペットボトル温灸の本も出されていますよね。ペットボトル温灸が効くのも、同じ理由ですか?
若林 同じですね。テープも鍼もペットボトル温灸も米粒も同じ。
仲野 そういえば、首に米粒を貼るだけで凝りが取れるとも書いてはりましたね。
若林 いけるんですよ! だから鍼がない場合は、「米でもなんでも貼れば効くよ」と言うんですよね。「米は玄米がいいですか?」と聞かれても、「別になんでもいいです」と答える。
仲野 それね、玄米貼りたくなる気持ちわかりますよ。「特殊なことせえへんと効かない」と思いこんでる人が結構多い。
若林 そうなんですよ。別になんでもいいんですけど。
仲野 「なんでもいい、なんでもいい」って若林先生、鍼灸師の敵とか呼ばれることはないですか?
若林 敵じゃないですけどねえ(笑)。すごくラディカルだとは言われます。私はどこの流派にも属さないでやってきているので、わりと言いたい放題なんですよ。
仲野 よく効く鍼灸師と効かない鍼灸師ではなにがちがうんです?
若林 身体の表面にどんな反応が出ているのかを、上手に触知できる人は、やっぱりよく効かせられますね。
仲野 あー、そういう非科学的なところがやっぱり嫌やなぁ。せっかく、ええところまでいってたのに(笑)。
若林 「ここがおかしいな」とか、あとは筋肉の緊張状態とかを、触ることで感じ取れる人と、そうでない人がいるんです。だから上手かどうかは、指先の感覚によると思います。
昔の鍼は、釘のように太かった
仲野 鍼灸は日本にいつ頃伝わったんですか?
若林 奈良時代かな? 伝わった当初は、お灸のほうが重要でした。
仲野 お灸ってお線香みたいで、なんとなく宗教的ですよね。なんか関係あるんでしょうか?
若林 やっぱり宗教的なことも関係したと思いますよ。お灸に使うヨモギは、魔除けになると考えられていましたから。
仲野 逆に鍼は消毒が大変やったろうしね。当時は火で炙るくらいしかできなかったはずやから。
若林 あと、当時の技術だと、太い鍼しかつくれなかったんで。
仲野 それは嫌やなぁ。釘みたいになってしまいますやん。
若林 本当に釘みたいでした。外科手術みたいなものだったんですよ。だからあんまり使われなかった。金属の加工技術が向上して、今の鍼の形に近くなったのは江戸時代です。当時は金や銀、特に金は粘性展性に富むので、細いのが作れました。
仲野 あっ、昔は金やったんですか。今は?
若林 今はステンレスがほとんどで、ディスポ(ディスポーザブル:使い捨て)です。でも、金のディスポもあるんですけどね。ステンレスだと1本50円しないところ、金は1本500円ですからね。もったいないなあと思いますけど。
仲野 「金でやってくれ」という人はいますか?
若林 私は使わないので言われませんが、「金がいいなあ、柔らかいなあ」という人も多いという話を聞きます。
仲野 それはやっぱり「玄米」の人と同じような考えですよね。
若林 注射針を金で作ったからと言って痛みが少ないかどうかと言われると・・・
仲野 まあ一緒でしょ。でもなんとなく金を使っとけばええことがありそうな気がする。「あああ、金が刺さっとる」って(笑)。顔に金の鍼をさしまくって写真撮る人とかおるやろね。
若林 インスタ映えしそう。
会場 (笑)
経絡ってないよね。医学的に。
仲野 中国4000年の歴史で、あ、ここは効くということでツボを考え出して、経絡があるというふうに導いたのはまあよしとしましょう。
※ 「経絡」・・・東洋医学において、気や血などの通り道と考えられているもの。体内の不調は、経絡を通じて経穴(ツボ)に伝えられる。反対に鍼や灸によってこの経穴に刺激を与えて病気をコントロールすることができるとされる。――(出典)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「経絡」
若林 よしとしましょう。ありがとうございます(笑)
仲野 でも経絡ってないよね。医学的に。というか、解剖学的に。
若林 あれは医学的にはないんですよ。解剖しても見えないから、全身を結ぶラインがあるわけではない。というので、最近は経絡自体というのを、筋膜の表面にあるなんらかの硬結部位なんじゃないかと捉えていますね。
仲野 それがね、ぼくらやっぱりはじめに基礎医学を学んで「こうこうこうこうなってるから、こういう治療をします」という論理体系でいくわけですよ。それが「効くからいいじゃん」的に考えられると、ちょっと困る。むしろ、無理に経絡なんかを仮定する必要があるのかという疑問がわいてくるんですわ。そもそも経絡ってどういう経緯でできたものなんですか?
若林 経絡の起源は、気の流れとかは関係なく、「この辺りのライン上にツボが出やすいよ」っていうのから始まったみたいなんですよ。そこからだんだん、気の流れとかを絡めて考えるようになっていった。
仲野 最初は「このへん押したらきもちいいな」ぐらいだったんですね。僕はそのほうが腑に落ちますね。今の生命科学でいうと、たぶん、経絡なんかではなくて、高次脳機能で説明できる、というか、すべきような気がします。でも理屈がわかったところで、意味ないというたら意味ないですもんね。効きゃええんですから。
若林 そうなんです、結果的に効いているからいいだろうとしか言いようがないものなんですよね。
ツボにまつわるエトセトラ
仲野 温泉の脱衣所とかに、腎臓だの肝臓だの書いてあるいわゆる「足ツボ」が置いてあるじゃないですか? あれは経絡と関係ありますか?
若林 ああ、あれは鍼灸だと思われがちですが違うんです。あれは「リフレクソロジー」というもので、鍼灸とは全然別物です。リフレクソロジーはあるスウェーデン人が。
仲野 ちゃうんですか。
若林 あれね、作ったのは台湾に行ったスウェーデン人の宣教師なんですよ。謎でしょ?
仲野 「足ツボ」は好きな人多いですよね。
若林 多いです。私も「ここは腎臓ですよね?」とかよく言われます。そういうときには、「それは東洋医学じゃないからわかんないです」って言います。
仲野 またひとつ疑問が解けました。今日はむっちゃかしこなってきたなあ(笑)。逆子がなおるツボがあると聞いたのですが。
若林 6〜7割くらい治るというエビデンスを取っている人もいますよ。
仲野 効くんですねえ。あれはツボを刺激している間に逆子が動くんですよね? どういう仕組みで効くんです?
若林 そうそう、エコーで見るとわかります。どういう仕組みで効くのか、不思議ですよね。だって足の小指の先端にお灸のせるだけなんですよ?
仲野 足の小指の先端? それは鍼ではなくお灸なんですか?
若林 はい。至陰(しいん)のツボといいます。ここにお灸をすると、胎動が激しくなるんですよ。お灸で効くツボと、鍼で効くツボがあって、使い分けてます。
仲野 そうなんですか。またかしこなった(笑)。
病気をしない劇的な方法なんてない
仲野 この本でもうひとつ、いいことが書いてあるなぁと思ったのは、「若いうちから健康に気をつけなあかん」ということ。
若林 はい。
仲野 120歳まで生きようと思ったら、特にね。
若林 相当若いうちからじゃないと。
仲野 だいたい、気をつけ始めるのは、60歳ぐらいですよ。これでは手遅れなんです。本気で長生きしようと思ったら、生まれたときからアンチエイジングを・・・
会場 (笑)
仲野 いや、もうこうなったらアンチエイジングとはちゃいますけど(笑)。
若林 子どものうちからでも、よい生活習慣をつけようということですよね。仲野先生の『(あまり)病気をしない暮らし』も、同じことを書いてるなと思った。
仲野 この本は『(あまり)病気をしないくらし』というタイトルですけど、その具体的な方法についてはあんまり書いてないんですよね。だからインターネットのレビューに、「病気にならない方法が書いてない」みたいなことが書いてある。わかってる、っちゅうねん。
若林 でも「病気をしないくらし」というのは、結局「寝る」「食べる」「動くこと」に、しっかり気をつけることですよね。
仲野 そうなんですよ。たとえば国立がん研究センターがガンを防ぐために呼びかけているのは、「太りすぎず痩せすぎない」とか、「バランスを取った食事をする」、そのくらいのことなんです。つまり、病気をしない劇的な方法なんてないんです。
若林さんのこの本で、早寝早起きとラジオ体操をすすめてるんですけど、私もまさにそれやってるんです。研究したり経験したりしてきたことは全然違ってるのに、たどり着くところは同じなんやとびっくりしました。不思議みたいな気がしますけど、まっとうに考えたらそうなるんかもしれんですね。
若林 本当にそうですね。

(終)


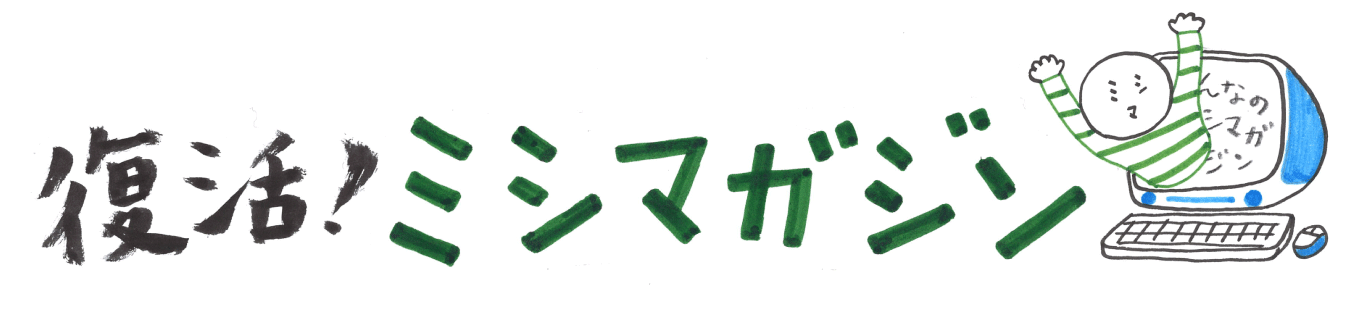
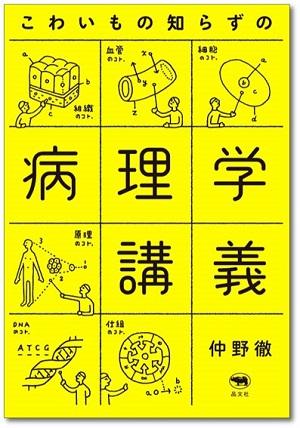
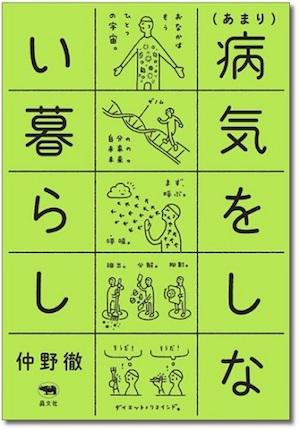




-thumb-800xauto-15803.jpg)
