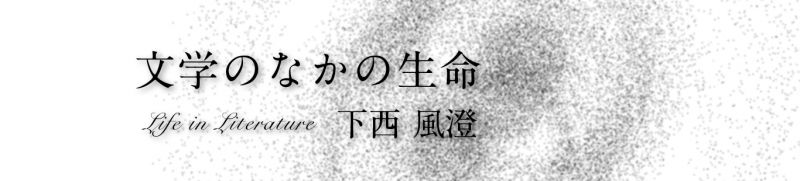第18回
ワンダフルライフ
2023.10.27更新
大きな声だった。
ケンカでも始まったのだろうかと、僕は思わず振り返った。
街の雑踏、人混みの中で歩いている一人の黒人女性が目に入った。黒い肌に赤い髪。細い紐のように編み込まれた長い赤髪が美しく頭上でまとめられている。彼女は確かに大きな声で何事かを話している。いや、叫んでいると言った方がいい。彼女の言葉は虚空へと向けられていた。空を仰ぎ、大声を上げる。あるいは地面に向かって、口を尖らせ強い言葉を発している。
イタリア語が分からない僕には、彼女が何を話しているのかもちろん理解できない。
立ち止まっていた僕には目もくれず、彼女は僕を追い抜いていった。
彼女は叫び続ける。驚くほど大きな声であるのに、街ゆく人は誰一人彼女に興味はないようだった。それどころか誰も彼女の存在に気づいてすらいないように思えた。
大声で叫んでいる彼女の横を、全く見向きもせずに大勢の人が通り過ぎていく。
そんなあり得ない状況が現実味を薄めさせ、白昼夢を見ているような気になった。
横断歩道で信号を待つ彼女と再び一緒になった。さっきまでの大声がまるで嘘だったかのように、彼女は静かだ。さりげなく横顔を覗き込むと彼女の目に涙が溜まっていることに気がついた。信号が青になり、彼女は音もなく歩き始めた。
彼女の去っていく後ろ姿を見ながら、もしかしたらあの叫びは祈りだったのかもしれない、そんな考えがふと頭をよぎった。さっきまでの言葉は聖書の一説か何かだったのだろうか。なんの根拠もないのだが、そんな気がしてならなかった。
僕はミラノの街角に立っていた。
母の古い友人に母を任せて、積もる話もあるだろうと、一人で街へ出てきたのだ。
考えてみればヨーロッパの街を一人で歩くのはこれが初めてのことだった。
僕が普段暮らしている島とは何もかもが違う。
そもそも島では知っている人に会わないというのは難しいことだ。コンビニでもホームセンターでもスーパーでも、どこにいても誰かしら友人や知人に遭遇し、挨拶を交わすのが日常だ。車ですれ違うほんの一瞬の間ですら、手を振り合うような日々だ。
僕はこの日、全く逆の体験をした。当たり前のことなのだが、誰一人として僕の事を知らない。それどころか言葉すら全く通じない。街の中を一人で歩くとき、僕は完璧なまでに他者だった。誰も日本語を話すことはできないし、僕にはなんの興味もない。まるで自分が透明人間にでもなったかのような気分だった。首から下げていたカメラだけが世界との繋がりであるかのようだった。
ビルとビルの間の路地に卓球台を並べて、笑い合いながら卓球に熱中する若者たち。
紙の手作りボールを蹴り合いながらかけていく子供たち。
信号待ちの自転車でイヤホンの音楽に意識を集中しているのだろう、目を瞑っている若い女性。
家に帰る途中だろうか、リュックを背負った少年はとても嬉しそうに体を揺らして歩いていく。
夕暮れ時、橋の上でタバコをうまそうに吸っている青年は鼻の穴から勢いよく煙を放つ。
橋の反対側の歩道には哲学者のような初老の男性が物思いに耽りながら、夕陽を背に歩いていく。
偶然にそこで再会したのだろう、大きな歓声をあげて抱きしめ合う二人の女性。
3人組のおじいさんがエスプレッソを飲みながら何かに熱弁を奮っている。
レストランの窓際で食事をしている女性。彼女が顔を上げると、花束を持った男性がガラス越しに彼女を見つめて立っている。
僕はファインダーすら覗かずにたくさんのシャッターを切った。
写真を撮りながら思い出していたのは、「ワンダフルライフ」という一本の映画だ。学生時代に好きだった若き是枝監督の名作で、テーマは自分の死後に人生を振り返るというもの。自分の人生の全ての瞬間が映画のように記録されていて、自分が死んだ後に一つの場面を選ぶことができる。その選ぶ場面、そこにある気持ちこそが、その人にとっての天国であるというような話だ。
旅の中、すれ違っていく大勢の人々の表情を見ながら、その誰しもに、人生という時間が同じように流れているという当たり前のことが、なんだかとても不思議に思えた。
もしも映画のように神様か誰かが全ての人の人生を記録しているとするなら、それはあるいはカメラのようなものかもしれない。
ほんの瞬きほどの時間だけだが、カメラは誰かの人生に居合わせることを可能にしてくれる。
日の暮れた街角、お菓子屋の前で、赤ちゃんを膝に乗せて座っているおじいさんがいた。身なりからしてこの人がお菓子屋の主人だろう。閉店前のお店の中にはピンク色のエプロンと帽子を身につけた奥さんらしきお婆さんが忙しそうに立ち働いている。
可愛い赤ちゃんと目が合って、思わず足を止めて微笑んでしまった僕に、おじいさんは優しく笑いかけてくれた。無表情だった赤ちゃんが突然体を起こし、一点を食い入るように見て笑い始めた。
視線の方角から現れたのはお兄ちゃんなのだろう、10歳くらいの少年が鞄を背にどこかから帰ってきた。兄も弟を見つめて近づいていく。二人のキラキラとした視線が交わり、手を取り合う。それを温かい目で見ているおじいちゃん、店の入り口からその様子を見て嬉しそうにしているおばあちゃん。あるお菓子屋の店先で、一つの家族の幸せがスローモーションのように滲み出していた。
こんな家族の風景が世界中のどこにでもあるとするなら、そんなに悪い世界ではないのかもしれない。
一日中歩き続けてすっかり足がくたびれてしまった。
空はすっかり暗くなっていたが、街の広場は街灯で照らされていた。どこか温かい色をした街灯だった。街灯の下にあるカフェの外のテーブル席に腰掛け、飲み物を注文した。散歩している時に、やたらと目についたうまそうな赤色のカクテル。あれをずっと飲んでみたかった。少し離れたテーブルでもその赤いカクテルを飲んでいる人がいたから、あれと同じものをくださいと伝えた。
運ばれてきたカクテル。透明な赤い液体の中に氷が揺れ、オレンジの輪切りが浮いていた。普段カクテルなんて飲むことはあまりないが、これは見るからにうまそうな代物だ。一口飲んでみる。飲んでみて初めて、喉が乾ききっていたことに気がついた。驚くほど美味かった。少しだけ甘いが、ほろ苦い。爽やかな炭酸の中にオレンジの酸味が加わる。そうやって飲むものではないのだろうが、気づいたら一気に飲み干してしまっていた。グラスをテーブルに置いて、息を吐き出した時に、一人の褐色の肌をした男が僕に近づいてきたことに気がついた。男はたくさんの光る棒を持っていた。子供むけの玩具なのだろうが、全く見たことのない物だった。しなっている細い棒の先に大きな風船のような球がついていて、その球体がうっすらと虹色に光っている。柔らかい杖の先で大きなシャボン玉が固まったような、不思議な物体だ。うちの子供が見たらすぐに欲しがるだろうと思うのと同時に、こんな大きなものは絶対にスーツケースに入らない。どんな売り文句を言われても絶対に買わないぞと心に誓った。
イタリア語で話しかけられたが、何を言っているのか分からない。英語で返してみるが全く通じない。そうだった。売り文句どころか、そもそも言葉がわからないのだ。
男は自分のことを指差して「アリ」と何度も言っている。名前なのだろう。状況がよくわからなかったが、反射的に僕も自分を指差し「ケン」と言ってみた。ケンタロウだと発音しづらいだろうと思って、そう口に出してみたが、バービー人形の隣にいる爽やかでマッチョな歯の白すぎる男が頭にチラつき、なんとなく嫌な気分になった。なんとか気を持ち直すために、日本人の正当なケン、つまり高倉健を必死に頭に思い浮かべた。僕が昭和生まれだからだろうか。これは思った以上に大きな効果があり、気分が落ち着いた。
アリはごく自然に隣の椅子に腰掛けた。え? そこに座るの? 驚いて少しドキドキしたが、何も動じることはない。何しろこちらには健さんがついている。
白人ばかりが行き交う中で、アリは褐色の肌で目立っていた。周りにはアジア人もいなかったから、こちらも少し目立っていたのかもしれない。アリはポケットからタバコを取り出し、こちらに薦めてきた。ここでタバコをもらってしまったら、この変な光る棒を売りつけられるに違いない。警戒していた僕はそれを手を振って断った。タバコに火を付けるアリ。
アリは優しい口調で話しかけてきた。その声は見た目に反して甲高かった。
「ファミリア?」
・・・ファミリア? ああ、家族ってこと? いるよ日本に。ジャパンに。アリもいるの?
「シーシー。・・バンビーノ?」
バンビーノ? ってなんだっけ? 子供? キッズ? うん、いるよ二人。ボーイとガール。アリは?
「シーシー。バンビーノ」
アリは笑顔でうなづいた。僕は地面を指差して聞いた。ここに子供がいるの? イタリアに?
「ノー」
笑顔が消え、悲しそうな顔で首を振るアリ。どうやらアリは外国人で、自分の国に家族を残してきているようだった。イタリアの移民政策について僕が知っていることは何もない。街の中でアリと同じ肌の色をした人を何人か見かけたが、それはみんなウーバーイーツの自転車に乗る人たちだった。きっとみんなそれぞれが出稼ぎのようにどこか外国から来ているのだろう。
その日は風のない日だった。アリの吐き出した煙は街灯の黄色い光を浴びて、とてもゆっくりと街の空へと昇っていった。アリは灰皿でタバコを消し、立ち上がった。
「チャオ、ケン」
握手を求めてきたアリの手を僕は握った。チャオ、アリ。
たくさんの光っている変な棒を抱えて、街の雑踏へとアリは消えていった。結局一度も買って欲しいと言われることはなかった。こんなことなら一緒にタバコを吸えばよかった。もう何年もタバコを吸っていないのにそう思ってしまったのは、きっと街灯を浴びたあの煙がものすごく綺麗だったからだ。
ファミリア。
アリの言ったその言葉がなぜか妙に耳に残っていた。