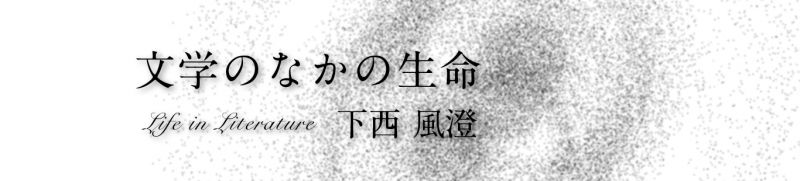第12回
右の手、左の手
2022.09.26更新
何もない土地に、妻と二人で座っている。
更地とはこういうことを言うのだろう。この場所から見えているのは海、浜辺、椰子の木、それに朝日くらいのものだ。
誰も歩いていないのが不思議になるほど綺麗な浜辺を見渡しながら、僕らは石垣に腰掛けている。その石垣はいつ作られたのかわからないくらい古い代物だが、丁寧に積み上げられた石たちは今も崩れる心配などまるでなさそうだ。
この場所をどうしていこう。どんな風に未来に残したらいいだろう。
僕らはそんな話をしていた。
散歩がてら、以前からよく訪れていた大好きなその場所を、縁あって本当に自分たちが管理していくことになったのだ。夢が今まさに現実に変わろうとしていた。
半年に一度ミシマ社が発刊している雑誌『ちゃぶ台』で、「共有地」を取りあげるという。ミシマ社の三島さんから連絡があったのもちょうどその頃だ。
「共有地」。
その言葉に何かピンとくるものがあった。
僕と妻がよく話していたのは、そこを公園のような場所にしていけないだろうかということだったからだ。
「共」という漢字の語源を古くまで辿っていくと、左右の手で器を持つ形を表すとのことだ。それもただの器ではない、神に供える礼器だ。
そこから転じて、ともにする、そなえるという意味が生まれていったとか。
これは白川静氏による考察だが、僕はこれを読みながら、かつて登った富士山の記憶がなぜか頭の中に蘇った。
山登りなど全くと言っていいほど挑戦したことのない僕だが、友人の口車に乗せられ一度だけ富士山を登ったことがある。初めてのまともな登山が富士山。しかも友人の中に経験者は誰もいない。僕らはズブの素人である自分達の浅はかさを思い知ることになる。
僕らは夕方から登り始め、山頂を目指し、朝日を拝んで帰ってくるという、早い話が徹夜で登山という最も困難な選択をしていた。なぜだかわからないが、そう決まってしまった。
「なんとかなるっしょ。いけるっしょ」
集合した男5人は何度もこの言葉を阿呆のように繰り返していた。登る前の緊張もあったのだろう、僕らは奇妙な興奮に包まれていた。
いざ登り始めると、当初思っていた爽やかな山登りのイメージは一変した。まず何より景色が悪い。夏であるにもかかわらず、青々とした草などはどこにも見あたらない。文字通り、草一本ない岩山だった。殺風景な岩山を登り続ける大勢の人たちの険しい顔はまるで地獄を思わせた。履いてきた靴も悪かった。一体なぜ僕はスニーカーを履いてきてしまったんだ。砂利で滑って登りづらいこと、この上ない。周りを見てみれば、どの登山客も立派な靴を履いているじゃないか。このスニーカーは下山の途中で壊れることになるのだが、登っている僕はまだそのことを知らない。
なんのために登っているんだ。何が楽しいんだ。登り始めたことを途中で何度も後悔していた。誘ってきた友人を恨めしく思う気持ちが徐々に募っていく。「引き返す」というワードが頭の中を何度もチラついたが、それまで登った分が水の泡になるのも、友人たちに根性無しと思われるのも、それはそれで悔しい気がした。やがて夜がやってきた。真夏だというのに、標高が上がるにつれてどんどんと寒くなり、上着を重ねていった。
僕らは途中の山小屋で、カレーを食べた。山で食べるカレーは格別だというが、大した記憶も残っていないことを考えるとそれほどうまいわけではなかったのだろう。それよりも気になったのは宿泊者である。山小屋の奥には大勢の登山客が横になって休んでいた。もっとはるかに早い時間に到着し、みんなしっかりと休息をとっている。そんな手があったとは。はっきり言って羨ましかった。そちらの部屋をただただ羨望の眼差しで僕は見ていた。狭くてもいい。知らないおじさんの髭面が目の前にあってもいい。あったかいところで横になりたい。なぜあっちのプランにしなかったのか。僕らはおそらく全員が同じことを思ったが、誰一人口には出さなかった。自分達の愚かさを呪っても遅かった。休む場所もなければ金もない。若さと体力だけを持つ男5人は後ろ髪を引かれながら、再び暗い夜の山へと出ていった。
山小屋を出てすぐのことだ。再び登り始めた僕らはとてつもなく大きな流れ星を見た。流れていく音が聞こえるんじゃないかと思うほどに大きな星だった。僕らの少し前を登っているグループがいるのだろう、前方の暗闇からも大きな歓声が上がった。山小屋の中で眠っていたら見ることはできなかったのだと思うと、この無茶な登山計画もそんなに悪いものではないように思えてきた。
いよいよ迫ってきた頂上付近で、杖をついて登るお婆さんの姿があった。それもかなり高齢の方だ。連れ合いの方に支えられながらも、大きく肩で息をしている。一体なにがこの人をここまで衝き動かしているのか。必死に山頂を目指すその姿が今も胸に焼きついている。
そしてついに辿り着いた山頂。大勢の人が朝日が登ってくるのを今か今かと待っていた。
空はもうすでに白んでいる。真夏だというのに、山頂の空気は真冬のそれよりも冷たかった。
青白い空から赤色へと徐々に変わっていく。真っ赤な太陽が少しずつその姿を見せ始めた。
気がつくと僕は手を合わせていた。右手と左手をぴったりと合わせて朝日を拝んでいた。僕だけじゃなかった。周りを見渡すと、山頂にいた大勢の人は誰もが手を合わせて朝日に向かっていた。先ほどの杖をついていたお婆さんも、手を合わせ何かを祈っている。知りもしないたくさんの誰かと、一緒になって手を合わせたのはあれが初めてのことだったと思う。
「共」という漢字が表すとされる右手と左手。
これを書きながら今ふと思ったのだが、あれはもしかしたら誰か別の人の手なんじゃないだろうか。
誰かと一緒に一つの器を持ち、神に供える。そこに他者の存在があってこそ初めて「共にする」ということになるんじゃないだろうか。
話を一番最初へと戻そう。
僕らは夫婦で広大な土地を前にして石垣に腰掛けている。凪いでいる海から聞こえてくる波の音はごくわずかだ。
未来、この場所はどうあってほしい?
僕のこの質問に対する妻の答えはこうだった。
「風の谷・・・みたいな場所かな」
これはもちろん宮崎駿監督の映画「風の谷のナウシカ」のことだろう。
多くの人がご存知の通り、映画の舞台は地球の未来だ。
戦争によって文明が滅んだ後の世界では、人類が撒き散らした毒を浄化するために腐海の森が生まれていた。森の放つ瘴気と呼ばれる毒ガスのために人類はマスクなしでは生活できない。風の谷は海からの風によって守られ、平和な暮らしが続いているが、世界ではいまだに戦争は絶えない。
旅人は言う、「この谷はいい。いつきても心が和む。なぜみんなこの谷のように暮らせんのだ」と。
主人公ナウシカは虫の声を聞き取り、意思疎通する力を持っている。やがてその力は周囲を巻き込み、戦争を止めるほどに大きなものへと変わっていく。
この映画が制作されたのは80年代だが、今思い返してみても、まさに現代とリンクするところばかりで驚いてしまう。
コロナウイルスによってマスクを手放せなくなったこともそうだが、ロシアがウクライナに侵攻を始めたこともそうだ。ウクライナの原子力発電所にミサイルが撃ち込まれたという、およそ正気とは思えないようなニュースが聞こえてきたのはつい10日ほど前のことだ。
人類が始まって以来、戦争がなくなった試しはない。この地上でそれを実現するのは不可能だ。そんなのはただの綺麗事だ。そう言う人もいるだろう。
確かにそうかもしれない。だけど、僕らは試されている。
圧倒的な他者と、その掌を合わせることができるだろうか。
生まれた場所も、年齢も、性別も、考え方も、宗教も、あらゆる面で違う他者と一緒に手を合わせることができるだろうか。
今一番求められているのはそういうことかもしれない。
この綺麗事を現実へと変えていかなければ、未来はきっとひどく陰鬱なものになってしまう。
大切な話し合いは会議室などではなく、どこか風の吹き抜ける自然の中でやってみてはどうだろう。朝日を望める砂浜もいいかもしれない。
僕らがこれから管理していくこの土地も、いつまでも風通しの良い開かれた場所として残していきたい。
実は僕らはこの広い土地の一角に、ミツバチのミュージアムを建てようと計画している。
ミツバチは社会性昆虫と呼ばれる生き物だ。耳慣れない言葉だろうが、これは独自の社会を形成し、集団で暮らしている昆虫のことだ。彼らは人間とは違う別の社会を持って暮らしている。アリやミツバチなどの社会性昆虫の質量は、実は地球上で一番大きいという説もある。その点だけを見たら、地球の支配者は人間などではなく彼らの方である。支配などという意識を持っているのは人間だけに違いないが、少なくとも、絶対的な事実としてわかっていることは、虫たちが僕ら人間の大先輩であるということだ。彼らは人類が生まれるよりも遥か前からこの星に暮らし、そしてさまざまな進化を遂げて生き延びてきた。
小さな虫の声に耳を澄ます事ができる場所。
気持ちの良い風がいつも吹き抜けていく場所。
誰が訪れても、そこにある海が受け入れてくれ、自分の中に何かを見つける事ができる場所。
できることならそんな場所を作りたいと思う。
さて、少し大きすぎる風呂敷を広げてしまったが、翻って足元である。
目の前の最初にして最大の他者である妻。まずはこの人ときちんと掌を合わすところから始めなくてはならない。
なにしろつい先日も、飲み過ぎの二日酔いできついお灸を何個も据えられたばかりである。
ちなみにミツバチの世界ではオスの立場はとても弱い。交尾が終わるその瞬間に、オスは死ぬ。それもただ死ぬのではない。性器がポンっと音を立ててもげて、死ぬらしい。
人間に生まれて本当によかった。
うちは二人の子供を授かったが、幸いにも僕の股間は今のところまだ無事である。