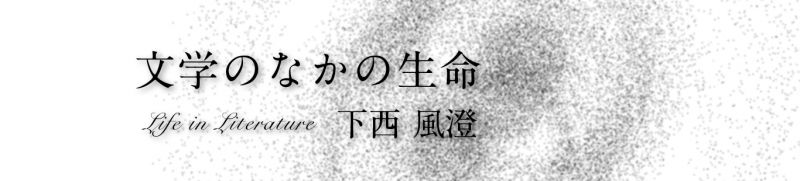第19回
ベッラビータ
2023.11.06更新
僕は母と二人、列車に乗っていた。
「世界の車窓から」というテレビ番組を幼少期に見ていたこともあって、初めてヨーロッパの鉄道に乗るのだと、乗車する前、僕は少なからず興奮していた。窓の外に広がる雄大な景色にどれほど自分は圧倒されるのだろうかと。だが、そんな期待は列車に乗った瞬間にあっさりと粉々に打ち砕かれた。
窓が汚ねえ。
なんにも見えねえ。
水垢なのか何なのか、驚くほどに曇っている。せっかくの窓際の席もこれではまるで意味がないじゃないか。途中の停車駅で止まるたびに、ダッシュで外へ行って窓を拭きたい欲求に駆られたが、日本の鉄道と違って、列車は何の予告もなく急に発車する。「世界の車窓から」のスタッフは撮影よりも何よりも前に、まず窓拭きのプロであるに違いないと思った。
途中の駅で大きな花束を抱えた若いカップルが乗ってきて、僕たちのすぐ目の前の席に座った。ケント・デリカット似の金髪メガネくんの隣にはペネロペ・クルス似の黒髪のスレンダーな美女。
さすがは愛の国イタリア。二人は人目も憚らずにキスを始めた。すごい。はっきり言ってすごい。濃厚すぎる。
窓の外がまるで見えないこともあり、ますます目のやり場がない。見たいわけではないのだが、いや本当は見たいのだが、どうしても視界に入ってきてしまう。ふと隣の席を見ると、仕切りに歯間ブラシを動かしている母がいる。食べていたサンドイッチの破片が詰まったのだろう。確かにさっきのハムチーズサンドはやたらと固かった。老いた母の歯の間にカンパーニュが詰まっていることは容易に想像できた。
ケントはペネロペとチュッチュしている。母は歯間ブラシでシャコシャコしている。
ケントはチュッチュ、母はシャコシャコ。チュッチュシャコシャコ。
もしも一瞬で誰かと入れ替わるという魔法が一度だけ自分に使えるなら、今この瞬間にケントに使うぞ! と、全力で念じて目を見開いてみたがそんな魔法は使えなかった。
やがて列車が停車し、ケント達は降りていった。汚い窓越しに目をこすりつけるようにしてうっすらと見えたのは、ホームで彼らを待っていたらしい老夫婦が二人をハグする姿だ。幸せそうな四人。結婚の挨拶に帰郷したのかもしれない。通りすがりの東洋人に、こんなにも見つめられていたと彼らが知ることは決してないだろう。さようならケンロペ、お幸せに。
僕と母の旅の最終目的地はドモドッソラという街だ。
山を一つ越えればスイスという、イタリア北端の街で観光客のいないとても静かな美しいところだという。
僕がこの街の話を今まで何度も聞いてきたのは、母にスイス人の友人であるフランチェスカとレグラという双子姉妹の親友がいるためだ。彼女たちが暮らしているのはスイスだが、たった30分列車に乗るだけで国境を越えて来られるという。島国で生まれ育った僕からすると、どうしてもこの列車で国境を越える感覚というのが分からないのだが、実際スイスでの物価高騰の影響もあって、多くのスイス人がドモドッソラの街の土曜市を目指して買い物にくるそうだ。
僕らがドモドッソラの駅に辿り着いたのはそんな土曜日のお昼頃だった。
母とホームをいそいそと歩いていると、前方から初老の女性二人組が駆け寄ってきた。フランチェスカとレグラだ。母と二人の抱擁はとても長く、久しぶりの再会を祝うようだった。
僕は初対面だったが、小さな頃から彼女達の写真は見ていたし、何より母に接するその態度に愛情が滲み出ていることにとても親近感を持った。
母の荷物を運ぼうと二人は奪い合っている。自分で運べると母は言ったが、自分達の方が3歳若いんだと、全ての荷物を母から取ってしまった。
彼女達は50年以上も前に母が通っていたペルージャの語学学校の同級生だったそうだ。母が20歳、彼女達が17歳の頃だ。
二人に先導してもらって僕らはドモドッソラの街へと歩き始めた。
静かな街、確かにそう聞いていた。
だが僕らが駅を降りて歩いていくと、ドモドッソラの街は狂乱の大騒ぎだった。
街の広場には音楽が溢れ、子供達は仮装して紙吹雪を投げあっている。真っ昼間だったが、飲み屋以外はどの店も閉まり誰もがコップを片手に乾杯している。
どうやら僕らは運がいいのか、悪いのか、年に一度のカルナヴァーレというお祭りの日にたまたま遭遇してしまったらしい。
大きな声で合唱する男たち。まるで野球の応援歌のような歌を、何度も繰り返し歌っては肩を叩き合い、大笑いし、酒を飲んでいる。
皆さまざまな仮面を付けて行き交っている。金色の妖しげなマスクをつけた美しい女性。マリオとルイージに扮する女の子。スパイダーマンの男の子。バットマンの格好で酒を運ぶ腹の出たおっさん。肌を真っ黒に塗り上げて黒人女性に扮するおっさん。警察官の格好をしている男の子。
中でも一際僕の目をひいたのは、自転車に乗っている青年だ。彼の自転車には長い釣り竿のようなものが垂直に突き刺さり、そのてっぺんにラジコンの飛行機がくくりつけられている。胸にはラジコンのコントローラーと音楽が流れるスピーカーが装着されている。なんとも陽気な自転車だ。彼は街の人気者のようで、あちこちでいろんな人に声をかけられては頬にキスをされていた。
歩いていると建物の窓から黄色い大きな布が垂れ下がっているのが目についた。よく見てみると、どの建物の窓からもその黄色い布がぶら下がっている。あれは一体なんなのか? 不思議そうに眺めていると、フランチェスカが、あれはポレンタだと教えてくれた。ポレンタ? それがなんなのか分からない僕の手を引くように、街の中心である広場へと連れて行ってくれた。そこにはいくつもの釜戸が置かれ、薪で湯を沸かしている。男たちが釜戸の上の大きな寸胴鍋を巨大な木べらでかき回している。なぜだかそこで料理をしているのはみんな男だった。広場のあちこちで湯気がモクモクと雲のように立ち昇っている。料理をしていた歯のないおじいさんが笑顔で一皿手渡してくれた。皿には黄色いペーストのような塊が盛られている。これがポレンタだという。僕には栗の入っていない栗きんとんにしか見えない。イタリアの赤飯のようなものだろうか。食べてみるとトウモロコシの香りが口に広がった。脇に添えられた大きな手作りソーセージと一緒に食べると、なんとも素朴で美味しかった。親指を立てて手渡してくれたおじいさんの笑顔が旨味を倍増させた。
広場の反対側に大勢の人が集まりはじめた。どうやら楽団の演奏が始まるらしい。近くまで行ってみると、やはりド派手な衣装に身を包んだ男たちが楽器を持って準備している。僕のすぐ脇に一人のお婆さんがいた。彼女は周りの空間から少し浮いていた。灰色のとても地味な服を纏い、誰とも話していない。何かに怒っているのか、どこか具合が悪いのか、顔も仏頂面でまるでつまらなさそうだ。
どん! と、太鼓の音を合図に音楽が始まった。陽気なリズムに再び紙吹雪が舞い始める。赤いとんがり帽子の周りに黄色い花を何本もくくりつけた音楽家が、サックスを高らかに吹き上げる。するとどうだろう、隣のお婆さんまでもが体を揺らし、ステップを踏み始めた。クルクルと回りながら、笑みを湛えて指を鳴らしている。その一瞬の変わりように、思わずこちらも微笑んでしまう。これは魔法だ。音楽の魔法。気がつけば、お婆さんのすぐ隣で踊りを踊っている自分がいた。
翌朝、大きなエンジン音で目を覚ました。
飲みすぎたようで、頭が痛い。夜中に宿の部屋に戻り、窓を閉めたところまでは覚えている。たしかそうだ。窓を閉めても、祭りの騒ぎはずっと部屋まで響いていたんだ。その音楽のリズムもなんだか心地よく、あっという間に眠ってしまったらしい。
すっかり寝坊し、慌てて準備をして外へ出ると、フランチェスカとレグラと母が準備万端で待っていた。今日は散歩に出かけるという。
二日酔いの身としては、はっきり言って散歩よりも睡眠が大事だったが今日は旅の最終日だ、そうも言っていられない。
街を歩き始めてすぐに、エンジン音の正体に気がついた。巨大な清掃車。大きなカバのような車体にぐるぐると回る電動ヤスリのようなブラシがついている。
そのカバの通り過ぎて行った街の道は驚くほど綺麗で、昨晩の大騒ぎがまるで夢だったかのように街は静かになっていた。あの山のような紙吹雪は、もうどこにも見当たらなかった。
僕ら4人は街はずれの道から巡礼の山道へと入った。山道と言ってもきちんと整備された石畳で、とても歩きやすい。聞くところによると、この巡礼の道は世界遺産の一つでありこのドモドッソラがあるピエモンテ州内に他にもいくつか存在しているらしい。その道の所々に聖蹟というのか、聖書での場面を描いた彫像や祠が鎮座しているという。
歩いている人の姿は僕らの他に誰もおらず、なんの音もしない。母がフランチェスカと話しながら前の方を歩いていたので、自然に僕はレグラと話をするようになった。
スイス人は多言語を話す人が多いという。レグラも5ヶ国語を話せるらしい。スイス語、イタリア語、英語、フランス語、ロシア語。一体どんな脳みそになっているのか、羨ましい限りだが、彼女たちが暮らすスイスでは、一つの食卓でも色んな国の言語が飛び交うのは当たり前のことだという。僕の拙い英語を彼女はきちんと理解してくれたので、とても話しやすかった。
どうしてそんな話になったのか覚えていないが、レグラが僕に聞いてきた。
「健太郎って名前はどういう意味なの?」
難しい質問だった。親がどんな思いを込めて名前をつけたのか、これは学校の作文などでも度々登場するポピュラーなテーマだが、名付け親である父に聞いても満足のいく答えをもらったことはない。曰く、呼びやすい名前にしたかったとか。ここは漢字の意味で答えるしかない。健は健やか、健康の健だからヘルシー。太郎は男を意味するのだからボーイだ。ヘルシーボーイ。気がつくと僕はレグラにそう答えていた。答えた瞬間にすでに後悔していた。
ヘルシーボーイ。なんて愚かな響きだろう。40を過ぎたヘルシーでボーイなおっさん。
返答に困ったレグラは、やや言葉に詰まりながらも、いい名前ね、と言ってくれた。
彼女はとてもいい人であった。
「リンカーネーションを信じる?」
リンカーネーション。知らない単語だった。ポケットの中のiphoneを取り出して、グーグル翻訳で検索した。生まれ変わり。転生。再来。
あー、輪廻のこと? 信じてるよ。とてもアジア的な、仏教的な考えだと思ってたけど、クリスチャンの人たちも信じてるの?
「人によるわね。私は信じてる」
じゃあ自分の前世がなんだったか分かったりする?
「ええ。東ヨーロッパの人間だった気がしているの。上手く言えないけど、そう確信したことが前にあるのよ」
母の前世はイタリア人だと思うよ。きっとレグラとフランチェスカとも友達だったんじゃないかな。じゃなきゃ50年も友達でいられないよきっと。
レグラはぱあっと笑顔になって、前を歩いていた母たちに駆け寄って同じ話題を話しはじめた。肩を叩きあって、笑っている三人。三人はそれぞれ70前後の老いた女性たちだが、今、目の前で笑い合っているのは20歳の母と、17歳の美しい双子姉妹だ。彼女たちのそんな時代を見たことはないはずなのに、今まさに映像のように目の前に浮かんでいた。
自転車の青年が通りかかった。祭りの時に見たあの飛行機付きの陽気な自転車だ。フランチェスカとレグラは知り合いらしく、挨拶を交わす。
かっこいい自転車だね。飛行機がついた自転車なんてきっと世界に一台だけだね。
日本語で話したから通じたはずはないのだが、彼は胸に取り付けたコントローラーで飛行機のプロペラを回して見せてくれた。僕が歓声を上げると、子供のような笑顔で手を差し伸べてきた。手を取り握手をすると、僕の目をじっと覗き込んで「ベッラビータ」と彼は呟いた。近くで見るとドキッとするほどに彼は透き通った目をしていた。
腹の前に括り付けられているスピーカーからは、サンバのように躍動する音楽が響きはじめ、彼は颯爽と走り去っていった。
彼の背中に手を振っている僕のそばにレグラがやってきて、耳元で言った。
「彼は精神に障害を持っているの。だけどとても心の綺麗な青年よ。彼はあなたに今、『美しい人生を』。そう言ったのよ」
お祭りのための自転車だとばかり思っていたが、どうやら違っていたらしい。
彼の自転車にはいつもあのラジコンの飛行機が取り付けられている。
彼が力強く漕ぐペダルと一緒に、プロペラもいつだって回っている。
そしていつも陽気な音楽を街中に響かせながら疾走している。
きっとこれを書いている、まさに今この瞬間にも。