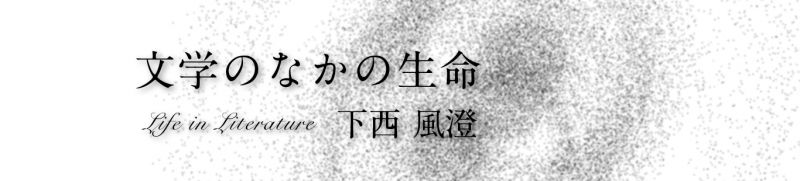第11回
匂いたいのに
2022.08.19更新
なんの匂いもしなかった。
片手に持っているのは香草の中でも特に強い香りを放つローズマリーだ。
それがどうしたことだろう。今日に限ってなんの匂いもしない。いくら鼻に近づけても、まるでそこに存在しないように、何も感じることができない。
ローズマリーは家の庭の一角に妻が植えていたものだが、最近ものすごい勢いで成長している。僕は料理への使い方は全く知らないが、近頃風呂へ入れることを覚えた。たまたまインターネットの記事でその効能を目にしたのがきっかけだったが、実際にやってみるとローズマリー風呂はとてつもなく気持ちのいいものだった。温泉も顔負けの心地よさである。ぬるめのお湯ではいけない。ローズマリーの持つ力を存分に発揮させるには、ハーブティーを煮出すかのように高温のお湯が必要だ。
そこへゆくと我が家にはとても便利なものがある。他の地域でなんと呼ばれているのか知らないが、ここ周防大島では「
ローズマリーを煮出すにはまさにうってつけの代物だった。
頭からつま先まで湯船に浸かって、全身を温める。のぼせそうになったらそのまま外へ出る。
島の民家の風呂には、庭から直接入れるよう扉がついている場合が多い。これは海から帰ってきた時にすぐに塩や砂を流せるためなのだと思うが、うちの風呂にも庭への扉がある。
体を芯まで温めたら、僕はその扉から外へと出る。そして外に置いてある椅子に深く腰掛け、そのまま全裸で外気浴だ。都会でやったら一瞬で逮捕されそうだが、何しろここは限界集落だ。
たとえ生まれたままの姿であっても誰に見られることもない。せいぜい近所のおばあちゃんが目の前の道を通るくらいだろう。その時はいつものように元気な声で挨拶をしよう。
もともと風呂好きであった僕はすっかりこれにハマり、今では庭のローズマリーを収穫してくるというのはほとんど日課のようになっていた。
それなのに、である。
ある日突然になんの匂いもしなくなってしまった。少し触るだけで、手についた匂いがしばらくとれないほど強烈なローズマリーの匂いを全く感じることができない。
嗅覚異常。明らかな異変が体に起きていた。
僕は片っ端からいろんなものを嗅いでみた。妻の香水や石鹸、シャンプー、洗濯物。汗臭いはずの自分の服。
どれひとつとして、なんの匂いもしなかった。
息子が屁をこく音がしたので、藁にすがるような気持ちで尻に顔を埋めたが、やはりなんの匂いもなかった。
あれほどまでに臭かったものがわからないなんて。
僕は自分の五感の一つを完全に失ってしまっていた。足元の方からじわりと恐怖感がやってくるのを感じた。
こうなってしまった原因は明らかだ。
少し前に家族全員でかかったコロナウイルス。家族みんな体調はすっかり回復していたが、どうやら僕にだけ後遺症があるようだった。
文字通りの味気ない生活が始まった。
まず何よりも食事が楽しくない。味覚はあるにはあったが、どうやら人間はその香りも一緒に食べているらしい。塩や醤油やソースの味、肉や魚の味。いつもの味噌汁の味。かろうじて感じることはできるのだが、美味いという感覚は遥か遠くにいってしまったように思えた。
なんだか目には見えないオブラートのような、膜のようなもので自分が包まれているみたいだった。膜の中から見える世界は色彩がなく、モノトーンだ。
自分が感じないものだから、自分の屁に対してもどんどん興味が薄れていった。自分が臭くないのだから、他人もきっと臭くないだろう。そんなあり得ないはずの錯覚を覚え、僕は所構わず放屁するようになっていった。
気がつけば、トイレで一人自分の排泄物と睨み合っていることも増えた。
そこにずっしりと横たわる糞がまるで自分のモノではないようによそよそしい。もはや糞でもいい。匂いたい。誰か嗅覚を返してくれ。
そんな匂いのない生活が続くある日、狸が死んでいるところに出くわした。
国道の真ん中。ちょうど中央線の上あたりで倒れていた。太陽はまだ上ったばかりだったから、暗い時間に車に轢かれたのだろう。
僕は仕事柄、いつもトラックで移動している。トラックには養蜂で使う道具以外にも、手袋やスコップ、新聞紙なども載せている場合が多い。この日もちょうどそんな道具が積んであった。僕はブレーキをかけて車を停めた。
田舎の道ではしょっちゅう色んな動物が死んでいる。まず圧倒的に多いのが野良猫だ。その次が猪、狸、蛇くらいの順番だろう。
先に正直に書いておくと、自分が野良猫をはねて、そのまま通り過ぎてしまったことも何度かある。そんな時もきっと誰かが片付けてくれたのだろう、次にその道を通るときは何事もなかったように綺麗になっていた。
その誰かが自分である。これは自分の番がきたかもしれない・・・。
そう思ったときはなるべく片付けるようにしている。そう思った時というのは、つまり手袋あるいは新聞なんかを持っていて、その上あまり急いでいない時だ。
この日はまさにそんな日だった。
死骸に近づいていくと、それは思った通り狸だった。死んでからまだほとんど時間が経っていないようで、口からはみ出ている舌は乾いておらず、濡れていた。さすがに素手で触るのは気が引けるので新聞紙を一枚かけてから抱えてやった。新聞紙越しに狸の体温が伝わってくる。本当についさっき死んだばかりなのだ。体はまだ温かく、柔らかだったが、やはりなんの匂いもしなかった。
この狸を食べる人はいるだろうか?
狸が永眠することになる穴を掘りながら、妙な考えが一瞬頭に浮かぶ。
もちろん現代の日本にそんな人はいないだろう。だがほんの少し時代を遡れば、この狸はご馳走であったはずだ。死んだばかりだ。ある意味フレッシュだ。昔話でもよく出てくるじゃないか。もしも僕が登場人物のお爺さんであったなら、このまま家に持ち帰り、包丁を研ぐ。
そして丁寧に皮を剥ぎ取り、内臓を取り出す。それからお婆さんと一緒に温かい鍋を囲んでいたはずだ。
前に一度、わな猟をやっている友人から丁寧に捌かれた猪の肉と一緒に、大きな骨をもらったことがある。骨も美味しいスープになるから是非試してほしいとのことだった。
その時期はちょうど冬だったから、薪ストーブの上に大きな鍋を置いて三日間ほど煮込んだ。
煮込んでいることをすっかり忘れて家に帰ってきて玄関を開けると、中からご飯の炊けるようないい香りが漂ってくる。あれ? 炊飯器のスイッチ入れてないよね? 妻と顔を見合わせる。
僕らはその時、初めて知った。猪の骨のスープはご飯が炊き上がるようないい香りがするということを。
この話をすると、都会で暮らす親や兄弟は眉をひそめたが、それは本当になんともいい香りだった。そのスープで作った中華粥はまさに絶品だった。
あの日から今に至るまで、猪を見かけるたびに、中華粥の鍋がヒョコヒョコ歩いていると想像してしまう。
僕は獣にとどめを刺すことはできないから猟をすることは今後もないだろう。魚の首を落とすのが精一杯で、鶏の首すら絞められそうにない。もしも本当に食べるものが無いほどに飢えていたら、きっと話は変わるのだろうが、今のところ近所の友人と肉屋さん頼りである。
これまでたくさんの動物の死骸を見てきた。それは職業柄、日常的に農道を走り回っているから普通より遭遇する可能性が高いためだろう。
印象に残っている出来事が一つある。
その日、僕はいつものように軽トラックで農道を走っていた。まだ開業したばかりの頃だったので、ミツバチの巣箱を置くための新しい場所を探しては、島の中を毎日隈無く走り回っていた。
僕は滅多に人の通らない山奥の農道で、一匹の動物の死骸に出くわした。
その時、その死体がなんであるのか、僕には判別できなかった。死んでからの時間が経ちすぎていて、骨と皮だけになっていた。猪なのか、犬なのか、それすらもわからなかった。
誰も通らない場所なだけに、これは自分の番だなと感じた僕は、穴を掘って土に埋めてやった。
その日の晩のことだ。すごく風の強い日だった思う。
僕は夜中に目を覚ました。建てつけの悪い窓が風でガタガタと揺れていたこともあったが、外から何か動物の気配がしたためだ。妻も目を覚ました。
気配の主は窓のすぐ向こう側にいる。僕らの布団の目と鼻の先だ。
「クゥーン、クゥーン」
どこか甘えるような犬の鳴き声だった。
なんだ野良犬か。
普通ならそう思うかもしれないが、僕らはそう思わなかった。なぜならこの辺りで野良犬を見たことは一度もなかったし、犬を飼っている人にも、散歩で連れられる犬にも出くわしたことは全くなかったのだ。
僕の背中は少し冷たくなっていたと思う。
犬は鳴きやむことなく、甘い声を出し続けている。
とうとう妻は手を伸ばし、カーテンを開けようとしたが、僕はそれを静かに制した。窓の向こうにいるのは、日中埋めてあげた動物に違いない、そう思えてならなかった。あれはきっと犬の死骸だったのだ。もしカーテンを開けたら、骨と皮だけの犬が失くした目玉でじっとこちらを見ているんじゃないか、僕は本気でそう思った。
甘い声を出していたそれは、数分の間、窓の外にいたが、こちらが何の反応もしなかったからか、しばらくするとゆっくりとした足取りで去っていった。
あれはただの偶然だったのだろうか。
島に住んで11年になるが、いまだに野良犬を見たことは一度もない。あの日の夜に限って野良犬が家まで訪ねてくるなんて、そんな不思議なことがあるだろうか。
もしもあの時カーテンを開けていたらどうだったろう。
何かもっと特別なことが起こったのだろうか。
もしかしたら打出の小槌を咥えた犬が、そこにいたのかもしれない。
あるいは、それは声だけで、そこには何の姿もなかったのかもしれない。
今頃になって、そんな想像をして笑っている。