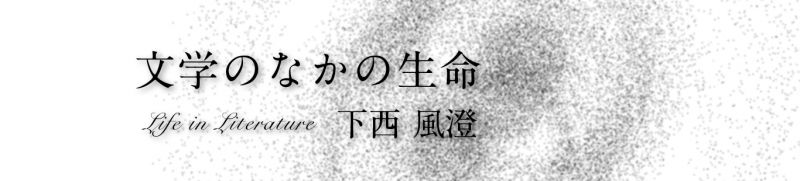第8回
口下手なおじさん
2022.05.13更新
もう何年も前のことになるが、はちみつ工房にいる時に電話が鳴って妻がとった。声が似ていたのだろうか、なぜか妻はその時、電話の主と父親を間違えた。
「もしもし、あ、お父さん? ・・・じゃないですね。すいません、失礼しました」
僕は部屋の傍で別の作業をしながら、なんとなく耳を傾けていた。いつもなら聞いているだけで誰からの電話なのか見当がつくものだが、この時はよくわからなかった。
しばらく続いた電話の受け答えから察するに、やや風変わりなお客からという感じだ。妻は話を受け流している。
養蜂を生業としているので当たり前だが、かかってくる電話のほとんどは蜂蜜の注文である。だがこの時の電話の主は、特に蜂蜜を注文するというわけでもなく、どうしてこんなに美味しいのか、その秘密は一体なんなのか、とにかく話を聞きたい。そんな様子だった。
今振り返っても、ああいう類の電話はあの時一度きりだ。
数分間続いたやり取りの後で、妻は電話の主に言われるがまま、携帯番号をメモし始めた。これも奇妙な光景だった。なぜこちらが電話番号をメモする必要があるのか。
「はい。ヤナギヤさん・・。はい。電話番号控えました。ヤナギヤさんですね。わかりました。良かったらぜひ今度周防大島にも遊びにいらしてくださいね。それではまた」
電話を切る妻。
「なになに? どういうこと? 結局誰からだったの?」
「なんか口下手なおじさんだったよ。こんな美味しい蜂蜜食べたことないって。すごい気に入ったって言ってたよ。それで、よくわかんないんだけど電話番号教えるからメモしろって。変な人だよね。コサンジさんだって。名前も変」
・・・え?
僕は目の前にあったパソコンですぐに検索をした。
そして震えた。
柳家小三治。
人間国宝。
「おい! 人間国宝の落語家さんだぞ!!」
ようやく、ことの重大さに気づいた僕らは二人で慌てふためいた。
国の宝である噺家に向かって口下手なおじさんはあんまりである。
それから数ヶ月後、縁あって松江での独演会にお邪魔する機会に恵まれた。
本番前だというのに、小三治師匠は気さくにも控え室に招き入れてくださった。落語界の中でも甘い物好き、蜂蜜好きだというのは有名らしく、お土産に持っていった新作の蜂蜜もとても喜んでくれた。
国宝と呼ばれるほどだから、さぞやすごいオーラに包まれた方なんだろうと想像していたが、楽屋の扉を開けて中から出てきたのは無精髭の普通のおじいさんだった。こう書くのは恐れ多いが、田舎によくある農協の紺地にオレンジの刺繍が入った帽子でも被ってもらったらよく似合いそうだ。そしてそのまま島の中を歩いていたとしても、完全に溶け込んできっと誰にも気づかれることはないだろう。
本当にこの人がそんなにすごい方なんだろうか?
門外漢である僕は自分の置かれている状況を理解していなかったが、楽屋へ案内してくれた落語事務所の方はすぐ隣で背筋を伸ばしきって緊張して立っておられる。
本番直前のこの時間にお邪魔するということがよほど大それたことであるとようやく気がつき、手短に挨拶を終え、そそくさとお暇した。
「美味しい蜂蜜これからも作ってね」
とても優しい笑顔を浮かべてそう言ってくださった。
カチコチに緊張しながらも、「はい! 頑張ります!」と僕は返事をし、固い握手を交わした。
「俺のほうも頑張るから」
そう言った小三治師匠は笑っていたが、目の奥の方からは何か静かに燃えるような光を感じた。
席に戻って、独演会が始まるのを待った。時間となりパッと客席の電灯が消える。ざわついていた会場内の空気がしんと静まり返った。舞台の上にだけライトがそっと落ちていく。舞台の袖から人が現れる。
小三治師匠だ。
だがその姿はまるで別人だった。
とてもゆっくりとした足取りで舞台の中央に向かって歩いていくその姿を見ながら、さっき会った人は本当は誰か別の人だったんじゃないか、そう思わずにはいられなかった。
髭は綺麗に剃られ、和服に身を包んでいる。
目に見える姿だけじゃない。体を纏っている凛とした空気そのものが、さっきとはまるで違っている気がした。
演目の前に自由に語られるイントロ、いわゆる落語の「まくら」の部分で小三治師匠がその日何を話したのか、その全てをここで思い出すことはできないが、一つだけはっきりと覚えている。
師匠はこの日、会場近くの美術館へ行ってきたらしい。そこで前から見たかったという、日本画の巨匠・横山大観の絵を見てきた話をされていた。その絵がいかに素晴らしいものであったかをユーモアを込めて話す師匠から感じたのは、勝負する世界は違えど、自分も負けてはいられないぞという噺家としての矜持のようなものだった。
小三治師匠は80歳を目前にしながらなお、表現者として、芸の道を進む一人の者として、更なる高みを見ているのだ。国の宝と呼ばれようが、人からどれほど評価されようがこの人自身にはなんの関係もなく、常に前だけを見て進んで行こうとしている。
先ほど楽屋で見た、目の奥で燃えている炎の正体にほんの少しだけ触れたような気がした。
僕はこの日初めて、一人の噺家によって、物語の世界に吸いこまれるという体験をした。自分の肌が粟立つのを何度も感じた。
体験という言葉が的確だと思う。聞くというよりは、体ごと渦の中に引きずり込まれて行く感じだ。
その日の演目の最後は「青菜」だった。
ある庭師が手入れをしているお屋敷で、そこの主人がひょんなことから庭師をもてなしてくれる。客人として自分を扱ってくれるその言葉遣いや気遣い、飲む酒や食べ物の違い、主人と奥方のやりとりなど。主人から受ける歓待のその端々で、庭師は大きく心を打たれ、そして憧れる。
庭師は自分の小さな家に戻り、今度は自分が主人として客をもてなそうと試みるのだが・・・。
演目の後半部分は、その前半を再現していくという話の作りになっている。
つまり観客である僕たちは主人公の庭師が次に何をやり始めるのか、何を語るのかを、あらかじめ分かっている。分かっているはずなのに、腹が捩れる、涙が溢れてくる。あまりにもうまくいかないその滑稽さに。その語り口に。
会場中のあちこちからうめき声のような笑いが起きる。物語の終盤、僕のすぐ隣に座っている人はひきつけを起こしたかと思うような笑い声をあげ、体をぶるぶると震わせた。
無理はない。僕もほとんど同じような状況だった。笑いすぎた涙で視界が霞んでいるのだ。誰もこの空間から逃れられない。小三治師匠が作り出したのは、イメージの渦だ。その渦の中に一人残らず引きずり込まれ、涙を流している。
それはまさに至福の時間だった。
見ず知らずの人たちが一堂に集まって、日常のさまざまな煩悩を忘れていく。その目の前に浮かび上がる話に吸い込まれ、笑い、そして涙する。
もしも仏教でいう極楽浄土があるとするなら、こんな場所かもしれない、そんな考えが一瞬だけ頭をよぎった。
ちょうど先日、ある本の中で女優の小林聡美さんが小三治師匠についてこんな文章を書かれているのを見つけた。
「入我我入」という言葉がある。密教の用語で、仏と我が入り混じり一体となる境地の事をいうそうだ。その言葉の意味を聞いたとき、小三治の落語みたいだな、と思った。聴くものの中に小三治の噺が入り、小三治の噺の中に聴くものが入る。そして小三治もきっとそんな境地で噺を紡いでいるのではないかな、と。
まことにうまいことを言う人である。僕は何度も膝を打った。小三治師匠の落語を体験したことのある人ならきっと誰もが頷くだろう。
何か一つの道を極めていく。
そのぶれない生き方に憧れてしまうのは、きっと自分がちっともそうではないからだろう。残りの人生でやりたいことを考えると片手では足らないどころか、すぐに両手両足まで必要になってくる。あまりの気の多さに我ながら呆れてしまう。
人間国宝と自分のような凡夫を比べるつもりは毛頭ないが、小三治師匠もどうやら気の多い人であったようだ。
先日読み始めた小三治師匠の『ま・く・ら』の中になんとミツバチの話を見つけた。
そこで師匠はミツバチの生態を語っていた。女王蜂の恐るべき産卵力や、雄蜂の怠けぶり。その交尾の不思議さや、雄蜂の死に方に至るまで。おそらく養蜂家ですら知らない人も沢山いるだろう、かなり専門的な話を面白おかしく語っておられた。本当にさまざまなことに研究熱心な方だったのだと頭が下がる。
ちょうどその本を読み終えた頃に小三治師匠の訃報が届いた。
本の中では養蜂場にも行ってみたいと語られていた。あともう少しタイミングが違えば、周防大島で蜜蜂を一緒に見てもらうこともできたのかもしれない。そう思うと残念でならない。そして何よりあの渦のような空間がもうこの世に存在しないのかと思うと、とてもやりきれない。
死後の世界を信じているわけではないが、あったらいいなと思う時もある。
極楽で落語。
こう文字にしてみるとなんだかとても相性がいい気がする。そんなこともあるかもしれないと思えてくる。
もしかしたら今も肉体を失った魂たちがこんな会話をしているかもしれない。
「なんだいこの行列は?」
「ああ、今日は志ん生がやる日だってよ」
「本当かよ? 俺も見てえなあ、だけどこの人だかりじゃとても入れねえなあ」
「明日は新しい名人が来るってよ」
「本当かい? 誰だい?」
「柳家小三治だってよ」
「おお、そりゃあいいねえ待ってました。明日はもっと早起きして来ようじゃねえか」
ミツバチの方はどうだろうか? 天国に存在するだろうか?
天国と蜂蜜。ヘブンとハニー。
なんだかこれもすごく相性がいいように思えるのは僕だけなんだろうか。
小三治師匠の脇に僕が立っている。二人でミツバチの巣箱を覗き込んでいる。
「小三治師匠これを見てください、これが働き蜂です。全部メスの蜂ですね」
「どれどれ。おお、おお、なんだか健気な感じがするねえ。可愛らしいねえ」
「そしてこっち。のそのそと歩いている働かない蜂、これがオス蜂ですね」
「これかい? なんだなんだ揃いも揃って不細工な奴らだなあ。見るからに怠けもんって顔に書いてあるじゃねえか。男ってやつはどうしてこうなのかねえ」
もしかしたらこんな会話ができる日が、いつかやって来るかもしれない。
夢の続きは死後の世界で。