第24回
「私の手放し」
2025.04.29更新
母は徐々に歩行能力を失った。今考えると、立つことができず這いまわるようになった頃が、一番混乱していたのかもしれない。手に触れるものをすべて引き倒していた。電話の台、室内用物干しラック、積み重ねた衣装ケースなど容赦なくひっくり返した。仕事から帰宅して部屋の惨状を目の当たりにすると、怒りよりもため息が先に漏れたものだ。けれどもその期間は思いのほか短く母はあっという間に寝たきりとなった。
やがて言葉も出づらくなった。口数も減っていく。言葉が出づらいのは脳挫傷の後遺症だろう。口数が減ったのは話す気がしなくなったからだと思う。
「ご飯食べる? 止めとく?」「起きる? まだ寝とく?」「トイレに行く? 行かない?」
母に対して、そんな声しか掛けていなかった。それがしゃべる気持ちを削いだのだ。
選択肢を設けることは意思の尊重につながると信じていたし、人を支援するときの正しいセオリーでもある。けれども母からすれば「どうする?」と尋ねられるばかりで、常に決断を迫られる。その度に母は自分が常に介護される側にいることを思い知らされていたのではないか。
そのことに気がついてからは、介護とは無関係の言葉を漏らすことにした。
「猫が1匹帰ってこない」と漏らしてみると「探して~」と母。
「ああ~、今日も疲れた~」と漏らしてみると「そればっかり~」と母。
「俺の方が、あなたより先に死ぬかもね」と漏らしてみると「死んでいいよ~」と母は優しい口調で応えた。
何の目的も意味もない僕の実感に母の実感が絡んでくる。その速度は反射に近かった。たわいのない会話が母と僕の間になかったことに改めて気がつく。
母が僕の声掛けに返事をしない理由をもうひとつ考えてみた。それは母が「いま、ここ」を生きる存在へと移行しつつあることと関係があるのではないだろうか。
「ご飯食べる? 止めとく?」「起きる? まだ寝とく?」「トイレに行く? 行かない?」は、「今をどうしたいのか?」を聞いているようで、実はほんのちょっと先の未来を尋ねているのだと思う。
排泄の面から考えてみる。これまで母に「オシッコ出る?」と幾度となく聞いてきた。その度に困った顔をする。頷きながらも首を横に振るような、「したい」とも「したくない」ともとれる曖昧な仕草だった。「も~、どっちね」と、しばし業を煮やした。
僕が母に尋ねていたのは尿意である。尿意とは「排尿したい」という感覚をいう。「そろそろ出るかな」といった程度のものを初発尿意と呼び、「もう我慢できない」という切迫した状態を最大尿意という。
膀胱にある程度の尿が溜まると膀胱壁が圧力を感じて尿意が生じるのだが、それをトイレに行くという行為に結びつけるのは脳である。それも「トイレで排泄する」という文化を学んだ脳でなければならない。最大尿意を迎える前にトイレに行かないと、とてつもない恥ずかしい目に会うのだと教え込まれた脳である。「お漏らし」=「恥ずかし」という強制的な学習が、ちょっと先の未来を予測させているんじゃないか。そして僕は母に代って予測してトイレに誘う(ちなみに解剖生理学的にも便器に座ってした方が体によいので、その理由からも誘います)。
けれども母は自分でトイレに行けなくなっても「トイレに行きたい」と訴えなかった。オナラひとつ聞かせたこともない。きっと体から漏れ出るものを人に曝せないタイプである。それじゃあトイレに行きたくても頼めない。
そういえば母はベッドの上で「あああああああッ」と雄叫びを上げることがあった。あの時、「恥ずかしい」という自意識が母に初期尿意をスルーさせ続け、やがて迎えた最大尿意に耐えられずパットに排尿していたのだろう。それを繰り返すうちに尿意と恥ずかしい思う自意識を失ったのだ。同時に予測という時系列的思考も不必要となった。結果的に母は「どうしたい?」というちょっと先の未来に対して応答できなくなったのではないか。そのような過程を経ながら「いま、ここ」にしか生じない実感の世界へと移行しているのではないかと想像している。
実感には熱さが瞬間にやって来て去っていくのと同じスピード感がある。「美しい」という実感も同様にあっという間にやって来て去っていく。母の自意識は現れては去っていく実感の受け皿に変容しつつあるのだろう。すなわち「私」という自意識の手放しである。
寝たきりの母がぽかんと天井を見ているときの顔は空虚感が漂っているように見える。でもそれは、ぼけのある人は知的な衰えがあるという世間から培われた偏見の投影である。「いま、ここ」を生きるとは瞬間、瞬間に現れては去っていく出来事に向かい合い続けることで、過去に囚われたり、未来を憂いたりする暇などないのである。現代社会を生きる僕らはそれとは逆の態度で暮らしている。過去に原因を探し続けたり、未来を予見したりすることに夢中で「いま、ここ」を感じる暇がない。
母にはさまざまな実感が押し寄せている。足を包む電気毛布の温み、揺らぎながら移動する陽射し、人の顔に見える天井の木目、エアマットが漏らす空気音、鳴りっぱなしのラジオ、鳥のさえずりや風の音、自分のオナラの臭い。今まさに溢れ出る温かいオシッコ。そして冷たくなっていくオシッコ。体をとりまく内外の環境は多種多様に満ちている。母はそれらを意思によって取捨選択することなく受け取っている感じもする。その豊穣に呆然となりポカンとしているようでもある。
圧倒的な量で迫る豊かさに感覚が没入している状況で自意識が手放されていくとするなら、それは空虚とは真逆の充実した世界に母はいるのだと考えたりもする。
最近、母の僕を見る目が変わってきた。僕の顔を見ているようで、その後ろを見ているのではないかと思わせる射程がある。思わず後ろを振り向いて距離を測り直してみるのだが、やっぱり僕の顔を見ている。
あの瞳の変化に心当たりがあるとするなら、かつて僕を苛立させた思惑や目論見が母から消え始めていることだ。何か言いたそうな不満に満ちた母の瞳。そんな印象が僕の記憶に居座ってきた。けれどもいつも審判されているような居心地の悪さが小さくなりつつある。つまり僕を支配してきた母らしい思惑(自意識)が小さくなることで、僕は母の手の内から母は僕の抗いから互いに自由になりつつある。
なんだか交流を許さないところに、母が行こうとしている感じもする。それは僕を寂しくもさせた。けれども母からじっと見つめられると、ちょっと怖い感じがする。畏怖の念に通じる怖さだと思う。
仕事で接してきたご老体たちにも「私の手放し」が生じると尊い気持ちが湧いていた。母がそのような存在に近づいているのだとしたら素直に尊敬できそうだ。それにしても修行することなく仏陀の境地に導いてくれる老いに改めてワクワクする。





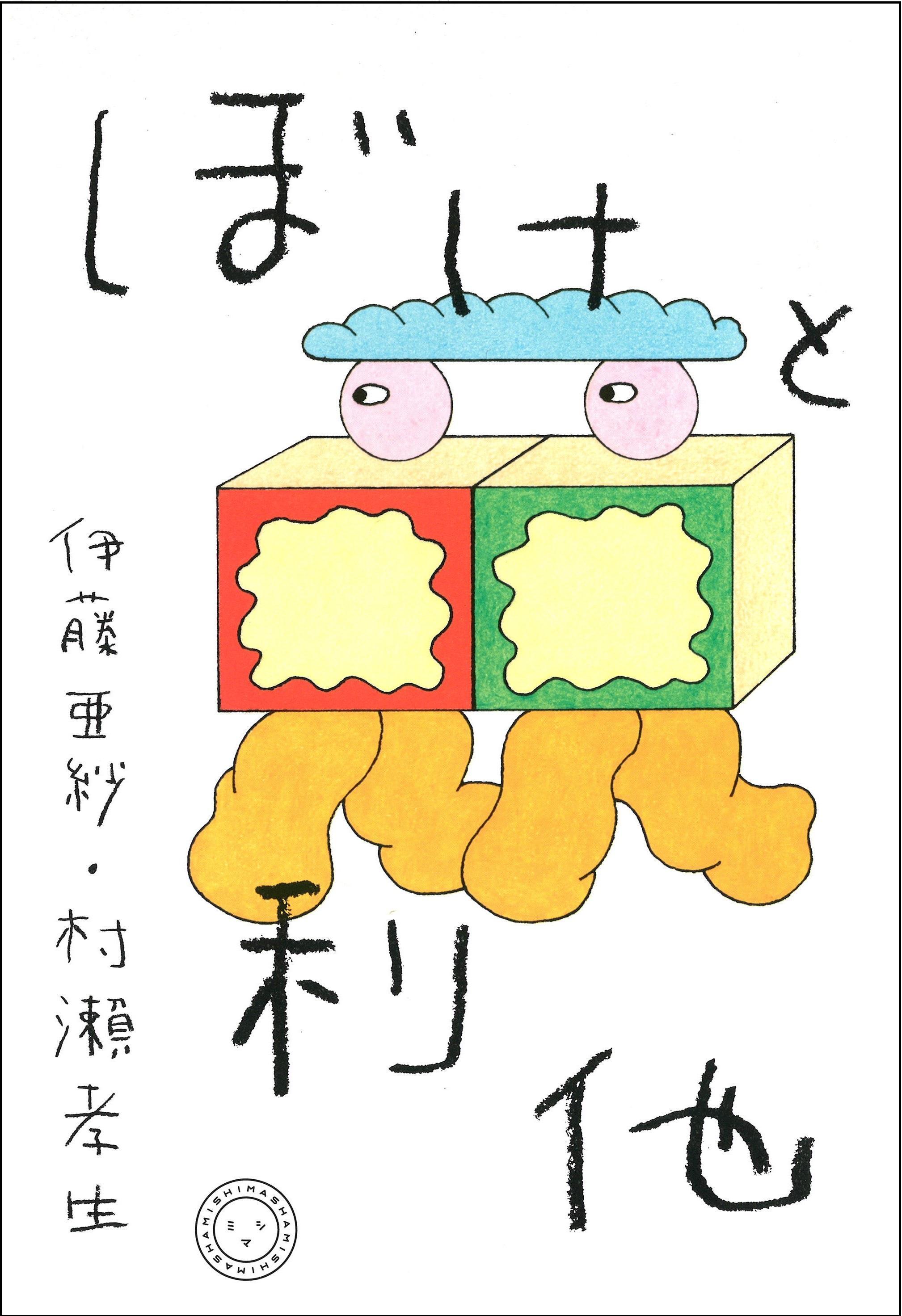




-thumb-800xauto-15803.jpg)
