第22回
35歳大学院生、早大野球部で研究する
2025.08.19更新
毎日5試合野球観戦する日々を過ごしています。朝8時から高校野球を4試合。夜はプロ野球。一日12時間以上野球を観ているのですが、飽きることはありません。自分でもなぜここまで野球が好きなのか、不思議なくらいです。ただ、昔とは見る角度が変わってきたなというのは自分でも感じています。大学院に進学する前は、いち野球ファンとして、試合展開や実況で紹介される選手の背景に感動していましたが、今は「この投手は胸郭の動きがよくなさそうだな」とか、「この選手は腰が痛いのかな?」と、選手の身体の使い方に目がいくようになりました。これも、大学院で野球選手の障害・予防について学んだからです。今回は修士論文執筆に向けての研究、そしてエビデンスが叶えてくれた夢についてお話しします。
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科の2年制修士課程では、修了するにあたり、30単位を取得する必要があります。1年生の間にすべて取り終え、2年生は修士論文執筆に向けた研究に集中するというのが、王道です。研究室を跨いで、たくさんの同期が助けてくれたおかげで、なんとか1年で30単位を取り終え、1年目の春休みからいよいよ研究を本格スタートしました。
修士論文のテーマは "ピラティスベースのモーターコントロールエクササイズ介入による野球選手の骨盤前/後傾可動性および腰部障害へ与える影響" 。こうやって振り返ると、なんとも難しいタイトルになったなぁと思いますが、要は "野球選手の腰痛に対して、ピラティスは効果的か" ということです。先行研究では、非アスリートの腰痛に対して、約3か月間のピラティスなどのモーターコントロールエクササイズ(身体をコントロールするエクササイズ)介入は、効果が見られたというものが多くあります。それを日ごろ身体に負荷をかけている野球選手にも効果があるのか検証しようというものです。
介入研究になるので、ピラティスを実施してもらう前と後を比較する必要があります。今回の研究では大きく分けて3つの要素を比較しました。1つ目は、選手本人が感じている腰痛などの痛みの程度が、介入前後で変化するか。入学直後から、野球部の選手にはアンケートを週に1回回答してもらっており、腰痛などの障害の状況を把握していました。2つ目は、腰痛の発生因子になりうるハムストリングスや股関節などの柔軟性や可動性を計測し、それらが改善するか。そして3つ目は、整形外科医である金岡先生に介入前後で診察してもらい、腰痛の身体所見がどのように変化するかです。
アンケートに関しては、回答率を上げるのに苦労しました。高校の部活動とは違い、大学生は自主性に任されています。しかも、部員ではない大学院生の私からの依頼ということもあり、事前に研究説明会を実施しているものの、選手が十分に理解できないままアンケート調査を開始してしまっている部分もありました。とても優秀な敏腕マネジャーが毎日のように声をかけてくれたのですが、回答率は半分にも満たず・・・結果、回答率のいい選手の中で腰痛を訴えた選手に介入に参加してもらうことにしました。
アンケートでの躓きもあり、思ったような人数が集まらなかったのですが、10人以上いれば大丈夫とのことで、結果的に12人の選手が柔軟性・可動性の計測と、金岡先生の診察を受けてくれることになりました。
次に立ちはだかったのは、そう、コロナです。私が入学した2021年はまだまだコロナ渦。大学院の授業もオンラインで行われるものも多く、働きながら学ぶのには大変助かったのですが、対面での研究には大きな影響が出ました。本来なら、2年目の4月までにすべての計測と3か月間の介入を終えるスケジュールで、あとは解析と執筆に取り組む予定だったのですが、介入前の計測を予定していた時期に学内でコロナ罹患者が多く出たということで、計測できなくなってしまいました。介入もうまくいくか不安だったため、結局何もできずに終わってしまうのではないかという不安にも襲われました。
しかし、こればかりはどうしようもありません。研究デザインをもう一度考えたり、介入するピラティスのメニューを考えたりする時間にあて、計測できるようになったらうまくいくように準備するのみでした。この時の研究だけに言えることではないのですが、基本的に心配症で、自信のないお仕事はとにかく準備を大切にします。準備をいくらしても不安なのですが、「そんなことまで調べなくていいでしょ?」ということまで調べないと、落ち着かないタイプです。少し慣れがあるお仕事より、このような自信がないくらいのお仕事の方がうまくいくことが多いです。慣れがあっても同じくらい準備しなさいと、書きながら自分に突っ込んでおきます(笑)。
話はそれましたが、3月に計測ができることになり、コロナがもたらしてくれた準備期間のおかげで、スムーズに介入前の計測ができました。可動域だけでなく、打撃動作や投球動作の変化も知りたかったため、計測は全て3次元の動作解析装置を使用しました。身体の各関節に反射マーカーを付け、8台のカメラで取り囲み撮影し、各関節の可動域や投球・打撃動作を計測しました。少しでもマーカーが読み取りにくかったりすると正しく解析ができないため、選手一人当たり約2時間かかり、貴重な練習時間に抜けてきてもらうには、大きな負担をかけました。
そしていよいよ介入です。今回の研究では週に1回約1時間のピラティスを実施しました。が、これもまたコロナに翻弄されるのです。本来なら12回すべてを対面で実施すべきなのですが、大切なリーグ戦期間中の介入であり、なおかつまだ罹患者が多い世の中の状況でしたので、介入はほとんどがオンラインでの実施になりました。幸い参加者が多くなかったことから、オンラインでも一人一人の動きを細かく確認することができました。指定したレッスンに参加できない選手には、参加率を下げないためにフォローレッスンもしました。21時から実施した日もありました。それに関しては、オンラインだからこそ臨機応変に対応できたことでもありました。
無事に3か月の介入を終えて、最後の計測もスムーズに終わりました。ちなみに、3次元の動作解析装置は組み立てからなかなか大変で、毎回研究室のメンバー5人ほどにお手伝いいただいていました。仕事と違って時給は発生しないので、このように時間をかけて手伝ってくれる仲間や被験者がいてこそ、エビデンスが残っていくのだなと身をもって感じました。協力していただいたみなさんに感謝です。
中でも間に入ってくれたマネジャーには感謝してもしきれません。アンケートも含めると、長期にわたる研究で、最も大変だったのは、野球部のスケジュールと選手の授業のスケジュール、介入のタイミング、これらをすべて合わせること。大阪の進学校出身の彼は、19歳にして「ご教示ください」「恐れ入りますが」など、完璧なビジネス用語を使いこなしていました。私が学生のころには、絶対そのような日本語を使えなかったと思います。彼から引き継いでくれた後輩マネジャーも同じように、学生とは思えないほどしっかりしており、早稲田大学野球部ではこのようなこともしっかりご指導されているのだなと勉強になりました。これも、大学院に通わなければ知りえなかったことです。卒業前にはみんなで一緒に野球談議に花を咲かせて、おいしいお酒もいただき、すっかり野球友達になりました。
さて、研究の結果をお伝えしていませんでしたが、実験前後に身体所見を行った結果、エクササイズによって腰痛がほとんど解消されたことに加え、多くの部位で実験前に比べて可動域が広がりました。研究を通じて、ピラティスが野球選手の腰痛に一定の効果があることを確認することができました。このエビデンスが、私がピラティスの道に進んだ時に掲げた夢を叶えてくれることになります。
確か電話だったと思います。阪神タイガースのリポーターを務めていた時にお世話になっていた球団スタッフの方からでした。「研究の成果はどうやった?」。大学院進学を報告した時から、私の研究に興味を持ってくださっていました。早稲田大学野球部の腰痛有訴者に対して、一定の効果があったことを伝えました。その流れだったか、後日だったかは忘れてしまいましたが、「うちにも、指導に来てもらえへんかな?」という言葉をいただきました。私が? 阪神タイガースの選手にピラティス指導?
ピラティストレーナーとして目標にしていた、阪神タイガースの選手へレッスンする機会をいただけることになったのです。まるで孫の帰省? 次回は初めての阪神タイガースキャンプについて、お話しします。


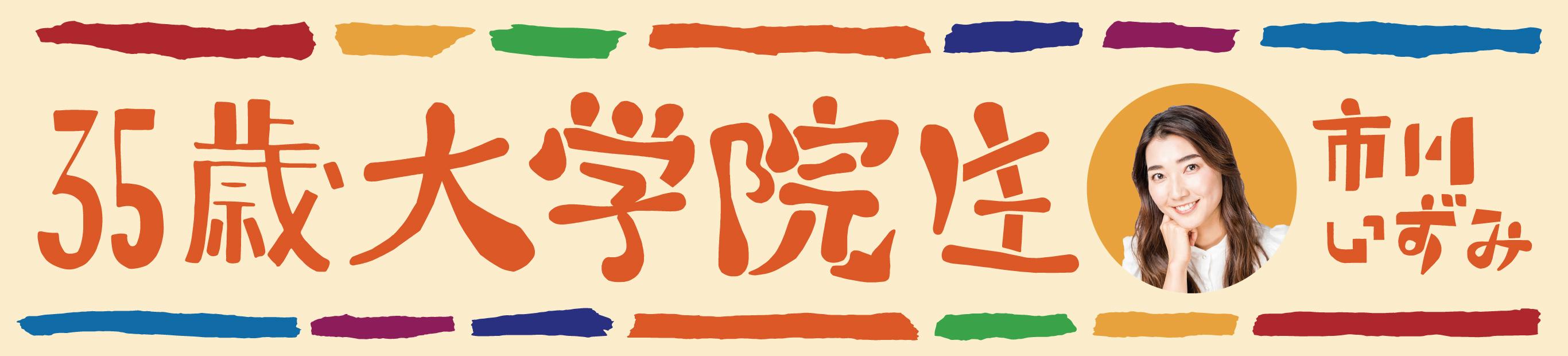



-thumb-800xauto-15803.jpg)


