第25回
ワ―ママに正解はない
2025.11.19更新
「よいお年を!」。気づけば今年も残すところ50日を切り、このような挨拶も耳にするようになりました。つい先日まで猛暑にさらされていたと思っていましたが、秋はどこへやら消えてしまい、冬に突入。インフルエンザが猛威を振るい、小中学校では学年閉鎖になっているところもあるようです。息子も鼻水を垂らしていたりするので「いつ発熱するか・・・」とヒヤヒヤしながら日々を過ごしています。そう、ワ―ママの一番のストレスは、日々のオペレーションに常に頭を悩ませていることなのです。
産前から仕事復帰は早くしたいと思っていました。前回のコラムでもお伝えしましたが、これまで積み上げてきたものが全てなくなってしまう、ゼロどころかマイナスになってしまうことが怖く、焦りの気持ちが大きかったことが一番の理由です。フリーランスですから、戻る席が確保されているわけではありません。そうでなくても、椅子取りゲームの世界。長い間、座っていた椅子を空席にするわけにはいきません。大きなお腹を抱えながら、保活(保育園探し)をしました。
この時の条件は、生後3か月ごろから入園可能で、なおかつ空きがある園。「生後3か月で、もう保育園に預けるの?」「かわいそう」。嫌というほど、色々な方からこのように言われました。「私、犯罪でもしたのかな?」産後の寝不足状態に、ホルモンバランスも不安定な中、夫婦で決めたことに対してこのように言われることは、そのくらい堪えました。"保育園 早く預ける かわいそう"。何度もこのワードで検索し、インターネット上に溢れる様々な情報を見ては、藁をもすがる思いで肯定派の意見を探しました。同じように、産後復職している友人に話を聞かせてもらったことも。自分の中でも、早くから預けることに、きっと罪悪感があったからだと思います。それなのにどうして預けるの? という声も聞こえてきそうですが、自分のキャリアのためだけがそうさせたわけではありません。
もう一つの理由は、経済面です。会社員だと、産休育休期間中も手当てがあります。フルタイム勤務と同じようにとはいかないかもしれませんが、働いていない期間も収入があります。しかし、フリーランスの場合は、そうではありません。手当、補助は一切なく、"働かない=収入ゼロ"。むしろ、健康保険や年金などは支払う必要があるので、休めば休むほど赤字なのです(出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料の免除はあります)。扶養に入れば? という声も続けて聞こえてきそうですが、育児や家庭内のルールに関しては、その人その家庭によって考えは様々だと思っています。私の場合、35歳まで仕事に没頭してきたので、自分にかかるお金、例えばスマートホン代や美容院代、コスメ代などは自分の収入から出さないと、夫のお財布からは使いにくいと思ってしまいます。また、自分が働くことで対価を得ることに充実感を覚えるタイプなので、自分自身の収入がピタッと途絶えることに妊娠期間中生きづらさを感じていました。
主にこのような理由から、早期復職を目指して保活していたわけです。ちなみに、これからもし保活をするという方がいらっしゃったら、必ず見学に行くことをおすすめします。当初は家から近い園を希望しようと思っていたのですが、見学に行くと、なんとなーくどんよりとした空気が漂っていました。4歳児クラスを見学した際には、音楽に合わせて手を叩く先生の目が笑っていなくて、「ちょっと、ここは・・・」となりました。そのあとに、今お世話になっている園に見学に行くと、先生たちみんなが明るく挨拶をして下さり、とても雰囲気が良かったので、自宅からは少し遠いのですがここに決めました。結局、公園で会うママたちと世間話をしていると、最初に希望していた園は地元ですごく評判が悪いことが判明。長時間お世話になる場所なので、自分の目で見て肌で感じるのはすごく大切だなと思います。
無事に保育園も決まり、生後3か月を少し過ぎたあたりから慣らし保育が始まりました。あれだけ社会復帰を望んでいたにもかかわらず、いざ息子を預けるとなると、寂しくて寂しくて。仕事もしたい、でも乳児期の息子と一緒にいられるのも一瞬のこと。初日の夜は、何が正解かわからないと泣きました。しかし、実家も近くない、知り合いも全くいない場所で育児をしていると、誰とも会話せずに一日が終わることもあり、毎日が孤独。産前の生活とのギャップが大きすぎて、この生活が長く続くと病んでしまいそうな状態ではありました。綾野剛さんが主演のコウノドリというドラマをご覧になったことはありますか? 妊娠期から産後までに起こりうるさまざまなトラブルを描いている医療ドラマなのですが、第3話では、高橋メアリージュンさん演じるキャリアウーマンが、産後鬱状態に。とても他人ごとではありませんでした。
実際、保育園に預け始めてからも"洗礼"と言われる発熱などで思うように仕事はできず。ピラティスの新規のお客様や、アナウンサーとして代わりのきかない仕事などは、「当日息子の発熱でキャンセルする可能性がある・・・その方が信頼を失うのではないか」と、提案してもらっても、受けることができませんでした。そうしていると、知らないうちにルールが変わり、仕事の進め方も、人間関係も少し違うように見えてきました。みんなは当たり前のように共有している話題に、ついていけないことが増えました。最初は「ブランクだから仕方ない」と思っていましたが、徐々にコミュニケーションが減り、「もう必要ないのでは?」と感じるようになりました。誰かに何かをされたわけでもないのですが、"置いてけぼりになった"という感覚です。余計に孤独を感じ、車を運転しながら、自然と涙が止まらなくなった時もありました。今思えば、これも産後鬱の兆候だったかもしれません。
高市早苗総理大臣になり、女性が活躍できる社会を目指していく風潮にあります。助成金や制度の整備、柔軟な働き方の推進も大切なことですが、私が身をもって感じたのは、それ以上に「人を気にかけるフォロー」が必要だということです。たとえば、産休・育休中にちょっとした業務の変化や近況を伝えてもらったり、「おかえり」と声をかけてもらえたりするだけで、不安は軽くなりますし、「仲間なんだな」と、感じられます。大げさなサポートは求めておらず、"つながりを切らさない"ことが何よりの支えになると感じました。もしこれから先、私が誰かと一緒に仕事をすることになったときは、孤独にしないように心配りをしたいなと思っています。
こんな思いまでして、それでも仕事したいんですか? と、突っ込まれそうですね(笑)。仕事人間にとっては、仕事をすることが、育児の息抜き。1時間でも仕事ができると、とてもリフレッシュできて、帰宅後の息子と全力で向き合うことができるんです。今は、在宅で出来るオンラインレッスンや、単発のイベント司会をメインにし、そのほかの時間はトレーナーとしての勉強や、研究に充てています。3歳になるまでは極力9時登園の16時降園にしたいと思っていて、その時間外はなるべく働かないようにしていたり、土日に司会業が入れば、平日はお休みさせたりして、家族の予定を優先して過ごしています。もちろん、仕事をお断りするとその分収入も減るのですが、息子の笑顔をみると、今はそれでいいと思えるようになりました。
ワ―ママとして、キャリアを再スタートさせたときは、「あの家庭はうまくやっているなぁ」と、他の家庭と比較したり、インターネット上に溢れる働き方などを調べたり、それらを真似してみようとしたり。"正解"を探し求めていたように思います。しかし、1年以上が経ち、"正解"なんてものはないんだなと気づきました。
働き方も、家事の分担も、子どもの性格も、サポート環境も、家庭ごとにまったく違う。だからこそ、他の家庭のやり方をそのまま自分たちに当てはめる必要なんてないんですね。話し合って、「これが我が家のやり方!」と決めたことこそが、正解。その選択で家族が笑っていられるなら、それ以上の模範解答はないと思います。すべてに120%の全力投球をしてしまう性格なので、当初は、「もっとこうしなきゃ」「ちゃんとやらなきゃ」と肩に力が入っていました。今ならその時の自分に、「周りと比べて焦る必要はないし、誰かのルールに自分を合わせなくていい」と、声をかけてあげたいです。家庭の幸せの形は、外からは見えないところにこそ宿っているのだと思います。
現在も仕事の仕方や保育園の送迎のオペレーションなど、試行錯誤を繰り返しています。その中で強く感じたことは、仕事をいただく受け身な状態ではなく、自分で仕事を生み出せるといいのではないか、ということです。そうすることで、家族を優先しながら、理想の働き方ができるのではないかと考えています。その上で必要なのが、自身のスキルアップ。実は、産後すぐから新たな資格取得のために、勉強していることがあります。
次回は、その挑戦について、そして今後ワーママとして働き続けるにあたって考えているビジョンについてお話します。


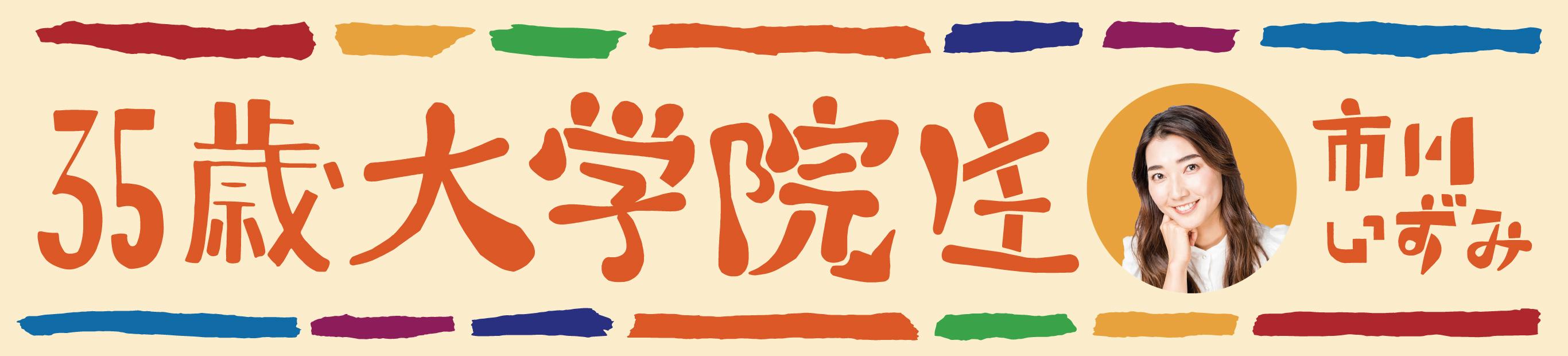





-thumb-800xauto-15803.jpg)
