第28回
直腸の「ごっくん」
2025.08.27更新
母の食欲回復について、あれこれ考えている。考えはさらに拡張し、もはや妄想の域に達している。その話しを20年ともに働いてきた戦友のような同僚に話したら「お母さんと一体になっていますね」と半ばあきれたように言われた。素直に喜べない複雑な今日この頃である。
これまで「母の食欲回復は、僕が母の癖を克服したからだ」と考えていた。でもその言い方は、まるで僕の努力が母の癖に勝ったような口調である。「癖の克服」という表現に僕の自意識が丸出しだ。母もまた食事介助されることで、僕の癖を受け止めてきたのだった。
実相はというと、母と僕の「息が合ってきた」のだと思う。毎日、繰り返される食事介助。母の間合いと僕の間合い。全く違う二つの間合い。食事という行為を媒介に、お互いの間合いを、母は母なりに、僕は僕なりに受け止め合った。受け止め合いの繰り返しによって生じた調べに二人が乗っている。つまり、母と僕は調子に乗っているのである。
ある朝の摘便に、ささやかな発見をした。それは「ごっくん」の存在である。いつものように、僕のお母さん指を母の御門に差し込む。緊張しきった括約筋。彼の主たる役割は「漏らすまじ」にあると思う。その任務にひたむきな彼を僕のお母さん指が労う。
「今は、その緊張を解いていいよ。お疲れ様」
すると、4種類ある結腸に時間差のある波が生じる。スタジアムに陣取る観客たちが起こす応援のウエーブのように。最高潮に達した波が直腸へと達した時、固く閉じられた括約筋が嘘のように伸び始める。その感触には、イソギンチャクの口盤が開き繊毛がゆらゆらと漂うような優雅な風情がある。
括約筋が大いに解れ、母の御門が最大限の開帳を成し遂げた直後であった。直腸が「ごっくん」をしたのである。この「ごっくん」は、僕にも身に覚えがある。結腸に溜まったうんこが調子よくお出ましになる時が稀にあるが、あと少しで綺麗な一本を産み落とすというときに、下部直腸が「ごっくん」をしてしまい、肛門が天晴な1本を分断するギロチンと化す。あの少し残念な気持ちにさせる「ごっくん」だ。
「ごっくん」の後は、そっと見守らなければならない。なぜなら、括約筋が巾着袋を閉める紐のように頑なになる時間なのだ。あれは「漏らすまじ」のミッションに取り組んでいる訳ではない。閉じる、開く、の繰り返し運動を継続するために必要な「息継ぎ」なのだ。
息を継いでいる最中に、お母さん指を差し込んではいけない。マッサージをしては、なおいけない。腸にも必要不可欠な間合いがあって、それを無視すると括約筋はますます頑なになる。それは、僕の一方的な食事介助に抗うときに垣間見せる、蛸のように尖らせた母の口を連想させた。
食べ物を咀嚼し飲み込む時「ごっくん」が生じることは誰もが体験している。食べ物を消化器官に迎え入れる時と同じように、うんことなった食べ物を送りだす時にも出口で「ごっくん」が生じているのであった。
喉が行う「ごっくん」。直腸が行う「ごっくん」。両者に共通しているのは、口も肛門もしっかりと閉ざされることだ。食事介助も摘便も頑なに閉じる時間を尊重しなければならない。閉じるという停止した状態に、神妙になるのが「待ち」である。待っていると見えてくる。口と肛門にも「今日の間合い」のあることが。
口と肛門はひとつの管の入り口と出口だ。食べる時の「ごっくん」と、出る時の「ごっくん」。僕はその両方の間合いを感じている。このふたつの間合いを実感していることと、母の食事がスムースになっていることは無関係ではない気がしてきた。
僕は毎週2~4回ほど母に摘便をする。括約筋のマッサージから始まって、腸のウエーブを感じ、直腸の運動を指で捉える。そこには、ある種の周期や法則のあることに気づく。
けれども、摘便がスムースに行かない時は決まって、いま、ここに於いてしか生じない「ごっくん」を感じることなく、手順化した法則に囚われている。その囚われの轍に嵌ってしまうのは、過去に得た成功体験を再現しようとする僕の執着によるものだ。そこには母も直腸も存在していない。
面白いことに食事介助や敵便をすればするほど、母の消化器官に向き合っている、というよりは、僕の今日の気持ちに向き合うことになってゆく。開かない口と肛門は僕の心を写す鏡のようだ。
このような状況になっていくのは、きっと、母の自意識が縮小している証なのだろう。2~3年前は、介護は苦しさのピークだった。互いの自意識がぶつかり合っていたのだと思う。母の自意識が薄くなることで、僕の自意識が交流先を見失っている。そこには、ひとつの寂しさがあるが、これまで得たことのない安らぎを母との関係において見出してもいる。
母の体にある間合いに、僕の体の間合いを合わせることに集中することが、僕の自意識の発動をさらに抑えているのだと思う。
互いの自意識が希薄になった先に、新しい親子関係が生じるような気がしている。それが、どんな世界なのかは、母の老いに素直に導かれるより踏み込めないと感じる今日この頃。





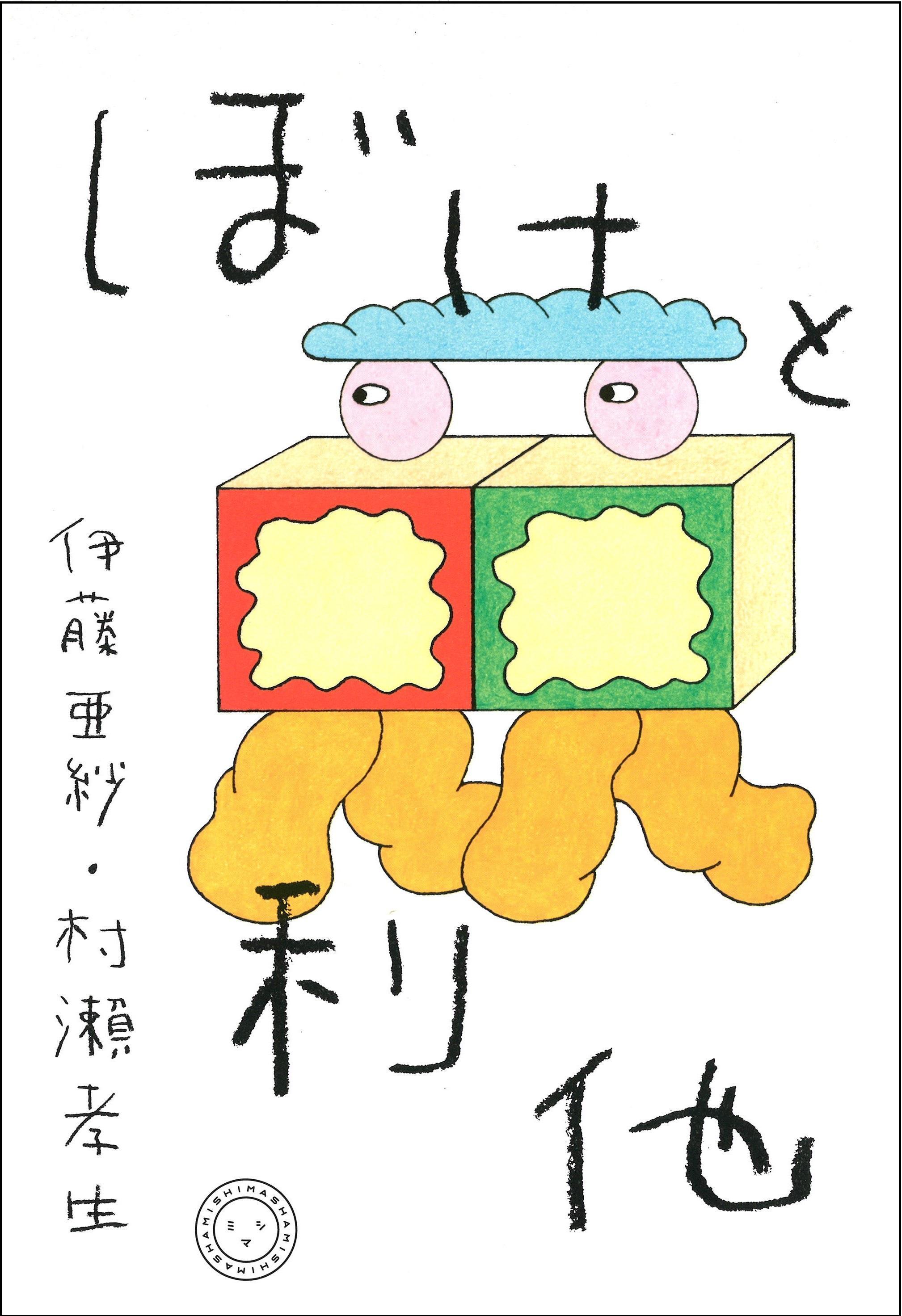


-thumb-800xauto-15803.jpg)


