第30回
「いのち」に死はない
2025.10.30更新
僕の職場は宅老所よりあいという。マンションの2階に住まう一人の婆様から始まった。身寄りがなく、天涯孤独と言ってもよい人だった。
食べ物の腐臭やお漏らしによる排泄臭は住民の悩みの種だった。強烈な臭いは1階のエントラスにまで漏れ出るほど。もっと怖いのは小火である。本人はもとよりマンション住民の命すら脅かしかねない事態に関係者は老人ホームへの入居を勧めた。
「見も知らん人間が、いきなりやって来て、老人ホームに入れとは何事か。わたくしは、ここで野垂れ死ぬ覚悟で生きとる。いたらん、こったい」
施設入居の説得に赴いた介護職に、婆様はそう啖呵を切った。1990年のことである。
こういうのを明治女の気骨と呼ぶのかもしれない。婆様の野垂れ死にを見守りたいという情動に駆られた女性3人が巻き込まれる形で宅老所よりあいが始まるのであった。
婆様は98歳で死んだ。
僕は死に際に立ち会うことができた。
「ビールが好きやったもんね」
飲み食べをしなくなった婆様の口をビールを浸した綿花で潤す。
あの世からのお迎えを婆様と共に待っていると、ぐらりと建物が揺れた。
「いやぁ~ 凄いなぁ~ 婆様が地震を招いた!」と誰かが声を上げた。すると、「凄い!凄い!」「さすが婆様」「一筋通った、頑固者やったもんなぁ~」と、それぞれの声が続く。
まだ死んでいない婆様を囲み、一人一人が体験した彼女の武勇伝をみんなで語り尽す夜。
なぜ、人は看取るのだろうか。息を引き取る瞬間に立ち会おうとするのだろうか。未だに、よくわからない。
人はみな生理的に同じ経過を辿って死ぬ。けれども、その死を取り囲む環境はひとり、ひとり違う。その違いに物語のようなものが生まれる。それは、とても真面目で滑稽だ。そんな時間に触れると、看取れてよかった、今際の際に立ち会えてよかったと素直に感じる。
その一方で、誰からも看取られず、独りで死ぬことは寂しいことなのだろうか、という疑問が浮かぶ。
職場に棲み付いていた猫、チャチャはパソコンのキーボードを打つ僕の傍で気持ちよさげに寝っ転がることが習慣だった。時折、頭を撫でてやると両手足をピ~ンと伸ばして、「もっと」「もっと」と催促する。
ある日のこと、頭や首筋にイボのようなものが手に触れた。イボはあっというまに全身に広がり、みるみるうちに痩せこけてしまった。獣医師から不治の病であることが告げられた。
捨て子だったチャチャは常に人と共に生きてきた。死ぬときも僕らから見守られて逝くんじゃないかと思った。婆様や爺様たちと同じように。
骨と皮になりつつあるチャチャの体を撫でる。最初は気持ちよさそうな素振りを見せるのだが、ずっと撫で続けていると、「もう、いいや」といった顔になる。「放って置いてくれませんか」といった雰囲気を醸し出す。結局、チャチャは死に際を見せなかった。あれは、ひとつの野垂れ死にかもしれない。
ふとした時に、チャチャのことを思い出す。独りであの世に逝くことも「ありだな」と考えるようになった。むしろ、その気持ちは強くなりつつある。
今思えば、宅老所よりあいが誕生する切っ掛けを創った婆様が放った「野垂れ死ぬ」も関係者が考えるほどの悲壮感が当人にはなかったのかもしれない。僕らは婆様を野垂れ死にさせなかった。婆様と共に創ってきた人間関係の下で息を引き取り、その瞬間を目の当たりにした。最期まで生きるその姿に「いのち」そのものを見た。「いのち」に死などないのである。
地域社会では孤独死が問題となっている。自治会や民生員さんも、その問題に心を砕いている。その取り組みに関わる度に、「孤立死はできるだけ防ぎたいけど、孤独死は防ぐ対象ではないんじゃないでしょうか」と発言してきた。
「孤立死」はその存在を誰からも知られず一人ぼっちで死ぬこと。「孤独死」はあの世に逝くタイミングがたまたま独りだっただけである。
いずれにしても「孤立死」であれ「孤独死」であれ、自分の担当区域から、そのような死を出してしまった民生委員さんや自治会の人たちは、なんとも言えない罪悪感や、うしろめたさを感じてしまう。たとえ天寿を全うしたとしても、発見が遅れたときに接する変わり果てた姿に非業を見るのだ。
そのこともあってか、いかに「孤立死・孤独死」を我が街から出さずに済むかに精を出す。見守りや人との繋がりを強化することに努める。しかし、その真面目さは時に排除を生む。
単身者世帯が中心になりつつある地域社会にとって「孤独死」を出さないことは至難の業である。よって、その可能性のある人に対して早期の施設入所を勧めがちになる。哀しいかな頑なに自宅で暮らすことを主張する独居老人は「ちょっと困った人」になりかねない。
ぼけや認知症状を抱えたご老体もまた、「孤独死・孤立死」に似た見守りの対象になりやすい。徘徊に伴う行方不明や遺体での発見にも非業を見る。そのような死を出さないという誠実であるはずの見守りが監視へと変容することすらある。実現不可な取り組みを担わされると予防的な排除に反転する。
思うに、非業と感じられる死を避けるために奔走した人たちだからこそ、その死にざまにたいする哀しみが深いのだ。
「あの人は大丈夫だろうか?」「今、何をしているかな?」「明日の茶話会に声をかけてみようかな」
日頃から気にかけ、心配し続けていることで、すでにケアは達成されている。その後に生じる結果がどのようになろうとも、そのことを審判できる人は誰もいないはず。だから、自罰的な反省は不要だと思う。自分に課した罰が、明日には他者への罰へとなるだけだから。
見守った者も、見守られた者も、見守りの成果を求めることはできない。
人間社会において、独りで死ぬことや徘徊にともなう死が、なぜ「非業」となるのだろうか。きっと、僕たちの社会が閉じてしまったからだと思う。人間だけで自己完結しているのだ。都会はその象徴である。
「爺捨て山」と称した開拓を島で行い始めたのは、人間だけで自己完結する閉塞した社会が生み出す息苦しさから抜け出すためでもあった。自然を外界にしてしまい、人間たちだけで閉じこもった社会であるからこそ、人は人に帰属できなくなる。自然界にある人間以外の生き物、そこで起きる事象に触れることで、人は人に属し類としての存在であることを知るのではないだろうか。その関係性から生じる叡智なるものがあると思える。
島での自然に触れるたびに、閉じた人間社会の中で死ぬことのほうが「非業」であると感じるようになった。いつ、どこで、何をしていても、大地は審判することなく僕の死を迎え入れる。他の生き物たちは、集って僕の躯を喰らう。そして、土へと還してくれる。僕は大地の一部となり、新しい「いのち」の苗床となる。このような寿ぎに包摂されたい。
爺捨て山の開拓とは大地への信頼を僕自身が取り戻すこと。もし僕が徘徊の果てに行方不明となり、力尽きて死んでしまっても、ひとりぼっちで死ぬわけじゃない。人間以外の生き物が看取ってくれる。そうして、大きな「いのち」の営みへと一体になる。そこに死はない。
もし、僕の身に起こった事を非業と感じ、悲しんでいる人がいたとするなら、「僕は寿ぎの世界にいるよ」と伝えることができる気がしている。





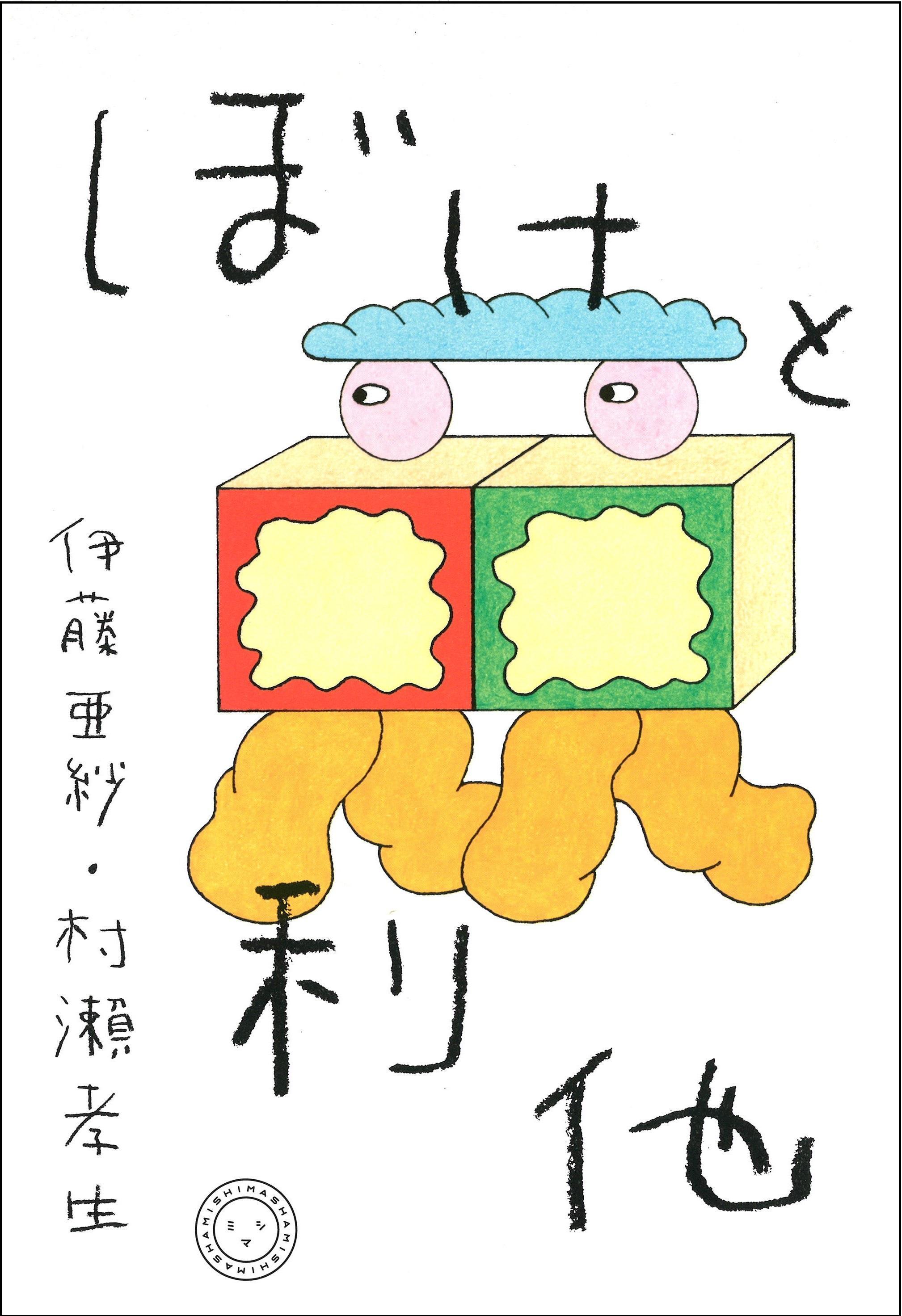


-thumb-800xauto-15803.jpg)


