第29回
自然の循環への帰還
2025.09.26更新
先日、東京へ行った。品川駅高輪口は昭和の匂いが、わずかに残っている。駅の向かいには昔ながらの洋食屋さんがあって、お昼前にはハンバーグ目当てらしき客が列を作る。同じ並びには、くたびれ気味のラーメン店。その隣奥には、何を生業としているのかよく分からない怪しげな事務所が目立たないように構えている。
駅前の一等地であるにも関わらず、かつてあった建物の気配を残した更地が朽ちかけている。高度成長期を支えたであろう老舗のホテルには、リニューアルを繰り返しながらも、過去の栄華を払拭しきれない寂しさがあった。そういった雰囲気が九州の片田舎から上京した僕を少し安堵させるのだ。
仕事の打ち合わせは高輪口の反対にある港南口の居酒屋だった。スマホのナビを頼りに待ち合わせの場所へ急ぐことにした。駅の構内を横断すれば、すぐのはずなのに、わざわざ迂回せよと示す。所要時間は10分近い。(そんな馬鹿な)。スマホのナビに頼らなくても、どこにでも行けた自分はどこに行ったのだろう。
とりあえず、高輪口の階段を駆け上る。やがて、ドームのようなトンネルにさしかった。ここに来ると変な空間感覚に陥る。おそらく、60年の人生で初めてお目にかかった空間なのだ。その戸惑いが僕の時間を停止させるようで、まだ体験したことのない無重力を感じてしまう。
そのトンネルドームを抜けて港南口にたどり着く。階下へ降りなくてもよいように、駅から周辺のビルを直接渡っていけるぺデストリアンデッキに佇んだ。スマホのナビは、すぐ傍にあるはずの居酒屋を一度通り過ぎた後、Uターンして戻ってくるルートを教えた。(なんじゃ、僕以上に混乱し取るやないか)。
途方に暮れて空を見た。そして、気がついた。天にむけて聳え立つビル群。首関節の可動域を全開して仰ぎ見る。電球色の優しい灯りがキラキラしながら、全面ガラス張りの建物に反射しあっている。夜ということもあって、ちょっと幻想的だった。
繁華街にみるような俗物的な看板はない。そのスマートな無機質さと、ビルの巨大さと、光が反射し合う空間を、ぺデストリアンデッキが空中でつないでいる。極めて合理的に。(ここは、宇宙戦艦のドッグか、何かですか)。
打合せを終えて、再びあの空間を歩く。キラキラと輝くお洒落な光を見ながらビルの屋上へと目を這わせる。凄いな。綺麗だな。造形が美しいな。圧倒されるな。これは、当たり前じゃないな。奇跡だな。
人間という生き物は奇跡を起こしたんだな。こんな奇跡を起こしちゃったんだから、滅亡も近いな。そう思った。ここには人間しかいない。緑の植栽もあるけれど、それは、計算された飾りでしかない。目に映らない生き物たちが、したたかに存在しているのだとは思うけれど、あからさまに人間しか感じられない。天高く、地下深く、直線と水平を基調とする巨大空間は、自然から隔絶しないと作れないのだ。
残念ながら、同じ人間でもヨボヨボでヨレヨレのご老体は生息できないだろう。社会は多様性を叫ぶけど、どんな多様性? ここはみんなが利用する駅界隈だろう? 老人の入り口に立つ僕でさえ(ここは無理)と思った。都会にはすべての人間を包摂できる普遍性はないのだと思う。
旧約聖書の「創世記」11章に登場する、バベルの塔が頭に浮かぶ。神様が人間の言葉を乱し、塔の建設を頓挫させた理由を僕なりに理解できた気がした。高い塔を作り上げ、神様に近づこうとした傲慢を罰したのではなく、自然の循環から外れ、他の生き物と共に協力し合うことをしなくなったことを嘆いているのではないか。非言語世界と共に創る社会を、神様を望んでいるのではないか。
僕は、とある島で「爺捨て山」を開拓している。最終的には、この地で野垂れ死んで土に還りたい。そのための開拓なのだ。農地にするのでもない。家を建てるのでもない。僕の躯が、この地に棲む生き物たちに喰われ、その者たちの命となり、糞となって、土になる。そんな場所を妄想を実践している。
躯が順調に分解されるには、多種多様な生き物たちで溢れる土地であることが大切なのだ。せっせと野糞をしているのも、そのためだ。決して性癖ではない。汚物処理システムがなくても、埋めるだけで悪臭すら立てず土になる。ウンコは汚物ではなく、菌や微生物、虫たちのご馳走なのだ。僕も死んでご馳走になる。それが、僕にとっての最後の晩餐である。
わずか20年ほどではあるが、この地の植生の移り変わりを目にしてきた。初めてここに来たときは、笹竹が一面を占有していた。花を咲かせ一斉に枯れた後、セイタカアワダチソウが独占した。並行して野バラが繫栄し、人はおろかイノシシの立ち入りをも阻んでいたのである。開拓を始めたときは、鎌と剪定鋏を片手に人力で切り拓くことができるのだろうか? と怖気づいてしまった。
それでも、こつこつと手を入れた。すると、春はハマダイコンが咲き誇るようなり、最近はレースフラワーも負けていない。夏から秋にかけてママコノシリヌグイが全体を覆う。サイズの小さくなったセイタカアワダチソウも量を減らしながらも居なくならない。秋がさしかかると、ムラサキツユクサが花を咲かせ始める。高層の植物たちがサイズを小さくしながら中層へと変化し、そのおかげで低層の植物に陽が届き増え始めた。ここでは、書ききれないほどの植物が蔓延っている。イノシシも進入しやすくなったのか、いたるところに大穴を掘って、地中に酸素を送り込む。
当然、虫たちも大いに賑わう。黒アゲハは、臭木の咲かせる花の蜜が好物なようだ。けれども、臭木は草原を森に還す先鋒のような植物で繁殖が凄まじい。放っておくとあっという間に雑木林にしてしまう。だから、蝶たちの蜜が無くならない程度に残している。オニヤンマに出くわすと心が躍る。「今年も会えたね」という気分になる。来年の夏に再会するには、彼らが幼少期に過ごす小川や沼が清浄でなければならない。ささやかに湧き出る水の周辺で沢蟹を見ると、その水がきれいであることを証明してくれているようで嬉しくなる。
ここにきて、なんとなく感じていることがある。
たとえ植物であっても、一世を風靡し独占状態になると、やがて一斉にいなくなる。そして、次に控える植物が独占する。きっと、単一の植物が永遠に栄え続けることはないのだ。地中にはいろんな種が眠っていて、発芽の機会を今か、今か、と待ち構えている。そして、人間が手を入れなければ、草原はゆっくりと森になっていく。
実は人間は、いろんな生き物と共に在ることが得意な動物ではなかろうか。過剰な生産に置いている軸足を分解へと移し、自然の循環に帰還できたなら、その能力を遺憾なく発揮できる気もするのだ。多種多様な植物が、順番待ちをしなくても、一緒にいることができるように調整する力があるように思う。





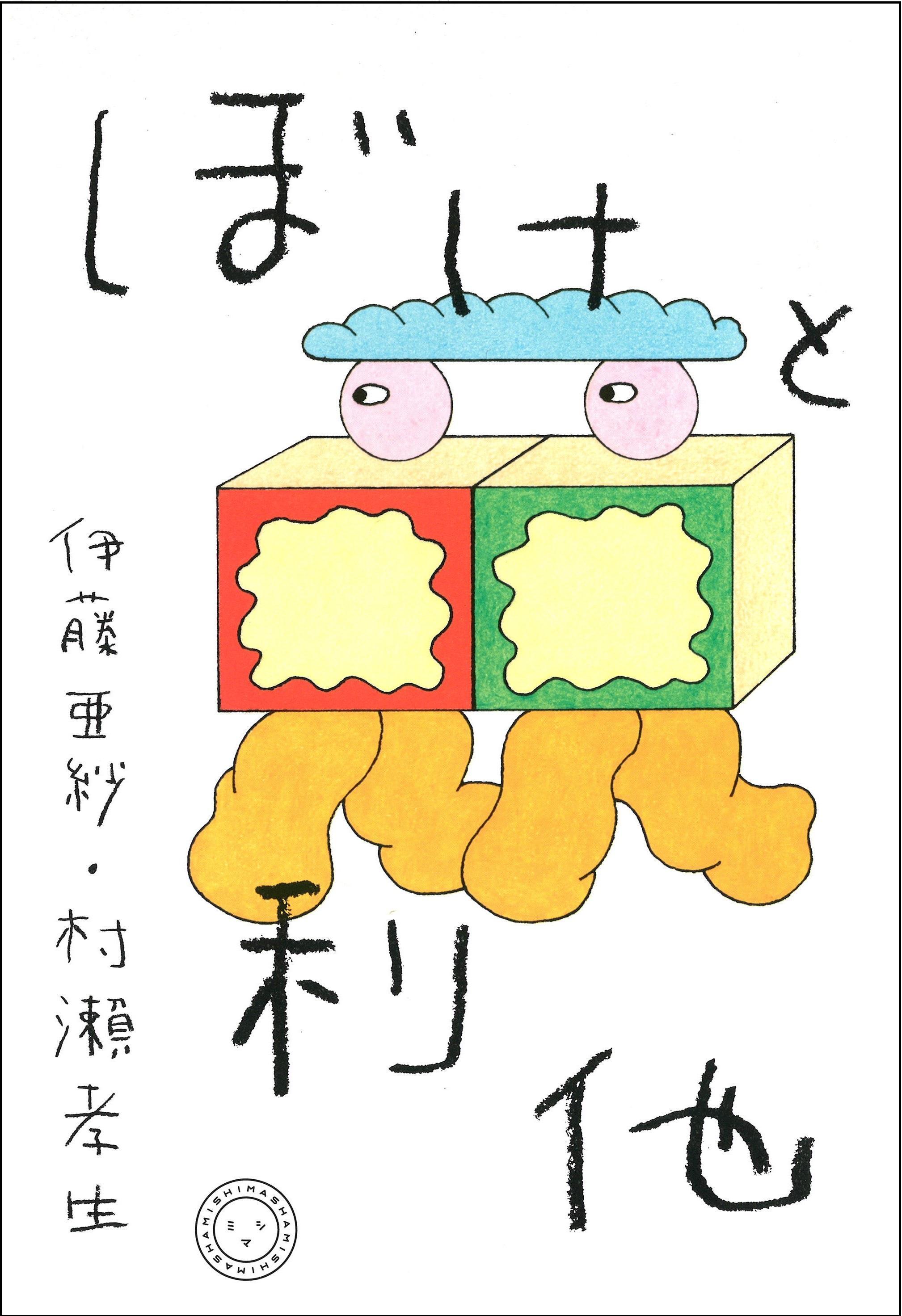




-thumb-800xauto-15803.jpg)
