第25回
さようならをやりつくす
2025.07.14更新
中央線のドアが、なんだか、なかなか閉まりませんでした。義母が電車に乗り込み、私はホームから義母を見送り、立ち去ろうとしたところだったのですが、さよなら〜と、お互いの手を振る行為がひと段落しても、なかなかドアが閉まりません。しかたがないのでもう一回手を振りはじめると、義母もまた手を振ってくれます。なにか不具合があったのか、いいかげん発車してほしい塩梅でもドアはやっぱりひらいたままで、顔は見えてるのにお互いの声が届かない距離にやや気まずくなり、私はいったんホーム上の横の柱に隠れました。柱の影で数秒やり過ごしたあと、もう一回ひょいっと顔を出しました。義母は、あらまだいたの、みたいな感じで笑いながらもう一回手をふってくれました。このターンで終わればいいな、と淡い期待を持ちながら、私もまたヒラヒラと手を振ります。しかし、どうしてもドアは閉まりません。もはやいったん立ち去るふりをして、柱の影に今度は数十秒隠れ、もう一回......と顔を出して手を振ると、義母は、今度は少しエッという顔をして、手を振るヒラヒラだけじゃなく、表情とジェスチャーをまじえ(あんたまだいたの、もういいわよ、行っていいのよ! またね〜!)というようなことを伝えてきて、私も、まあさすがにもういいか......と思い、義母にうなずきその場からいなくなりました。しかし、電車に乗って走り去る義母を見届けられなかったことでお別れが完遂できなかったな、という思いは残り、東京駅で新幹線に乗った、というLINEをもらったときに初めて、本当に義母は去ったんだな、と思いました。
小さい頃、友達にとてもしつこくバイバイをしていました。別れ際にふんぎりをつけるのがへたくそで、こちらのバイバイに相手がバイバイを返し、そのバイバイに対してさらにバイバイを返し、そうなると相手もまたバイバイをしてくれるので、さらにバイバイを...とやってはよくバイバイループにおちいり、相手がもうバイバイを諦めて背中を見せると勝ち誇ったような気持ちにすらなりました。
子どもの頃の別れ際には、いくつもの気持ちが詰まっていて、主なのは、今日遊んでたのしかった、別れるのが寂しい、また明日も遊ぼうね、の3つでした。さっきまでそばにいて同じ時間を過ごしていた2人がそれぞれの自宅の方向に遠ざかっていく、という実際の距離感に加え、それらの気持ちが加わると、なんかもう、だめでした。バイバイをし続けることでそれらの気持ちの複雑な噛み合いが通り過ぎるのを待ちました。
大人になっても、私はやっぱりずっとバイバイがしていたくて、知り合いとごはんを食べたあとは、じゃあ、と別れても何度も振り返ってしまいます。子どもの頃と違うのは、同じ会社とかでもない限り、明日も会える楽しみはないところです。だから、一層寂しい気持ちがしそうなものですが、私たちはそれぞれ一人の時間を満喫できるようにもなっていて、ごはんや打ち合わせのあとに道を歩きながら、もしくは電車にのりながら、さっきの時間を思い出します。あの瞬間おもしろかった、あれはおいしかった、あんなことを言うんじゃなかった、とつらつら振り返りながら、スマホをいじってSNSのタイムラインを見たりして、自分一人に戻っていくときの感じも、私はとても好きです。大人になってからのバイバイには、時間の共有が終わり、それぞれの生活に戻っていくときのスライド感みたいなものが詰まっています。寂しくはないのですが、それぞれの生活に戻っていく角度をより良いものに調整するために私はバイバイを入念におこなってしまいます。
ひるがえって、オンラインでの別れ際ではしつこくバイバイをすることが許されません。じゃあそろそろーと言われ、そうですねそろそろーと答え、ではではーとか言い合う頃には相手も自分も退出ボタンにマウスで照準を合わせ、プツンと共有を切断し、唐突に自分一人の時間に戻されます。なんでこんなにやりにくいんだろう、と常々感じますが、やっぱり、お互いが物理的に遠ざからないからだと思います。もうこの時間もおしまいですね、となったときに、画面にうつる自分の顔と相手の顔がだんだん遠くなっていけば、つまりお互いの顔がだんだん小さくなっていけば、共有している時間から一人になる時間への、スライド感が得られるんじゃないかと思います。お互いすごく奥行きのある部屋で打ち合わせをするようにして、別れ際は椅子をずーっとうしろに引いて画面から遠ざかれば、お別れっぽくなるんじゃないか、などと考えてみましたが、それだと退出ボタンが押せません。どうしてもオンラインの別れ際は苦手です。
誰かといてから一人になるとき、その境目にお別れはあります。子どもを保育園に送ったあと、編集者の人と打ち合わせをしたあと、昔からの友達とごはんを食べたあと、毎日の中で小さなお別れを、私もほかの人も、何回も何回も繰り返していると思います。子どものことは夕方にお迎えに行くけれど、編集者の人とはこの仕事が終わったらしばらく会わないかもしれないし、昔からの友達は、数ヶ月後にまた誘ってみようかな、それぞれの人とのお別れの深さはいろいろあります。一人になったかと思うとまたすぐ誰かと出会い直すから、ついおろそかになってしまうのですが、どんな小さなお別れのことも、なるべく堪能できたらよいです。そしてゆくゆくは自分が死ぬときに、さようならをやりつくしてきた経験を、発揮したいと思います。



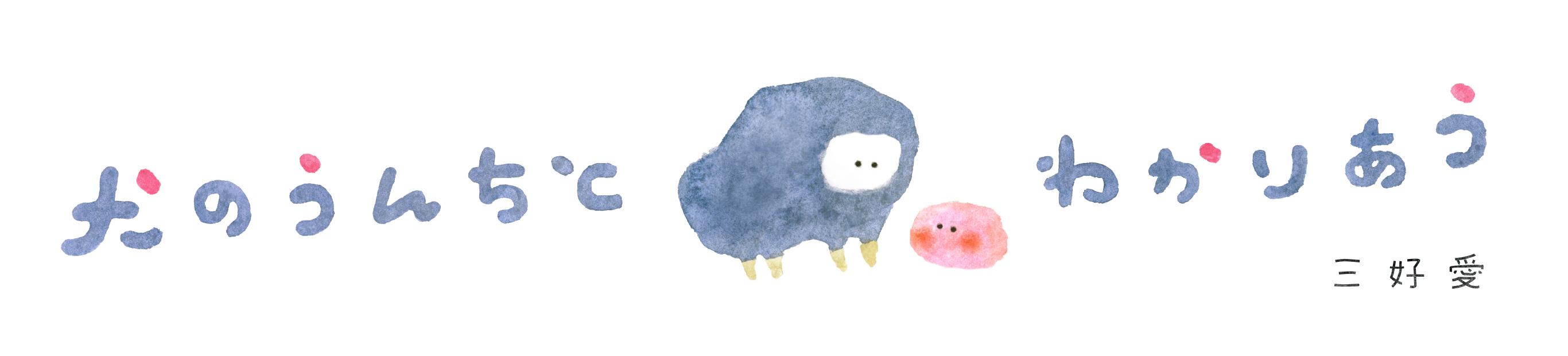



-thumb-800xauto-15803.jpg)


