第28回
うんちを世界に馴染ませる
2025.10.15更新
いいうんちだねえ、と思わずもらすと、ありがと! という声が元気よく返ってきました。答えたのはうんちではなく子どもでした。自分がいいうんちを出した成果をまっすぐ誇らしく思っていて、すばらしいなと感心しました。けれど同時に、私は激しい寂しさに襲われました。うんちが子どもをつつみこむ時代は、確実に終わってしまったんだ、と思いました。今からさかのぼること3年前、うんちは、うんちという役割以上の、たくさんのことを私たちにあたえてくれていました。子どもが日頃経験している世界を、言葉はおろか意思すらあやうい子どもにかわり、その形状で真摯に伝えてくれたからです。そのあと子どもは、うんちは勝手に出るものではないと気づき、うんちの手なずけ方を徐々に会得してきました。そして最近は、おむつからパンツに移行すべく、がんばっていました。「がんばっていた」というのは保育園からの連絡帳に書かれていた言葉で、子どもは、保育園でパンツを履くようになり、保育士さんによると、おしっこやうんちが出るタイミングでトイレに行くことを「とてもがんばっています⭐︎」とのことでした。
排泄をがんばる、というのは大人になった私から見るとやや不思議な文脈だな、と思います。私は、どんなにがんばっていない日でも、おしっこやうんちをトイレでします。どんなに生活も仕事もやりたくないような日でも、うんちやおしっこはどうしたってトイレでします。がんばる、という言葉には身の丈にあっていないことでも背伸びしてやってみる、という意味合いを感じていて、大人の排泄にそれは当てはまらないな、と思いました。でも子どもは、がんばらないとできないんだ、と思いました。そんなにがんばる、がんばらせる必要があるの? とも思いました。現に子どもは、保育園から帰ってきて家へとたどりつくと、途端にがんばる気持ちをなくし、ソファにすわり、テレビのリモコンで「おかあさんといっしょ」をつけ、私に「おむつ」と言いました。おむつを受け取ると、サッとズボンとパンツを脱ぎ捨て、おむつをはき、そこではじめて、がんばる気持ちから解放されるようでした。そのあとは寝るまで、おむつにうんちやおしっこをしていて、私が「トイレには行かないの?」と聞いてみても、ただ、だまってくびを振るばかりでした。
がんばることに疲れているんだ、と私は思いました。子どもは今日、保育園から帰る途中で、「すこし、でちゃった」と立ち止まりました。そして、「おむつとパンツ、どっちをはいているんだっけ」とズボンのおなかのところを少しひろげてのぞきこみ、「パンツだった」と残念そうにつぶやきました。
子どもは、今の自分が、うんちやおしっこを出すことをコントロールできると知っていました。うんちやおしっこの気配に耳をすませ、必要なときにトイレへ行くことができました。でも、それを全部うまくやるには、まだ自分が力不足であることも知っていました。子どもにとって、尿意や便意は自分に近すぎて気付けない存在ではありませんでした。かと言って、得体のしれない大きすぎる衝動でもありませんでした。自分自身で把握はできるが、身体と結びつけて制御しきるにはまだ少し実力が足りない、と言ったところでした。
だから子どもは、おむつとパンツを使い分けていました。家で甘えたいときや遊びたいとき、自分の内にこもりたいときは、おむつを好んで履きました。保育園でしっかり生活したいとき、トイレに行けた成果を保育士さんに褒められたいときは、パンツをがんばって履きました。その使い分けは不思議に器用で、同時に、トイレで排泄をする行為が人間にとって容易なものでないことを、改めて感じさせました。うんちが勝手に出るんじゃない、うんちを出すのは自分で、だから、うんちは自分じゃなくて、自分はうんちを支配する存在なんだと気づいた子どもが、次にいどまなければならないのは、おしりより、おむつより、さらに外側にある世界(トイレ)なのでした。
子どものおしっこやうんちが外側の世界にひらかれていく様子は、子どもの言葉や感情が他者にひらかれていく様子に似ているな、と私は思いました。3歳を過ぎてから、顔や声にあらわす感情の種類が増えて、親以外にも自分のささいな心の経緯を話すことができるようになっていました。保育園の保育士さんやお友達がそれを確かに受け止めてくれました。受け止めてもらえると、安心して、もっと先に進めるようになりました。子どもは、自分だけがただここにいるのではなくて、世界にはいろんな人やものがあって、そのたくさんの中に自分はいるのだと、肌で知り始めているようでした。
まわりの様子を見てみると同じ年頃の子どもはどんどんパンツへと一本化されており、私には、やや焦る気持ちがありました。でも、子どものおむつとパンツのあいだで揺れ動く気持ちは日々変化しているみたいで、その詳細は、本人にしかわかりえないものでした。そこには、できる、できない、だけではなくて、達成感や誇りや恥じらいや恐れや、こちらが把握しきれないたくさんの感情がつまっていました。つまり、私が子どもと排泄のあいだに介在できる期間は、やっぱりもう終わったんだと思いました。あとは、子どもと、うんちとおしっこのあいだで、どうにかやってもらうしかないようでした。
いま子どもは、世界に自分を馴染ませようとしています。たくさんの感情を外に出して、自分以外の人たちと言葉を交わし、同じようにおしっこやうんちを、自分のできる範囲でトイレに出すことで、新しい世界に少しずつ馴染もうとしています。がんばる、というのはきっとそういうことで、私は、子どもが世界に馴染むのを、じっとここで待っていよう、と思いました。



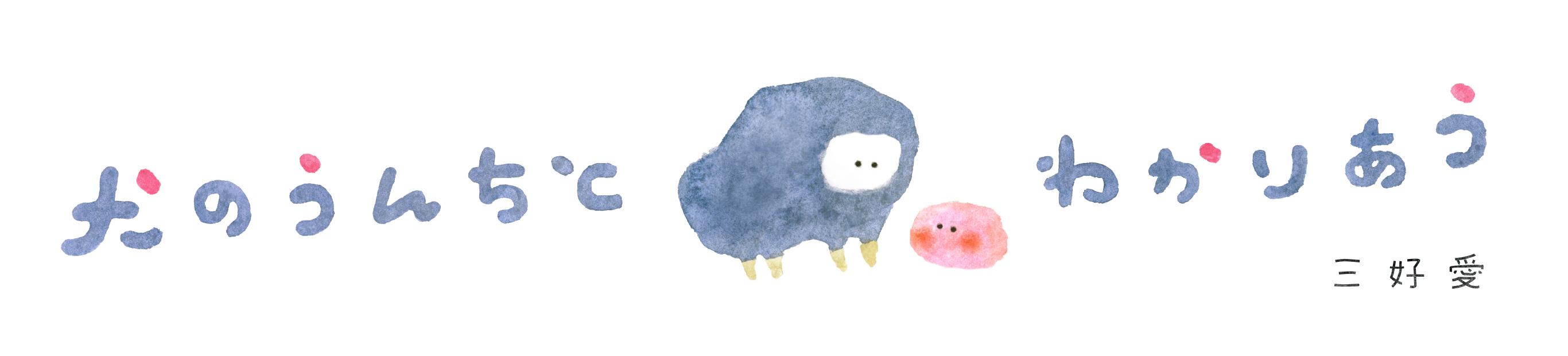



-thumb-800xauto-15803.jpg)


