第28回
「苦手」という言葉が、もう苦手じゃなくなる日まで
2025.11.05更新
序章:納豆が差し出す、一枚の不思議な招待状
その夜、私は群馬県の渋川にある小さな居酒屋のカウンターに座っていました。兵役を終えて大学院を休学中、二度目の日本滞在で、多少は日本語にも慣れてきた頃です。連れてきてくれたのは、地元をよく知る私の叔父でした。カウンターの隣に座った親切なサラリーマンの田中さんが、日本の食文化の素晴らしさについて熱弁をふるいながら、満面の笑みで私にこう尋ねてきました。
「ところで、納豆はもう食べましたか? 日本人の魂の食べ物ですよ! 大将、こっちに納豆一丁!」
その瞬間、私の頭の中は真っ白になりました。あの独特の発酵した豆の香りが、記憶の奥から突然よみがえってきたのです。そう、以前、好奇心にかられて一度だけ挑戦したことがありましたが、見事に玉砕、一口で戦意喪失という苦い思い出。正直に言えば、食べられない。いや、身体が本能的に拒否する、と言った方が正確かもしれません。
しかし、ここで何と答えるべきか。韓国語なら「싫어해요(シロヘヨ/嫌いです)」あるいは「못 먹어요(モンモゴヨ/食べられません)」と素直に言ってしまうでしょう。けれども、目の前で善意100%の笑顔を向けてくれている田中さんに「嫌いです」と断言するのは、まるで彼の「魂の食べ物」そのものを切り捨てるようで、あまりにも鋭い刃のように感じられました。かといって「食べられません」と言えば、アレルギーか何かと誤解され、余計な心配をかけてしまうかもしれません。
私が逡巡していると、叔父と一緒にいた友人の由紀さんが、まるでタイミングを見計らったかのように助け舟を出してくれました。
「この人、納豆はちょっと苦手なんです」
「ああ、なるほど、苦手か! じゃあ仕方ないね! 大将、納豆はこっちだけで!」
田中さんは嫌な顔一つせず、あっさりと引き下がりました。その場の空気は少しも濁ることなく、むしろ日本酒の香りと一緒に和やかに流れていきます。私は安堵のため息をつきながら、ふと心の中に大きなクエスチョンマークを浮かべました。
「苦手(にがて)」
なんと不思議な響きを持つ言葉なのでしょう。それは「嫌い」という言葉が持つ、相手を突き放すような冷たさも、「できない」という言葉が持つ、断定的な硬さもありませんでした。まるで、柔らかいオブラートのように、私の「拒絶」という事実を優しく包み込み、相手の善意を傷つけることなく、そっと横に置いてくれる。それはまるで、高度な技術を要する外交交渉で使われる、魔法の言葉のように思えたのです。
この夜の出来事が、私を「苦手」という言葉の広大で深い森へと誘う、一枚の招待状となりました。たった一つの単語が、これほどまでに豊かな社会的機能と、繊細な感情のグラデーションを内包している。それは、日本語という言語が持つ、そして日本文化が育んできた、コミュニケーションの精髄に触れる旅の始まりを告げる、静かな鐘の音だったのです。
第一幕:「できない」の海と「嫌い」の山の間に広がる、広大な平野
「苦手」という言葉の探検を始めるにあたり、私はまず、その言葉が持つ意味の地図を広げてみることにしました。多くの日本語学習者が最初にこの言葉に出会うのは、おそらく「能力や技術が不足していること」を示す文脈でしょう。
「私は日本語の発音が苦手です」 「彼は車の運転が苦手らしい」 「計算問題が苦手で、いつもテストで苦労します」
これらは、韓国語の「서툴다(ソトゥルダ/下手だ、不得意だ)」に近い意味合いで、比較的理解しやすい領域です。これは「苦手」の地図における、いわば出発点の街と言えるでしょう。そこでは、「できる/できない」という分かりやすい二元論が支配しています。
しかし、私が居酒屋で経験したように、この言葉の旅はそこでは終わりません。地図をさらに進むと、全く異なる風景が広がってきます。それは、「好き/嫌い」という感情の領域に属する使い方です。
「私はパクチーが苦手です」 「満員電車のような人混みは苦手だ」 「ホラー映画だけは、どうも苦手で・・・」
ここで、多くの学習者は最初の混乱に陥ります。なぜなら、これらの感情を表すためには「嫌い(きらい)」という、より直接的でパワフルな言葉が既に存在しているからです。なぜ日本人は、わざわざ「苦手」という言葉を迂回ルートのように使うのでしょうか。
ここにこそ、「苦手」という言葉の真髄に迫る、最初の鍵が隠されています。もし私が「パクチーが嫌いです」と言ったなら、そこには私の強い「意志」と「判断」が表明されます。それは「私はパクチーという存在を拒絶する」という、主観的で断定的な宣言です。
一方で、「パクチーが苦手です」と言った場合、そのニュアンスは微妙に変化します。言葉の主体が、私の「意志」から、私の「体質」や「性質」へと、そっとスライドするのです。それはまるで、「私の意志がパクチーを拒否しているのではなく、私の身体がどういうわけかパクチーを受け付けないのです。だから、これはパクチーのせいでも、私のわがままでもありません」と語っているかのようです。
この絶妙な責任の所在の移行こそが、「苦手」が持つ驚くべき社会的潤滑油としての機能なのです。「嫌い」が、自分と相手の間に壁を築く言葉だとすれば、「苦手」は、その間にクッションを置く言葉と言えるでしょう。それは、自分の感覚を正直に伝えつつも、相手の価値観を否定せず、波風を立てないという、日本社会における高度なコミュニケーション技術の結晶なのです。
それはまるで、色のスペクトルに似ています。「嫌い」が一切の光を吸収する漆黒だとすれば、「苦手」は、黒に近いけれども、どこか光を透過させる部分を残した、深い紫色や藍色のようなものです。そこには、「今は受け入れられないけれど、もしかしたら将来的には変わるかもしれない」という可能性の余地や、「あなたの好きなものを否定するつもりはない」という敬意の気配が、かすかに残されています。
第二幕:対人関係という名の霧の中を照らす、かすかな灯台の光
「苦手」の探検は、さらに深く、複雑な領域へと足を踏み入れていきます。それは、この言葉が「人」に対して使われる時です。
「私は、あの上司が少し苦手です」 「彼女は、ああいうおしゃべりなタイプの人が苦手らしい」 「初対面の人と話すのが苦手で、パーティーは緊張します」
この用法は、私にとって最も衝撃的で、カルチャーショックに近いものでした。韓国語で特定の人を指して「嫌いだ」ということはもちろんありますが、この「苦手だ」という表現にぴったりと重なる言葉を見つけるのは、非常に困難です。
もし「あの上司が嫌いです」と言えば、それはその上司の人格や行動に対する、全面的で強い否定となります。そこには、個人的な感情の対立が明確に示され、関係改善の可能性を閉ざしてしまうような、決定的な響きがあります。
しかし、「あの上司が苦手です」と言った瞬間、その構図は劇的に変わります。ここでもまた、問題の焦点が「相手(上司)」から「自分自身」へと、魔法のようにシフトするのです。この言葉が暗示するのは、「あの上司が悪い人間だ」ということではありません。むしろ、「私自身のコミュニケーション能力や性格が、どういうわけかあの上司のそれと上手く噛み合わないのです」という、関係性の不具合についての告白なのです。
これは、人間関係を一種の化学反応として捉えるような視点です。二つの物質が出会った時、必ずしも美しい反応が起きるとは限りません。時には、反発し合ったり、上手く混ざり合わなかったりすることもあるでしょう。しかし、それはどちらかの物質が「悪い」からではありません。ただ、二つの「相性」が良くなかった、というだけのことです。「人が苦手」という表現は、まさにこの人間関係における「相性の問題」を、驚くほど的確に、そして円滑に表現する言葉なのです。
この感覚を、比喩で表現するならば、それは二つの磁石の関係に似ているかもしれません。「嫌い」は、S極とN極が引き合うように、明確な「反発」という感情で相手を強く意識している状態です。しかし、「苦手」は、同じ極同士を近づけた時の、あの目に見えない抵抗感、すっと反発し合う、あの居心地の悪い空気感に近いのです。どちらの磁石が悪いわけでもない。ただ、そこには自然な物理法則としての「反発」が存在するだけなのです。
このように、「苦手」という言葉は、対人関係という濃い霧の中で、相手を断罪することなく、自分との間に適切な距離を保つための、かすかな灯台の光のような役割を果たしています。それは、複雑で多面的な人間性を尊重し、白黒つけがたい関係性をそのまま受け入れようとする、成熟した精神が生み出した、知恵の言葉と言えるのではないでしょうか。
第三幕:日本人自身も気づいていない、「苦手」の深層心理
この探検を通して、私はある仮説にたどり着きました。それは、「苦手」という言葉が、日本人自身も無意識のうちに活用している、日本文化の深層構造と深く結びついているのではないか、ということです。
日本文化の根底には、しばしば「和を以て貴しと為す」という精神が流れていると言われます。個人の強い自己主張よりも、集団全体の調和を重んじる価値観です。この文脈において、「嫌い」という言葉は、あまりにもパワフルで、属人的なナイフです。それは、集団の和を乱しかねない、危険な切れ味を持っています。
それに対して、「苦手」は、驚くほど安全なツールです。前述の通り、この言葉は、問題の根源を「個人の性質」や「相性」といった、ある種「不可抗力」とも言える領域に置きます。それは、「私のこの感情は、私の意志を超えたものであり、仕方のないことなのです」という諦念にも似たニュアンスを帯びています。この「仕方がない」という感覚は、集団の調和を維持する上で、非常に重要な役割を果たします。なぜなら、それは対立を個人的な感情のぶつかり合いから、「運命」や「自然の摂理」といった、より大きな次元の出来事へと昇華させ、個人の責任を曖昧にしてくれるからです。
さらに、「苦手」という言葉は、自分自身の「未熟さ」を表明するという、謙遜の美徳とも結びついているように思えます。例えば、「英語が苦手です」と言う時、そこには単に「英語が下手だ」という事実だけでなく、「本来はできなければならないのに、自分の努力不足でできていない」という、ある種の自己反省の響きが含まれています。
この感覚は、食べ物や人に対しても適用されます。「納豆が苦手です」は、「多くの日本人が愛するこの素晴らしい食べ物の価値を、残念ながら私にはまだ理解できないのです」という未熟さの告白にも聞こえます。「あの上司が苦手です」もまた、「円満な人間関係を築くべき社会人として、特定の人と上手くやれない私は、まだ未熟者です」という謙遜の表明として機能することがあるのです。
このように、「苦手」という言葉の多用は、日本人がいかに他者との関係性や社会全体の調和に心を配り、自己を客観視し、波風を立てないように努めているかの、言語的な証左と言えるのかもしれません。それは、外国語として日本語を学ぶ私のような者にとっては、単語の意味を覚えるだけでなく、その背景にある文化的なOSそのものを理解しなければ、決して使いこなすことのできない、奥深い言葉なのです。
終章:言葉を学ぶことは、新しい世界を生きること
私の「苦手」を巡る旅は、納豆の入った一つの小鉢から始まりました。そして、能力の海、感情の平野、対人関係の霧を抜け、日本文化の深層にまで至りました。この旅を通して、私は外国語を学ぶことの本当の意味を、改めて噛み締めています。
外国語の学習とは、単に自分の国の言葉を、別の国の記号に置き換える作業ではありません。それは、今まで自分が持っていた世界を切り分けるためのナイフ(=母国語)とは、全く別の形をした、新しいナイフを手に入れることです。
韓国語というナイフでは、ざっくりと「嫌い」と「できない」に切り分けられていた世界が、日本語の「苦手」というナイフを手にした途端、その間に存在していた、広大で名もなき領域の存在に気づかされるのです。そこには、体質、性質、相性、謙遜、諦念、そして調和への願いといった、これまで一つの言葉では捉えきれなかった、複雑な感情や関係性のグラデーションが広がっていました。
新しい言葉を一つ学ぶことは、世界に新しい色を一つ見つけることに似ています。それまで同じ「青」にしか見えなかった空に、「群青色」「瑠璃色」「空色」といった無数の青が存在することを知るように。「苦手」という言葉は、私の感情の世界に、これまでなかった新しい色彩を与えてくれました。
そして、この発見は、鏡のように私自身の母国語と文化を振り返らせます。「なぜ韓国語には『苦手』に相当する便利な言葉がないのだろうか? それは、私たちがコミュニケーションにおいて、より直接性を重んじる文化を持っているからだろうか?」と。外国語という窓を通して初めて、自分がずっと暮らしてきた部屋(=自文化)の形や特徴を、客観的に眺めることができるのです。
もはや私にとって、「苦手」は単なる便利な日本語の単語ではありません。それは、人間関係の繊細さ、コミュニケーションの奥深さ、そして文化の多様性を教えてくれた、一人の賢明な師匠のような存在です。
最近では、この「苦手」という言葉をわりと自然に使えるようになってきた気がします。たとえば、今年の初めに京都のミシマ社を訪れたときのこと。京都駅からミシマ社に電話をして、Sさんに道を尋ねたら「205番の市バスに乗れば大丈夫ですよ」とのこと。言われた通りに駅前でやってきた205番に、仲間と一緒に勢いよく飛び乗ったのですが――なんと反対方向行きでした。20分で着くはずが、まさかの1時間コース。同行の友人たちには、ただただ申し訳ない気持ちでいっぱいでした。
数日後、今度は一人でSさんに会いに行き、帰り道を尋ねたら「また205番で京都駅まで戻ればいいですよ」とのこと。その瞬間、私は息をつく暇もなく、こう答えてしまったのです。
「・・・205番が苦手です」
その一言に、Sさんも笑い、私も笑いました。
今夜、もし私が再び居酒屋で「納豆はいかがですか?」と尋ねられたなら、もううろたえることはないでしょう。私はきっと、少し微笑みながら、こう答えるはずです。
「ありがとうございます。納豆は昔は苦手だったのですが、いまは大好きです」
そしてその一言が、私をこの豊かで奥深い日本語の世界へと導いてくれた、最初の扉だったことを思い出しながら、日本の夜を静かに楽しむことができるのです。言葉を学ぶ旅は、なんと面白く、そして人間的な営みなのでしょうか。その探検に、終わりはありません。


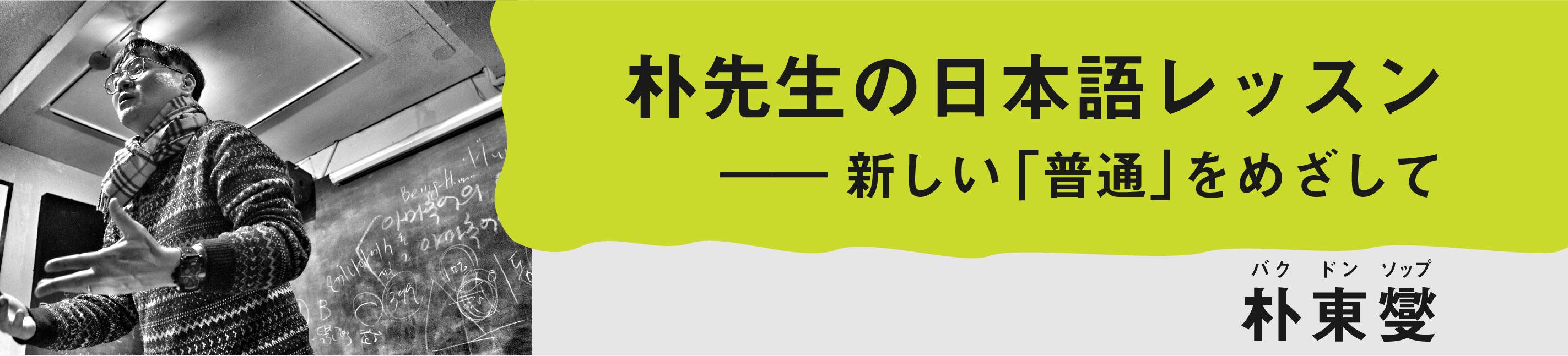



-thumb-800xauto-15803.jpg)


