第14回
はじめてのお話発表会!
2023.09.01更新
「あるところにエパミナンダスという男の子がいました!」僕が語り始めると、目の前には20名の大地の子どもたち。キラキラした瞳がぐっとこちらに注意を向けている。今日は、大地の父親五人によるお話発表会。半年前から、月に1回、朝の7時から2、3時間の勉強会を積み重ね、それぞれのお話を仕上げてきた。僕が人生で初めて取り組んだのは、「エパミナンダス」というお話だ。
おっちょこちょいの男の子が、お母さんからのお使いで、次々に見当違いなことを繰り広げていく、愛すべき七転八倒物語。大地で、話し手たちが愛用するお話集『おはなしのろうそく』(東京子ども図書館)の第1巻の巻頭に掲載されている。翻訳は日本の児童文学を牽引してきた松岡享子さんだ。
エパミナンダスは、おばさんの家でもらったケーキを、思わず手でぎゅっと握りしめて家まで帰ってしまう。家についたときには、もう手にクズがくっついているだけ。それを見てお母さんは、エパミナンダスをたしなめる。
「エパミナンダスや、お前は頭がないねえ。ケーキをそんな風にもらってきちゃだめじゃないか。ケーキをもらったら、綺麗な葉っぱに包んで、それを帽子の中に入れて、その帽子をかぶって、そーと歩いて帰ってくるもんだ。」
母からの注意をエパミナンダスは、「うん、わかったよ。おっかちゃん!」と元気に受け止めてまた翌日おばさんの家にいく。今度はおばさんは、できたてのバターを一ポンドくれたのだ。エパミナンダスは、お母さんの言われた通りに、バターを葉っぱに包み、帽子の中に入れて、その帽子をかぶって帰宅の途につくのだが、その日は運悪くとても暑い日で・・・。
子どもたちは、エパミナンダスがヘマをやらかすたびに、弾けたような声をあげて笑った。話してるこちらが、気持ち良いくらいにお話に反応してくれる。彼らの話し手を見つめるまなざし、物語を聞きたいというエネルギーが毛穴から沸き立っているような姿勢が、場を特別な空気にしている。
さて、このエパミナンダス。やること、なすことが、全部裏目にでて、お母さんにたしなめられ続ける。それでも、健気に母の注意を聞いて、またお使いに出かけていく姿に、僕は共感を覚えずにいられない。リクルートに入社したころの、新入社員だった僕にそっくりなのだ。マネージャーの吉名あらたさんから、
「あっちゃん、このクライアントの資料をまとめておいて」
「あっちゃん、このエクセルに営業進捗を記録しておいて」
「あっちゃん、プレゼンの提案ストーリーを考えておいて」
様々な、お使い(仕事)を振られるわけだが、僕はやることなすこと、見当違い、たびたび、あらたさんに、ご指導を受けた。エパミナンダスは、このころの僕を彷彿とさせ、僕にとってはまるで自分ごとを話すかのように、切実に語ってしまった。
我が家の長男たかちゃんを含む、大地のみんなはそんなことを知る由もなく、最後まで笑い通しでお話を聞いてくれ、大盛り上がりで僕のお話デビューは幕を閉じた。ありがとう、エパミナンダス。ありがとう、新入社員のころの自分。(ちなみに、あらたさんはその後、一年かけて吉名あらたのミラクル★営業トレーニングを僕に稽古として授けてくれた。その結果、社内の誰もが驚いた躍進を遂げることになる)
お話のあとに、保護者ののぶえさんが「たかちゃん、お父さんがお話している様子、なんとも嬉しそうな顔で見つめてたよ!」と教えてくれた。ええ、ちゃんと彼の「なんとも嬉しそうなにんまりした顔」は僕からも見えてました。エパミナンダスは7分ほどの比較的覚えやすい短いお話だ。それでも初めて語る僕にとっては、どうやって物語を自分のものにすればいいのか、わからない。車を運転しながら、ぶつぶつ音読したり、それを助手席の妻に直されたり、僕より先に暗唱してしまったたかちゃんに直されたりしながら、なんとか会得することができたのだ。そのプロセスも見ていたたかちゃんからすれば、僕がみんなの大爆笑を獲得している様子は、してやったりだったに違いない。
その後も他のお父さんたちの渾身の語りが子どもたちを沸かし続けた。小型帆船のキャプテン、ひろとさんは「チムラビットと三羽のかささぎ」(『チム・ラビットのぼうけん』アリソン・アトリー著、石井桃子・中川李枝子訳)というお話。お母さんラビットが毛布の洗濯を終えて、外に干した。乾かしている間、風で飛ばされないように見張ってほしいと頼まれたチム。そこに三羽のかささぎがやってきて、毛布を持ち飛び去ってしまい・・・。
すべての人類と仲良くなれるきんちゃんが話したのは、「まのいいりょうし」(瀬田貞二再話)。一人の猟師が息子の誕生祝いのために、猟に出かける。しかし、鉄砲が曲がってしまった。猟師は鴨を見つけて、その曲がった銃を放つと信じられない獲物たちが・・・。
中締めでは、あおちゃんが登場。グリム童話のお話「6人男、世界を股にかける」を語った。ある男がいろいろな特技を持つ仲間たちと出会いながら、不遇した王様を見返すための冒険を繰り広げていく。そのカリスマ的な主人公のあり方があおちゃんとそっくりだと、お父さんたちは納得した。
お父さんのお話サークルのリーダー的存在である優理さんは「京のかえると大阪のかえる」「もちは金仏さま」の二本を披露。京都出身の優理さんが関西にルーツを持つお話を語り、はまらないわけがない。そして、締めは大作「やかましやのヤカちゃん」を藤松さんが語りきった。なんと、この「やかちゃん」、フルで語ると20分以上のスケールのあるお話。よく多忙な仕事をやりくりしながら、覚えきったものだ、と舞台裏を知るお父さんたちは最大限の労いの拍手を、語りきった藤松さんに贈ったのだった。
それぞれのお父さんの人となりが、お話の存在感とマッチして、独特の魅力を放つ。お話は、ある意味でその人の「生き様」を鮮烈に表現してしまうのだと痛感した。そして、松岡亨子さん、石井桃子さん、瀬田貞二さんら「日本の子どもたちのための文学」の礎を築いてくれた方達の息吹を、僕たちはそれぞれの話からヒリヒリと感じることができる。お話を語るとは、彼、彼女たちのお話への愛、子どもたちにその楽しさを伝えたいという情熱をお話を通じて全身に感じることができる不思議な営みだ。
こうして、大盛り上がりで幕を閉じた父親お話会。翌朝の早朝から大地で打ち上げを予定していた。大地の一室で、薪ストーブをあおちゃんが新設し、琉球調に設えた部屋があった。その部屋でストーブを囲んで琉球にまつわるものを持ち寄り宴会しようか、と準備していた。その時である。のんたん母さんが一言、何気なくつぶやいた。
「飯綱登山なんかおもしろいんじゃない」
この一言から事態は急展開を迎える。
「それ、いいねえ! 日々積み重ねて覚えてきたお話の一歩一歩は、頂上を目指す登山と似ている」とあおちゃん。
まさかの展開にお父さん一同
「ええええ〜!!!!」と驚きつつ。
こんな即興のノリにも対応するのが大地の父親たちの醍醐味なのだ。
すぐに、「おもしろそう!」「いきますか!」と声が上がる。ストーブを囲んでの乾杯があっという間に、冬の飯綱山頂で乾杯に急遽変更。こうして、僕たちは翌朝早朝に集合して飯綱山の山頂アタックをかけることになった。
翌朝二時半に、お父さんたちは大地に集合した。金ちゃんのハイエースに乗り込むと飯綱山の登山口を目指し走り出した。飯綱山は、標高1917メートル。北信五岳の黒姫、戸隠、斑尾、妙高の一角で、古くから修験道の山として知られている。この5つの山はそれぞれが修験道の修行の場で、五峰それぞれ解放され広大な修行エリアを描いていたそうだ。特に飯綱山は天狗伝説や忍者の発祥の地として知られている。
さて、雪山登山。僕は、冬に山に登ったことがない。「雪崩とか大丈夫なんでしょうか?」とあおちゃんに尋ねると、「飯綱山は雪崩が起きにくい山だから大丈夫!」とのこと。
登山口に到着しても、当然あたりは真っ暗闇だ。それぞれヘッドライト、アイゼンを足に装着する。僕は雪山登山用のアイゼンを持っていなかったので、あおちゃんから借りた。初めて手にするアイゼンは金属の鋭利なギザギザが闇ににぶく光っている。3時半、三日月と明けの明星に見守られながら、僕たちは登り始めた。ざっくざっく、と小気味良い音を立てながら雪を踏みしめる。アイゼンの安定感に支えられながら進んで行く。明け方であたりはシーンとしている中、お父さんたちの雪を踏みしめる音しかしない。星とヘッドライトに照らされた雪景色はあまりに幻想的で、物語の世界のようだ。
だんだんに空に赤みがさすなかで、山の雪景色も移ろいを変えていく。僕の前を行くのは、お話会のリーダー優理さん。彼と、大地に来てからのお互いの変化について語りながら、山頂へ歩んでいった。赤木優理さんは大地に出会ってから5年が経つベテランお父さんだ。長女のゆいちゃんが2歳のころ、東京から飯綱に引っ越してきて大地に通い始めた。長男のゆうごくん、次女のほのちゃんと3人の子育て真っ最中の父だ。優理さんは東京に暮らしていたころ、子どもたちにとっての理想の教育プログラムを探していたそうだ。しかし、どれも釈然としない。そんな時に縁あって大地に出会うことになる。大地に通う中で優理さんがわかってきたのは、大事なのはプログラムではない、ということだった。「結局、子どもは親の真似をするので、親がどういう生き方をしているのか、どういう日々を過ごしているのかが大事なんだということ。それをあおちゃんたちはずっと僕たち親に言ってるんじゃないか。そのことに気づいたのが、大きな変化になった」という。
たしかに、大地ではよく「親がどういう風に生きるのか問われている」という話になる。優理さんは続ける。
「子どもは親たちの生き様、行動を指の先まで、よく見ている。いくら偉そうなことを言っていても、だらしないお父さんだったらいうこと聞かないし。もともと教育プログラムが大事だと思っていたのは、子どもに何かさせよう、と思っていたわけです。親として子どもを怒るということも、子どもにしつけをしようとガミガミ言うことも、結局、親がどうあるべきかを見せていれば、別に言わなくてもいいんだということが、ちょっとずつわかってきた。僕はもともと、けっこう言う方だったから、大地の教えを通して、自分の子どもに対する行動っていうのが変わってきたと感じます。」
優理さんの話は、ガツーンと頭に食らったような気がした。たしかに早稲田大学の恩師のひとりである山西優二先生も言ってたっけ。「どんな環境、学校に通っても、親と子どもの関係性がしっかりしていれば、最終的にはどんな外の出来事も家族としての学びに変えていける」と。
さて、おしゃべりに盛り上がりつつもだんだん斜面が急になりきつくなってきた。中腹で小休憩を挟み、フィックスロープの急坂の難所に差し掛かった。万が一、滑り落ちてしまったら、どこまで滑り落ちてしまうのだろう、と不安がよぎるも、冬山初体験の僕にとっては興奮が勝った。そのくらい息を飲む美しい景色が続いていた。目標としていた6時に山頂にたどり着いた。
僕たちは各々手持ちのスコップで風除けの壁をつくりそこに腰をかけてご来光を待った。それぞれが持ち寄りのおやつを広げる。優理さんは、なんと水筒に熱燗を入れてきてくれた。いよいよ雲の切れ間から光が差し込んでくる。東の方から、美しい赤みが空を覆っていく。ついに元気玉のような赤とも橙色とも言えるようなお天道様が顔を出してくれた。僕たちはそれぞれの杯を掲げて、朝日に乾杯し杯を飲み干した。真っ白な雪野原は、モルゲンロートに染め上げられていった。
それにしても、不思議だ。僕たちはお話発表を終えて、打ち上げをするはずだった。それなのに、早朝未明から雪山を登ってご来光を望んでいる。大地よ、なんであなたはそんなに不思議な体験をもたらしてくれるのだろうか。
しばらくご来光を祝った僕らは、山頂がとてつもない風にさらされ、自分たちが凍えそうになっていることに気づいた。僕たちは、足元に気をつけながら、時に滑り落ちながら、下山していった。途中、プチ滑落するお父さんの姿もあり、登り以上に緊迫した帰り道になったが、なんとかみんな無事に下山した。
大地に通い始めてから、僕の中で子育てについての考え方に変化が生まれていた。子育てというけど、子ども「を」育てるというよりは、子ども「と」育つという方が実際に近いのではないか。そして優理さんが大地から受け取っているメッセージは僕の肚に落ちた。
「親が子どもにどうなってほしいと求めるのではない。子どもは親の模倣なのだから、問われているのは親の生き方であり、あり方なのではないか」
だから、好奇心旺盛な子に育つように願うなら、自分自身が好奇心を発露したらいい。楽しく幸せな生き方を願うなら、自分自身が満たされ、楽しく生きるんだ。それを自分だけでなく、夫婦のパートナーシップとしてどう体現していくのか。問われているのはそこなのか。
下山して食べた朝ごはんは、体に染みるようにうまかった。




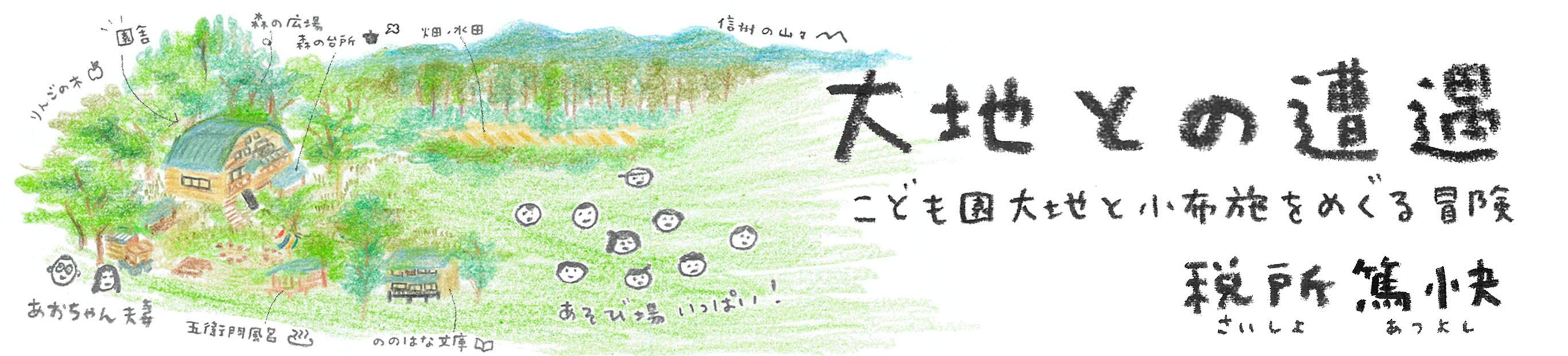





-thumb-800xauto-15803.jpg)
