第9回
冬の大地 はじめての保育ボランティア
2023.06.15更新
「おはようございます! あっちゃんです。今日はみんなと遊びにきました。よろしくね!」
大地の朝の会で、僕はぐるりと円になった子どもたちに挨拶した。晴天に雪の白が映える今日、僕は大地で保育士見習いとして1日目を迎えていた。
あおちゃんに保育の現場に入りたいとお願いしてから1年の月日がたっていた。あのとき、あおちゃんからはオッケーをもらったものの、現場の保育士あおちゃんねえちゃんに相談したら、
「親が保育の現場に入るのって難しいのよね。子どもも本来の力を出せなくなってしまうこともある。いまたかちゃん、本領発揮してきたから、なおさらね・・・」と言われた。たしかにその通りだ。結果的に、僕は1年くらい、その思いを持ったまま、ついに今年の2月に改めてあおちゃんに保育ボランティアの相談をした。たかちゃんも大地に入園して1年半近くになり、ようやく機は熟したように思えた。
月曜日の朝の会は、室内からはじまる。ひとりふたり、とどんどん子どもたちが園舎に入ってくる。僕は薪ストーブの前で絵本を広げて、子どもたちにお話を聞かせる。目の前に数人だった子どもたちがどんどん増えて行く。しまいには、20数名の子どもたちがこちらを見つめている。この量の子どもたちに向けて、絵本を読むのは、とてもドキドキする。無垢な集中力の束を一身に引き受けることは日常生活でそんなにない。
子どもたちが勢ぞろいすると、朝の会はわらべうたで、はじまる。手や足など全身をつかったわらべうたをみんなで使い、楽しみながら気分を盛り上げていく。
「ふゆのだいち〜」(わらべうた)
月曜の朝はにじみ絵からはじまることが多い。にじみ絵とは、シュタイナー教育で実践される絵画手法で、濡れた画用紙に水で溶かした絵の具で描くのが特徴だ。赤、青、黄の3色の絵の具が水に溶かされ、ジャム瓶に入れられた。それを3〜4人でシェアする。僕は年少の「かぜさん」チームに混ざって絵筆を握った。僕は大人になってから絵筆を握ったことはなかったので、ずいぶん久しぶりに絵の具に触れたことになる。「にじみ絵」が素敵なのは、その表現に上手い下手の概念が入りにくいことだと感じた。三色を思うままに、走らせ、たらし、描いていくのだが、濡れた画用紙はよく色を引き立ててくれ、どうやっても美しくなってしまうのだ。
そもそも「にじみ絵」には、「きれいに描けた」というような観点もそぐわない。親や保育者は、あまり子どもたちが描いた絵を「手放しで褒めない、関心を注ぎすぎないように」注意を受けた。子どもたちが親や保育者に褒めてもらうために、絵筆を持つようになるのは、シュタイナー教育の本意ではないからだ。
たかちゃんがにじみ絵を大地でやりはじめて、定期的に家に描いた絵を持って帰ってくるのだが、それを見ながら毎回、「僕もやってみてえなあ・・・」と密かに思っていたので、ついに僕も初体験することができた。
絵筆を絵の具に浸す感覚が、まず自分には新しい。青の絵の具をたっぷり絵筆に吸い込ませ、濡れた画用紙にぽたぽた垂らして見る。青の斑点がひとつひとつ広がり、不思議な光沢を放っている。徐々に青を重ねていく。時々、体に染みついている「きれいな絵を描かなければ」という考えが顔を出すのだが、横をみてみると、かぜさんたちが楽しそうに絵筆を走らせているのを見て、そんな想いを打ち消し、心の呪縛を解く。
「これ、めっちゃ楽しいやん!」
このにじみ絵の背景には、ゲーテの『色彩論』が横たわっている。シュタイナーは思想家として、ゲーテ、ニーチェ、シラーの3人から大いに影響を受けたという話を先日、「シュタイナー道場破り列伝」の第一弾でお会いした東京理科大の井藤元さんに伺った(この話はまた後日お話ししますね)。
シュタイナー教育の教員養成課程で、大人たちがシュタイナー教育を学んでいると、たびたび、自分自身の子ども時代の体験を追体験したり、それが失われていた場合、それを取り戻すプロセスが発現するらしい。大人になってから、いや、中学生を卒業してから絵筆を持っていなかった僕にとって、それはよくわかった。
僕の18歳からの相棒、三好大助が、詩人として作品を発表しながら絵筆を持って絵を描きだしたのは4〜5年前からだった。(彼の初詩集『生きとし生けるあなたに』はこちら)彼が様々な色を絵筆で表現していく様子は、僕にとってとても新鮮で、どこか羨ましかったのだが、自分でもやってみようとは思わなかった。なぜだろう。どこか、「絵筆をつかった表現は自分の領分ではないから」と線を引いていたからだろう。それはどこで引かれたものだろう? たぶん、高校生の時に、音楽か美術を選択する必要があり、音楽を選択したとき? いつのころからか、絵を描くという表現を、自分には向かないと切り捨てていたときがあった。三好大助の活躍は、僕の中に、絵筆へのうずうずを掻き立て、このにじみ絵体験が、色って楽しい! という想いを沸き立たせた。
「なにか描いてみたい!」
そんな、なにかが自分の中で渦巻いているうちに、子どもたちはどんどん絵を終えて立ち上がっていってしまった。描いた作品には一顧すらしない。あおちゃんに言わせると、子どもたちが筆を使っている瞬間に意味があり、終わった後は、ある意味では「その燃えかす」だという。
その後、僕たちは室内遊びへ。年少のみあさちゃんたちと僕は、病院ごっこをする。ベッドの上に患者の人形を載せて、診察する。みあさちゃんがドクターで僕は看護助手的な見立てだ。大地では先日、ユニークな内科検診が行われた影響で、子どもたちにも病院ごっこが流行していた。ベッドの上の人形をみて、「えええ!」とびっくりする。ふかふかした触り心地は、普通の人形と変わりないが、その顔である。目や口がほぼない、点くらいしかない。一瞬、のっぺらぼうかと見紛うほどだ。そんなのはあたり前といわんばかりに、みあさちゃんは診察を続ける。
これはシュタイナー教育で用いられるウォルドルフ人形の特徴だ。目や口など顔のパーツを極力小さくすることで、表情が生まれず、子どもたちの、そのときの気持ちによって、様々な表情を見せてくれるという。たしかに、診察のためにずっと見つめて、みあさちゃんと会話をしていると、その能面のような顔からなにか表情が湧き立ってくるような気がしないでもない・・・うーん、まだまだ僕は自分の中の子どもを解放しきれてないみたいだ。
それにしても、園舎の中を見渡すとにぎやかだ。四隅の一角の大型薪ストーブの前には、うちのたかちゃんと、ここちゃんが「リリアン」に取り組んでいる。リリアンとは、手仕事を重視するシュタイナー教育で実施される編み物で、Yの字の編棒を使うことで、通常の編み物よりシンプルに編むことができる。
四隅の一角は僕とみあさちゃんたちの病院。中央部では、ボーイズたちが木の椅子と棒を消防車両に見立てた「レスキュー隊」たち。さらに四隅の一角は、あろちゃんたちが中心となった「ろうや」があったり。それぞれが自由闊達に遊んでいるエネルギーはどうだろう。僕はウィーンでみたブリューゲルの「子どもの遊び」という絵画を思い出した。絵画のなかいっぱいに、子どもたちがそれぞれの遊びを跳梁跋扈しているめちゃくちゃ楽しい絵だ。さてはブリューゲルさん、あなたどこかの幼稚園でこれを書きましたね?
そして、時間の流れがゆっくりだ。たぶん、子どもたちの時間軸をはじめて体験する僕が自分の時間軸を乱されているのだろう。だんだん、お弁当の時間はまだだろうか、とお腹をさすりだした自分に気づいた。しかし、彼らの遊びはまだまだ終わらない。たいちゃんに手を引っ張られて、粘土コーナーへ。午前中のフィナーレは粘土遊びである。そこでは、何人かが粘土をこねこねしていた。
さて、この粘土もなんだか一風変わっている。こちらも、シュタイナー教育で使われるドイツシュットクマー社の「蜜ろう粘土」。文字通り、ミツバチの巣から取れた蜜ろうでつくられている。匂いを嗅いでみると、どこかほのかに甘い匂いがする。シュタイナー教育では7歳までは知的学習というよりは、想像力やファンタジーの世界を体感したり、体や手首を動かすことを重視している。にじみ絵、ヴァドルフ人形、蜜ろう粘土と様々なおもちゃはその思想から紡ぎ出された。
この蜜ろう粘土の第一感触は、「か、かてえ・・・」である。室内の気温が低かったせいか、そもそもの粘土の性質もあるのか、ずいぶん粘土が硬い。子どもたちから「あっちゃん、これ柔らかくして〜」とどんどんリクエストがくるので、僕はひたすら蜜ろう粘土をこねた。こねてこねて、こねまくっていくと段々に柔くなっていき、それを子供達に次々渡す。今度は、ようくんから、「ステゴサウルスつくって〜」と依頼がきた。「ステゴサウルス? ん〜む、じゃあやってみようか」と、二人で悪戦苦闘していると、どこからともなく、木琴の音が。ついにお昼の時間になった。
お部屋の片付けをして、お弁当をみんなで出す。お当番さんが前にでて、手を合わせる。大地のお昼のわらべうたがはじまる。
「わたしのおててては、いつつのはなびら あさにひらいて よるにとじる」
「だいちがつくり、たいようがみのらせた おいしい しょくじに ありがとう かんしゃをこめて いただきます」
「いただきます〜!」
僕はお腹が減っていたので、妻のつくってくれたお弁当を猛然と食べ始めた。子どもたちは、「お弁当に、たまご入ってる人〜?」と誰かが呼びかけると、「何人かが「はーい!」と答える。「お弁当に梅干し入ってる人〜?」とまた誰かが呼びかけると、誰かが答える。そんな穏やかなランチタイムが過ぎていった。
お弁当の時間が終わると、子どもたちは洗面台で歯磨きとガラガラペー。そしてスキーウェアに着替える。僕は子どもたちの着替えを手伝う。スキーウェアの腕が通らない、スパッツがはけない、手袋がつけられないなど、おおにぎわい。今日は年少さんと年中さんは、大地の横の「魔女の森」で雪遊び。大地の雪遊びの花形といえば、「お尻滑り」である。大地は飯綱町のちょっとした丘の上にあり、ここでのお尻滑りは東京からやってきた僕の想像を超えるものだった。おそらく建物、3〜4階、いや4〜5階だての高さがあるだろう丘の上から、木立のなかを、シューっ! お尻で滑っていくのだ。ゆるやかなポイントもあれば、急加速するポイントもある。使い古したスキーウェアであればあるほど、摩擦が少なくよく滑る。
まずは降りたての雪の上にコースを設営する。保育士のさおりさんが、まずずず〜とすべりながら、大人の体重で圧雪する。すると、次から滑る子どもたちは軽快にスピードが出て続々と滑っていく。特に気温が低く、雪が凍るとこのお尻滑り、尋常ではないスピードが出るので注意が必要だ。すべての年少さんははじめて大地でお尻滑りをやるときには、コースアウトするために体をずらして、「脱出」するための方法を伝授される。
僕も昨年から、お迎えのときに、たまにお尻滑りを体験させてもらったのだが、この楽しいことといったらなかった。僕の密かな夢は気がすむまで、大地でお尻滑りがしたいというものだった。ついにこの日、その夢は叶う。年少のけいとくんをまたに挟んで、2人連結して、スタート台にたった。ドキドキしながら、お尻をすべり始める、「シュー、シュー、シュッー!」と徐々にスピードが出て、木々のなかを疾走する。
途中、コースは微妙に蛇行し、そのたびに体の方向が変わっていく。そうか、お尻滑りとは、人間ボブスレーだったのか! 「シューシュバッ!!!!!」と、ゴール地点近くでコースアウト。雪のなかに僕はまみれた。けいとくんも一緒に雪にまみれた。しばらく二人で横たわって笑い合いながら、青い空を見つめる。僕の耳元に、けいとくんの身体があった。彼の心臓の音がどくどくっと打っているのが聞こえる。3歳のこんなに小さな体だが。あたりまえだが心臓が脈打っている。なんだか、そんなあたりまえのことに感動する。
朝から僕が一緒に過ごしているこの20数名。小さい身体ながらも、みんなこの心臓がばっくんばっくん動いているのか。それってすごいことだよな・・・けいとくんの心臓の音を聞きながら、そんなことを思った。そして、この心臓たちは間違いなく僕の心臓よりも長く脈を打ち続けるだろう。
さて、ここからはひたすらに、滑っては丘をよじのぼり、お尻滑りをするの繰り返し。子ども達が、「あっちゃん、次は一緒にすべろう!」とたくさん誘ってくれるので、どんどんすべり、どんどん登る。登るといったって、半端な傾斜ではないこの斜面を雪に足をとられながら登るのだ。これはなかなかにヘビーな運動量だ。子ども達もお尻滑りだけでなく、全身をつかったスーパーマンのようなすべりや、上体を起こさずに完全に寝転んでしまってすべる、より人間ボブスレーに近いすべり、友だちと連れ立って滑る連結すべり、スノボーすべりなど、バリエーション豊かなすべり方で楽しんでいる。横では、さおりさんたちと何人かが新しいコースを開拓して、コースのバリエーションを増やしていく。
子どもたちと連結すべりしながら、一緒にコースアウトしたりしていて気付いたことがある。子どもたちのそばで彼らの「顔」をまじまじと見ていると、その面構えが目に止まる。その子の顔が、親たちの面影をありありと残しているのに気づく。アメリーちゃんの瞳の深さはお母さんのシャーロットだし、鼻立ちはお父さんのサムだ。さとちゃんの目元や笑顔はお母さんのゆまさんだけど、顔立ちはどこかお父さんの藤田さんだ。ようくんの顔の形はお父さんの季典さんだけど、目や口元はお母さんのあきさんだとか。それぞれの子どもが親の面影を残している。しかも、割とありありと。これって当たり前だけど、とても凄まじいことではないだろうか。
その親の面影を残しているということは、その上の親の面影が一部に残っているということだ。その上の親の面影は、またその上の親の面影を残しているということだろう。その子は、ある意味で、そのファミリーの面影の集積の最もニュータイプということになる。僕が、アメリーや、さとちゃん、ようくんに見たのは、その両親の面影だけでなく、これまでの彼彼女たちの上の世代のみなさんの面影を見たことにもならないだろうか。だんだん、僕には子どもたちの上に家系図湧き立って連綿としたいのちのつながりが、見えてくるような気がした。その家系図の広大さを想像すると小さい身体の彼らの上を大きく見上げなければならない。
あまりにハードなお尻滑りが続き、僕の中古のスキーウェアは浸水。なかのズボンとパンツも濡らしはじめた。僕はだんだん、終了時間を心待ちにしはじめていた。なによりの希望は、帰り道のコンビニで熱いコーヒーを飲みたい。それだけだった。午後14時すぎ、ついに終了のホイッスルならぬ、素敵な笛の音が聞こえてきた。帰りの会を終えて、1日の保育は14時半に終了する。9時半から14時半。親からするとあっという間の保育時間である。それにしても、一歩踏み出して、子どもたちの目線からこの時間を体感すると、なんて豊かで濃い遊びの時間だろう。勇気を出して、保育ボランティアに手をあげてみてよかった。
帰り道、あおちゃんにたしなめられるであろう、コンビニでの買い食いをついついやってしまった。たかちゃんにアンパンマングミ、僕はコーヒーとエクレア。ああ、なんて幸せなコンビニコーヒー。そして、お尻は着替えたけどまだ冷たかった。


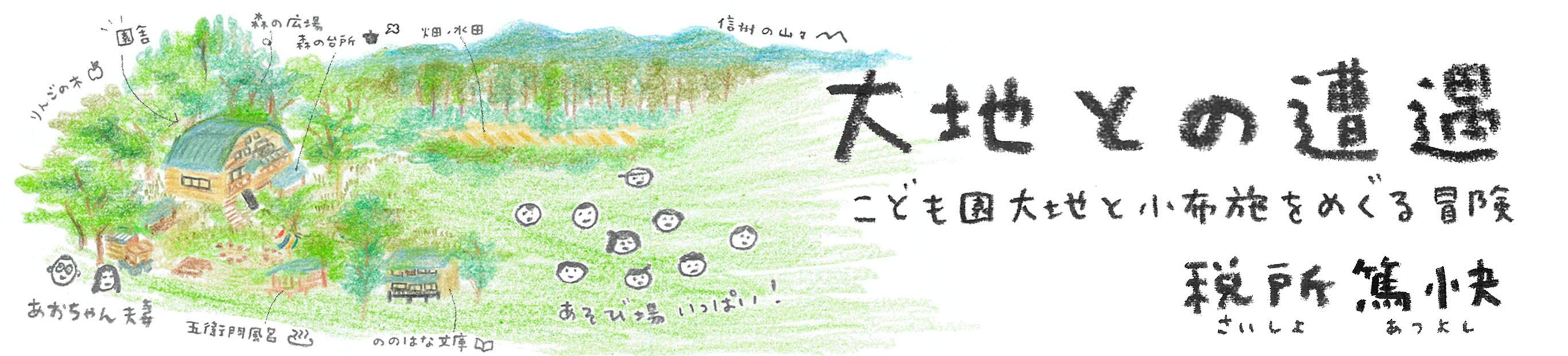





-thumb-800xauto-15803.jpg)
