第90回
那須耕介さん、小田嶋隆さん、二人の遺稿集を編集してみて、今
2022.08.27更新
お盆。終戦の日。多くの人が、死者たちに思いを馳せる時期であろう。私も例外ではない。心静かにこの日を過ごしている。明日(8月16日)は、京都では五山の送り火が催される。せめて、そのときまで心穏やかにいたいものだと切に願う。
*
個人的なことから申せば、この一年の間に身近な大切な方たち(3名)が他界した。一人は、親戚のおじ。お二人のうち、一人が那須耕介さん、もう一人が小田嶋隆さんである。どちらの方も、闘病生活の末のことだった。ご病気であることは知っていたとはいえ、まだ自分の中で整理できないでいる。
昨年9月7日に他界された那須さんは53歳、6月24日にお亡くなりになった小田嶋さんは65歳だった。那須さんとの仕事は「これから」であったし、小田嶋さんとは「まだまだいっぱい」ご一緒するつもりでいた。私がどれほど望もうとも、もう、それは叶わない。頭では十分わかっているつもりだが、くやしさや後悔を拭うことは簡単ではない。
悲しさは、仕事とは離れてある。気を緩めた隙に入り込んできては、ときおり呑み込まれそうになっている。呑み込まれそうになっては、ハッとなる。その往復運動を幾度かくりかえすうちに、さまざまな悲しみが積層していく。ただ、これは幸いというほかないが、那須さん、小田嶋さん、それぞれの遺稿集を手がけることになった。この作業があったおかげで、完全にのみ込まれることを免れ得たと今は思う。
というのは、本づくりでは、現実(と呼ばれる)世界での作業に徹することを求められる。むろん、原稿を読む過程で、故人を思い出し、涙にくれることもあるだろう。あるいは、ある一文から著者との対話が始まる。気づけば、何時間もページをくることもなく、その対話に浸ることもあるかもしれない。
だが、編集者である私は、ずっとそこに留まることを自らに許すわけにはいかない。いうまでもなく、編集者がそこで止まってしまい、手を動かすことをやめれば、永久未刊という事態になりかねないからだ。
それは、誰ひとり望んでいることではない。故人も、遺族も、私自身も。
もし、泣き暮れるあまり本づくりを怠れば、草葉の陰から「ミシマさん、悲しんでくれるのはいいけど、本ができてからにしてよ」と言われることだろう。実際、編集作業に入った初期段階で、そういう声が聞こえた気がした。裏を返せば、原稿を誰よりも早く通読するという恩恵に浴す過程で、ぞんぶんに涙を流せた。その行為を経たからこそ、切り替えることができたのかもしれない。
できるかぎり私情に流されないようにしよう。目の前の原稿が一冊として、最高のものになることだけに集中する。そのことを自らに言い聞かせて編集作業に入った。
さて、いざ本づくりを始めると、普段の編集作業とほとんど変わらない。素読みをし、初校ゲラを読み、鉛筆を入れ、著者校正を経て赤字を戻し、再校ゲラを出す。もう一度、同じ過程を経て、校了する。ただ一つ、決定的に違うのは、確認する「著者」が書き手本人ではないこと。遺稿集のばあい、遺族の方に確認してもらうことになる。
以前、遺稿集を一冊だけ編集した(『奇跡の本屋をつくりたい』)。著者の久住邦晴さんにとってそれが初めての本であったこともあり、また、本人が校正の手を入れる以前の原稿であったため、明らかに文意が通っていない、意味がわかりづらい箇所がいくつかあった。そうしたところは、ご遺族に確認をとりながら、修正を加えた。対して今回は、お二人ともに何作も著作がある。つまりは書き慣れている。どころか、名文家であり、文章の達人である。残されたテキストの完成度はきわめて高かった。そのため、遺族、編集者ともに、著者の意図・意思を最大限尊重し、誤字・脱字をはじめとする必要最低限の修正にとどめた。
むずかしいのは、仕上がりのイメージの共有だ。
那須さん、小田嶋さん、それぞれのお人柄が、その人らしさが滲みでるような本にしたい。当初からそう考えていた。ただ、「お人柄」や「その人らしさ」なんて、どうやったら共有できるだろう?
実際のはなし、実物をお見せするまで共有することは不可能にちがいない。とくに、ミシマ社のようなやり方をとるばあい・・・。校了直前まで、すこしでもよくなるのであれば、変更に変更を重ねることを厭わない。そういう編集方針である以上、完成したものでしか共有は困難であろう。
出来上がった本を見て、「本人と違う」と思われる可能性が大いにある。限りなく、その人らしさを出したつもりでも、「違う」と感じられないとは限らない。そのことを覚悟したうえで本づくりをしなければいけないと思っていた。「全面的にお任せします」と言ってくださっていただけに、いっそうプレッシャーがのしかかった。
どう感じられるか。そのことを考えると、校了を終え、完全に手を離れた今は緊張しかない。
もっとも、遺稿集に限らず、著者および作品そのものの世界と編集側が目指す仕上がりイメージには、必ずズレがある。誤解を恐れずにいえば、ズレがないといけないと思う。問われるのは、それがいいズレであるかどうか。編集者の仕事とは、つまるところ、その「いいズレ」が生まれるよう尽力することにほかならない。
では、「いいズレ」とは何か? と言うと、それがあることで、著者のもつ世界と、出来上がる本とのあいだに、気持ちよく読者が入りこめる。本が完成した暁には、そのあいだ、ズレは立体的なスキマとなり、そのスキマから新しい読者が著者や本の世界に入りこむことができるのだ。
仮に、ズレがない本を想像してみる。
それは、コアな著者のファンだけが、入ることのできる一冊。著者のことを徹頭徹尾、全面的にすでに理解している人たちだけが、入ることを許される。必然、ある種、排他的な佇まいをもつことになる可能性がたかい。いわゆるファンブックのようなものであれば、そのほうがより望まれるだろう。
だが、広く読まれる本、新たな読者との出会いを願ってつくられる一冊を求めるばあい、適度なズレがないことには始まらない。そう、適度なズレだ。
その度合いが適度でなくなると、わるいズレになる。
わるいズレには大きく二種類ある。ひとつは、著者の世界をくずすかたちでズレをつくるばあい。端的にいえば、「売れる」ことを最優先されるとき。その本や著者の築いた世界を温めることより、問答無用に売れればいいとされるケース。もちろん、ただズレているというトンチンカンなことだってある。
もうひとつは、編集側(あるいは出版社側)の思い込みが強すぎて、そちらに引っ張られたままかたちになるばあい。必ずしも著者の意図とちがうわけではないものの、著者の意図のある一部だけをとりだし、それを全部のように見せる。そうしたケースは、編集のみならず営業の仕事において見られることもある。
いいズレは、著者の作品、世界を全てひきうけたうえで、新たな読者との出会いをもとめて、その殻の外へ飛び出すときに生まれるもの。
その加減が絶妙なぐあいで仕上がったとき、著者も、読者も、その本が存在しなかったら出会うことのなかった他者同士がなんともいえぬ心地よさのなかに身をおける。・・・という前提で、毎回それをめざしている。うまくいっているかは心もとないが。
今回もそれをめざして編集した。はたして、それが叶ったかどうか、現時点ではわからない。
ただ、ほどよい手応えはある。それはひとえにデザイナーの方々の力によるところが大きい。『つたなさの方へ』はクラフト・エヴィング商會の吉田篤弘・浩美さん。『小田嶋隆のコラムの向こう側』は尾原史和さん。
私情に流されない、と決めて編集に臨んだものの、たぶん、けっこう流されていたのだろう。打ち合わせ時、尾原さんが「とはいえ、ウェットになりすぎないほうがいいもんね」とぼそっと述べた。そのことばに、凝縮しているように思う。
ともあれ、ようやく、一読者として、この2冊に向き合うことができる。もう、なにも抑えることもない。泣いたってかまわない。たっぷりと、二人っきりの対話を味わおう。デザイナーさんたちが、心地よく、浸れるスキマを用意してくれたのだから。あとは思いっきり、そこに身をおくだけでいい。
*
最後にひとつ。
遺稿集と言われる書籍を同時に2冊編集することになったわけだが、むろん、偶然でしかない。
那須さんの『つたなさの方へ』は約9カ月ほど、小田嶋さんの『コラムの向こう側』は約1カ月半の制作期間であった。
那須さんのばあい、一周忌までに発刊する。小田嶋さんのばあい、亡くなられる4日前にお会いし、その場でご本人がタイトルを決められた。そのとき、「できるだけ早くつくりますね」とお約束した。見本ができあがるのを気持ちのハリにしていただきたい、
そういうわけで制作時期がたまたま重なった。
偶然、平行して編集することになった2冊であるが、ときおり、お二人が重なったみえた。もちろん、外見も生き様も出身地も、あらゆる点でちがうお二人であるが、それでも共通点を感じずにいられなかった。
孤高の人。
ひとことでいえば、そうなるだろうか。その孤高の具合は・・・? 私がこれ以上語ることは野暮でしかないだろう。それぞれの本を読むことで直接感じていただければと願うばかりだ。
編集部からのお知らせ
8月新刊のお知らせ
ミシマ社を長年支えてくださっていたお二人のご遺稿集を刊行いたします。
本日8月26日(金)、リアル書店先行発売です。ネット書店を含むすべてのお店での公式発売日は、8月31日(水)となります。
『つたなさの方へ』那須耕介(著)
☆ちいさいミシマ社レーベル
もう一つの小さなものさしを いつも手元にしのばせておきたい
余計なこと、みにくさ、へり、根拠のない楽観・・・法哲学という学問の世界に身を置きながら、「余白」に宿る可能性を希求しつづけた人が、余命のなかで静かな熱とともに残した随筆15篇。
『小田嶋隆のコラムの向こう側』小田嶋隆(著)
「文章を書く人間は、時にはテーマに拘泥することをやめて、筆を遊ばせなければならない」(本文より)
コロナ下、病気が悪化したこの2 年の中で、小田嶋隆が残した最後の言葉とは――
9/8(木)ウスビ・サコ先生 イベントのお知らせ
ミシマ社が半年に一度刊行する雑誌『ちゃぶ台』。2022年12月刊行予定の次号『ちゃぶ台10』では、特集に「母語ボゴボゴ、土っ!」を掲げます。
私たちには、「母国語」でも「外国語」でもなく「母語」があるはず。その「母語」とは何か?、という疑問が浮かんだとき、まっさきにお話を伺いたいと願った人が、ウスビ・サコ先生でした。
『ちゃぶ台』編集長の三島邦弘が聞き手となり、言語の達人であるサコ先生に、私たちの生活を支える言葉についてオンラインでたっぷりインタビューいたします!
9/8(木)19:00~20:30
「編集長が訊く! サコ先生、『母語』ってなんですか?」
小田嶋隆さんロングインタビュー動画を配信中です
 『小田嶋隆のコラムの向こう側』の発刊を記念して、2020年10月に開催したMSLive! 木村俊介さんオンライン講座「インタビュー」内の小田嶋さんへのロングインタビューを、復刻アーカイブ配信しています。
『小田嶋隆のコラムの向こう側』の発刊を記念して、2020年10月に開催したMSLive! 木村俊介さんオンライン講座「インタビュー」内の小田嶋さんへのロングインタビューを、復刻アーカイブ配信しています。


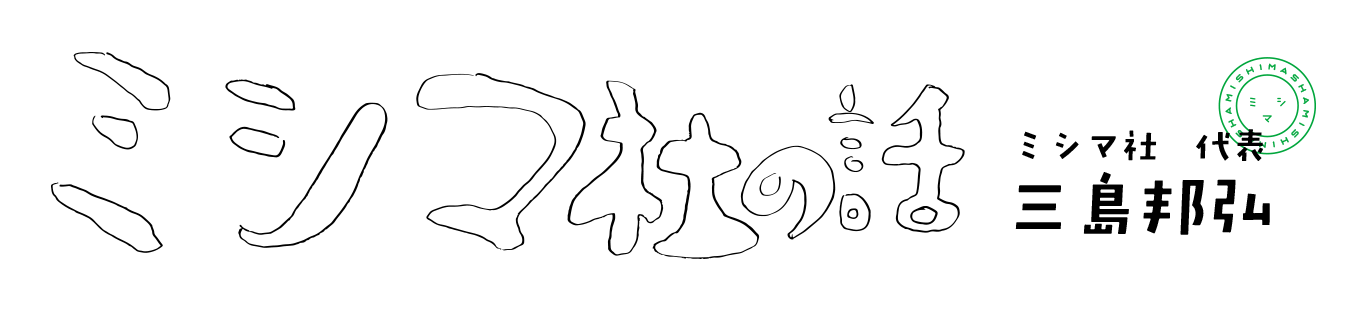
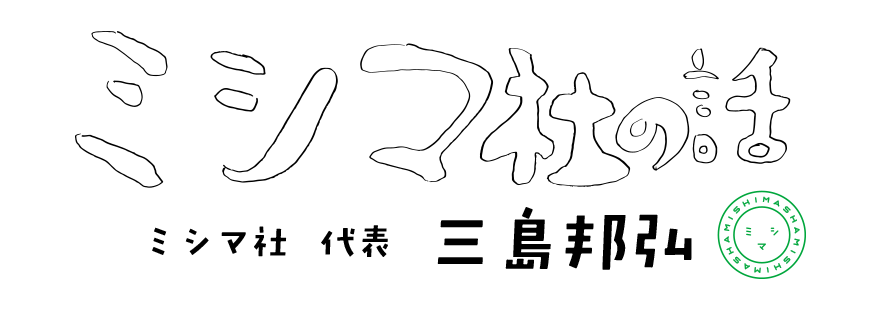






-thumb-800xauto-15803.jpg)


