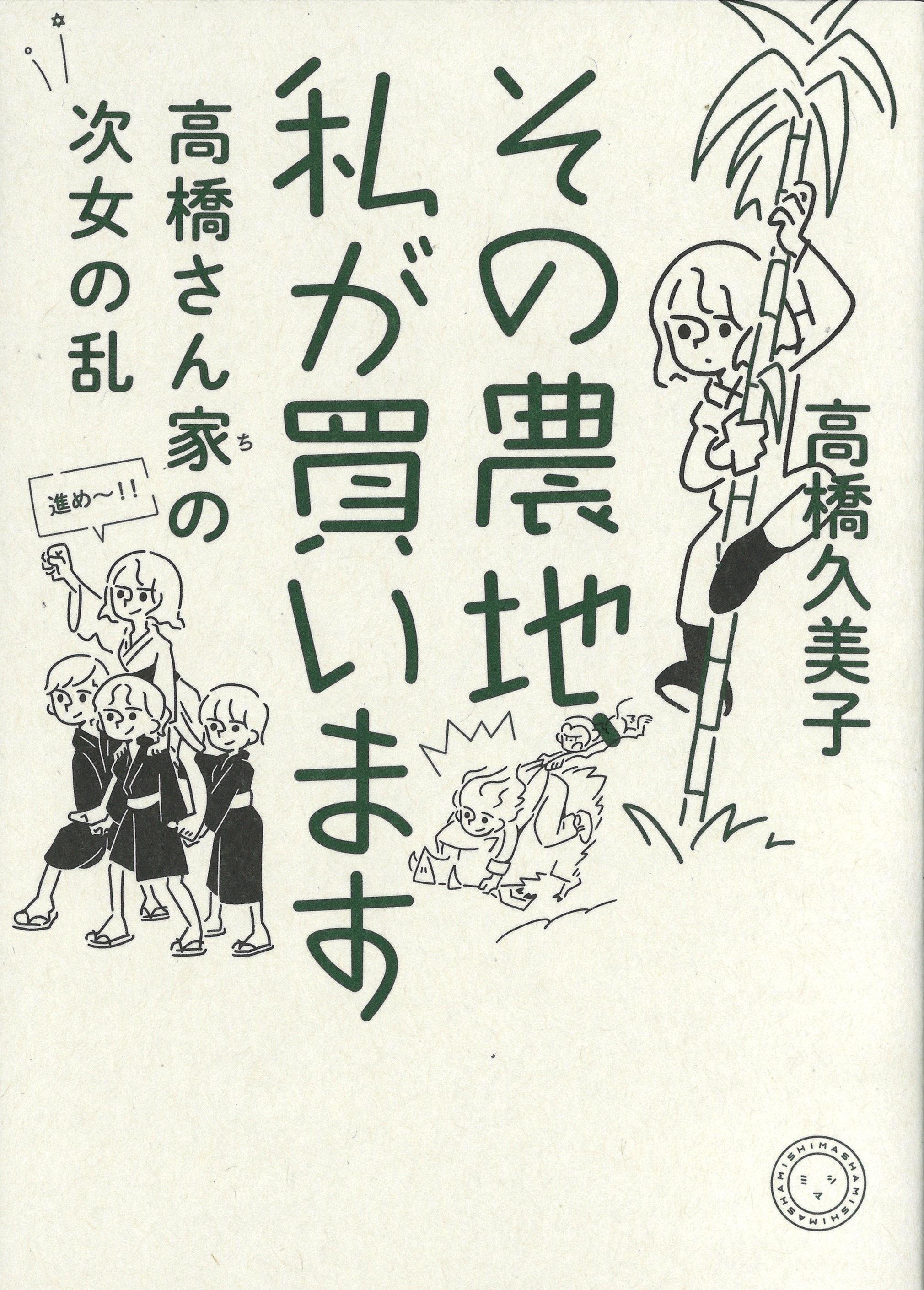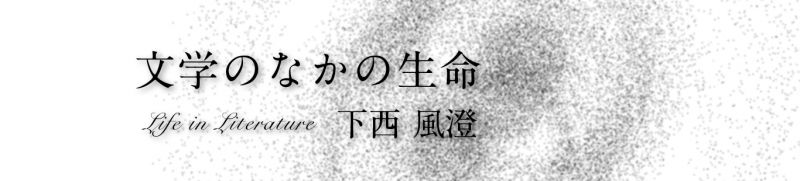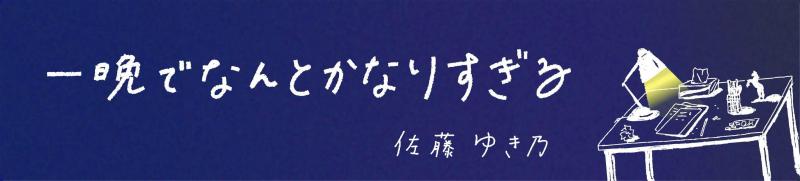第24回
農道のポルシェ
2023.09.26更新
待ちに待った軽トラが来た!
農道のポルシェ、スバルのSAMBERである。祖父がずっとSAMBERに乗っていたので、軽トラを買うならSAMBERにしようと思っていた。が、2012年までしかスバル製のSAMBERは造られていない。どうやらポルシェと同様のエンジン配置なので、造れば造るほど赤字になったのだとか(知り合いの農家さん談)。その後、ダイハツからOEMで出されているそうだ。でも・・・エンジンが違うんだそうで。やっぱSAMBERはスバルだよねと軽トラ好きは口を揃えるのだった。だから、中古でスバル時代のSAMBERを探している人が山のようにいるんだって。農家さんが集まると、軽トラ談義は尽きない。あと、ホンダのアクティも名車だそう。私も大分詳しくなってきたよ。
私の町はスーパーの駐車場の三割は軽トラが占めている。お、こいつSAMBERの最後の年のだとか、お!アクティだとか、軽トラによるマウント取り合いもあったりなかったり。
春から、市内外いろんな車屋さんに探してもらったが、お手頃のSAMBERはなかなか見つからなかった。あったと思っても15万キロくらい走っていたり、いいお値段だったり。
ネットで買おうかなあと思っていたら、「何かあったときのために、やっぱり地元の車屋さんで買った方がいいんじゃないかな」と、メカに詳しいうらちゃんが助言してくれて、すぐ近くの車屋さんに行ってみた。
その車屋さんのおじいさん、行くと一時間は軽トラの話をしてくれた。そして、綺麗な高いのを進めてくれた。セリで落としてメンテナンスするとどうしてもその値段になると。SAMBERではない。うーん。どうしようかなあ。山を走ればすぐボコボコになるから、こんなに綺麗でなくてもいいしなあ。
毎日のようにおじいさんのところへ通っていたら、「仕方ない。お得意さんのおばあさんが新しい軽トラに買い替えるからもうじきSAMBERを下請けしてメンテナンスするんよ。それを売ってあげる」と秘蔵っ子を出してくれることに。5年ほど前から軽トラの新車はなかなか手に入らなくなったそうだ。そして、中古でも10年前の2倍くらいになり、高額でも店頭に出せば数日で売れるのだそう。SAMBERともなると出した瞬間に売れるのだそう。
それを、農業のいろんな話をしているうちに、店頭に出す前に良心的なお値段で売ってくれると約束してくれたのです。それから半年・・・全く連絡がない。もしや、おじいさん忘れてるんじゃないかと、東京からも時々電話をしてみる。しぶとい私。約束は6月だったのに連絡がこなくて不安にもなった。
「5月に出す言いよったんじゃけど8月まで乗るそうでなあ」
そうして9月
「もう整備もできたけんね。あとは車検だけ!いつでも来て!」
もう新車と見間違うくらいぴっかぴかに磨いて塗装し直してくれて、へこんでいたドアも変えてくれたみたい。
他の自動車屋さんも親身になってくれた。おじいさんのところで見つかった車の価格と状態を報告したら、
「その軽トラ絶対いいですよ!」
と、背中を押してくれた。
ほんとに、いろんな方にお世話になりました。出会うべくして出会ったマイカーだ。ありがとうございました。大切に乗ります。
というわけで、我が家には軽トラが2台になった。そもそも父が軽トラを貸してくれず「自分のを買え!」というので買ったわけなんだけど、父の軽トラの半額近くで買ったのに、私の軽トラの方が揺れないし静かなので、父は羨ましそう。換えてあげないよー。やっぱSAMBERすごいな。エンジンが全然違うんだって、車屋さんのおじいさんも言っていたよ。
ナンバーを935にするか最後の最後まで迷ったけど、バレバレなのでやめておいた。
さっそく、チガヤメンバーや姪っ子を代わる代わる乗せて農道を走っている。やっぱりミッション車が最高だよなあ。早く山へ行って4WDっぷりを発揮したいなあ。
環境のことを考えて、当初は父の軽トラを一緒に使わせてもらえるようにお願いしていた。父は乗用車も持っていて、乗用車なら高確率で貸してもらえたが、軽トラだけは駄目だった。やっぱり自分の農機具などを常に荷台に積んでいたいというのと、私が畑や山を走るので汚されるのが嫌だったみたいね。ちなみに、私の軽トラの前持ち主も、おじいさんとおばあさん、それぞれに軽トラを持っていたそうだ。確かに相棒感は強いのかもしれないな。
軽トラが来たばっかりで嬉しすぎて、軽トラのことばかり書いてしまいました。
新しいといえば、新メンバーも入りましたよ。なんと二十歳の青年、愛媛くん(仮名)。2つ向こうの地域から、そしてやはり農業初心者だ。地元の子がなかなか参加してくれないのは、畑も田んぼも飽き飽きしているからなんやろうな。月金で働いてせっかくの休みになんで草刈りしたり畝を作ったりせないかんの。という気持ち、分からなくはない。
愛媛くん、まだ若いのでどうかなあ・・・同じ年頃の子とスタバとか行きたいんやないかなあ。と思っていたが、毎回「楽しかったです」と言ってくれる。
とってもシャイな青年なので、断りきれず来てくれてるんやないかな、などと不安に思ったりするけれど、まずはみんなで集まることに楽しさを感じてくれているのかな。それに農作業も新鮮なのだと思う。
うらちゃんが、鎌をプレゼントしていた。うらちゃんには、なっちゃんが少し前に鎌をプレゼントしていて、なんだか部活の先輩後輩の儀式みたいで素敵だなあと思った。
愛媛くん、今はまだ研修生として、全体で作っている里芋やサトウキビの手伝いをしてもらっているけれど、そのうち、おっくんやゾエのように、マイ畝を持ち、自分の食べたい作物を作れるようになるといいなと思う。
それから、もう一人。愛媛県内でも離れた地域に住むカナさんも、ピンチヒッターのように来てくれている。例えば他のメンバーが誰も来られないときとか、人手が必要なときなど。
彼女は子どもの頃におばあちゃんの家庭菜園を手伝った経験があるそうだ。とはいえ、鎌や鍬は殆ど使ったことはないということで慣れてはいない。だからこそ新鮮で楽しそうだ。彼女は食に興味があるので、手伝った分の作物を嬉しそうに持って帰って、料理写真を送ってくれる。
そういうふうに、作物と力の交換ができるととてもいいな。
うらちゃんの妹が今北欧で暮らしているんだけれど、先日テレビ電話をしたところ、ボランティアが当たり前に行われていると言っていた。日本ではそのために仕事を休むことはまだまだスタンダードではないし、農作業を手伝ってもらったとしたら、作物以外の対価を(お金とか買ったもの)払うという暗黙の了解がある気がする。もちろん長時間であればそれは当然だが、農繁期の一日を手伝う分には、作物を渡すことでいいんじゃないかしらねえ。祖父母の若い頃はお互いに助けあって農作業するのが普通だったけど、今は気を遣い合って、近所や親戚同士でもお金とかそれに見合った物を渡すようになった。
確かに持ちつ持たれつの割合っていうのは難しいよねえ・・・。農作業の体験をしたい!というのと、手伝ってほしい!の需要と供給のバランスが合えばいいけれど、田舎では喜んで農作業をしてくれるっていうのはないだろうから、賃金を払い合うというのが平和的なのだろう。ときどき観光農業もみかけるよね。いちご狩りとか、ぶどう狩りみたいなね。あれは収穫だから楽しいけど、観光農業で夏場の草刈りとか、水路の土砂かきとかやったら成り立たんやろうね。それを、チームで助け合って最後には収穫をして一緒に食を楽しむっていうところまでできたら素敵だなあと思っている。となると、やはり求めているものが一致しなければいけない。
例えば、先週の日曜はまあまあ広い畑(半反くらいかな)で作っていた里芋の収穫を行い、新メンバーの愛媛くん、カナちゃんも来てくれた。
でも、ただの里芋掘りではない。今までにも書いてきたように、うちの地域は猿による被害がひどい。絶対食べられなかった里芋まで食べ始めた。8月、暑いなかぐるりと柵で囲い、天井までメンバーたちがネットを張ってくれた。それが・・・高さ約140センチほどしかないので、草刈りも一苦労。腰が痛いのなんの。さらに、せっかく草を刈ると芋の葉が猿の目につき、再び襲撃があったので、草を伸ばすことにした。
もう、近所でも有名なジャングルである。父は怒り「草を刈れと久美子に言え」と母に言う。でも、草刈ったら猿に見つかって食べられる。私達は収穫まで草をぼーぼーにした。
からの収穫である。もはや里芋の葉より草の背の方が高い。ネットから草が飛び出て見事に暴れている。ええやん。芋食べられるよりましやんか。
ということで、まずは、草を刈るところから収穫のスタートだ。9月とはいえ暑くて、みんな汗だくだ。綱のように太くなった草を手作業で刈っていく。1人だったらねを上げていただろう。愛媛くんには収穫で一番花形の、芋を鍬で掘り出すのを任せた。でも、鍬を振り下ろすにも、中腰でなかなか大変だったと思う。彼は、一つ一つ、非常に丁寧に芋を傷つけることなく掘り出してくれた。こんなに丁寧にしかも早くやってくれてありがとうと言ったら「みなさんがここまで大切に育ててきた芋を傷つけるわけにはいけませんから」と。
ええ子やなあ。私達の大変だったことを話していたので、きっといろいろ感じ取ってくれたのだと思う。
普通なら、時給いくらかを払って来てもらうだろう。けれど、私達は自分たちが食べるために作っているので、殆どそういった貨幣でのやりとりはしていない。売上は農機具や動物対策の費用でほぼなくなる。あとは時々、みんなでご飯を食べにいったりバーベキューしたり。
ここで数年体験を積んでもらい、おっくんのように自分の畑を持つステップになったらいいなと思うし、愛媛に来たけど友達ができなかったと言っていたうらちゃんにとっては、農作業プラス同じ年頃の子と会話することも楽しみに繋がっているのではないかと思う。幼稚園で野菜作りの隊長をしはじめたなっちゃんも、やはり、ここで母や土からいろんなことを学んだのではないだろうか。
大規模農家さんの場合は機械化を進めているので、採算がとれているのかもしれないけれど、中・小規模農家の場合(しかも高齢夫婦だと)は、バイトさんという形で人を雇ってしまうと、結局赤字だったり、とんとんだったりというのを、うちの地域でもよく耳にする。
自分でやってみて、まさにそうだろうなと思う。
収穫を終えて、帰っていると、あんな草ぼーぼーの中で芋ができとるわけないと「芋、なかったんだろ?」とにやにやしながら近所のおっちゃんおばちゃんが、コンテナの中をのぞいてくる。
「少ないけどありましたよ」と見せたらめちゃくちゃ驚いている。
「ええ!芋の葉も草で見えてなかったけど、できとったん?」
えっへん。ありますとも!小さいけど、いえ小さいからこそおいしい里芋です。草のおかげで日光も当たってませんしね。
それにしても、猿の被害には頭を抱える。
今年は、イノシシの被害も大きく、父の田んぼも収穫直前にイノシシの群れの襲撃を受けてしまい、お米の収量が半減してしまった。イノシシはどろんこが大好きなので、田んぼに入って、背中をこすってずりずり。ミミズを掘ってぱくぱく。ああ、さぞ楽しいやろうなあ。
イノシシのずりずりしたお米は臭くて臭くて食べられないので、全部刈り取って捨てることになるのだ。疲れ果てた父が姉に電話して「犬をしばらく貸してくれ」とな。
いくら外で飼っている番犬でも、そんなんオッケーしてくれるわけなかろう。
柵や網をしていたというのに、私達の畑もイノシシに入られて、盛大にやられてしまった。翌日、畑にいくと、うわー獣臭いー!!菊芋の茎をばっきばきに折られてしまった。せっかくのでかい里芋も食べられている。悲しいけどもう慣れてきた部分もある。
猿軍団には、うらちゃんの買ってきた爆竹をお見舞いしたが、10分もすればまた道を走り出した。今繁殖期だから、オス同士の喧嘩の声もすさまじいよー。
猿から死守した里芋は、チガヤ農作物店で販売しておりますので、是非食べてみてください。クリーミーで、今年も本当においしいですよ。
https://chigaya2022.stores.jp