第4回
名前と針が刺さるとき
2022.06.04更新
高く伸びてしまった枝に、僕は巻き付くように登っていく。梅の木での収穫の模様だ。ほとんどの場合一人でやっているので、たまに上から落ちてこけたときも一人で「痛ぇーっ」と叫ぶだけで、その叫びは瞬時に山中の畑に吸い込まれていく。その状況は少しさみしい。けれども周りの生き物、特に鳥のさえずりは圧倒的存在感を放ち、地面に叩きつけられた自分もしばらくしてクスクス笑ってしまう。
つい先日の収穫のとき、高い枝の先の実に手を伸ばすと手袋の中の手にビシッと強い痛みを感じた。よく見ると、アシナガバチが巣を作っている最中だった。伸びてきた手を敵と判断し、まさに「蜂のように刺す」。太い針で刺したような痛みだった。けれど収穫の締め切りがあるのですぐさま作業に戻り、しばらくすると痛みもなくなっていた。女王であろうそのハチも、すぐ巣作りの作業に戻っていた。また間違って手を伸ばしたら、ブーンと旋回してきた。危ねえ。
冒頭で、高く枝が「伸びてしまった」と書いたけど、実際は僕がそのようにわざと仕立てているので「高く伸ばしてしまった」が適切か。以前は、樹木が勝手に伸びていくのに「この枝を伸ばす」とか「実を付けさせる」という言い方をする意味がわからなかったけど、だんだんニュアンスが理解できるようになってきた。樹木は人の手が入ると、それに応じて形を変えていくんだな、ということを毎年の様子で見させてもらってきたからだ。
人の手が入る、それは植えたときからすでに始まっているのかもしれない。
剪定という作業、正確には「整枝剪定」だと教わった。樹木の活動が静かな時期に枝をハサミやノコギリで切っていく。暖かい時期になると、切った後の枝から新しい梢が芽生えて、それがだんだん新しい枝になっていく。そこに花がついたり、葉が生まれ、実ができる。梢がそのうち一つの幹としても育っていく。切らなければ切らないなりの、切ったら切ったなりの樹形にどんどん変化していく。当たり前といえば当たり前かもしれないのだけど、それが面白く感じられる。
***
農業を始める際の10年前。「やりたい」と一念発起しても、どこから何を学んで農の営みに漕ぎ出していいか、全くわからなかった。その最初の頼りはあちこちの書店で目が合った「本」で、これという本を読み込み、ネットでも調べては手がかりを集めていった。調べたことから今度は各地で「研修」があるということがわかって、その都度研修に申し込み、足を運んだ。あるときは日帰り、あるときは泊まりこみ。あるときは何日間かの勉強会、種の交換会。30日間の研修ではバイトしながら毎日通った。
研修につきものの懇親会でこんな場面に出くわした。石川県羽咋市での大きな勉強会の懇親の席でのことだ。
みんな名刺を持って、交換している。僕は、持っていない。
僕はもらうのに、返せないといううしろめたさを初めて感じた。それまでバンドでは「プレイが名刺代わりじゃ!」ぐらいのテンションでいた。実際には「名前だけでも憶えて帰ってください」だったけど、とにかく名刺を持つというアイデア自体が僕にはなかった。バンドの人同士で名刺を交換したこともなかった。だからこの場面がくるとどうしたらいいのか、ドギマギした。
懇親会で僕はなにか無作法のような、無礼なような気持ちがしたし、僕のことを憶えて帰ってもらうことができないのがなんだか悲しい気がした。なので考えあぐねた結果、メモ用に持っていたノートを名刺サイズにちぎって、一枚ずつ名刺を手書きで作り始めた。飲み会のテーブルで、せっせと作った。名刺をもらってから時間差で「ちょっと待っていてください」と渡していく名刺。字がぐにゃぐにゃだったけど、そんなやつは居なかったみたいで、逆に喜んでもらえてうれしかった。
その時にいた人たちと、今も時折連絡をとったり梅の注文をいただいたりしている。なんともありがたいことだ。
そういえば、急に話は脱線するけど―――。中学生の娘がいま、スマホを持つべきかどうか僕と妻で悩んでいる。
本当は、まだ持つ必要がないと思っている僕。でも、同級生のなかで娘だけがまだ僕たちにスマホを持たされていないので、子どもたち同士の連絡の輪に全く入れていないということが発覚したのだ。この現場を目の当たりにした妻は、考え方を変えざるを得ないと思った。遊びにも誘われず、写メの撮り合いもできず。かわいそうだと。
もしかしたら都市部では持っていない人もちらほらいるかもしれないけれど、こちらでは子どもの人数が少ないので「一人だけ連絡手段を持っていない」というのは、娘の社会では相当な負荷がかかっていることに初めて気づいた。
1人だけ名刺を持っていないのと同じ、いや比にならないくらいのインパクトだろう。さみしい思いをしているに違いない。
ただ連絡するだけのことと、ありえないくらい高まった機能を持つスマホ。そのギャップよ。スマホよ、なぜ登場した。スマートホン。ホ? 手書き名刺ではダメか。ダメだよな・・・。
いま高校生である先輩、少し前まで「スマホ持たざる人」だった、同じ環境に置かれていた子のアドバイスを真摯に聞かせてもらっている。
話を戻すと、懇親会ではいろいろなタイプの農家さん、ベテランの方や始めて数年、あるいはこれから始める人。そして流通の人、飲食店の人などに会った。そこで様々なあり方を学ばせてもらった。
その日に、こんなことも教えてもらった。
「果樹の剪定なら、木村さんと道法さんのやり方を学んだら完ぺきだよ」
むむむ、そうなのですか。木村さんとは、青森県弘前でリンゴの無農薬栽培に成功した木村秋則さん。道法さんとは、ミカンの栽培をはじめあらゆる作物の無農薬栽培の方法を瀬戸内から伝えている道法正徳さんだ。このときのアドバイスが頭にしっかり入って、のちに研修で実際に木村さんの剪定方法、そして道法さんの剪定方法を生で学ばせてもらった。その考え方や立ち居振る舞い、手さばきを、いま作物の栽培の際に活かさせてもらっている。それを踏まえての、高く育つ木たちなのだ。
***
今、僕は刺してきたアシナガバチの巣を落とすかどうか悩んでいる。繁殖したあと、働きバチがそこら中を飛び回ることを考えると落とした方がいい。でも作業するのはほぼ僕一人だし、その高い枝周辺は収穫が済んでしまったから僕が手を伸ばすことも基本ない。お互い邪魔することもないだろう。働きバチは周りの昆虫を捕食するのかな。ガやカメムシが増えることがあるから、いてくれたほうが助かるかも。でも、いるのを忘れてまた不意に近づいたら今度は僕がハチの巣にされてしまう。それはいやだな。
前に住んでいた家では、玄関の真上にキイロスズメバチが巣を作ったことがあった。屋根裏に巣を作ってしまったので処置するのが難しく、結局ワンシーズンずっと僕たち家族もスズメバチも出入りして、やり過ごした。
梅畑でもスズメバチが巣を作り始めて、これは危ないと思ったので高枝切狭みで何メートルも先からビビりながら落とした。
今回は、まだ結論が出ていない。とにかく「鎮まってくれ」という気持ちである。

編集部からのお知らせ
『ちゃぶ台9』に中村明珍さんの寄稿
「何様ランドーー共有地」掲載!
5/31に発刊となった『ちゃぶ台9 特集:書店、再び共有地』に中村明珍さんによるエッセーが「何様ランドーー共有地」が掲載されています! ぜひお近くの書店でお手に取ってみてください。




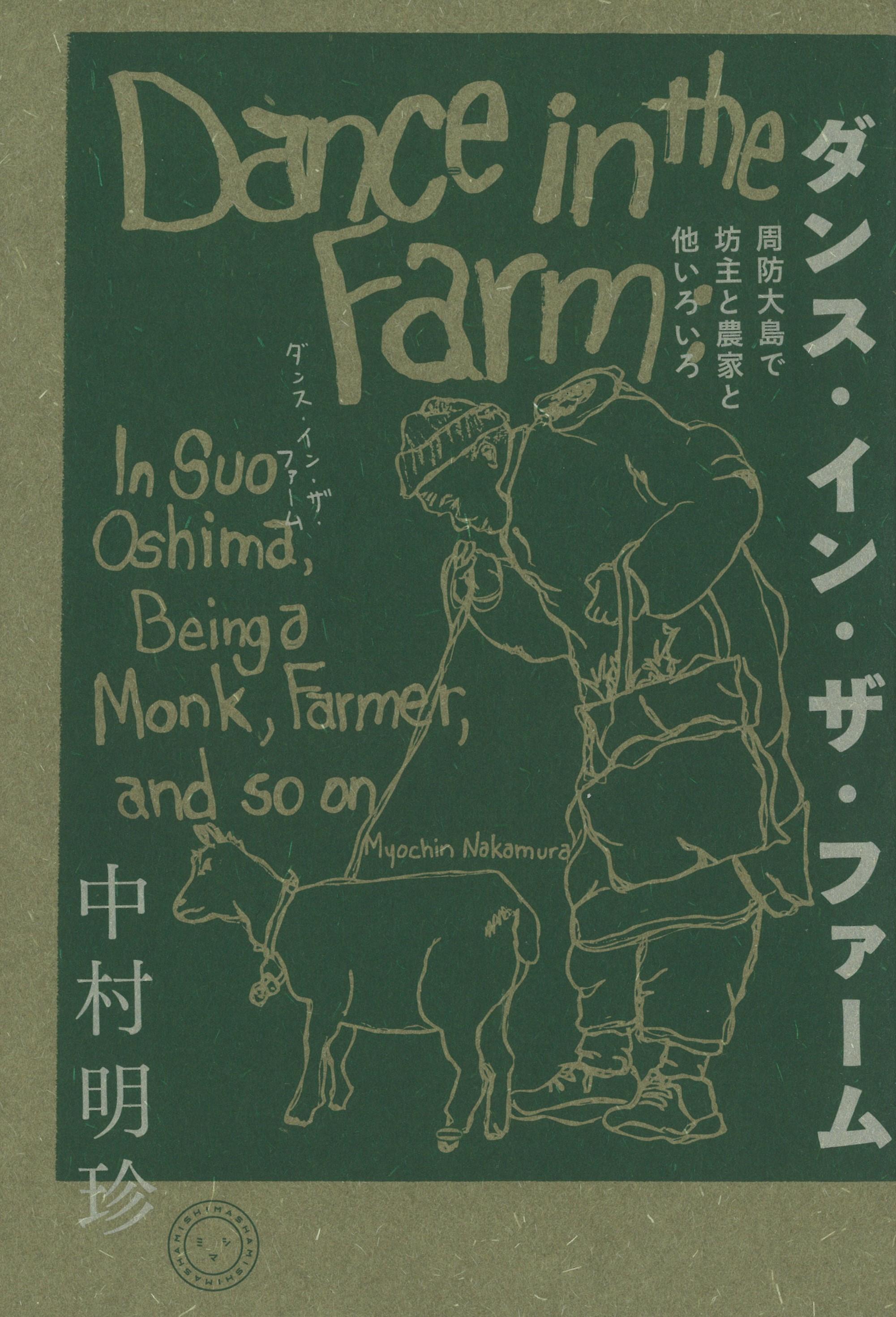
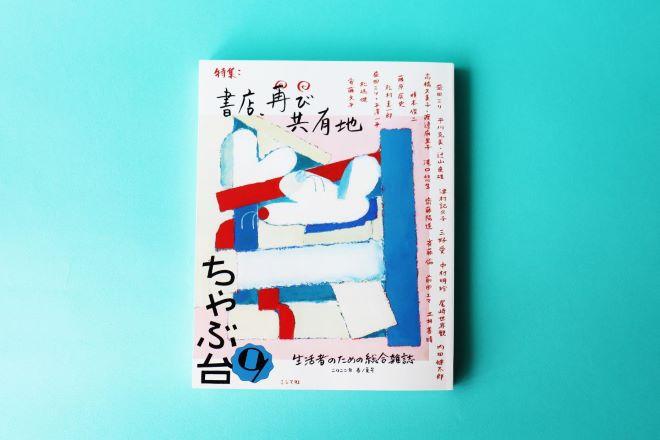


-thumb-800xauto-15803.jpg)


