第31回
廻向
2024.08.29更新
7月から8月の田んぼの作業。日中の暑さが辛すぎる。
というのも、上からの日差しと空気が暑さを運んでくるのと同時に、下からの熱気がたまらないからだ。水田の「水」がお湯みたいに熱い。稲はこんなに熱くても大丈夫なのかと感心してしまう。小川の取水口に近づくにつれて、フレッシュな水の温度に近づいていく。ああ、こっちは気持ちがいいな。
果樹栽培を行っている山手と違って日陰もないし、文字通りの炎天下。2024年の今年、僕が住んでいる地域では8月19日まで雨が降らなかった。そのあとも降っていない。近くのおじさんは、
「ついに井戸が枯れた」
と川へ、農業用水をポリタンクで汲みに行っていた。
そして、いつも興味深いなと思うのが、島のなかでも地域によって雨が降ったり降らなかったりと、天候がまるで違うことだ。
作業中、あまりに暑くてすぐ休憩したくなる。日陰が近くにないこともあり、休憩しようとしても体の熱気が逃げてくれない。そこですぐ、小川に入って休憩することを覚えた。何回も何回も入っては、
「はあああ、気持ちいい」
としばし動けなくなる。クーラーの利いた部屋に入ったときと少し似ている。ちょぼちょぼちょぼちょ、流れの音に包まれて。川の温度が低いことと、水田の温度が高いのが不思議だ。気持ち良すぎて出られないなあ。
どんどん川から出たくなくなってくる。体の熱はいい感じで下がっていく。
すると、しばらく浸していた両手に不意にムズムズした感触が伝わってきた。な、な、なんなんだこれは。
川のなかをじっと見ていて驚いた。体長1センチから3センチほどのたくさんの川エビたちが、みんな同じ方向を向いて、上流へと泳いでいく。そのうちの一部が僕の両手や腕に着地してウロウロしているのだった。くすぐったいぞ。
普段よく見かける川エビたちは、それぞれが好きな方向へと泳ぎまわっているか、水草や藻、石の陰などに潜んでいるイメージだ。だから、イワシやアジのように群れて、隊列を組んで進むような姿に「なにごとが起きたのか」と思った。
そういえば、この地域では「いつもと違うこと」が起きているときにこう声を掛けられる。
「なにごとか?」
これは、僕の生まれ育った環境ではよっぽどのことが起きていないと聞かれない言葉だったので、慣れるまでに少し時間がかかった。
ここではかなり些細なことでもすぐに顔を出す。たとえば、いつもは1台しか停まっていない場所に3台停まっているとき。あるいは、近所で誰かと誰かがたまたま立ち話をしている場面。はたまた、何か思いふけって呆然と立ち尽くしている場合、など。
これらは都市部とは違って、ここでは少しだけ珍しい出来事ではある。そんなとき、挨拶のように掛けられる言葉なのだった。
そう考えると、じつは毎日、一瞬一瞬が「なにごとか」という驚きに包まれている。そんなことを、川のなかでエビにくすぐられながら思っていた。川の水が冷たくて、田は暑い。稲が育つ。風がぬるい。エビから見たら僕はなんだと思われているのだろう。腕は木か何かと思われているかな。
仕事に戻ろうと、僕は浸っていた川から這い出て、下流へと歩いていった。すると今度は、川を上から覆う状態になっているコンクリートの下から、歌声が聞こえてきた。暗い川の中からだ。
人だ! 隣の畑を管理しているFさんだった。
♪♪♪
歌詞は聞き取れないが、何やらとにかく楽しそうだ。川を囲むコンクリートのなかで歌声が反響して、いい塩梅にエコーがかかっている。
「こんにちは~」
と話しかけると、
「お~、川のなかは涼しいよ~」
と、こだまが返ってきた。
ともに川で涼む男たち。僕とFさんは考えていることが同じだった。
***
過日。用事を済まそうと、わが家から海辺へ向かう車のなかで、同乗の人から唐突に言われた。
「死体が上がったらしいと親戚から連絡があった」
急にどういうことだ。車が進むにつれて、消防車やパトカーやらが目に飛び込んできた。そのむこうの浜に警察官がたくさんいる。近所の知り合いも2人だけいた。僕は、車から降りて知り合いに話を聞いてみようと思った。
これは今年のお盆のさなかの出来事。わが家でも甥っ子なども帰省していたし、地域のうわさ話は脚色されて"尾ひれはひれ"がついている場合があるので、本当のところを確かめてみたかったのだ。
どうやら、人が溺れたのを助けた家族がいたこと。そして溺れた方は病院に運ばれているが身元がわからない状況、ということがわかった。
お盆は泳いではいけない。
という言い伝えを聞いたことがある。それを最近、周囲の人に聞いてみたところ、島で生まれ育ったり、どこか地方で生まれ育った人は大体その言い伝えを知っていて、人によっては実際に「泳がないようにしている」こともわかった。だけど、反対に「そんな話は聞いたことがない」という人も同じくらいいた。島で育っている義母もなぜか「知らない」と話していた。海なし県育ちである僕も、知らなかったうちの一人だ。
「クラゲが出るから」とか「霊が足を引っ張るから」とか「潮目が変わるから」など、いくつかの理由を聞いている。
ちょうどこのころ僕は、「この言い伝えは、無効になったのかな」と考えていた。
というのも、僕が今見ているお盆の海は、多くの人たちが海水浴を楽しんでいる海だから。多くの人にとってのお盆は、仕事や学校などの「休み」で、つかの間の観光やレジャーを楽しんで、また日々の生活に戻っていくまでの期間でもある。
一方、島で迎える側でも、その観光シーズンはいわば「かき入れどき」で、多くのお店もその時期に備えている。
わが家の子どもたちも、帰省してきた親戚の子どもやその友達と毎日のように泳いでいて、しまいには「海でおよぐの、もうあきた」というほどだった。それでも泳ぎつづけている。
言い伝えは、もうその役割を終えたのかもしれない、と思った。言い伝えを信じる人が減って、知らない人の数が一定の割合以上に増えたから、か。
6年前の周防大島を思い出す。「スーパーボランティア」の尾畠さんの登場で一躍名が知られた、幼児の救出劇。こちらは海近くから山へ上がった沢にいるところを、3日目に発見された。たしかこの間に誕生日を迎えて2歳から3歳に。この季節の空気とセミの鳴き声が、当時を思い起こさせてくれる。
これもお盆だった。僕は少し不思議に思ってしまう。どうしてこういうことが起こるのだろう。
今回の海のことでは、助けた人は近所の知人家族で、帰省中の兄弟・親子たちだった。異変を発見した子ども、沖まで泳いでいき浜まで抱えて帰った兄弟、救急車を呼ぶ母子。意識がなかった方は、一人で海に出ていたそう。浜で兄弟が心臓マッサージをして効果があり、「AEDは使わなくて大丈夫です」と駆けつけた救急隊員にいわれたとか。「人命救助にあたるので表彰の際は・・・」と尋ねられて、その兄弟は再びこちらに来るのが面倒なので辞退された、とあとで聞いた。当たり前のことをしたまでです、という気持ちもあったのかもしれない。
地元のおっちゃんから、「今頃は南風から北風へと風向きが変わっちょる」とも教わった。陸と違って、沖では山で遮られていたはずの風が吹いていて、流される方向も変わることも考えられる。どんなことが洋上で起こっていたのかはわからない。
僕は僧侶だから、祈ることしかできなかった。祈ることも決して無力ではないと思った。
この話を後日、近くの親戚と話していた。すると、
「めぐっているのかもね」
と話し始めた。聞くと、この親戚のお父さん(以前のこの連載でも登場した故人の"おっちゃん")は、だいぶ前に、畑で倒れている女性を発見したのだという。
それが、今回助けた方の家族のおばあちゃんであった。このときはすでに畑で亡くなっていたそうだけど、普段誰も通りかかることがないような場所だったので、見つけられてよかったという話だった。
今度は、その形が海で、別の家族へと起こった。亡くなったおばあちゃんの孫にあたる兄弟が、別の家族を見つけた。何かがめぐったのかもしれない。そうして順々に伝わっていくものなのかもね、と。親戚のおねえさんはそう教えてくれた。





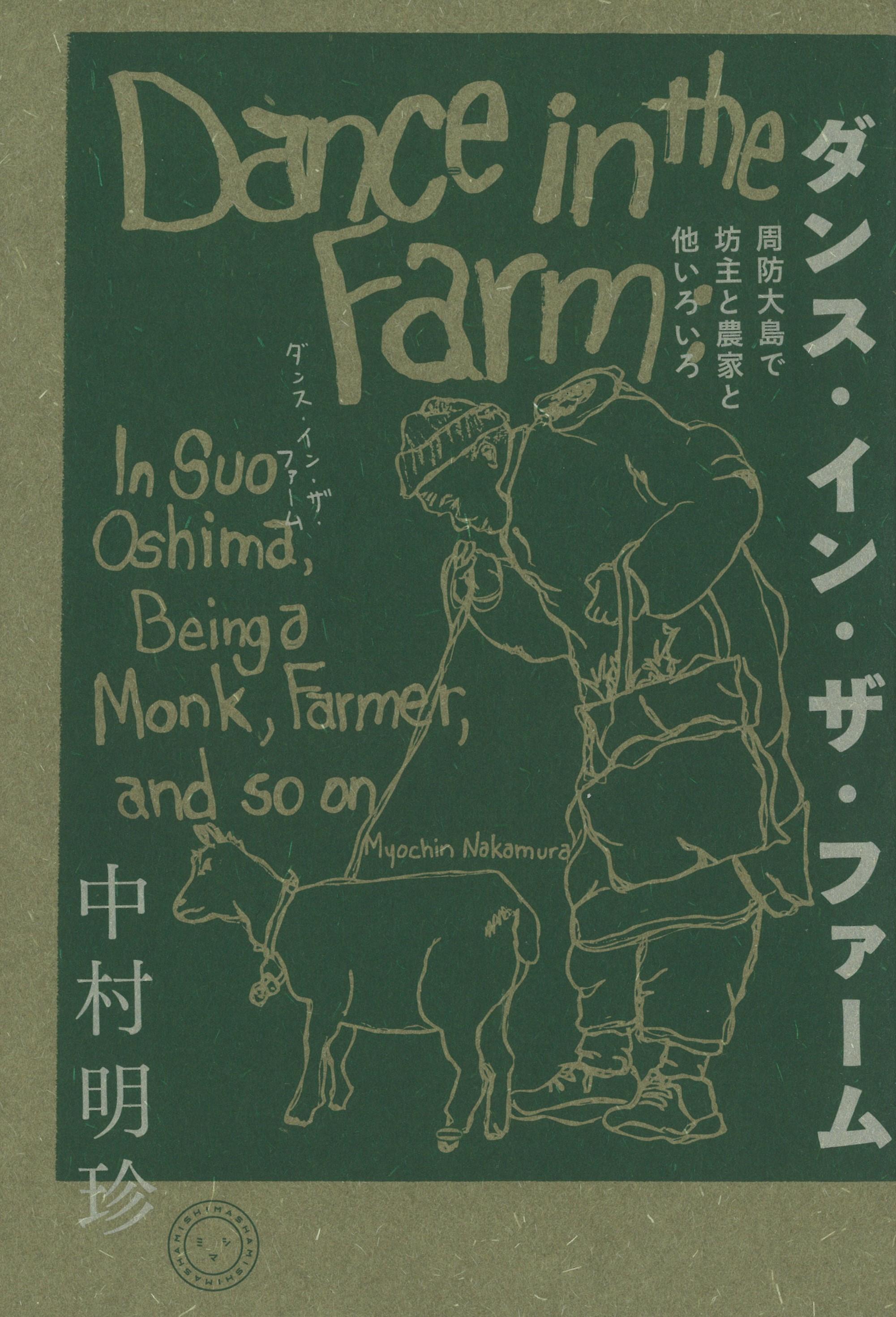




-thumb-800xauto-15803.jpg)
