第41回
投票立会体験記
2025.07.29更新
前回書いた、僕が住んでいる自治会の「一票」の話から一転。今度は国の選挙が行われた。だけどこの地域では、選挙が行われる場所は同じ。集落の小さな新公民館だ。100人単位の投票から一気に1億人単位の投票へ。2025年7月の参議院選挙のこと。
僕は今年再び自治会役員になったため、初めて選挙の「投票立会人」という係に任命された。規模が違う投票を、同じ場所で見届けることになって少し不思議な気持ち。
聞いてびっくりこの係、朝7時から夕方6時までずっと公民館内にいないといけない。拘束時間、長いな・・・。一体なにをするんだろう。
選挙管理委員会から届いた通知書にはこう書いてあった。
※昼食については、各自でご準備ください。
なるほど、外に出ての昼休憩は許されていないわけだ。気になる任務内容はこう。
〈投票立会人の任務〉
投票立会人は、投票が行われる際に、投票管理者の事務の執行に必要な補助を行うとともに、投票事務の執行が公正に行われるよう監視することがその役目です。
ほうほう。うーん。あんまり頭に入ってこないけど、事務の補助、監視と。そして、
その主な事務は次の通りです。
(1) 投票全般について立ち会うこと。
(2) 次の場合に意見を述べること。
と続き、意見を述べるときの例が3つほど記載されている。その3つの場面は読んだだけではよくわからなかったので、現場で様子をみることにした。
僕には、翌日に自分の寺の法要があるため、済ませておきたいことがあった。7時の任務開始前の早朝に、島外の寺に行って掃除して帰ってきて6時58分に公民館にインした。ギリギリだ。メンバーの皆さま、すみません。
会場はすでにスタンバイOK。今すぐにでも投票できる態勢になっていて、記入台、投票箱、受付と立会人の机や席が設営されていた。前日に準備していたのだそう。
選挙の事務は、役場職員の方たちが担当していて、すでに全島の投票所に散らばっている。この公民館では2名の若手の方が来ていて、選挙はがきで名前をチェックする係と、投票券を説明しながら1枚ずつ計2枚渡す係とに分かれていた。
さて午前7時。真夏だけどここではまだこの時間帯は涼しくて、エアコンをつけずに窓を開けて風を通していた。山の方でセミが鳴いている。静かだ。まだ、誰も来ない。
こういうときはおしゃべりだ。集落の先輩2人と役場職員の方たちとざっくばらんな会話が弾む。昔話、最近の島事情。近所で今にも咲きそうなリュウゼツランという花の情報。
そして職員の1人がいう。
「前回の選挙は大変でした。終わったのが2時半だったんです」
夜中の2時30分。聞いてびっくり、そこまで開票作業を行っていたのだそう。実際の票の数と、名簿での数がどうしても合わず、それが合うまで終われないのだとか。夜中にようやくどこでズレていたのかが判明して、無事に終了できた。
ここは周防大島。開票は島内各地の投票所で行うのかと思っていたらそうではなく、それぞれの投票箱を島の一か所に集めて、せーので全島分の開票を行うのだった。なぜそんなことを。
しかも、前回の周防大島は町の選挙が重なってしまっていた。もともと4年に一度の周防大島町長選挙、町議員選挙が予定されていたことに加えて、当時の総理大臣が衆議院を解散させたために、同じ日の投開票で国の衆議院選挙も入ってきた。そこに最高裁判所裁判官の国民審査も加わる。3つも4つも投票があるなんて、受付はそれだけ煩雑になる。色の違った一枚ずつを、間違わずに記入してもらわなければならない。
その職員さんの担当した会場は、今回とは別のもう少し大きい集落で、そこではお昼ご飯を食べるヒマが全くなかったのだとか。受付で人を待たせながら、間違いのないように捌くので精一杯。ゆっくり昼食が取れなかったそのときの経験を活かして、今回はカロリーメイトを持参したそうだ。
「前回は大変でしたよ」
そのときの選挙翌日は月曜日。役場にはいつも通り、平日の通常業務がある。開票作業が遅くになればなるほど通常出勤が迫ってくる。書面上では「休める」というルールはあるけれど、全員が休んでしまうと役場の業務が回らなくなるので、よっぽどでない限り実際に休むことは困難だと。「大変」って、そういうことだったんですね。
今回は翌日が祝日なので、
「本当によかった」
と言葉に心がこもっていた。立ち会い任務冒頭30分ほどで、知らなかった選挙の実務が垣間見えた。
数字が合うまで大量の開票が終わらないこと。投票箱を懇切丁寧に運んでいくこと。とにかく「不正」が行われないための工夫が散りばめられているのだと、なんとなく理解できてきた。そして、「解散」とか「政治日程」といった東京中央でのさじ加減が、こうして末端にしわとなって寄るんだな、とも思った。
***
そうこうしているうちに最初の投票者が歩いて現れた。集落のKさん。高齢だけど元気で、先日は「自由に使いんさい」「応援してるから」とタケノコを掘ってきてくれた優しい方。あるときは、専用のモリを両手に持って干潮の浜に出て、石のすき間に潜むタコを獲る名人。先日、
「最近はタコどうですか?」
と聞くと、
「年がら年中獲ってるワケじゃないけえの」
と笑ってたしなめられた。季節じゃなければやらないよと。自治会の方によると、Kさんはいつも投票一番乗りなんだそうだ。
「それでは」
といって、今度は役場職員の2人が投票箱の前に出ていく。なんだなんだ。
「何も入っていないことを確認します」
トップバッターのKさんが投票する面前で、職員が投票箱を開け、僕たち立会人も見守るなかで、箱の中身が空っぽであることを確認した。手品の「タネも仕掛けもありませんね」の要領。そうして箱にカギをかける。
これも、不正がない選挙を積み上げていく一手なのだと理解した。
無事、選挙区の1票目と、比例代表の2票目を投じて、Kさんはにこやかに帰っていかれた。暑いなか徒歩でご苦労さまです。
2番目は、杖をついて現れたMのおばあちゃん。歳は90歳代。さすがに徒歩ではなく、ゆっくり動くスクーターのような乗り物で近くまで来て、補助の手すりなどを使いながら入場。自分のペースで投票していく。いつも大きな声で話す快活なおばあちゃんだけど、投票所ではなんだか神妙な面持ちだ。
「ああ、たかひろさんね」
そのおばあちゃんにはいつも本名で呼ばれるのだった。おばちゃんも、ご苦労様です。
そのあと、ポツリ、ポツリと地域の方たちが訪れるようになった。車で相乗りして来る人、原付バイクで来る人、自転車の人、歩きの人。近所の方と連れ立ってきたり、夫婦で来られる方もかなり多い。ある年配の女性は、
「なんとなく緊張する」
とつぶやいていた。きっと今まで何回も投票してきただろうに。この営みに非日常を感じているのかもしれない。
皆さん1人ずつ、ときどき職員さんに「なんて?」と記入と投票の仕方を尋ねながら、投票箱に入れていく。
ちなみにこの日、仕事終わりに来られた1人以外、投票所に来られたのは全員僕より年上。つまり46歳以上。その下がほぼ皆無。住んでいないのだから仕方がない。
自動車で来られて、スロープと手押し車を使って会場に入ってきた高齢のご夫婦と、介助をするお子さん夫婦がいた。すごくゆっくりと、介助されながら1枚ずつ投票を行っていく。そのとき、おばあちゃんが票を入れたあと、投票箱に向かって手を合わせて深々と礼をしていたのを見た。
もしかしたらおばあちゃんのなかでは、賽銭箱にお金を入れる場面と混ざってしまったのかもしれない。でも、こういった一コマ一コマを見ながら、昔はどうだったんだろうと思った。女性の参政権----女性も選挙に投票できるようになったのは、昭和21年4月10日。終戦の翌年春、日本国憲法の公布の前か。とはいえ、法律で制定されたあとでも政治に対して「女子供は口を出すんじゃない」という風潮もあっただろうし、手が合わされたこの1票のたどってきた経緯を想像してしまう。
昼食を食べる時間がたっぷりあったので、こんな昔話が聞けた。
「昔の選挙のときはね、隣の集落との境の峠に見張りが立っていて、時々家まで追いかけていったこともあったんよ」
その見張りが追いかけていって、誰に投票するのかを把握するぐらいだったそう。モノも飛び交っていたそうだ。今ではアウトな行為だろうし、当時も本当はアウトだろう。それだけ何かに必死だったのかもしれない。
この仕組みの生まれ故郷のヨーロッパでは、投票箱に手を合わせるようなことはあるのかな。見張りが追いかけていくことはあるのかな。
「午後以降は全然人が来なくなるよ」
と聞いていたけど、本当にそうだった。長い昼下がりが始まる。さすがに暑くて途中で冷房を入れた。そして午後のひとときのなかで、
「投票所を閉めたあと、投票箱の運搬の同行をしてほしい」
という打診を受けた。そ、そうなんだ!? 本当はこのあと法事の予定があったので戸惑ったけど、他に対応できる人はいないので、先方に遅れますという連絡を入れて任務を遂行することになった。周防大島の庁舎付近まで往復1時間30分。手当として夕食代1000円が出るという。
投票箱にカギをかけ、そのカギを職員が保管しながら、有権者の個々人が投票用紙にえんぴつで候補者名・党名を書いて箱に入れる。そうした形で選挙が進んできた。そして終了時間になり、投票箱を立会人と職員がカギとともに、責任を持って開票所まで持っていく。つまり、かなりアナログな方法で不正を防ぎながら開票へとバトンタッチしていく。
おじいちゃんおばあちゃんは、「選挙は大事なことだと思っている」ということが、朝からの様子で伝わってきていた。そして現時点では、その方たちが紙以外で投票している光景は想像できなかった。不正防止と実際の皆さんの動きから見るに、まだアナログ強しといった趣き。
でも一方で、投票所に来た人が僕より年下の人が1人しかいなかったという状況から、その間の世代や、選挙権を持っていない子どもたちの声はどうなるのか、どうしたら反映されるのか、とも思った。さらに反対に、当地の自治会内では赤ちゃんから選挙権を持っていることから問題が浮上した。どちらも両極端という感じだろうか。なんとか、これからのためのいい落としどころは探れないかな。ついつい揺れてしまう。
16歳の高校生の娘は、この期間中、部活が終わったあとに選挙の話題になっていたそうだ。TikTokとかインスタとかで流れてくるから、どうしてもその情報に触れることになる。どこがよさそうか、よくなさそうかなども考えるそうだ。
選挙権が20歳から18歳に引き下げられたのは、2015年6月17日とのこと。それから10年、うちの高校生はその権利を持つまであと少し。僕の高校時代とはいろいろ違う。
***
周防大島の開票所は想像していたより大きな会場だった。投票箱を持って中に入ると、他の地域からも続々と運ばれてきていた。周防大島町の住民1万3344人分(2025年6月1日現在・周防大島町広報より)の思いが詰まっている、のか。あるいは当日有権者1万2200人分の思い、なのか(2025年7月20日・選挙管理委員会資料)。こうやってみると、選挙権を持っていない子どもたちは1000人ほどしかいないんだな。
開票所では知り合いにも会って「お久しぶりです」「お疲れ様です」と声を掛け合う。役場職員さんたちは20時から一斉に開票を始めるので、それに備える。
僕は無事に箱を届けて任務を終え、集落に引き返して急いで衣に着替えて、おばあちゃんの仏壇に向かう。お待たせしました。そこでは、施主とその幼馴染のおっちゃんが飲んでいた。
「おう、たかひろくんか。わしはたまたま飲みに来たんよ。あんた今から拝むんか。ほんなら帰ろうかな」
とおっちゃんがいうと、
「あんた、一緒に拝んでいきんさいよ」
と引き留められる。ほんならそうしようか、ばあちゃんだしな、と幼馴染らしい会話が繰り広げられる。
30分ほど心を込めてお勤めをした。そしてうしろを振り向いたら、おっちゃんが目を赤くして泣いていた。飲みに来たはずなのにどうしたんだ。片付けをしながら「ごはんを食べていきんさい」といわれたので食卓にいくと、まだおっちゃんが泣いていた。
「ばあちゃん、よかったなあ」
いつも勢いのあるおっちゃんなので、僕は不意打ちを食らってもらい泣きしそうになった。横ではテレビがついていて選挙特番が流れている。箱を届けてからちょうど1時間経ったばかりの21時だというのに、もうこの選挙区の当確が出ている。何がどうなってるんだ。
しばらくするといつものおっちゃんに戻って、昔話に花が咲いた。夜中にイチゴを盗んだ話、親戚のスイカを盗んだ話。テレビから当選した人の声が耳に入ってくる。そのなかで僕はこんなことを思っていた。
「選挙も入試みたいだな」
僕たちは、子どものときから試験に慣れすぎているのかもしれないと思った。
〈試験もなんにもない〉
そんな世界もあることを、子どものころから教えてもらっているけれど。受かるかどうか、ここで心が頂点に達するような形式。胸の花のブローチ。桜咲く。勝つか負けるか。僕はこれを冷やかに笑いたいわけではない。でも僕が救ってもらった音楽の世界には、コンテストもないし、誰かとの勝ち負けもない。そういう世界もある。
ちなみに、僕は旧公民館を取得して館長になったと同時に、今年から新公民館の館長にも任命されてしまった。一体何をやっているんだ僕は。
集落ではリュウゼツランのつぼみが日に日に膨らんでいっている。数十年に1度しか咲かず、1度咲いたら枯れてしまうのだそうだ。今、この話で集落は静かに盛り上がっている。僕は揺れながら考えている。そうして考えながら、この上に、伝統的で新しい行事を今からまた置こうとしている。





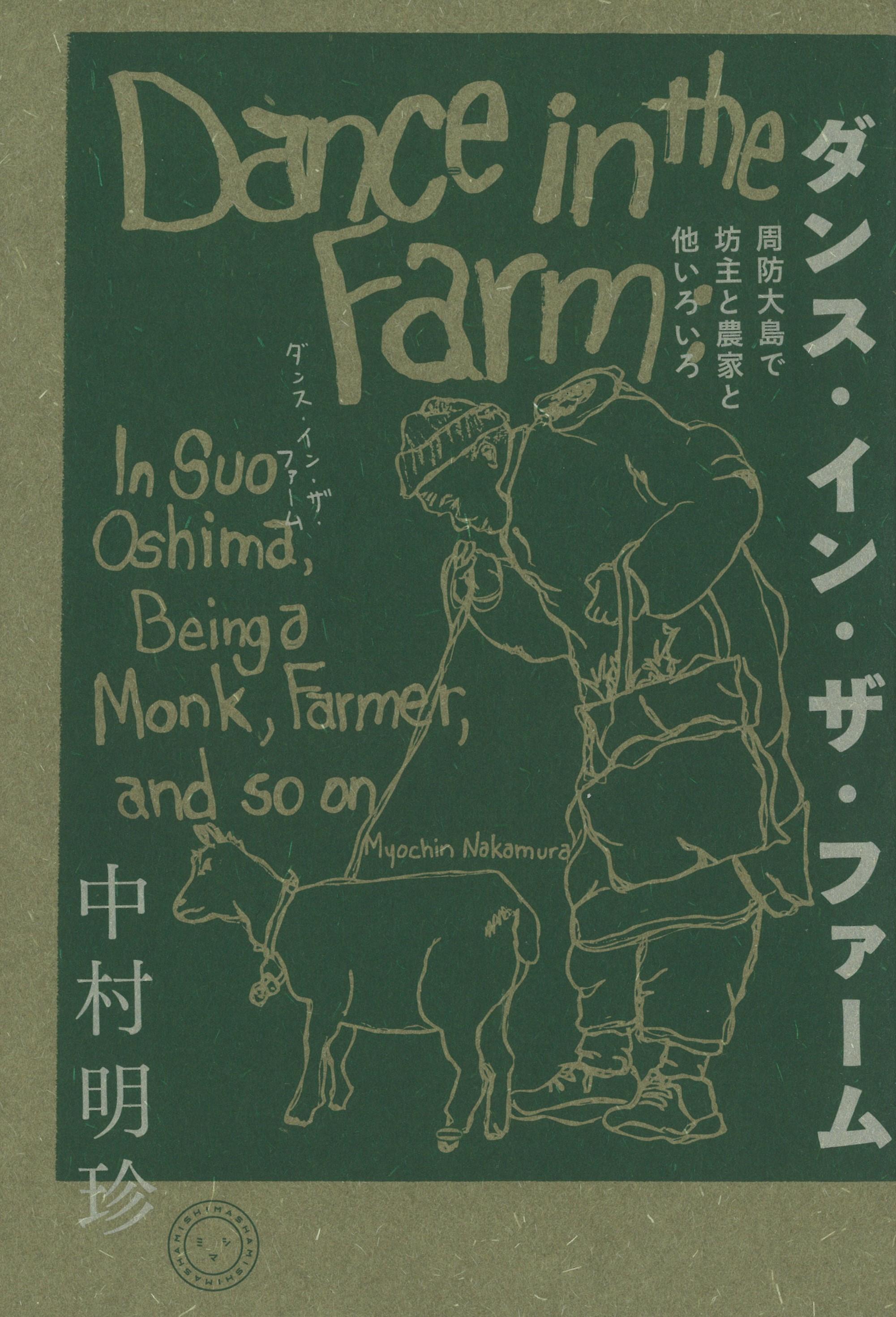


-thumb-800xauto-15803.jpg)


