第44回
見えないものの流通 前編
2025.11.17更新
「料理があってシェフがいて、そこにお金を払って、って形を一回やめてみたいんだよね」
とそのころ、友人のシェフが会うたびに語っていた。周防大島和佐の旧公民館あらため「和佐星舎」の厨房、そこで友人たちと作って食べながらのおしゃべり会がたびたび行われていた。餃子を皮から手作りして食べる餃子会だ。加えて彼が、
「おいしいタコス食べたいよね」
と熱っぽく語り始める。いいね、と盛り上がる。料理人として「一回やめてみたい」っていうのはなかなかすごい思いだ。
これと前後して、僕たちは全国ツアー中のバンドGEZANの広島公演を観に行き、GEZANチームが周防大島に来てくれて、一緒にご飯を食べ、そしてまた山口・防府公演を観に行くという3日間があった。
この3日間を過ごしたあと、僕たちは衝撃を受けていた。そのときに話題にのぼっていいたのは、「どうしてこんなすごいことが起こるんだろう」「どうしてこんなチームワークがありえるんだろう」ということだった。バイブレーションが周囲に波及していた。そんな会話のなかから、
「最高のタコスを作って、喜んでもらおう」
とシェフがいい始めたのだった。ここ和佐星舎で、皮から作って、最高のタコスの会を。そうしたときに起こることを見てみたい、と。対価としての値段はつけずに、投げ銭で。さらに、
「名前は『無限タコス』だ!」
と続けた。「無限って、どうして無限?」とご飯を食べながらみんなから突っ込みがあったが、シェフは、「無限は無限でしょう」といい切った。そして「GEZANという名前に引っ張られてるかも」ともいって、笑った。
この前後で、独立研究者の森田真生さんの話題にもなっていた。森田さんと僕で「生命ラジオ」というオンラインでの学びの取り組みを毎週行っていて、まもなく丸5年。このタコスの会を話している面々もその参加メンバーで、毎週聴いてくれているのだった。僕たちのなかで、そのラジオで話されていたことを元に会話が展開することがしばしば。このころ話していた大きな学びは「地形」についてだ(参考:小説すばる2025年8月号「ともにゆく道」第9回「地形」)。
そういった流れのなかで、この無限タコスは、GEZANと森田さんの影響によって、今まさに発芽しようとしていた。頭文字をとってG&Mという名前で呼ばれるようになった。6月のことだ。
厨房でごはんを作って食べながら、G&M=無限タコスはお盆前の8月上旬に開催しようという話に。その打ち合わせのなかで、
「『無限』はかっこいい響きだけど、来ていただく人にはもしかしたらわかりにくいのではないか」
という疑問も出て、それはそうだと思った。その問いかけを受けてタイトルを「投げ銭タコス」に変更しようとしては、
「それも伝わりにくいのではないか」
「かえって普通に対価を支払っていただく形態の方がいいのでは」
などと、議論が何日も続いた。
一方、僕は会場であるこの建物の「館長」という立場になっていた。といいながらもともと「長」がつく肩書きは苦手だと思っていたので、自分では普段「管理人」といっている。けれど、消防署の調査のときに「『館長』といっていただけるのがありがたい」といわれた。とにかく、この場所の責任者ということだ。
最高のタコスと投げ銭制、これはかっこいい。未知の領域でわくわくする。ただ、もともとこの会場を維持管理してきた地域の住民の人たちにとっては、馴染みのない組み合わせで、もしかしたらポカーンとしてしまうのではないか。あとで、「ああ、あのときなんか集まりやってた?」と地域が置いてけぼりになりはしないか。もしそうなるとしたら、もったいなく感じる。
なので、タコスだけでなく、地域の人が食べやすいものを用意することも提案した。すると、メンバーからとなりの集落の同世代の名前が挙がった。お惣菜屋さんで、僕たち家族も普段愛用しているお弁当を作っている方だ。その方にも声をかけよう。
さらに、「投げ銭」という仕組みはとっつきにくいから、何かいい伝え方はないかと話し合っていた。あるいは「無料」と宣言した場合、それはそれで微妙にニュアンスが変わってしまう恐れもある。
そのなかで、「お接待」というあり方が浮上した。四国遍路に由来する施しの文化だ。この言葉であれば、島に住んでいるお年寄りから子どもまで馴染みがあって、しかも実現したいことが伝わりそうだ。ふるまう文化の裏には、祈りが入っている。
ただ、これも投げ銭とは微妙にニュアンスが変わってしまうこともあり、何度も「これでいいのだろうか」とみんなで逡巡しながら進めていくことになった。
そうしたなかで、名前が挙がった先のお惣菜屋さん・Kさんに「じつは『お接待』をしたいんですが、力を貸していただけませんか?」と持ち掛けた。この女性は地元育ちで、東京にて仕事をしたのち、Uターンされた方だ。どうして普通のイベントではなくお接待なのか。おそるおそる話をしてみると、やはり「どうしてお接待?」という疑問の声もあった。じつはこのアイデアを周囲の人に伝え始めたとき「なんでお接待???」「むしろ普通にお金をもらえばいいのに」としょっちゅう突っ込まれていた。
そんな会話がありながらもKさんから、こんな言葉があった。
「じつは私も、お接待をやりたいと思っていたんです」
えええーーーっ。聞くと、Kさんが住んでいる集落にもお堂があり、以前は縁日になると「お接待」を行っていて、おにぎりなどが定番だった。だけど近年は他の集落と同様にお堂の守り手が高齢になってきていて、ついにお接待という行事がなくなった。それがさみしいからなんとか復活できないかと、思うところがあったそうだ。
僕は同世代でこんな関心をもっている方がいてうれしくなった。なかなか理解しにくい営みだ。もし今回、和佐星舎でやってみてうまくいったら、今度はそちらでもやってみましょうと盛り上がった。
こうして、8月に「お接待タコス&お惣菜」という名前の行事が誕生することになった。
ただこの行事、走り始めると前日まで毎日トラブルというか、小さなつまずきがあった。おそらくそれは、普通にただイベントを置いていけばいいという種類の行事ではなかったから。まだ知らない、見たことがない場を模索して、話を重ねながらアイデアと心意気で育てていく種類のものだったからだと思う。楽しみながらも、真剣に向き合わないと何かに飲まれる。そんな心持で、もしかしたら、これはうまくいかないどころか、
「結局当日できないのではないか」
とつまずくたびに、真面目に思っていた。
***
前日、本格的な準備が始まった。当日は何名くらい、どんな方たちが来てくれるだろうか。遠くの人も、歩いてすぐの方も、いろんな人たちに来てほしい。開かれた場所でありたい。でも初めてのことだから想像しきれない。皮を焼くためにトウモロコシの粉をこねたり、肉の仕込みをしたり、テーブル、席の配置を考えたり。シェフのもとで次々に準備していく。どんな場になるのだろうと思い浮かべながら。何枚焼けるかと話しながら。
その頃、隣の集落のKさんもお惣菜に取り掛かり始めてくれていて、メニューが送られてきては歓喜した。「こんなにいろんなものを作ってくれるんだ!」。きっと喜ばれそうだ。
SNSでの告知はわりと直前にした。SNSは遠くまで届くけれども、過疎の地域の場合とくに、思った以上に近くに届かない。そのあたりのさじ加減もいちいち考えながら作っていく。逆に回覧板をまわそうと思っていたけど、回覧しきる時間を逆算すると間に合わないことと、回覧担当の方に迷惑をかけそうだったので、集落の友人に新聞配達のついでにお知らせを配ってもらった。
今回の行事は15時から20時の時間帯。こちらも話し合いながらベストを探って、決めた。そうして当日を迎えた。
どきどきしながらスタートの15時がやってきた。その少し前からすでに地域のおばあちゃんたちや、近隣の方たちがぽつぽつと集まってきていた。誰も来ないことも充分ありえたので、もううれしくなった。
迎える提供チームは、シェフをはじめ、このころ「周防大島若者クラブ」と名乗り始めた若者メンバーに加えて、さらにその友人が東京から駆けつけたり、友人が友人の子どもを連れてきたりして気づけば想像していなかったメンバー構成になっていた。下は小学4年生から中学生2人も含むスタッフチーム。手作りタコスはとてもおいしそうな彩りと匂いを漂わせている。笑い声と真剣な眼差しが交差する。
そうして、大人も子どもたちも大活躍を始めた。来場者がどんどんやってくる。子どもたち同士でも教え合い、現場をよりよく回していく。ここには大人も子どもも違いはなく、垣根がなくなっていた。それぞれ場面場面で必要な持ち場についていく。
すると隣の集落で仕込んでいたお惣菜のKさんから第1便が届く。「わあ~っ」。何種類ものおいしそうな大皿。タコスと和食の共演だ。いずれもどんどん来場の方のお皿に取られていく。「持ち帰りしていい?」と集落のご夫婦。もちろんです。「またあとで第2便、3便作って来ますね」とKさん。
シェフもKさんも、臨機応変にその場でメニューを変更して繰り出していく。
「こ、これは・・・ライブなんだ」
そう思わずにはおれなかった。現在進行形で、ベストの形でものごとが動いていく。ここに来ている人たちはお客さまなのか、はたまたお参りの方なのか。
「お代はどうしたら?」
という質問もしょっちゅうあってそのたびに、
「お接待なので気にせずに」
というやりとりがあった。皆さまから「ええ~」という反応で、「お金を払わないと申し訳ない」という声もあちこちで聞かれたのは、シェフとKさんが料理で喜んでもらうことを想像して、力を尽くしたからだ。関わったチームの1人1人がいいと思うことを積み重ねたからだ。
気づけば設定していた時間中、近くの人から遠くの人まで、さまざまなところから途切れることなく来場があった。
しまいには1時間延長して、それぞれの席で歓談する時間になった。いよいよ終了する時間がきて、締めではなぜか拍手が起こった。
そのなかで、会場に来られたある夫婦の方からの、思わぬ次の展開が待っていた。

ーーーーー
【イベント開催のお知らせ】
2025年12月20日(土)
数学の演奏会 in 周防大島 2025師走
出演:森田真生
会場:周防大島「和佐星舎」




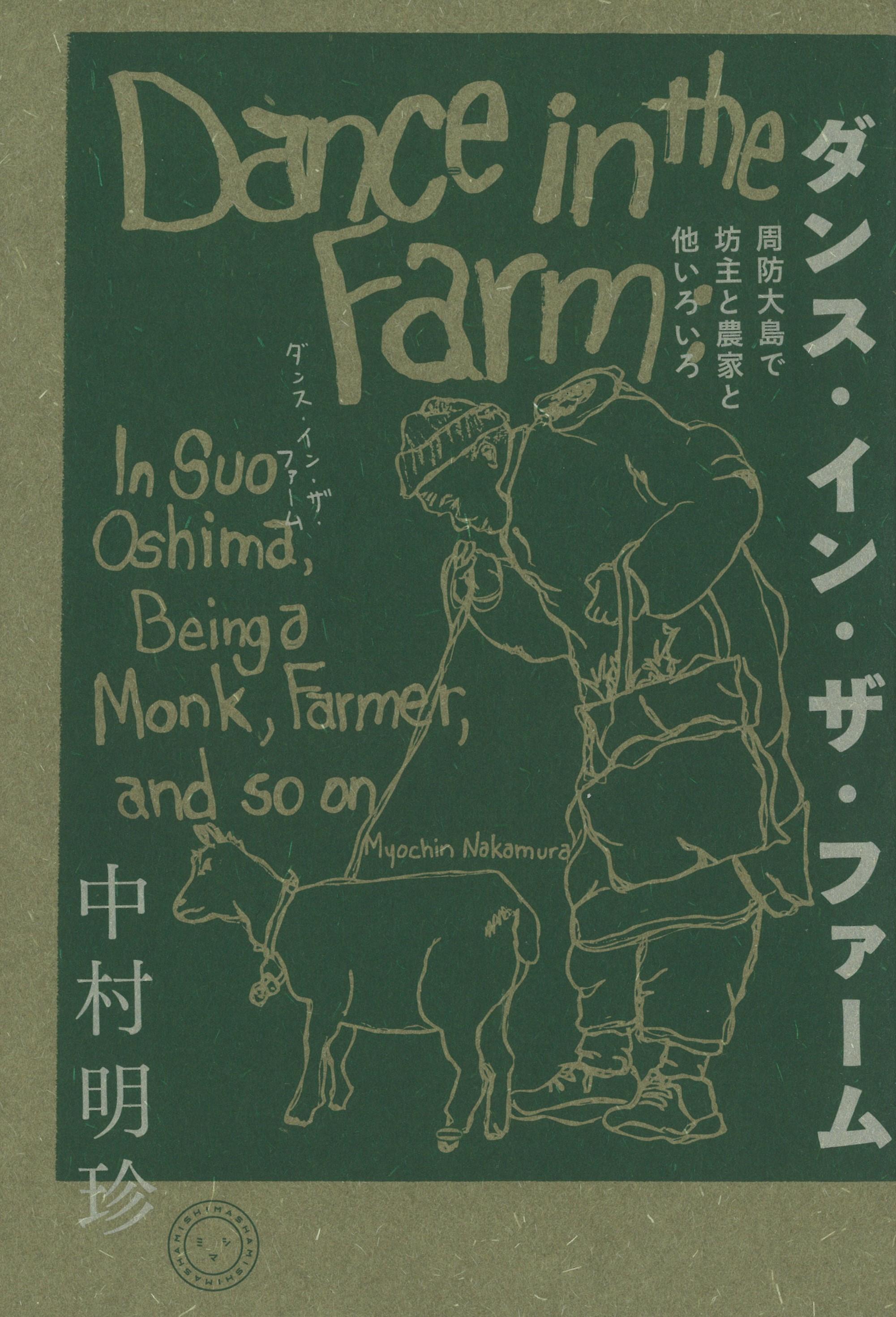




-thumb-800xauto-15803.jpg)
